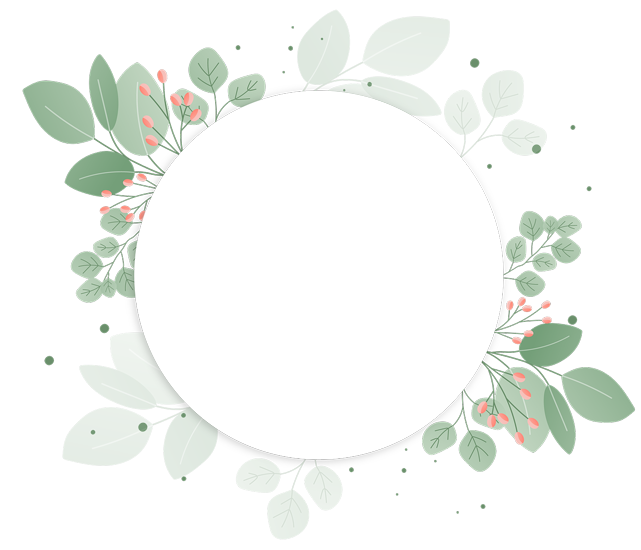どちらかと言えば興味のないことには集中力が持続しない香穂子は、専門教科と違って後からテキストとノートを見直しておけばキャッチアップできる一般科目の講義の際にはついつい気が抜けがちで、ぼーっと物思いに耽ったり、うっかり居眠りをしたりして、土浦のノートに頼ることも多い。だが今日の土浦は、視線は黒板の方に向けられてはいたものの、左手で頬杖を付いたまま、一向に板書する右手が動く気配がない。
おかげで、日頃土浦にお世話になりっぱなしの香穂子の集中力は最大限に発揮できて、講師が気まぐれに書いては消し、消しては書く黒板の文字を、きっちりノートにまとめることが出来たのである。
やがて、1時間半の長い講義が終わり、チャイムが鳴るや否やぞろぞろと多くの学生たちが昼食のために講義室を出ていく頃になっても、土浦は黒板に視線を向けたまま、右手で器用にペンをくるくると回して弄んでいる。
……実は昔から香穂子も片手でペンを回す仕草がかっこよく見えて憧れていたのだが、中学時代に頑張って練習したのにも関わらず上手く回すことが出来なくて、そもそもあの行為は鑑賞するためものなのだと諦めている。……余談である。
「土浦くん?……講義終わったけど」
つん、と指先で肩をつつき、話しかけると、ふと我に返った土浦が軽く瞬きをする。綺麗に拭き清められた黒板と、既に人がまばらな周囲を見渡して、深く溜息を付いた。
「ああ、悪い。何かぼーっとしてた……。ノート取り損ねちまったな」
「だと思った。今日は私がばっちり取っておいたから、安心して」
「……まあ、たまにはそんな日もないとな」
ノートを掲げて自慢げに香穂子が言うと、土浦が苦笑する。
確かに、これまでほぼ10割の確率で逆の図式だったのだから、あまり威張れたものではないのだが、土浦のその一言で香穂子に名案が浮かんだ。
「でも土浦くん、私のノートってお高いんだよ」
「てかお前、これまでの恩を無視して、見返り求める気かよ」
呆れる土浦に、香穂子が真面目な顔で向き直る。
「土浦くん、午後は講義なかったよね?」
「無視か」
「このノートと引き換えに、土浦くんの悩み事教えて。土浦くんってそういうことの切り換え上手いはずなのに、全く講義に身が入らないとかってただ事じゃないよね?」
とにかく、香穂子が心配なのはそこだった。
基本、土浦は遊びも生活もヴァイオリンも全てが一緒くたの香穂子と違い、ちょっとした日常の切り換え方が上手い。例えば香穂子はヴァイオリンの練習がつまづいたりすると、そこに意識が集中してしまい、友人と遊んでいる時や講義を受けている時に悶々と悩んでいたりするのだが、土浦の場合は指揮の勉強が引っかかる時でも、別の講義の時にはその内容に集中するし、体力づくりのために仲がいい友人たちと続けているサッカーでストレス発散して、いい結果を導いたりもする。そんな土浦が講義をそっちのけで物思いに耽ること自体相当に珍しいことだったのだ。
「……別に、深刻って話でもないけどな」
お見通しか、と土浦が息を付いて視線を落とす。不安げに様子を見守る香穂子に、土浦が思い切ったように顔を上げた。
「お前から言い出してくれたのは幸運だった。確かにただ事じゃない事態だ。是非ともお前の協力が欲しい」
「……は? ……ええ?」
思いがけず前のめりの土浦に、反射的に香穂子は後ずさってしまった。
「……罰ゲーム?」
「そう」
学生たちでごったがえす学食に移動し、片隅の席で向かい合って、二人は軽い昼食を取る。食事をしながら、香穂子は土浦から一連の話を聞かされた。
香穂子の高校時代の級友で土浦のサッカー仲間でもあった佐々木と、現在指揮科で土浦と一緒に講義を受けているサッカー好きの友人数名とで一人暮らしをしている学生の部屋に上がり込み、海外サッカーの観戦をしていた際、贔屓のチームについてアレコレ議論が白熱し、誰の贔屓チームがトーナメントで勝ち残るかについて、賭けをしたらしい。
詳しくないながらも、香穂子もそういう話はよく耳にするし、男の人っていつまで経っても子どもなんだなと微笑ましくもあるのだが、まさかその話の矛先が最終的に自分に関与してくるなどとは、さすがに思わない。
結果として土浦はその賭けに負けたらしいのだが、その際に負けた場合の罰ゲームが提示されていたのだという。
賭けのメンバーの中には彼女有りと無しが半々だったので、罰ゲームは2種類でどちらかを選んで実行しなければならないそうなのだが……。
「『皆でカラオケに行く』か、『彼女持ちは「メンズバレンタインデー」を実行する』か……」
香穂子にしてみれば『皆でカラオケに行く』というのが罰ゲームになり得るのか?と首を傾げるのだが、カラオケ嫌いを公言する土浦にとっては、この上ない苦行になるらしい。
そもそも土浦が応援しているチームは今季の成績が思わしくなく、罰ゲームの内容を決定したのは佐々木だというから、香穂子には初めから佐々木が土浦を狙い撃ちしたいがための賭けにしか思えない。
「……佐々木くん、高校の頃からずっと土浦くんとカラオケ行きたいって言ってたもんね。そうまでして行きたいって言うんだから、一回くらい付き合ってあげればいいのに」
「絶対嫌だ」
香穂子がカラオケに行きたいと言う時は、渋々ながらも三回に一回くらいは付き合ってくれるので、どうしてもカラオケに行けないということもないだろうと香穂子は思う。歌は苦手だというが、香穂子が聞いた数少ない貴重な土浦の歌は、確かにものすごく上手いとは言えないが、普通の歌唱力だった。壮絶に音痴とかなら頑なに拒否するのも分からなくはないが。
土浦曰く、行くこと自体は構わないが、歌うことを強要されるのが大嫌いだという。J-POPにそこまで興味がないのでレパートリーもないし、歌わないのに行くのはそもそも無駄だという結論になるらしい。
「数曲レパートリー持っておいて、毎回そればっかり歌ってれば、一緒に行く子も飽きるし、しつこく誘われなくなると思うんだけどな。まあ、土浦くんがどうしてもカラオケの方じゃなく、「メンズバレンタインデー」の方にするっていうなら、それは土浦くんの自由だと思うけど。……そもそも「メンズバレンタインデー」って何?」
眉間に皺を寄せた香穂子が首を傾げる。
どうしても佐々木とカラオケに行くのが嫌な土浦は、葛藤の末にもうひとつの罰ゲームである「メンズバレンタインデー」を実行することを決断したらしいのだが、そのためには香穂子の協力が必要だと言う。土浦が授業が身に入らないほど苦悩するくらいなら、自分が協力出来ることはしようと思う香穂子だが、そもそも「メンズバレンタインデー」とやらを知らないため、何を協力したらいいのかも全く分からないのだった。
「出来れば、知っていてくれたら説明が省けて楽だったんだが……、そこまで甘える訳にもいかねえよな」
「バレンタインっていうくらいだから、何か土浦くんから貰えばいいのかなとは思ったけど……」
本来のバレンタインデーの内容を考えると、「メンズ」の「バレンタインデー」なのだから、男の子から女の子へ愛の告白と共にチョコレートを貰うものかと香穂子は考えた。甘いものは大好きだし、土浦もそのことを知っている。だが、そういう単純な記念日ならば、土浦がここまで悩む理由が分からない。
「チョコなら全然貰うよ?特に銘柄とかにこだわりないし、コンビニとかで普通に売ってる安いやつでも美味しく食べるけど」
「……本当にそんな単純な記念日だったなら、俺の苦悩はなかったし、罰ゲームにもならなかったな……」
がっくりと項垂れ、土浦が深い溜息を付く。ますます困惑する香穂子に、土浦が答えを教えてくれた。
「香穂……金は俺が出すから、……下着を買ってくれないか?」
「……………………………は?」
長い長い沈黙の後、香穂子はようやく一言を吐き出した。
「ねえ、それ誰のための罰ゲーム? 男物の下着買うとか、絶対嫌なんだけど!」
「馬鹿、俺じゃなくて、お前のだよ!」
反射的に大声で叫び返し、土浦はハッとして片手で口元を押さえ、辺りを見渡す。
幸い昼食中でごった返す学食内では、土浦の声はそこまで目立つものではなかった。
「……女装趣味とかでもなくて……?」
「だから、俺じゃなくてお前のだって言ってるだろ。いいから最後まで話聞けって」
そうして土浦が話してくれた罰ゲームの中身は、香穂子が今まで全く縁がなかった記念日にまつわるものだった。
そもそもメンズバレンタインデーというものは、男性から女性へ愛の告白とともに下着を贈るという記念日らしい。当然土浦もそんな記念日の存在は知らなかったが、試合観戦をしていたメンバーの中にやたらと雑学に詳しい人物がいて、日も近いし面白いのではと提案してきたと言う。
「まあ下着メーカーの販促って面もあるらしくて、認知度低い記念日だけどな。どう考えても彼女持ちがやるイベントだし」
「そうだね……、いくら告白の時のプレゼントって言っても、彼氏でもない男の子に下着持ってこられたら、私ならドン引きする」
だよな、と土浦も頷いた。
「それで、私が下着を買うって話になるんだね」
更に土浦が頷く。本来なら土浦が自力で購入して、サプライズで香穂子に渡すのが罰ゲームの本題ということになるのだが、どうしても自分で女性ものの下着を買う勇気が出ず、それが講義にも身が入らない悩みの元だったらしい。香穂子にして欲しいと言う協力とは、代金土浦持ちで下着を購入し、それをサプライズでもらったと、佐々木たちに証言して欲しいというものだった。
「私には何もマイナス面がないし、それで土浦くんの気が楽になるなら協力するけど……」
物は下着であろうと、自分の財布は開かずに奢ってもらえるものだし、それをサプライズでもらったと佐々木たちに証言することも、嘘をつくことに多少の罪悪感はあれど、誰に迷惑がかかる訳でもない可愛い嘘なので抵抗があるわけでもない。唯一思うことといえば、
「……やっぱりカラオケ行くほうがよくない? そっちの方が土浦くんの負担、絶対小さいと思うよ?」
「絶対、嫌だ」
……どうやら、罰ゲームの中身というより、佐々木の思惑通りになることの方が土浦は気に食わないらしい。
「その辺りは土浦くんの判断だから、私は構わないけど。でも女性用下着でプレゼントレベルのものになると、そこそこのお値段するけど、それでいい?」
「……どのくらいだ?」
土浦の問いに、香穂子が少し考える仕草をする。
「好みにもよると思うけど……一式揃えるつもりで考えると、5千円から1万強ってところじゃない?」
予想を超えたのだろう。少し青ざめた土浦が愕然として、「マジかよ」と呟いた。
女性用下着の値段は少々土浦の決断を揺らがす一因にはなったようだが、それでも翻すには至らなかったらしい。
どうやらそこには普段の香穂子の態度もあったようだ。土浦の友人たちの話を聞くと、彼らの彼女たちの要求の多さとレベルの高さに辟易するらしいのだが、それに比べて香穂子の我儘は、ほとんどないに等しい。クリスマスや誕生日のプレゼントですら贅沢を言わないものだから、逆に土浦なりにずっと申し訳なさを感じていたらしい。
「それでもちゃんと私が欲しいもの貰ってるんだから、別に気にしなくてもいいのに」
9月14日、件の『メンズバレンタインデー』当日。
香穂子は土浦と待ち合わせて、ファッションビルのテナントに入っているそれなりに名の知れたランジェリーブランドの店へと向かう。可愛らしいデザインでありながらお値段はそこそこリーズナブルなので、香穂子の友人たちにも評判のいいブランドだった。
「まあ、ふざけた記念日だとは思うが、一応は恋人同士のイベントなわけだしな。そこで出し惜しみするのも野暮だろ」
これまで香穂子へのプレゼントにそこまで金額をかけてこなかった分も、ということで、今日の予算の上限は香穂子が考えていたよりもずっと上だった。おかげで香穂子がこれまでに身に着けたことのない上質のものを購入できそうだ。
「初めて土浦くんに買ってもらう高額商品がランジェリーって言うのも、何かちょっと笑えるよね」
「……その辺りは、お前には悪かったと思ってるよ」
結局は香穂子を自分の意地に付き合わせた形になるわけで、そこの後ろめたさもあるらしい。気にしなくていいのにな、と内心香穂子は苦笑する。
原因はなんであれ、香穂子は今まで縁のなかった高級ランジェリーを代金土浦持ちで購入できるのだし、それで土浦の気苦労が和らぐのであれば、何よりだ。
「じゃあ、ちょっと行って任務遂行してくるね! 土浦くんはどこかで時間つぶしてて。一時間後にまたここで待ち合わせね」
店の前に立って土浦から予算分の現金を受け取り、香穂子が冗談めかして敬礼する。どうせなら自分にきちんと合ったものを購入したいと、香穂子はサイズをきちんと測ってもらったり、店員のアドバイスを受けたりして、じっくり選びたいと言う。その間入り口でただ香穂子を待つというのは土浦にとって苦行でしかないので、香穂子の気遣いに遠慮なく甘えさせてもらい、土浦はビル内をうろついて時間を潰すために、店とは逆の方向へ爪先を向けた。
そして小一時間、特に目当ての店もなかった土浦は、とにかくショッピングビルの最上階から地下階まで当てもなく建物の中を歩き回り、適当に時間を食い潰して、また香穂子と別れたランジェリーショップの入り口まで戻って来る。自動ドアの前に辿り着いたところでタイミングよく、大きな手提げ袋を肩から下げた香穂子が、「ありがとうございました」とトーンの高い店員の声を背に受けながら、外へ出て来るところだった。
「お待たせ!」
香穂子はすぐに土浦に気が付いて駆け寄ってくる。小さく笑いながら「どうだった?」と土浦が尋ねると、「上々!」と満面の笑みで答える。
「こういうところ初めてだから、ちょっと緊張してたんだけど、いろいろ面白かった。可愛い下着いろいろ見るのも楽しいしね」
馴染みがないだけに物珍しくて、香穂子はそれなりにショッピングを満喫してくれたらしい。目の前の状況を素直に楽しんでしまえる香穂子の性格は、土浦にとってありがたいものでしかない。
「待ち時間、結構長かったでしょ? 土浦くんは、何してたの?」
「あー……とりあえず、建物の中ぶらぶらしてた。特に目当ての店もないしな」
「じゃあ、疲れたでしょ? どっかで休憩がてら、お茶でもしよっか」
香穂子の提案に、土浦は散策の際にある程度目星を付けていたコーヒーショップへ香穂子を案内する。昼前の中途半端な時間だったせいか、店内は思いのほか空いていた。
「……ねえ、土浦くん。私買い物しててちょっと思ったんだけど」
席に落ち着いて、注文した土浦のアイスコーヒーと香穂子のアイスティーとが運ばれてきた後、ふと思い出したように香穂子が口を開いた。
「土浦くん、目的のもの買ったら証拠の写メ撮って、今度佐々木くんたちに会った時にメンズバレンタインにサプライズで貰ったって証言すればいいって言ってたけど……男の子たちってこれを写メったところで、中身が女性用の下着だって分かるものなの?」
足元の籠の中に置いた例のランジェリーショップの手提げ袋を指し示し、香穂子が尋ねる。思いがけない指摘に、土浦が虚を突かれた。
上品で落ち着いたデザインの箱は、そのブランド名のロゴが遠慮がちに入っているものの、大っぴらに中身が下着であることを主張していない。そのブランドは確かに女性物の下着メーカーとしては有名どころではあるが、男性にまでその名が浸透しているのかどうかは微妙なところだった。
しかも香穂子の想像では、おそらく佐々木は土浦とカラオケに行くことの方が本命で、土浦がそちらを選ばざるをえないよう、選択肢の片方のレベルを爆上げしている。ちょっとしたことでも揚げ足を取って駄目出しをし、何としても土浦をカラオケに連れて行こうとするだろう。
(佐々木くん、何なのかな。そんなに土浦くん好きかな?)
そう考えると、土浦の彼女の立場としては土浦と同じく何とか『カラオケ』という選択を潰したい。少しの齟齬もないよう、こちらも充分に対策を練ることが必要だった。
「言われてみれば、確かにそこ突かれると痛いな。正直、俺も予め下着だってことを知ってないと、これだけ見て下着って判断しろって言われても、無理だ」
「だよね……」
アイスティーのストローをくわえ、頬杖を付いた香穂子がしばし思案する。ややして、名案とばかりに顔を上げて言った。
「いっそ、中身も写メっちゃうか!」
「は? 何言ってんだよお前」
驚いたように土浦が声を上げる。香穂子が逆に驚いたように、目を丸くした。
「だって、一番手っ取り早くない? 中身ちゃんと下着って分かるし、私が一緒に写ってれば、ちゃんとプレゼントされたってことも伝わるし」
「そりゃそうだが……」
抵抗ないのか?と土浦が尋ねる。
幾らなんでもそこまで香穂子を巻き込むわけにはいかないと土浦は思う。そもそもこれは単なる土浦たちの意地の張り合いであって、香穂子を巻き込まざるをえなかったことですら、土浦にとっては後ろめたさしかないのに。
「全くないと言えば嘘になるけど、別にこれを着て写真撮るわけじゃないし。一緒に写るくらいなら別にいいんじゃない?」
あっけらかんと香穂子が言う。
……だが、そこで土浦はようやく我に返った。
長い長い沈黙の間、土浦は片手で頭を抱え……そして、ぽつりと「……止めだ」と呟く。
「……え?」
「意地張るの止めだ。佐々木の望みどおり、カラオケでも何でも行ってやるよ。お前の言うとおり、何回か付き合ってやれば俺と一緒に行ったところで大して面白くもないってことを、佐々木が思い知るだろうしな」
「え、やだ。ちょっと待って。だってこれ……」
せっかく買ったのに。と香穂子が足元の箱を見やる。土浦が二択の罰ゲームの逆を選ぶと言うのなら、これはそもそも必要がない贅沢だ。
「私なら大丈夫なのに。下着と一緒に写メ撮るくらい」
「……俺が嫌なんだよ」
頬杖を付いて、香穂子から目を反らし、土浦が吐き捨てるように言う。
「実際には身に着けてなくても、男は想像するだろ。……女と一緒に下着なんか写ってたら、それを着てる姿をさ」
そこで済むならいいが、おそらくその先を想像しない男もいない。……十中八九、下着に隠れたその中身をこそ、思い浮かべるだろう。
「……お前をそんな野郎どもの視線に晒すわけにはいかないだろ。それくらいなら、どれだけ不本意であろうとも佐々木の思惑に乗るさ」
「土浦くん……」
意地の張り合いより、大切にするべき、守るべきものはちゃんとある。香穂子がここまで身を切る覚悟をしてくれなければ、土浦はそのことに気が付かず、香穂子の理解があることをいいことに、うっかりつまらない意地を張り通してしまうところだった。
「……なら、ちょっと勿体なかったね。これ、そこそこ値段張ったし。何か、結局私が得しただけになっちゃった」
「まあ、それはそれ。……本当に『メンズバレンタインデー』を楽しんだと思えば、それでいいんじゃないか?」
香穂子に対し、自分が何もかもを与え足りてないと常々感じていたことは事実だ。きっかけはただの意地であれ、香穂子が少しでも喜んでくれたのなら、それでいいと土浦は思う。
「それにさ……」
言いかけて、土浦はそれが周囲に他人がいる状況で、大っぴらに伝えていい言葉ではないことに気が付く。テーブルに身を乗り出して、近付くよう身振りで指示すると、香穂子は素直に土浦の唇に耳を寄せた。
「………………………」
小声で香穂子の耳に囁く。香穂子は眉間に皺を寄せ、それから一気に耳まで真っ赤になって。
思い切り土浦の額を掌で押し、距離を取った。
「考えてみれば、そもそもちょっと久しぶりのデートなんだよな。……少しくらい遅くなっても平気なんだろ?」
香穂子は赤くなったままそっぽを向いていて、答えない。
それでも、テーブルに乗せた土浦の手の甲に、恐る恐る指先が触れてきて、離れようとしないので。「そういうところは素直じゃないな」と土浦は苦笑する。
躊躇いがちの香穂子の指先を、逃げられないように緩く握り締めた。
(他の男に見せる必要はないから)
(そのプレゼント、俺にだけはちゃんと見せてくれ)
あとがきという名の言い訳
冥加に引き続き何かギャグテイストにしかならない「メンズバレンタインデー」(笑)でも確かに、よっぽど女慣れしてる種族じゃないとカッコよくこなせる記念日にならない気がする……。
衛藤創作より先にネタが出来ていたものですけど、いざ書き出してみれば終盤は衛藤の流れと被ってる(笑・でもこちらが先)
予定のものを予定通りに書き終えてますが、分量としてはだいたい衛藤創作と同じくらいになりました。2キャラはこのくらいに落ち着くのかな?
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2018.11.10