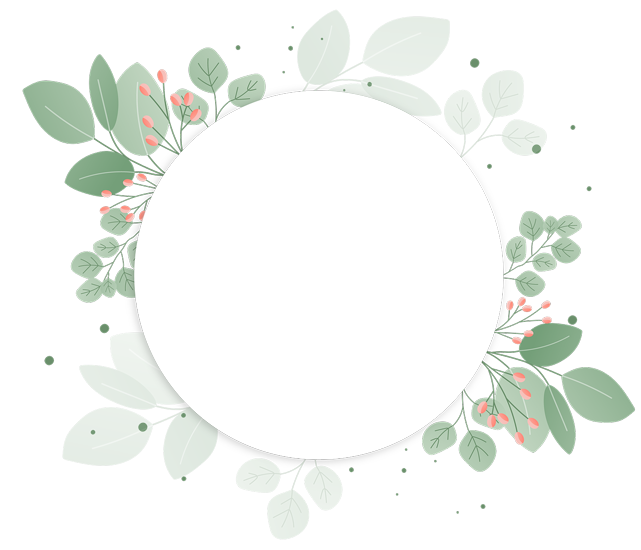もちろん『記念日』という類のものにそこまで思い入れがない香穂子であっても、恋人と一緒に過ごしたいという欲求は普通に存在するので、世間の常識として恋人同士が一緒に過ごすことを推奨している日に好きな人に逢いたい気持ちに偽りはない。だが、一般常識に自分たちの身を照らし合わせようとすると、少々変わった職に就いてしまったが故の弊害がそこに現れる。
「……空いてない、ですよねえ。やっぱり」
『そうだな。……むしろ俺もお前さんも、正に稼ぎ時だしなあ』
電話の相手は、のんびりとした口調でそう応じ、香穂子もそりゃそうですね、と溜息を付いた。
話は単純で、恋人同士が過ごす記念日としてはスタンダードなクリスマスを、香穂子とその恋人である金澤紘人とが一緒に過ごすというミッションを、果たして完遂できるのかどうか。……結論としては、答えは「否」だ。
香穂子はヴァイオリニスト、金澤は声楽家という肩書で生きており、二人ともその名だけで会場を満杯に出来るほどの名声ではないが、ほどほどに実力と伝手とを兼ね備えている。つまり、クリスマスという音楽イベント目白押しな季節は、当然のことながらスケジュールが真っ黒に埋まっており、イヴもクリスマス本番も、二人はそれぞれ別のコンサートに参加することになっていたのだ。
先述通り、香穂子はそれほど記念日というものにこだわる方ではないのだが、それでもクリスマスに金澤と一緒に過ごせないという現実には多少気を落としていた。記念日にこだわりはなくとも、やはり大っぴらに恋人と一緒に過ごせる理由がある時には、出来れば一緒に過ごしたい。
『逆に考えてみれば、喜ばしいことこの上ないじゃないか。この時期にスケジュールが埋まってるってことは、お互いに仕事が順調なことの表れだろ?』
金澤の反応は、淡々としたものだった。
そもそも金澤は香穂子より10歳以上年上で、付き合い始めた当初から記念日の類には無頓着だった。最初は律儀に誕生日だの、バレンタインデーだのというイベント事を楽しみにしていた香穂子でさえ、今ではそこまで気にしなくなってしまったのだから、金澤の反応が淡白なのも無理はない。
「それはそうなんですけど……せっかくだから、久しぶりにゆっくり逢いたかったのにな……」
幾分拗ねた口調で香穂子が呟く。
クリスマス本番はさすがに無理だと分かっていたけれど、その前後のどこかでクリスマスの代わりが出来ないか……二人で過ごす時間が取れないかと模索していたのだが、コンサートはその当日だけ体が空いていればいいというものではない。ソロではないので当然他の演奏者と合わせるための練習があるし、リハーサルもある。コンサート終了後には打ち上げや反省会なども予定されていて、更には有難いことに年末や新年にもコンサートの予定があって、そもそも香穂子自身がそんなに時間に余裕があるわけではないのだ。
だが、その年末から新年にかけての予定のために香穂子も金澤もここ最近多忙で、逢えない日々が続いていることも事実だ。連絡を取るためのツールは多岐に渡るので、お互いの状況はしっかりと把握してはいるものの、それでもやはり可能ならば直に逢いたいと願うのはおかしな話ではないだろう。
『……まあ俺だって、別にお前さんに逢いたくないってわけじゃあないからな』
香穂子の言葉にしばらく沈黙していた金澤が、低い声でそう呟く。そして、またしばらく口を噤んだ後、金澤は意外な提案をしてきた。
『お前さん、クリスマスに特別こだわりがあるってわけじゃないんだろ? なら、もう少し早く逢うのならどうだ? ……別に後でも構わんが、クリスマス後となると年末年始を挟むことになるから、また随分先の話になってくるからな』
香穂子は大きく瞬きをする。
イベント事にこだわりはないはずなのに、逆にクリスマスという大義名分があったため、その時期に無意識のうちに捉われてしまっていた。確かに練習の追い込みやリハーサルが本格的になる前の12月上旬ならば、まだ多少はスケジュールに余裕がある。
「うん! 大丈夫! 前でいい、逢いたい!!」
つい前のめりになる香穂子に、電話の向こうで金澤が苦笑する気配がする。スケジュール帳だろうか、何か紙を捲るような乾いた音がした後、金澤の声が尋ねた。
『……12日はどうだ? その日なら俺は予定が入ってない。お前さんが無理そうならまた別の日を考えるが、その後となると俺もリハやら何やらが詰まってるから、更に前倒すか、年明けを考えないと難しくなるぞ』
「ま、待って! 予定見てみる!」
香穂子は慌てて、机の上に置いている卓上カレンダーを手に取る。
祈るような思いで手に取ったカレンダーの12月12日の欄には、幸いなことに何の文字も記入もされてなかった。
「私も空いてます、12日!」
『よし、じゃあ決まりだな。……あー、お前さんさえよければ、店とか細かいことは俺の方で決めさせてもらってもいいか? 仕事で知り合ったレストランのオーナーとかに店に誘われたりするんだが、なかなか義理を果たす機会がなくてな』
「あ、はい。それは、全然大丈夫です。……何だかんだと、紘人さんも付き合い大変なんですね」
珍しい申し出ではあったが、香穂子もコンサートやパーティなどでヴァイオリンを弾く機会に、飲食店のオーナーやシェフなどを紹介されることがある。格調高いレストランなどでは生演奏を披露するようなところがあるし、一見関係が薄いように見えても繋いだ人脈がどこで自分の仕事と重なってくるかは分からない。もちろんほとんどは社交辞令なのだろうが、名刺交換や挨拶の際に「是非一度うちの店へ」と誘われることは少なくないので、金澤が言わんとすることは、香穂子にも理解できた。
『まあ、そこはお互いにな』と少し曖昧に答えた金澤の声に、安堵の溜息が混じっていたことに、香穂子は気付かなかった。
前日までに金澤からメールで店の場所や待ち合わせの時間などの詳細が送られてくる。レストランの名前は香穂子が知らないものだった。あまり格式張った店ではないから気負う必要はないぞ、と金澤は言ってくれたが、金澤は良くても店が許すとは限らない。ドレスコードなどが不安で、金澤に教えられた店名をインターネットや雑誌で探してみると、なるほど金澤の説明通りそこまで格調高くはないが、予約限定・全席個室という、カップルに人気の店であるらしい。
仕事関係の伝手で店を選ぶと言っていたので、そこそこのレベルのレストランなのだろうと予測はしていたが、普段は居酒屋で飲む方が落ち着くと言って憚らない金澤の選択としては、このような女性が好みそうな店を選んだことは若干意外な気もする。だがそもそもがクリスマスの代替案なので、もしかしたら香穂子の好みに合わせてくれたのかもしれない。人気店ということなのでよく予約を取れたものだと思うが、平日ではあるし、近辺にクリスマスという一大行事が控えているため、意外に押さえやすかったのだろう。
幸運にもドレスコードには明確な指定がなく、香穂子が所持している余所行きの服のどれかで事足りそうだ。ステージ用のドレスなら何着かあるが、どれもステージで映えることを念頭に置かれたデザインなので、食事で身に着けるにはいささか派手すぎる。きちんとした指定があるならば姉のクローゼットをひっくり返すかレンタル屋、更には美容院にも駆け込まねばならないと考えていた香穂子はほっと安堵の息を零した。
当日の待ち合わせの時刻はは夕方なので、ゆっくり準備して出かけようと考えながら、香穂子はインターネットの波の中を当て所なくサーフする。
(……ん?)
一つの記事に、香穂子の視線が止まる。レストランのホームページから貼られたリンクからジャンプして辿り着いた、とあるフラワーショップのホームページ。色鮮やかな花束の写真に添えられた簡潔な説明文に、ふと興味を引かれた。
(これって、12月12日なんだ)
記事のタイトルには「記念日に花を贈ろう」とある。そこには12月中の記念日が幾つか紹介されており、その中には香穂子と金澤が逢う約束をした12月12日に該当する記念日についての説明が記されていた。
「私が知らない記念日、結構いっぱいあるんだな……」
昨今、歴史の古い格式高いものから単なる語呂合わせのささやかなものまで、いろいろな記念日が設定されている。重要性の高いものから低いものまで、記念日を設定した側の思惑がそこには色々あるのだろうが、繰り返す日常の中にほんの少しの変化をもたらすものとして、上手く付き合っていけば、確かに楽しいものなのだろうと香穂子も思う。
「……まあ、紘人さんは興味なさそうだけど」
苦笑しつつ、会話の種の一つにはなるだろうかと、香穂子はそこに記されている記念日についての一文を、とりあえず頭の片隅に記憶しておくことにした。
そして、12月12日当日。
夕方、待ち合わせた駅の改札口で香穂子と金澤は無事に落ち合う。師走の構内は賑わってはいたものの、平日の夜ということもあってか、特に目立った混乱はない。
「今日のお店、ネットでどんなところなのか見てみたんですけど、ちょっと紘人さんっぽくない感じのお店でしたね。クラシック好きの店員さんとでも知り合ったんですか?」
「……お前さん、俺が安い居酒屋しか知らないとか思ってないか? 俺だって、時と場合に応じて店の雰囲気ぐらいはちゃんと選ぶんだぞ」
真顔で切り出した香穂子に、金澤が大仰に顔をしかめる。時と場合、と口の中で呟きながら、香穂子が顔を上げる。
「それって、今日がクリスマスの代わりだからってこと? ……今までそんなに紘人さんがクリスマス意識してたこともなかった気がするんだけど」
そもそも記念日の類に興味が薄い金澤なので、付き合い始めた頃、香穂子がまだクリスマス、クリスマス!とうるさかった頃でさえ、とりあえずチキンとケーキが食えればいいだろと某フライドチキンのチェーン店のクリスマスセットと叩き売りのクリスマスケーキで誤魔化されたのだ。今更金澤がクリスマスの特別感をわざわざ演出するとは香穂子には思えない。
「失礼だなー、お前さん。……まあ、俺もやるときゃちゃんとやるってことだ。いいからさっさと店まで移動する! いつまでもこんなとこで油売ってると、予約時間に遅れちまうぞ~」
香穂子の後頭部を掌で軽く叩き、金澤が促す。腑に落ちなくはあったが、別に香穂子もクリスマス的特別扱いが不満なわけでは決してない。
安月給の高校教師生活を経て、一度は諦めた声楽家としての道を再度模索するために、痛めた喉の手術を乗り越え、全盛期までの状態には戻らないがながらも『声楽家』という肩書を取り戻して……そのうちに金澤の価値観にも若干の変化が現れてきたということなのだろうか。
金澤が欧州で脚光を浴びていた時期にはもっと洒落た生活をしていたと教えてくれたのは、今は香穂子の母校で理事長を務めている人物だった。テレビで贔屓の野球チームの試合を見つつ、ビールを飲むのがこれ以上にない至福と言い切る些かおっさんくさい金澤の印象しか香穂子は持っていないから意外に感じるだけで、案外こういう時にはそつのない男なのかもしれない。
「うーん、紘人さんって結構奥深いな。まだまだ私も修行が足りないか……」
それなりに長く付き合っているはずなのに、まだ自分の知らない一面を金澤が持っている。人によっては落ち込みの原因になりそうな事実を前向きに捉えられるのが、香穂子のいいところでもあった。
「……何をぶつくさ言ってるんだか」
そんな香穂子に苦笑しつつ、金澤は小さく肩を竦めるのだった。
予約されていたレストランは、こじんまりとしていて落ち着いた色彩で纏められた、それでいて香穂子好みの可愛らしい雰囲気の店だった。香穂子たち以外の個室に案内されていく客はネットでの評判通りカップルが多く、そして年齢層は意外に若い。つまりその年代でも無理なく楽しめる、リーズナブルな価格帯なのだろうと予測がついた。更に理由は他にもあり、金澤曰く完全個室なので多少マナーに疎くても困らないという利点があるらしい。
「メシを楽しむのが第一だからな。ここならお前さんも肩肘張らずに済むだろ」
ウェイターに案内されて予約した個室へと向かう途中、にやにやと意地悪く笑いながら金澤が言うので、ついつい香穂子はその背中をつねり上げた。金澤が悲鳴を呑み込んで香穂子を睨んできたが、香穂子も不機嫌に視線を反らすのみで、報復は一応その辺で留めておく。せっかく久しぶりに二人で逢えたのだし、初っ端から空気をギスギスとしたものにはしたくない。どの辺りまでが冗談で収まるのか、その匙加減については金澤も香穂子も互いの許容範囲をきちんと把握している。
仕事上の付き合いも多いため、香穂子も一通り困らない程度のマナーは身に着けているが、確かに金澤の指摘通り、意識せずに自然に振る舞えるほどには充分に浸透し切れていない。どこかでボロが出てしまわないかと緊張を強いられるのには違いがないので、あまり気にせずにいられるのであればもちろんその方が香穂子には都合がよかった。
そもそも金澤自身がそういう格式張った雰囲気を好まないはずなのだが、それでも香穂子と違い、金澤はいざ相応の振る舞いを要求されるなら、気負うことなく難なく対応できる技量があるのだということも香穂子は知っていた。それは香穂子が年齢を重ねて少しは成長できたように思えても、どうしても埋められない、金澤との積み重ねた年月の差だった。
以前はそんな自分の幼さに焦って、無理に背伸びをしたりして、逆に金澤をハラハラさせていた香穂子だったが、そんな幼い自分こそが自分だと呑み込めるようになった点では、今は少しは大人になれたのではないかと自負している。香穂子がその境地に達するまで、気長に待っていてくれた金澤には、もちろん感謝しかない。
部屋に通され、金澤は羽織っていたコートを脱いでウェイターに預ける。特にドレスコードが決められている店ではないが、さすがに普段着で来店するのは憚られる雰囲気のためか、金澤にしては珍しく落ち着いた深い闇色のスーツ姿だった。ステージでのタキシード姿なら見慣れているはずなのに、スーツとネクタイというスタイルは逆に新鮮で、香穂子はついつい見とれてしまう。
「お客様も、コートをお預かりいたします」
ウェイターに促されるまでぼんやりと金澤を見つめていた香穂子が、慌てて自分のコートを脱ぎ、ウェイターに預ける。ドアの側に備え付けられた小さなクローゼットに二人分のコートを丁寧に片付けたウェイターが、「では飲み物をお持ちいたします」と恭しく一礼して、部屋を出て行った。
「なーにをぼーっとしてたんだか。もしや、俺があんまりにもカッコいいから見とれてたのか―?」
席に着きながら呆れたように笑う金澤に、香穂子は思わず素直に頷いてしまう。からかうつもりの言葉に真面目な反応をされた金澤が、逆に驚いたように目を丸くした。
「あの……カッコいいです。すごく」
「そ、そうか? なら、タンスの奥で化石になりかけてたコイツを引っ張り出してきた甲斐があったってもんだな」
満更でもない風で微笑む金澤に、「だから写真撮っていいですか!」と香穂子が携帯電話を構えると、途端に表情をひきつらせた金澤が立ち上がって香穂子の掲げた携帯を片手で掴み、全力で拒否する。
写真を撮って香穂子だけが眺めるのなら金澤の許容範囲内だが、この前のめりっぷりでは香穂子が自慢がてら自分の仲のいい友人たちへデータを送りつけることが目に見えている。そこには更に情報を方々へ拡散させる「天羽菜美」というファクターがあることを、金澤は過去の経験から嫌というほど熟知していた。
食事前の一悶着に区切りをつけ気を取り直した二人は、前菜から始まり、メイン料理、スープ、サラダとタイミングよく次々に運ばれてくるお洒落な創作料理を充分に堪能していく。
室内には邪魔にならない程度の音量で明るい曲調のクラシック曲が流れており、ここ最近街に溢れているクリスマスソングに辟易していた二人は、その季節に迎合しない選曲にも感心した。料理の味付けも香穂子好みだったが、更にその料理の盛り付け方や食器などにもこだわりがあり、その一つ一つがいちいち可愛らしいものだった。新しいメニューが運ばれてくるたびに香穂子が喜んで歓声をあげるのを、金澤が微笑ましげに見守っている。
やがて次がデザートという段階で、空いた皿を片付けに来たウェイターが何事かを金澤に耳打ちし、僅かに緊張を含んだ表情で金澤が頷く。狭い個室だが、先程から流れているクラシック音楽に阻まれてその会話は香穂子の耳までは届かない。
そういえば、この店は金澤の仕事関係の伝手で選ぶと言っていた。もしかしてこの店のオーナーか、はたまたシェフか……そういう人が挨拶のために金澤を呼んでいるのかもしれない。そう考えた香穂子の予想はそこまで外れてはいないようで、布ナプキンを外してテーブルの片隅に置いた金澤が、ふと席を立った。
「……あー、お前さん。悪いがちょっと所用を片付けてくるから、しばらく一人で食べててくれるか? そんなに時間はかからずに戻れるとは思うが」
「あ、大丈夫です。私の事は気にせずに、ゆっくり行って来てください」
笑顔で香穂子が片手を振ると、金澤は苦笑しつつもドアを開けて待っていたウェイターに導かれるようにして部屋を出て行った。
香穂子一人が残された室内は、先程と同じクラシック音楽が続いて流れていたが、何だか急にその音量が大きくなったような気がする。自分が食器で奏でる音も、幾分か音量を増した気がして耳障りだ。少し経つと、先程まで給仕をしてくれていたウェイターとは別の人物が二人分のデザートを運んできて、香穂子の目の前に置いてくれる。本来なら飲み物は最後に出て来るものだが、デザートのケーキに合わせてか同時にテーブルに並べられた。
「では、どうぞごゆっくりお楽しみください」
部屋を出ていく上品な笑顔のウェイターに会釈を返しつつ、扉が閉まった途端、香穂子は思わず小さな溜息を吐く。目の前に置かれたケーキはこれまで通り可愛らしく、またとても美味しそうで、実に香穂子の好みなのに先程までの浮かれきった気持ちが何となく出てこない。
……すぐに戻って来るとは言っていたし、こんなに素敵なフルコースを楽しませてもらったのだ、お礼の一つも言って来てくれていいと思っているのに、それでも目の前に金澤がいてくれないと、こんなふうに気持ちが下降気味になる。
食べていていいとは言われたけれど、やはり金澤を待って、二人で美味しく食べたいと、香穂子は甘いチョコレートケーキを引き立てる苦いエスプレッソを一口含んだ。
そのタイミングで、扉が軽くノックされた。料理はデザートとコーヒーが届いているので、もうこれ以上のメニューはないはずだ。ならば金澤が戻ってきたのかもしれないが、そんなに時間がかからないとは言ってはいたものの、挨拶周りに行っていたならば逆に早すぎる。つい警戒しつつ、恐る恐る「……はい?」と小さく香穂子が答えると、徐にドアが大きく開く。
そして狭い個室の中が、突然華やかな色に彩られる。
「……えっ!?」
思わず香穂子が驚きの声を上げると、有無を言わさぬ勢いで、香穂子の両手の中にその明るい色彩が放り込まれる。慌てて反射的に受け取ってしまった香穂子は、腕の中のものと、それを放り投げてきた人物を代わる代わるに見比べた。
当然のことながら、香穂子の腕の中のものを放り投げて寄越した人物は金澤だった。そして、香穂子が受け取ったものは、香穂子の両腕に収まるくらいの小さな花束だ。色彩豊かなバラの花が綺麗にアレンジメントされている。
「これ……」
「まあ、何だ。ちょっと早めのクリスマスプレゼントっつーか……お前さんに、だ」
照れくさいのか、視線を反らしたまま、ぽつぽつと金澤が告げる。香穂子は改めて受け取った花束を見つめる。
色は様々だが、バラだけで纏められた花束。その本数は何度数え直してみても、12本、1ダース。
……金澤は、記念日や祝い事の類を気にするようなタイプじゃないし、興味も薄い。
だが決して『知らない』わけではない。
食事のマナーやお洒落なお店だって、柄じゃないから使わないだけであって、それが必要となれば選び出して使いこなすことが出来る。金澤自身が言っていたように、『やるときゃきちんとやる』、大人の男性なのだ。
「……伊達や酔狂でやってるわけじゃなくてだな、一応この花には意味があって……」
何かを説明しかけた金澤を片手で制し、香穂子は自分の腕の中の花束を見る。赤、白、ピンク、オレンジ……少し思い悩んで、白色のバラを一本抜き取った。そのまま呆気にとられている金澤のスーツの胸元のポケットに挿し込む。
これが正解かどうかは分からない。緊張の面持ちで金澤の反応を伺っていると、先程の香穂子と同じように、香穂子の顔と自分の胸元の白バラを見比べていた金澤が、安堵とも呆れとも取れる溜息を付いて、小さく苦笑を漏らす。
「……知ってたか、お前さん」
ああ、やはり。香穂子の解釈は間違っていなかった。
12月12日。ダズンローズデー。香穂子がこのレストランを調べていた時に、偶然リンクしていた花屋のホームページで紹介されていた記念日だ。
この日に贈られる12本のバラの花には、それぞれ感謝・誠実・幸福・信頼・希望・愛情・情熱・真実・尊敬・栄光・努力・永遠の12の意味が込められている。
欧米では12本のバラの花束を恋人に贈ると幸せになれるという習慣があり、ダズンローズデーはそれに因んだ記念日ということだったが、12種の言葉を相手に全て捧げるということで、プロポーズの演出としても使われると記してあった。
そしてそれを受け入れる場合は、花束の中から一輪を相手の胸に挿すのだと。
「……ここまでやっといて今更何だと思うかもしれんが、正直なところ俺は、お前さんにはもっとふさわしい相手がいるんじゃないかっていまだに思ってるんだよな」
「紘人さん……」
咎めるような香穂子の口調に、金澤は苦笑して首を横に振る。
「まあまあ、とにかく最後まで聞いてくれや。……お前さんは若い。更にその年でいろんな楽団から声がかかる、才能溢れる立派なヴァイオリニストでもある。わざわざ好き好んで俺のようなおっさんを選ばんでもよかろう。もっとお前さんに合った男が別にいるだろうと、我ながら後ろ向きに考えるわけだ」
だがな、と金澤は続ける。
「じゃあ、逆方向で考えてみる。果たしてこの先、俺がお前さん以外の誰かを、今のお前さんに向けるのと同じような感情で想えるのかってな。……するとこれが不思議なことに、全く考えられない。そうなれば、年も年だし、そろそろはっきり結論を出しておくべきじゃないかと思ってな。柄でもないが、ちょっと知り合いに協力してもらって、一応サプライズってやつを計画してみた」
言いながら、金澤は後ろ手に隠していたものを香穂子の目の前に差し出す。手のひらに収まるサイズの小さな箱。ここまでお膳立てされて、その中身の予想がつかないほど香穂子は察しが悪くはない。
金澤が、一つ咳払いをする。
「俺と、結婚してくれるか? 香穂子。……まあ、自信持って幸せにしてやるとは言い辛いが……俺に出来得る限り、大切にする」
「……そこは、自信持って幸せにしてやるって言うところじゃないですか? 多少はハッタリでも」
「根拠のない自信は持てないんだ。何せ年が年なだけに、現実が無駄に良く見えててな」
思わず吹き出して香穂子が突っ込むと、溜息交じりに金澤が答える。過小評価過ぎるとは思うが、ボーダーラインを低めに見積もるのは、金澤なりに自分の発言を嘘にしてしまわないための予防線なのだと香穂子も分かっている。
差し出されている箱に指先で触れ、上目遣いに金澤を見つめながら香穂子が呟く。
「それに、一応私もちゃんと返事したつもりなんですけど。そこは無視なんですか?」
贈られた12本のバラを1本胸元へ返すのは、承諾の証のはずだ。更に香穂子は返すバラに白を選んだ。白バラの花言葉は「純潔、あなたにふさわしい、深い尊敬、相思相愛」。……金澤の元へ嫁ぐ意味合いを含めて返したバラだったのだ。
「……花言葉まで、俺が詳しく把握してる訳がなかろうに」
それに、と金澤は苦笑する。
「サプライズはサプライズとして、お前さんにはちゃんとはっきり言葉で伝えておかないと、『察してくれ』で濁しちまうと、後でどれだけ恨み言を言われるか分からんからな」
確かにこれまでいろいろと金澤の本心を巡って、「皆まで言わずとも分かろう」という金澤の態度に、香穂子が不満を訴えていたことも事実だ。そこを指摘されると反論の言葉がない。
「そういうわけで、だ。俺は俺なりに、俺にできる最大限でストレートにお前さんに伝えてみたつもりだが、お前さんの方はどう答えてくれるんだ?」
そう促され、香穂子は悩む。
香穂子としては承諾の意は返したつもりだが、金澤は違うものを要求している。
要するに金澤がダズンローズにあやかっただけでなく、きちんと言葉でプロポーズしたことに対して、それ相応のものを返すように要求されているのだということは分かる。指輪を受け取って、それで「はい」と頷けば、一応言葉で返したということで、納得してもらえるのだろうか。
何か、足りないんじゃないのかな、と香穂子は思う。いや、金澤はちゃんと言葉で返せばそれで満足してくれるような気がする。それが足りないように思えるのは、やはりこのサプライズを香穂子がとても嬉しく思ったからだ。
……正直、いつかは言ってもらえるだろうという期待はあった。それでもこんなに早く金澤が決断してくれるとは思わなかった。仕事が順調だとか、自分の年齢を顧みてだとか、金澤なりに決断する理由があったにしてもだ。
だからこそ、香穂子もその金澤の決断に報いたいのだ。
「言葉で、言葉で」と懸命に想いを巡らせて、香穂子は頬を赤く染めながら、またちらりと上目遣いに金澤を見上げた。
「……か、金澤香穂子になります……と、か?」
呆気にとられた金澤が次の瞬間に盛大に吹き出す。「そこまで笑いますか!?」と憤慨する香穂子の片手の中に指輪の箱を押し込んで、肩を震わせたままの金澤が香穂子の細い身体を抱き寄せた。
「いや『喜んで』程度のことを言ってもらえればそれで満足だったんだが、ほんっとにお前さんはこっちの予想の遥か上を軽々と飛んでくれるなあ」
「喜んでますけど! 謹んでお受けしますけど! それ以外の別の言葉って考えても他に出てこないし」
「……うん、まあ。奇を衒った発言じゃなくても、普通に「喜んで」って受けてくれたら俺はそれで嬉しかったんだがな」
それならそうと言ってくれればいいのに、と尖らせた香穂子の唇に、軽く金澤の唇が触れる。
ぱちりと大きく瞬きをした香穂子が、ふと解けるように笑い、そして二人はまた、あまり深まることのない触れるだけの優しくて長いキスを交わす。
それはまるで、誓いのキスのように。
改めて二人で椅子に腰かけ、冷めかけたエスプレッソと甘い甘いチョコレートケーキを堪能している時に、ふと香穂子が思い出して指輪のケースを金澤に差し出す。
甘すぎる、とぼやきながらチョコレートケーキの欠片をしかめ面で口に運んでいる金澤に、香穂子が「これ、せっかくだから嵌めてください」と強請るのを、金澤は片手をひらりと振って一蹴する。
「デザートの片手間に嵌めるもんじゃないだろ。慌てる必要もなし、後々の楽しみにとっておけって」
「後って……いつですか?」
きょとんとして真っ直ぐに金澤を見つめ返す香穂子に、意味ありげに金澤は笑う。
「まさか、デートがここで終わりってことでもないだろ。……いい大人が揃いも揃って、さ」
今夜の宿で、ゆっくりなと囁かれ、また真っ赤に染まる香穂子が「スケベ親父!」とテーブルの下で金澤の脛辺りを蹴りつける。
お前さんな……と脛をさすりつつ睨み付けてくる金澤から視線を反らし、香穂子は口の中の甘い甘いチョコレートケーキをじっくりと味わうことにする。
今日という記念日が、このチョコレートケーキくらい、ただただ甘さに満ちて終わることを祈りながら。
あとがきという名の言い訳
氷渡くんと違って、もっと突っ込んだ形のダズンローズデー(笑)
このCPに関しては、金やんがどれだけ煮え切るかが全てだと思うので、いざとなれば一番展開が早いCPではないかと思います。
サプライズがどこから始まっているかというと、金やんが日付を指定してきたところから始まってます(笑)その後の謎解きをするのかしないのか……香穂ちゃんが気にしてないのなら、金やんは全てを暴露はしないと思うのですが。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2019.05.01