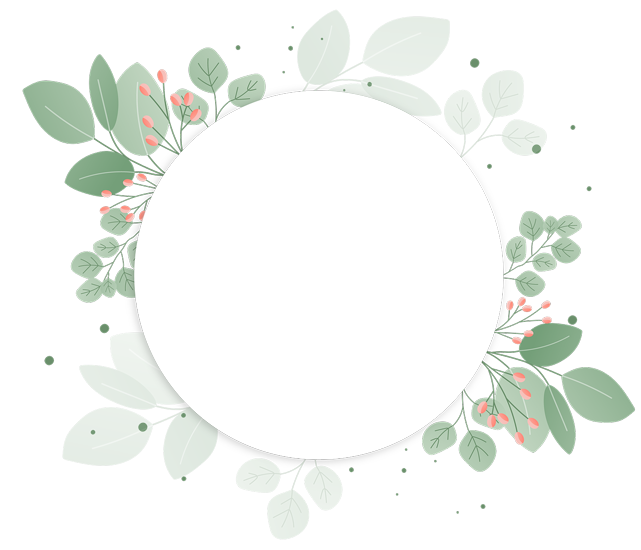どちらかと言えば、かなでは朝に弱い方なのだが、今日は珍しく早い時間に目を覚ますことが出来た。だが、あれやこれやと準備をしているうちに、結局は待ち合わせの場所には時間ギリギリの到着という、いつも通りの事態に収まりそうな予感だ。
ちなみに、待ち合わせ相手である如月響也もかなでと同じ菩提樹寮の男子棟で暮らしているため出発点は同じだが、どうせならせっかくのデート気分をしっかりと味わおうと、駅前の時計台の前で落ち合うことをかなでの方から提案した。
当然のことながら、そういうかなでのロマンチシズムにあまり理解が深くない響也には「マジで面倒くせえ!」と、かなり不評だったのだが。
かなでは去年の夏、自分自身のヴァイオリンを成長させるため、故郷の長野を離れ、幼馴染みで響也の兄でもある律が通う横浜の星奏学院音楽科に編入してきた。そしてまた響也もかなでに巻き込まれる形で、星奏学院への編入を余儀なくされたのだ。
自分の意志で進路を決めたかなでだが、暮らし慣れた故郷を離れることには、一抹の不安もあった。だからこそ、幼い頃からずっと傍にいた響也が一緒に横浜へ来てくれたことを、とても心強く感じていた。
そして、横浜でアンサンブルコンクールに纏わる数々の出来事を経験するうちに、二人は想いを寄せ合うようになり、コンクール後には幼馴染みから恋人という関係性へと変化した。だが、そうなったからと言って、幼い頃から積み上げてきたお互いの距離感はいきなり劇的に変わるものではない。故郷にいる頃から、あまりにいつも一緒に居過ぎるために、周囲からは『夫婦』とからかわれ続けていたのだが、それが冗談から事実になったという程度のものである。
もちろん二人の心情的にはこれまでとはまるで感覚が違うのだが、周囲から見れば、以前も今も、相変わらずいつも一緒にいる二人なのだろう。
だからこそ、そのまま二人で連れ立って菩提樹寮から出かけるのは、登下校の風景と大して変わらないのではないかとかなでは思うのだ。せっかくの『デート』なのだから、少しは普段と違う感覚を味わってみても、別に罰は当たらないはずだ。
それに、昨日の就寝時まではかなでに対し、ぶつぶつと聞こえよがしの不平不満を漏らしていた響也も、今朝かなでが諸々の準備を終え出かける時刻には、既に菩提樹寮から姿を消していた。響也もそれなりに納得してくれたのだろうと、かなではポジティブに考えることにした。
「さて、時間は……と」
せっかく響也がかなでの我儘を受け入れてくれたのだから、せめて遅刻はないようにと、かなでは早足で待ち合わせ場所へ向かいながら、バッグの中から携帯を取り出し、改めてディスプレイに表示されている時刻を確認する。
約束の時刻まで、残り十数分の時刻と共に表示される一つの単語がある。それは、今日という記念日の、名称だった。
この記念日の存在を知ったのは、全くの偶然だった。
かなでの携帯電話に日付に合わせた記念日の名称を表示する機能が内蔵されているのは知っていたが、どちらかと言えばそれほど記念日等にこだわりを持たないかなでは、当日にその記念日の名を知っては「そうなんだ」と感心するだけで終わっていた。そしてその機能はスケジュール帳とも連動しているらしく、オーケストラ部の予定を確認するために眺めていたカレンダーの中にあったこの記念日に、ふと目が止まった。
5月23日。かなではこの記念日を是非響也と一緒に過ごしたいと考えた。それはここ最近、ずっとかなでの胸の中でもやもやと燻っている想いがあったからだ。それを解決する一手として、この記念日を利用することをかなでは思い付いた。
かなで以上にイベントの類を気にしないように見える響也は、当然今日が何の日かなど知らないだろう。おそらく、知ったところで「えらくしょーもねー記念日だな」と呆れられそうな気もする。
だがかなでにとっては、何だか今の自分の気持ちを響也に伝えるためには、一番ふさわしい記念日であるような気がしたのだ。
「ごめん、響也。待った?」
時計台側の噴水の縁に腰かけ、手持無沙汰な様子で自分の携帯の画面を眺めていた響也のところへ、かなでが声をかけつつ駆け寄って行くと、顔を上げた響也が面白そうに笑った。
「お、それ待ち合わせの定番文句だよな。お前から聞くと、何か新鮮」
言われてみれば、確かにかなでが響也に対し、この言葉を使う機会はあまりないかもしれない。何のことはない、お互いの行動パターンがあまりにも似通っていて、改めて待ち合わせをすることが皆無に等しいからだ。
「まあ俺達の場合、デートらしく待ち合わせるってんなら、どっちかが先に菩提樹寮出て待つしかねえもんな。丁度いい時間に二人とも着こうとすりゃ、結局同じ時間に寮出る羽目になるんだからさ。……ったく、お前って、ホントしょうもねえこと思いつくよなあ」
口調は不満げなままだったが、そう言う響也の表情は穏やかで、変わらず笑顔のままだった。本気で呆れているわけではないことは分かる。
かなではほっと安堵の息を付いた。
そんなかなでから視線を反らし、片手で弄んでいた携帯をジーンズのポケットに押し込みつつ、響也が噴水の縁から立ち上がった。
「……で? 結局今日はどこに行くんだよ」
「え? ……えっーとね……」
改めて問われ、かなでが口籠る。
実は今日のかなでの一番の目的は、デート終わりに昨夜準備したバッグの中の物を響也に渡すことなのだ。勿論、菩提樹寮の中でも渡すことは充分可能だったのだが、他の寮生の目に止まると面倒な事になりそうで、デートを口実にとにかく響也を寮の外へ誘い出したかった。そのため、肝心なデートの内容の方は無計画なままだった。
「あの……適当にぶらぶらして……とにかく最後にどこか静かな場所で、二人でゆっくり話が出来ればいいんだけど」
「はあ? ……何だそりゃ?」
呆れた響也の声に責められる予感がして、かなでは思わず身を小さくする。
そもそも、初っ端の待ち合わせの件からかなでの我儘に付き合わせているので、響也が嫌だ、帰ると言っても文句は言えない。不安になりながら上目遣いに響也を見つめると、ちらりとかなでを見下ろし、小さく溜息を付いた響也が手を伸ばし、かなでの小さな手を、手の甲の上から覆うようにそっと握った。
「ゲーセンとかカラオケもいい加減飽きたしな。最後に静かな場所っていうと、丘公園、大さん橋……山下公園ってとこか? じゃあ、中華街か山手に行ってみっか。結構歩くことになると思うけど、お前大丈夫か?」
「う、うん」
「よし、決まりだな!」
笑った響也が、握ったかなでの手をまるでエスコートするかのように引いて、先に立って歩き出す。響也に導かれるようにして、二人は駅の改札を前後して通り抜けた。
そんな響也の、どこか楽しげな様子に、案外彼も今日のデートを楽しみにしていてくれていたのかもしれないと、かなでは何だか嬉しい気持ちになるのだった。
その後二人は港の見える丘公園で景色を堪能した後、中華街に向かい、せっかくだから長野の家族に横浜土産でも送ろうかという思い立ち、店先を端から端へ万遍なく冷やかして歩く。時折小龍包や中華まんなど、食べ歩き出来るものを仕入れては休息を取りつつ、じっくりと一軒一軒店を眺めて歩いていると、驚くほどあっという間に時間が過ぎていった。
長時間歩きっ放しなので、身体的な疲労は当然あるものの、初夏の気候は心地良く、天気も快晴で、絶好の観光日和だ。
何より響也と二人、他愛ない会話を交わしながら、様々な店に立ち寄るのは想像以上に楽しかった。
そして日暮れよりも少し早い時間に、最終目的地の山下公園へ辿り着いた二人は、さすがに疲労困憊で、大きな溜息と共に、並んでベンチにへたり込んだ。
山下公園を最終目的地に決めたのは響也の意見だったが、かなでは初め、逆に山下公園から最後に港の見える丘公園に辿り着く案を推していた。ゆっくり話すのが一番の目的なのだから、見晴らしのいい丘公園で過ごすのがいいと思ったからだ。
だが、これには響也が難色を示した。その理由が今になってかなでにも理解できる。確かに散々歩き回った後であの急勾配を登って、また下りて帰宅するというのは、かなりの重労働だっただろう。
「あー、さすがに歩き疲れたな。しばらくは動けねえかも。……中華街も、じっくり見て回れば、それなりに時間かかるもんだな」
ベンチの背もたれに体重を預け、響也が天を仰いだ。
「でも、お店見て回るの面白かったね。お母さんたち、お土産喜んでくれるといいなあ」
二人でああでもないこうでもないと思案しつつ、店から店へ様々な土産物を物色して歩いて、結局田舎に送ったのは、人気が高いと評判の月餅や中華まんなどの定番の品だった。
好奇心の強い……響也の言うところの『ゲテモノ食い』であるかなでは、あまり目にしない風変わりなものを選びたがったのだが、「自分で食う土産じゃねえんだから、定番の方が外さねえって」と呆れ顔の響也に止められたのだ。
「まあ、かなでが選んだんなら、ゲテモノでも何でも、喜んでくれるんだろうけどな。……ジイさんは特にな」
かなでという孫を溺愛していた彼女の祖父のことを思い出し、響也が笑う。何せ、かなでを心配するあまり、響也を星奏へ編入させた張本人だ。「そうだね」とかなでも笑って頷いた。
「さてと……で、こっからは?」
笑いをおさめ、響也がかなでに向き直った。
かなでは小さく首を傾げ、鸚鵡返しに尋ねた。
「『こっからは?』って?」
「いや、だから。そもそもオレに何か言いたいことあったから、今日誘ってきたんじゃねえのかよ。……ゆっくり話したかったんだろ?」
「……あ」
思わず口元に掌を当てると、「……まさか、忘れてたとか言わねえよな?」と響也が不愉快そうに眉間に皺を寄せた。
「もちろん、忘れてない! ……忘れては、いないんだけど……」
特にこれという目的もなかった、本日のデート。
気候も天気も文句なし、ただ歩き回るだけの時間が、響也と一緒だと想像以上に心地良かった。本来目的だったことが、何だかとっても小さなことだと、思ってしまうくらいに。
「あの……今になってみると、それは別にもういいかなとか思っちゃったりもしなくもなくて」
「結局どっちだよ。……まあ、『もういい』って思えるくらいの話なら、別にいいんだけどさ。お前に改まって話とか言われると、何か深刻な悩み事でも抱えてんじゃねえかって、心配になるからな」
どこか安堵したように、小さく息を付いて響也が笑うので。
その笑顔を目にしたかなでの気持ちも、何だか暖かくなる。
……ああ、何だろう。本当に今更なんだけど。
そういう何気ない響也の笑顔に、かなでもとても安心する。
本当に、昔から自分は響也のことが大好きだったんだなと、改めてかなでは気付かされた。
……そうだ、だからこそ。
かなでは、本来の目的を達成しなければならない。
ちゃんと響也に伝えなければならない気持ちがあるのだ。
「……あのね、響也。今日って何の日か知ってる?」
「は? 今日?」
突然のかなでの問いに、響也は顔をしかめて空を睨む。
今日は5月23日。お互いの誕生日でもなければ、身近な誰かの誕生日というわけでもない。当然、クリスマスやバレンタインなどの記念日でもない。
もしかして付き合って何日目等の、細かい自己設定の記念日なのだろうかと響也は思い到る。付き合い始めはそれなりに気にかけていたそういう記念日も、ここまで月日が経ってしまうと、逆にそんな細かいものはいちいち気にしなくなってしまう。
「……悪ぃ、降参。何かあったっけか?」
こういう時、長年の付き合いから響也は、変に誤魔化したり適当なことを言うよりも、素直に白状してしまう方がかなでが怒らないことを知っている。あっさり白旗を上げると、そんな響也の答えは予測が付いていたのだろう、特に表情を変えることなく、かなでが軽く頷き、バッグから取り出した自分の携帯をいじって、響也の鼻先に掲げて見せた。
「何……」
反射的に身を引きつつ、響也は視界に広がったかなでの携帯の画面を見つめる。デジタルの時刻表示の下に、小さく綴られている文字があった。
「……『ラブレターの日』?」
「面白いでしょ?」
携帯の陰から顔を出したかなでが、にっこりと邪気なく笑った。
「これ、映画の宣伝から出来た記念日らしいんだけど。五で『こい』、二、三、『ふ』『み』で恋文。それで、5月23日がラブレターの日なんだって」
「へえ。……そういや最近、語呂合わせでいろいろ変な記念日あるんだよな。7月10日が納豆の日とか、2月22日が『ニャー』3つで猫の日とかさ」
「そうそう」
こくこくと笑って頷きつつ携帯を下ろしたかなでは一転、今度は何処か緊張した面持ちで、ごそごそと自分のバッグの中を漁り始めた。
一体何が始まったのかと成り行きを見守る響也の鼻先に、かなでは取り出した『何か』を勢いよく突き付けた。
「だから……コレあげる!」
「これって……」
それは、一枚の薄い封書だった。かなでが好みそうな薄いブルー地に小花柄の可愛らしい封筒の表には、見慣れた少し癖のある丸っこいかなでの字で『如月響也さま』と書かれている。指先で差し出された封書を摘まみ取り、そのままひっくり返せば、ご丁寧に『小日向かなでより』と送り主の名まで書かれている。
「……つまりこれが、お前からオレへのラブレターってこと?」
ここまでの話の流れから当然分かり切ってはいたけれど、そこを敢えて念押しで確認すると、途端にかなでが耳まで真っ赤に染まる。
「そ、そうなんだけど。ラブレターっていうほどじゃなくて、ただ、なかなか面と向かって言えないことってあるから、この機会にちゃんと響也に伝えたいなって思って……」
「へーえ?」
興味深げに響也は、手に取った薄い封筒を裏へ表へひっくり返し、午後の陽の光に透かしてみる。そして封を開けようと、徐に糊付けされた部分に指先を引っかけると、かなでが悲鳴を上げて、封書を持つ響也の腕に飛び付いた。
「ちょ……っ、待って待って! 駄目だよ響也! それは私の目の前じゃなくて、菩提樹寮に帰ってから開けて読んで!!」
「今更何言ってんだよ。だいたい、こういうのってその場で読むのが礼儀ってもんだろ?」
封書を取り返そうと懸命に伸ばされるかなでの手を避けつつ、響也は器用に空中で封を開き、中から二つ折りにされた、封筒とお揃いの色の便箋を抜き取る。更に悲鳴を上げたかなでが、弾かれたようにベンチから立ち上がった。
「じゃじゃじゃじゃあ、私、飲み物でも買ってくる! だから、せめて私がいないうちにさっさと読んじゃって!!」
「りょーぉかい。あ、オレ、ジンジャーエールな」
勝ち誇った笑顔で注文を告げ、早く行けとばかりにひらひらと片手を振ってやると、かなでがむうっと頬を膨らませる。「さて、と」と片膝を立て、これ見よがしに便箋を開こうとすると、ひいっと怖いものでも見たような声を漏らして、かなでが脱兎のごとくその場を逃げ出した。
「……そこまで嫌がるか? かなでのヤツ、どんなこと書きやがったんだか……」
苦笑しながら、響也はかなでのころころとした小さな文字が並ぶ紙面に目を向ける。……如月響也さま。
如月響也さま
何か、改めて手紙を書くとなると何を書いていいのか分からなくなるんだけど、
響也の目の前ではなかなか恥ずかしくて言えないと思うので、
がんばって私の気持ちを書いてみます。
いつも、ワガママ言って響也に迷惑ばかりかけて、本当にごめんなさい。
星奏学院に編入するときも、ホントは全然響也は乗り気じゃなかったのに、
それでも私のこと心配して一緒に横浜まで来てくれたこと。
面と向かってはなかなか言えなかったけど、すごくうれしかったし、
今もとてもとても、響也に感謝しています。
「……んだよ、今更」
文字を追いながら、急に頬が熱くなるのが分かって、響也は無意識に手の甲で隠すように頬を覆う。
かなでは今まで一度だって、響也を巻き込んだことを悪いと思っている素振りを見せたことがなかった。
脳天気に笑って、時折愚痴を言う響也に「だったら別に一緒に来なくてもよかったのに」と悪態をついていた……だから、全く気にしていないのだと思っていた。
成程、これは確かにかなでが逃げ出すほどに恥ずかしい……かなでが心の奥にずっと隠したままだった、かなでの本心の言葉なのだろう。
あの夏のコンクールで、いろいろ大変なこともあったけど、
響也がいたからこそ乗り越えられたことがいっぱいありました。
私にとって響也がどれほど大事な人だったのか分かったので、
響也には迷惑だったかもしれないんだけど、コンクールで優勝できたことも含めて、
横浜に来て本当によかったと思ってます。
「まあ、それはオレもそうだよな……」
かなでが綴った言葉に、響也は素直に相槌を打つ。
かなでにとって響也の存在の大きさが分かったように、響也も自分の中にあるかなでとヴァイオリンの大切さが実感できた夏だった。
おそらく、自分たちはあの夏のコンクールを通して、当たり前のように隣にあった互いと音楽というものの存在が、自分たちにとってどれほど大事なものだったのかを思い知らされたのだ。
納得しながら、響也の視線は文面の先へと進む。
「……『これからも』」
これからもずっと、私が響也の隣に、一番近くにいられたら幸せだなあと思ってます。
私のことをいつも見守ってくれる、大事にしてくれる。
そんな響也のことが、本当に、心から。
世界中の誰よりも、大好きです。
小日向かなでより
「……っ!」
思わず片手で口元を覆い、響也は絶句する。先程の比じゃなく、自分の全身が赤く染まるような心地がした。
思えば、これまで響也が何かかなでの世話を焼くたびに、「大好き!」という言葉は、いつも冗談のように軽く放たれていた。
響也も何度も聞かされるうちに「ハイハイ」と適当にあしらう癖が付いた。それは、付き合い始めてからも変わりない。相変わらずの調子で『大好き』と繰り返すかなでに、響也もいつしかこの言葉をそこまで重く受け止めなくなっていた。
だが、この薄い便箋の上にこれ以上にないほど丁寧に書き綴られた『大好き』の文字は、これまでの響也が知るかなでの『大好き』とは、全く違う種類のもののように思える。それは、聞き慣れたかなでの声で形作られるものではなく、視覚に直接訴えかけてくる『文字』で作られたものだからだろうか。
そう、きっとかなで自身も分かっていた。幼い頃から何度も簡単に使ってきた『大好き』の言葉。今の響也に伝えたい、あの頃とは違うこの言葉の意味が、響也には、上手く伝わってはいなかったこと。
だからこそ、自分の気持ち通りの『大好き』を正しく伝えるために、普段と違う手段で響也にこの言葉を届けることを思いついたのだろう。
響也は顔を上げる。
飲み物を買いに行ったままのかなでは、まだ戻ってくる気配がない。
……ああ、どうして。
こんなに愛おしく想う瞬間に、目の前にかなでがいないんだろう。
(響也、もう読んじゃったかなあ……)
購入したジンジャーエールとアイスティーのペットボトルを抱え、かなでは落ち着きなくうろうろと自販機の前を歩き回る。
小さな便箋一枚の文章だ。別に深読みするものでもないし、数分あれば充分読み終えることができるだろう。当然響也もとっくに読み終わっている頃だと分かってはいるが、なかなか彼の元に戻る勇気が持てない。
「そもそも何で私、アレを夜中に書いたかなあ?」
その場に座り込んで、かなで思わず頭を抱える。
世間一般的に、真夜中の手紙と日記は読み返せる代物ではないと相場が決まっている。せめて日中の明るい時間帯に書いていれば、もう少し冷静な文面が書けたのではないだろうか。
もちろん書いた言葉は嘘じゃない。響也への日頃の感謝と、日々募る彼への想い。
面と向かってはなかなか言えない自分の素直な気持ちを、丁寧に書き記したつもりだ。だけど今思い返せば、それは全部馬鹿正直に伝えなくたってよかったのだ。感謝の気持ちはちゃんと伝えるにしても、最後の数行は余計だった気がする。
「『大好き』とか……」
うわあああっと、その場で転がり回りそうな勢いで、かなではじたばたともがく。
でも付き合い始めて以降、何かの折に響也に好きだと言う機会があっても、以前幼馴染みだった頃に連発してしまった軽い気持ちの「大好き」が災いして、あの頃とは違う、今の「大好き」の意味が、上手く響也に伝わっていない気がしていた。全然違う想いを込めた『大好き』なのに、以前と変わらず「ハイハイ、ありがとさん」と冗談のように受け止められる。
ならば、声じゃなく文字にしたら、ちょっとは違った気持ちで受け止めてもらえるのではないか。そんな時に見つけたこの『ラブレターの日』は、かなでが改めて響也に想いを伝えるために、実に好都合だったのだ。……だが。
「よくよく考えると、私すごく恥ずかしいこと書いてるし! もう、見せなきゃよかったよぅ……」
興奮がピークに達して、今にも泣いてしまいそうだ。ううう、と唸りつつその場にしゃがみ込んでいると、丸めた背中をつんつんと突く指先があった。
「おーい、小日向かなでさーん?」
上から降ってくる聞き慣れたその声に、びくっとかなでが背中を震わせた。
「ったく、お前どこまで飲み物買いに行ってんだよ。なかなか戻ってこねえし、心配すんだろ」
「……響也」
のろのろと顔を上げると、そんなかなでの顔を見るなり、響也が小さく吹き出した。
「何だよ、お前。スゲえ顔! 耳まで真っ赤だし、何か涙ぐんでんし」
「だって」
俯くかなでの前に同じように腰を落とし、響也は視線の高さをかなでに合わせ、指先に挟んだかなでからのラブレターをひらひらと揺らして見せる。
「これ読んだ。……ありがとな。すげえ、嬉しかった」
「……う、ん」
予想外に真剣で落ち着いた様子の響也に拍子抜けしつつ、かなでがこくりと頷く。何故か呆れたように溜息交じりに響也が続けた。
「あのなー、こういうものをだな。お前の言うこと馬鹿正直に聞いて、菩提樹寮に戻ってから読む羽目にならなくてよかったって、つくづく思ったぜ、オレは」
……落とすのはここか。拗ねたように唇を尖らせて、かなでが尋ねる。
「それは、爆笑するから?」
「バーカ」
小さく笑って、響也はかなでの両手を掴むと、よいしょっとその場に立ち上がり、かなでを引っ張り上げる。
立ち尽くしたかなでが、恐る恐る上目遣いに響也の表情を伺うと、想像したものとは違う、響也の真剣な眼差がそこに在った。
弦に鍛えられた硬い指先が、そっとかなでの頬を撫でた。ゆっくり近付いてきた響也の唇が、不意にかなでの唇に触れる。ぱち、と音がしそうなほど大きく瞬いてまじまじと響也を見つめ直すと、頬を染めて微笑んだ響也の腕の中に、ぎゅうっと強く抱き締められた。
「……もし自分の部屋でこれ読んだらさ、オレ絶対、お前のことすげえ触りたくなんのに、朝までずーっと我慢してなきゃならなかったんだぜ。それって、結構拷問だろ?」
力の抜けたかなでの両腕から、二本のペットボトルが落ちて、足元にころころと転がった。「おまっ! オレのは炭酸なのに!」という響也の抗議の声が、触れる部分から振動になって伝わってきた。
「だ、だって、響也がいきなり! だからっ! びっくりしてっ」
「ハイハイ、オレが悪い悪い」
苦笑する響也が腕を緩め、かなでの華奢な身体を解放する。思わず後ずさるかなでを尻目に、身を屈めた響也がかなでの転がしたペットボトルを拾い上げた。
「相変わらずお前って、オレのことがよく分かってねえよな……ってのが、あの手紙からよく分かった」
「わ、分かってなくはないでしょ? だって、ずっと一緒にいたし」
他の誰も知らない響也が落ち込むときに行く場所も、強気の発言の裏に隠された繊細な心根も、かなではちゃんと理解しているつもりだ。
不満げに唇を尖らせて否定するかなでに、ふと空を睨んで考え込んだ響也は、あっさりと頷く。
「……だな。訂正」
響也のどこか冗談交じりだった声が、不意に真剣味を帯びる。
「相変わらずお前、オレがお前のことどんだけ好きかってのが、分かってねえよな」
予想外の言葉に、かなでは思わず息を呑んだ。
そんなかなでの反応から目を反らし、まるで何事もなかったかのような態度で、「ほらよ」と響也はかなでの手の中に、拾ったアイスティーのペットボトルを押し込んだ。
自分のジンジャーエールのペットボトルの中身を不安げに眺めつつ、ぽつりと響也が呟く。
「……『ラブレターの日』か。今日がそういう記念日だって最初に言っといてくれたらさ、オレも書いてきたんだけどな、お前に」
「え! ホント? じゃあ教えておけばよかった!」
「……めっちゃ食いつきやがった」
先程までのどこか緊張した様子が打って変わり、途端に全開の笑顔になったかなでに、くくっ、と喉の奥で響也が笑う。そのシャツの袖を引っ張るかなでが、大きな瞳を期待にキラキラと輝かせて、響也の顔を覗き込んだ。
「ねえ響也、別に今日じゃなくてもいいよ。私、響也からの手紙貰いたい! 手紙なら、大事に残しておけるでしょ」
「……あー、まあ。それはまた来年でいいじゃん。もちろんオレはオレで、お前からの手紙、大事に残しておくからさ」
「ええー」
拗ねたようにかなでが唇を尖らせる。そんなかなでの反応に苦笑しながら、響也は徐に自分の携帯を取り出し、何やら操作をし始めた。ゲーム好きの響也が話しながら携帯をいじるのは別に今に始まったことではないので、かなでも特に気にならず、ただ小さな溜息を付いた。
「……でもまあ、そうだよね。私もそれだけ書くのにすっごい悩んだし、何回も書き直したし……大事な気持ちほど、簡単には書けるものじゃないんだって思った。何より、記念日当日に貰うのが、何か特別って感じするしね」
「そうそう」
「……じゃあ、そろそろ帰る? 一応これで私の今日の目的達成したし、響也も歩き回って疲れたでしょ? あ、でも夕飯は食べて帰らないと。確か今日は寮母さんのお休みの日だったよね」
視線を上げれば、いつの間にか空は夕焼けから夜の色へ移り変わろうとしている。
これ以上は特に予定もないし、菩提樹寮へ戻るにはちょうどいい時間かもしれない。だが今日は、食事の支度をしてくれる寮母の休暇日だったはずなので、夕飯は寮生が各々準備しなければならなかった。
「……いや、まだ帰らねえよ」
「うん、夕飯でしょ? 食べて帰らなきゃね。あ、簡単なものでよかったら帰って私が作ってもいいよ」
これから店に立ち寄って食事をするという手間を考えての提案だったが、響也は首を横に振る。
「……だから、帰らねえっての」
何かしらの操作を終え、響也は携帯を元のように自分のジーンズのポケットに突っ込んだ。そして手を伸ばし、かなでの手をそっと握り締める。
「……泊まるとこ、取った」
「え?」
「オレは、クラスメイトん家で夜通しゲームだって寮のヤツにメールしたから。お前も支倉に何か外泊の言い訳しとけ。あ、でも直接電話で言うのは止めとけよ。お前、上手く嘘付けねえと思うから」
「え? え?」
畳み掛けるように告げられる響也の言葉に、かなでは戸惑う。突然で話の展開が読めない。
かなでの手を握る響也の指先に、ぎゅっと力が込められる。
ひどく真面目な表情で、響也がかなでを見た。
「……言っただろ? 『オレがお前のことをどんだけ好きかお前は全然分かってない』って。お前は言いたいこと言って、それで満足なのかもしれないけどさ、あの手紙見せられて、お前の気持ち知らされて……はいそうですかって、このまま何もなかったみたいに、いつも通りに寮に戻ってそれで終わり……なんて、オレにはできねえんだよ」
どこか切羽詰まるような響也の声に、かなではようやく響也の言わんとしていることに辿り着く。
物心ついた頃から当たり前のように傍にいて、これまで16年と少々。長い年月をかけて育ってきたお互いの想いは、両想いになってからもその成長は緩やかで、実はまだそういう行為はキス止まりであるのは、二人だけの秘密だったりする。
どこまで進むのか、改めて確認するものでもない気がするので、成り行きにまかせていたが、あまりに一緒にいた時間が長すぎて、逆に『変わる』きっかけもなかなか見つけられずにいた。
そして今、その転換期が目の前に来たことに、かなでは気付く。
自分の心臓の在り処が、身体のどの辺りなのか、はっきりと実感できた。
……鼓動って、こんなにうるさくなることがあるんだ。
(ああ、でも。前にも一度、こんなふうに耳が痛くなるくらいの鼓動を聞いた)
……それは響也から、自分への想いを告げられた時だ。
嘘みたいで、夢みたいで。
まるで現実感がなくて、信じられなくて。
でも、これ以上にないくらいに嬉しくて、心の底から幸せだと思った、あの瞬間と同じ鼓動だ。
「あ、あの。響也」
「……まあ、お前がイヤだっつーんなら、無理強いはしねえけど」
ここまで来て、自分のためなのかかなでのためなのか、逃げ道を作ってしまうのが何とも響也らしい。
でも、かなでとしても、今更響也と共に進むと決めた自分の覚悟を疑われるなんて、心外もいいところなのだ。
「そうじゃなくて……ねえ、私ニアに何てメールしたらいいと思う!? 朝は別々に出てきてるし、昨日の夜は手紙書くのでいっぱいいっぱいでニアと話してないから、多分響也とデートしてることは知られてないとは思うんだけど!」
携帯を取り出し、メールの送信画面を表示させながら、心底困ったように眉を八の字の形にしながら、かなでが響也を見上げる。
虚を突かれて、一瞬言葉を失くして。
それから、は、と安堵の息を付いて笑う響也は、「アイツ、無駄に鋭いからなぁ」と愚痴りながら、かなでと一緒にその場に座り込み、聡い彼女の親友にデートの延長がばれないためのアリバイ作りに、ああでもないこうでもないと知恵を絞る。
自然な言い回しに悩みつつ、ようやくまとまった文面を、かなでが懸命に携帯に打ち込んでいると、それを待つ間、落下の衝撃のため封を切るなり溢れ出したジンジャーエールと格闘する響也と、ふと目が合う。
それは、何だか呼吸をするみたいにとても自然に。
磁石が引き合うみたいに、どちらからともなく。
夕暮れの色の世界の中で、唇が触れるだけの。
可愛らしいキスをした。
あとがきという名の言い訳
真っ先にネタが浮かんで、真っ先に書き上げた響かなです。ああ、楽しかった!(笑)
これが書き上がったおかげで、企画を始めようという気になれました。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2016.11.03