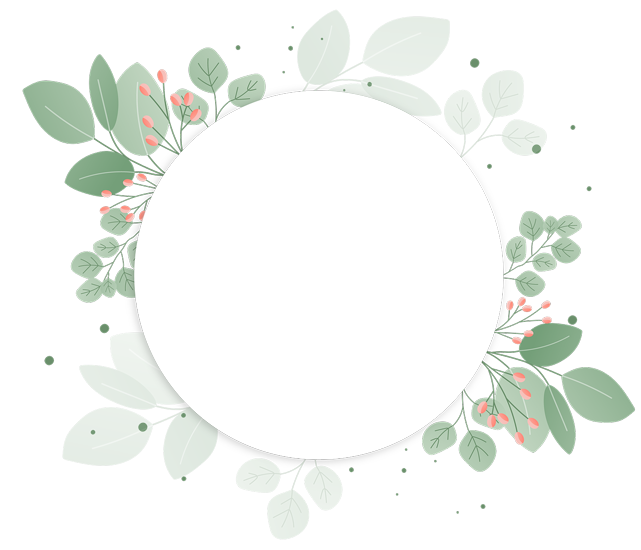至誠館高校吹奏楽部の部室の壁に貼られているカレンダーを眺め、水嶋新が声のトーンを上げた。棚の前で練習に使用した楽譜を整理整頓していた副部長の伊織浩平が、そんな水嶋を振り返った。
「う、うん。ゴールデンウィークに割と集中して練習したから、そろそろお休みも取っておいた方がいいかって……。4月のミーティングの時にちゃんとそう言ったのに、やっぱり新くん、聞いてなかったんだね……」
ここ数年何かと問題を抱えていた吹奏楽部だが、今年の春には無事に数人の新入部員を迎えることが出来た。夏のアンサンブルコンクールでの全国制覇を見据え、ゴールデンウィークに休み返上で猛特訓を行ったのだが、その過密スケジュールに一人の脱落者も出すことなく、新生・吹奏楽部は無事に軌道に乗ったと言える。
実力的にはまだまだではあるが、このまま地道に練習を重ねていけば、去年の雪辱を果たすことも夢ではないと、伊織も、そして現在の吹奏楽部を率いる火積司郎も安堵しているところだった。
そして今後吹奏楽部の厳しい練習に食らいついてこれるのか、新入部員の根性と心意気を見るために、ゴールデンウィーク返上で練習を行うことは、そもそも4月の入部期間で行ったミーティングの際に通告していた。それを達成した暁には休息を与えるということも。
その場には唯一の2年生である新も同席していたのだが、伊織の記憶にある限り、「火積部長の話って、真面目だからか、何かやたらと眠たくなりますよね……」とぼやきつつ、机に突っ伏していた姿しか思い浮かばない。当然、火積は苦虫をこれでもかと噛み潰したような渋面で握り拳を固めていたが、せっかく入部してくれた新1年生の目前でいきなりの鉄拳制裁はどうかと思ったのか、拳を固めるだけに留めていた。
「でもいきなり言われても、予定の立てようがなくて困っちゃいますよう。どうせなら、先週とかに『来週の土日の練習お休みです!』って宣言してくれたらよかったのにぃ~」
「み、ミーティングでも言ってるし、スケジュール表にも書いてあるし、わざわざ言う必要がなかったからだと思うけど……。火積くんも早くから予定決めてたみたいだよ。ぼくもちょっと気になってた食べ放題のお店、行きたいし……」
「練習の虫の火積部長が立てる予定って何なんでしょーねえ。スノボするにもシーズン終わっちゃってるしぃ……」
「横浜に行くって言ってたよ。久しぶりに、小日向さんに会うんじゃないかなあ」
何の気なしにぽつりと呟き、それから伊織は一気に自分の血の気が引くのが分かった。絶対に、水嶋だけには知られねえようにしてくれと、火積から念を押されていたのに。
「マジですか、伊織先輩!! 連休にってことは、もしや横浜一泊!?」
「く、詳しいことは知らないから……」
「せっかくのゴールデンウィークに練習三昧で、かなでちゃん放っといて、薄情な彼氏だなー、やっぱオレに乗り換えた方がお得だよーってアピールしようかなーなんて思ってたのに、意外にソツないんだからなー、火積部長ってば」
「あ、新くん……」
「しっかり連休にかなでちゃんと約束取り付けるとか、火積部長、結構やらし~……ん?そういや今度の連休って……ai!」
ふと何かを思い付き、カレンダーを見直そうとした新の脳天に激痛が走る。思わず頭を抱えてその場にしゃがみ込み、そろそろと視線を上げると、いつの間にか背後に火積が立っていた。
「……俺がいねえと思って、随分言いたい放題じゃねえか、水嶋」
「あ、あの、ごめんね、火積くん。新くんには知られないようにって言われてたのに、つい……」
恐縮して伊織が詫びると、火積は溜息混じりに首を横に振った。
「こいつのことだ。そのうちどっかから聞きつけてくるから、構わねえ」
一応口止めはしてみたものの、そもそも隠し事は上手くない伊織のことだ。先程のように何の気なしに教えてしまうか、もしくは隠そうとするあまりに不自然な態度をとって、新に看破されてしまうかのどちらかだったろう。伊織に知られた時点でいつかは新に知られるであろうことは予測済みではあった。
「そんなことより、火積部長~かなでちゃんに逢うのこの日って、もしや狙ってたんですかぁ?」
先ほどの鉄拳制裁もなんのその、にやにやと意味ありげに笑いつつ、新はカレンダーの今週末の日付をぐりぐりと指先で押す。火積は眉間に皺を寄せ、怪訝な顔をする。
5月23日、土曜日。特に祝日でも何でもなく、たまたま吹奏楽部の休暇日をそこに、と決めていたからその日にした。ゴールデンウィークというまとまった休みに、かなでに逢いに行ってやれなかったお詫びも兼ねて、ゆっくり過ごせるように一泊する準備もした。ただ、それだけだった。
「あれ? 何だか分かんないって顔してますねー? じゃあ、教えてあげましょう。ジャジャーン!何を隠そう、この日はズバリ、『キスの日』なんですよー!」
「「……は?」」
火積と伊織が同時に間の抜けた声を上げる。「ふっふっふー」と新が意地が悪そうな笑いを浮かべた。
「日本の映画で初めてキスシーンが上映されたとかで、記念日になってるんですよ。やだなあ、火積部長ってば。記念日にかこつけてかなでちゃんとちゅーしようとか」
「な、何言ってやがんだお前は!!」
反射的にまたもや新の脳天に鉄拳をお見舞いしてしまい、新が悲鳴を上げた。両手で頭を抑えつつ、新が唇を尖らせる。
「だってぇ、かなでちゃん嘆いてましたよー。『付き合い始めてもう半年以上経つのに、火積くんが何もしてくれない……』って。硬派なのは火積部長のいいとこかもしれませんけど、カノジョ不安にさせるとか有り得なくないですかー?」
「そ……れは」
再度振り上げかけた拳をどうにもできず、火積は硬く握り締める。
心当たりがないわけではない。お互いに遠距離恋愛だと分かっていて恋を始めたものの、やはり物理的な距離はどうしようもない。出来るだけ機会を伺って逢いに行くよう努力はしているが、物には限度というものがある。学生の身分では尚更だ。
その上、火積はその辺りのことが決して得意とは言えない。性格上周囲の誰かに相談するということも出来ず、彼女であるかなでの大らかさに救われながら、何とか順調に、だがゆっくりと、所謂『男女交際』というやつを手探りで進めているところだ。
自分の事で既に手一杯なのだから、当然のことながらかなでの心情までは気が回らない。かなでも彼氏が出来たのは初めてだとは言っていたが、かなでの常識と火積の常識が同じものだとは限らない。もしかしたら、火積には見せていないだけで、かなではいろんなことを不安に思っているのだろうか?
「……ど、どうでもいいんだけど、新くん……小日向さんとそんなぶっちゃけた話、してるの? 小日向さんって、あんまりそういうこと、他の人に愚痴ったりするような子じゃないかなあって思うんだけど……」
伊織が素朴な疑問を新にぶつける。へらっと笑う新が「メル友なんでー」と答えているが、そこで火積は我に返った。
例えば、本当にかなでがそういう悩みを抱えていたにしても、それを簡単に新に打ち明けるような彼女ではない。悩みが深ければ深いだけ、むしろ内に溜めこむタイプだ。
「おい、水嶋。小日向がテメエ相手にそんな悩み口にするはずねえだろ」
「あ、分かっちゃいました? さすがにカレシですねえ。かなでちゃんのことよく分かってるぅ~。……まあ、部長が手え出してくれないって悩んでるってのはぶっちゃけ嘘ですけどねー。吹奏楽部のこととか火積部長のこととか、結構心配してるってのはホントですよー」
あっさりと白状した新にもう一発と拳を固めたが、言葉の後半部分でふと火積の動きが止まる。確かに、今度の週末に逢うためにいろいろと打合せはしていたが、火積の現状についてはあまり報告していない。もうすぐ直接逢えると分かっているので、そこで話せばいいと思っていたからだ。
「さっきの話も。自分からそういうこと相談しちゃう子じゃないってのはそうですけど、何も悩んでないってこともないと思いますよー。火積部長のことだから、かなでちゃん大事にしなきゃと思ってるんでしょうけど、女の子側からすれば、大事にされすぎると不安になるってこともあるでしょうしねえ。せっかくの記念日だし、それを理由にして便乗しちゃってもいいんじゃないですかー?」
冗談めかした新の口調に、ほんの少しだけ、真面目な声音が混じっている。
おそらくはからかい八割、心配が二割……結局のところ、面白がられているというのが正解なのであろうが。
「……助言は助言として、一応頭の隅に留めておく」
そう言いつつも、嘘をついたことへの新への罰として、新入部員用にこの先一か月分の練習メニューを作成し、連休明けに提出することを命じる。鉄拳制裁を回避した、火積なりの譲歩のつもりだったが、楽器の異なる数名分の一か月分のメニューとなれば、それなりにボリュームはある。
「サヨナラ、オレの連休……」
と半泣きで遠くを見つめる新の肩を、宥めるように溜息交じりの伊織が叩いた。
そして、週末。
始発の新幹線を乗り継いで、かなでが暮らす星奏学院の寮・菩提樹寮の最寄駅に火積が降り立つと、駅前の噴水前のベンチに小日向かなでが既に腰かけていた。わらわらと駅から吐き出される人混みの中から火積を目敏く見つけると、顔を輝かせて駆け寄ってくる。
「おはよう、火積くん!」
かなでが躊躇なく火積の前に立つと、少しだけ火積を遠巻きにして歩いていた周囲の人たちが、驚いたような表情で火積とかなでとを見比べる。ただでさえ強面なのに更に額に大きな傷痕が残るため、かなでの幼馴染みの如月響也曰く「アッチ系の人」という印象である火積と、小柄でほわほわとした可愛らしい風貌のかなでとが並んで立つと、その関係性が想像つかないのだろう。いつもの光景なので、今更火積は気にならないが、かなでに申し訳ないという気持ちは毎度変わらない。
「……久しぶりだな。元気にしてたか?」
最初に何を言おうか迷って、結局唇から零れ落ちたのは普通の言葉だった。それでもかなでは嬉しそうに笑って、大きく頷く。
「元気だよ! 火積くんも忙しかったって聞いているけど、元気そうでよかった。……無理してこっち来てもらっちゃって、ごめんね?」
「……いや、それは別に……」
もごもごと火積が歯切れ悪く返事をする。
ただ、自分が逢いたいから逢いに来た。それだけではあるのだが、それを素直に言えるような性質でもない。
「そういや、俺が忙しかったって誰に聞いた?」
自分からかなでにそう言った覚えはない。もちろん新入生を迎える4月から部長である火積は忙しくはあったのだが、同じように星奏学院オーケストラ部の副部長であるかなでも忙しくしていたはずだし、お互い様なのだからわざわざ言う必要もないと思っていたからだ。
……もちろん、かなでの情報源には火積は心当たりがあったのだが。
「ん? 新くんだよ。『無事に新入部員も入って、ゴールデンウィークは練習三昧で超ハード~ 火積ぶちょー鬼ー』……って、愚痴メールが来たよ」
「……あの野郎」
途端に渋面になる火積に、かなでがくすくすと笑う。
「でも、新くんがそうやってメールくれるから、火積くんの様子も分かって助かってるんだよ。電話とかメールが減ったら新くんのメールと合わせてみて、『ああ、今忙しいんだな』って思って」
「……すまねえ」
確かに、ここ最近多忙に追われ、なかなかメールや電話も出来ないでいた。かなでからは短いながらも定期的に現状報告メールが届いていたのに、一言二言、返信するのがやっとで。
「あ、あの、ごめんね? 責めてるわけじゃなくって。私も忙しくしてたんだし、響也見てたら部長職ってホントに雑用とかも多くて、私が忙しいのとまたレベル違うなって思うから、そういう時に無理してメールとか電話とかしなくて大丈夫だし。……ただ、本当に忙しくしてるって新くんから教えてもらえるから、連絡が減ったのが私のことが嫌になったからじゃないんだって分かって、安心してられるって言うか……って、何言ってるのかな、私」
ごめんね、忘れて。と苦笑するかなでが話を畳む。
畳まれてしまったので、火積も何も言えずに黙り込んだ。
先日仙台で新に言われたことがふと頭に過った。
(何も悩んでないってことは、ないと思いますよ?)
……お世辞にも女性受けがいいとは言えない自分の外観と性格のことを、火積はよく分かっている。だからこそ、どこからどう見ても『可愛い女の子』なかなでが、自分の事を好きになってくれたのが奇跡のように思えるし、今でも本当は不安になる。
かなでの隣に立つのが、本当に自分でいいのかと。
そんなふうに、悩むのは自分の方の専売特許だと思っていたが、かなではかなでなりの悩みを持っているようだ。……まるで、火積と同じような悩みを。
こんな時に、自分はどう対応すればいいのだろう。
かなでの不安は杞憂でしかなく、男子校の至誠館で、しかも今は吹奏楽部を無事に夏のアンサンブルコンクール決勝まで導く使命がある以上、そういう色恋沙汰とはまるで縁がないわけだし、そもそも自分はかなで以外の女性とどうこう、などというのはまるで考えられないわけで。それをちゃんと彼女に伝えるべきかとも思うのだが、どう考えてみても。
(ガラじゃねえんだよな……)
内心困惑しつつ頭を抱える火積に、どうやら気持ちを切り替えたらしいかなでが「火積くん、早く行こうよ」と声をかけた。
二人のデートは、いつもかなでの希望を叶えることが多い。
火積の方にこれといってやりたいことがなく、傍にいてやれない罪悪感が働くため、「あんたの好きなところでいい」とかなでの希望を優先してしまうからだ。そうなると、ホントに普通の女子高生でしかないかなでは、故意ではないにしても火積が最も苦手とするエリアにこれでもかと火積を踏み込ませる暴挙に出ることになる。だが、何回かそういうデートを重ねていくうちに、何とかかなでも火積が妥協できる境界線を測ることに慣れてきた。もちろんかなでの希望を押し通しても、困惑はしてもちゃんと火積が付き合ってくれることは分かっているのだが、どうせなら二人とも心から楽しめることを楽しみたい。
そして今日かなでが選んだのは、電車を乗り継いで行く少し遠方の水族館だった。火積がこちらに一泊するので帰りの新幹線の時間を気にする必要がなく、いつも火積が頭を悩ませている年の離れた妹へのお土産も選びやすいだろうと思ったのだ。
「イルカとかペンギンとか、可愛い系のグッズは外れがないから喜んでくれると思うよ」
「……成程な」
休日ということもあり混み合った館内を、人の流れに逆らうようにのんびりと二人は歩いて回る。いつもはこれでもかとタイミングを模索してようよう繋ぐのに、はぐれないようにと自然に手を繋ぐことも出来た。
定番のイルカやアシカのショーに歓声をあげ、併設されたカフェで昼食を取る。
特に劇的な何かも起こることなく、時間は穏やかに、だがあっという間に過ぎて行った。
ほぼ丸一日水族館を堪能し、二人は最後に売店に立ち寄る。火積の家族へのお土産を選ぶためだ。
「実物はアレだけど、ぬいぐるみとかになるとやたら可愛くなるのがあるよね……」
積み上げられた様々なぬいぐるみを見上げ、かなでがぽつりと言った。
確かに、と火積も頷く。元々可愛いイルカやペンギン、カワウソなどは勿論だが、ジンベエザメやマンボウ、チンアナゴやウミウシなどというものまである。ここに来るまでに実際に本物を見ているので、こんなだったか?とつい首を傾げてしまうのだが、かなでは真剣な表情で「チンアナゴ、ちょう可愛い……」などと呟いている。火積には縞や水玉の模様が付いた長い棒にしか見えないのだが。
「……何か、買ってやろうか?」
唇に指先を当てて真顔で悩むかなでにそう声をかけてみると、かなでが慌てたように首を横に振る。
「え? う、ううん!そんなそんな! 火積くんには逢いに来てもらえたってだけで充分だし、ほら、ご家族へのお土産もあるんでしょ? 私のことは気にしないで。欲しいものは自分のお財布と相談して、ちゃんと自分で買うから!」
頑なに拒まれて、火積もそれ以上押すことはしない。かなでがこういう態度を取る時は絶対に折れないことを火積もこれまでの経験で学んでいる。お互いに土産物を選んで再度落ち合うことにして、火積は家族への土産と共に、自分の意志でかなでに何か記念になるものを買ってやろうと考える。火積が自分の財布と相談して、自分の希望でかなでにプレゼントしたいものを買うこと自体は、かなでは嫌がらないはずだ。それは、今もまだかなでの携帯で揺れている、去年火積がかなでにプレゼントした妖精のストラップが物語っている。
先ほどからかなでがチンアナゴのぬいぐるみの山の前で苦悩しているため、火積はふと目についたチンアナゴのブックマークを手に取った。かなでに読書の趣味があったかどうかは記憶していないが、勉強にしろ何にしろ、何も読まないということもないだろう。
(コレが可愛いのかどうかは、正直分からねえが……)
そう思いつつ、火積は家族と近所に配るように選んだ定番の菓子折りが幾つかと、妹用に選んだペンギンのぬいぐるみの入った買い物かごの中に、そっとブックマークを置いた。
会計を終えてかなでを探すと、かなではやはりまだぬいぐるみの山の前にいた。考える時の癖なのだろうか、ずっと唇に指を当てたまま、眉間に皺を寄せている。声をかけようか迷いつつ近くに歩み寄り、火積はふとかなでの唇が濡れたように光っていることに気が付いた。
決して見たくないわけではないのだが、かなでの顔を正面から見つめるのは正直勇気がいる。何のことはない、恥ずかしさが勝るからだ。今日のメインは水槽を眺めることだったので、かなでの顔をまじまじと見る機会が少なかった。昼食の時ですら、水槽が正面に見えるカフェエリアだったため、向かい合わせでなく並列で食事をしていて、今日の彼女の顔はほとんど横顔しか記憶していない。
だが、今かなでは思案しつつ指先を唇に当てているので、自然に火積の視線はかなでの唇に吸い寄せられる。かなでの視線が火積に向けられていないので、存分に火積はかなでを見つめていられる。そうして、やっとそのことに気付いた。
(化粧……か?)
火積を取り巻く異性は家族以外にはかなでしかおらず、家族と言っても母と年の離れた幼い妹なので比較の仕様がない。そして、かなでがこれまでに火積と逢う時にメイクをしていたことはない。……勿論、基礎的なケアはしているのかもしれないが、それは火積には気づけないレベルのものだ。
リップグロスというものに火積は触れる機会がない。だが濡れたように光るふっくらとした唇は、例の新の言葉を火積に思い出させるには充分だった。
(――やだなあ、火積部長ってば。記念日にかこつけてかなでちゃんとちゅーしようとか)
(――女の子側からすれば、大事にされすぎると不安になるってこともあるでしょうしねえ。せっかくの記念日だし、それを理由にして便乗しちゃってもいいんじゃないですかー?)
「……うるせえ!!」
脳内・水嶋新が畳み掛けるので、つい怒鳴りつけてしまう。はっと我に返ると、きょとんとしたかなでが火積の方を振り返っていた。
「……ごめん、私何か独り言でも言って……」
「い、いや、すまねえ。あんたがどうこうってことじゃねえんだ。ただ脳内水嶋が……」
「脳内新くん?」
「……いや、いい。それよりあんたは結局どうすんだ、それ……」
「それが、微妙に予算オーバーなんだよね。ぬいぐるみって高くって。だから、今日は諦めて、またお小遣い入ってから買いにこようかなって。多分言えばニアか響也が付き合ってくれるから」
屈託なく笑うかなでに、出来れば支倉と一緒にしてくれと言うべきなのかどうか、火積は迷った。
「海の近くって、やっぱり気持ちいいよね。今は季節もいいし」
水族館を後にし、かなでたちは山下公園まで移動する。火積が宿泊する予定のビジネスホテルが近いためだ。初めはいつものように菩提樹寮の空き部屋を使わせてもらえないか相談するつもりだったのだが、さすがに学校の予定として来ているわけではないので、甘えすぎるわけにはいかないと火積が固辞した。夏のコンクールの際にはまたお世話になるつもりなので、至誠館部長としての火積なりのけじめだった。
海風に去年の夏より少し伸びた髪を煽られながら、かなでが両手を掲げて大きく伸びをする。
「そうだ、火積くん。私夕飯まで一緒してもいいのかな。今日は寮母さんお休みの日で、菩提樹寮で夕飯が出なくって」
「あ、ああ。あんたがそれでいいなら」
振り返るかなでから不自然に目を反らし、火積が答える。
水族館を出て以降、かなでを見ようとするとどうしてもその唇に視線が行ってしまう。
火積から視線を反らされる度に、かなでの眉が八の字になり、肩が落ちることも分かっていながら、かなでの唇を見ればどうしてもあの新の言動が導き出されてしまうのだ。
かなでが火積のために、綺麗に丁寧に自分を飾っていることが分かるから尚更、火積は自分がどうするべきなのかが分からない。
(くそっ……、上手くねえ)
火積はつい頭を抱える。
溜息を付く火積を困ったようにかなでが見つめ……それから、何かを思い切ったように、かなでの小さな手が火積のシャツの裾を掴んだ。
「……火積くん」
その思い詰めたような声に、火積はぎょっとする。
確かに自分の態度は全然上手くはなかった。だが、ここまでかなでを気落ちさせるとも思っていなかったのだ。
「ずっとね、聞いてみたかったんだけど。……火積くんは、私と付き合ってるの、イヤだなあって思うことないの?」
「……あるわけねえだろ」
つい、声のトーンが落ちる。思った以上にドスの利いた声になり、怒られていると思ったのか、かなでが小さく肩を震わせて怯えた目で火積を見上げた。
「いや、その……あ、あんたの方こそねえのか。俺が嫌になること。俺は……見た目こんなだし、愛想ねえし、連絡もマメとは言えねえし、気が利かねえし」
かなでは首を横に振る。「それが、火積くんだから」ときっぱりと言い切った。
「それを言ったら、私もなかなか私の方からは逢いに行けないし、たまにデートする時も自分の好きなところばかり選んで火積くん振り回してる自覚あるし……それにね、いつも火積くんが言うでしょう?」
あんたみたいなお譲さんが、俺と一緒にいていいのか。
火積にはどうしても拭えない自分自身に対しての劣等感がある。
それはトランペットの技術から始まり、至誠館吹奏楽部を廃部の危機に追い込んだ負い目、そしてどうしても周囲を委縮させてしまう見た目にもある。総じて火積は自分という人間に対して自信が持てない。
かなでのことを好きなのは本当だし、彼女を手放したくない欲求も本物だ。だが、自分への劣等感がある以上、どうしても火積は自分自身を卑下してしまう。その不安が行きつく先が、果たして自分がかなでの恋人でいていいのだろうかという疑問なのだが、かなでの側からしてみれば、まるでそれは自分と火積の住む世界が違うと拒絶されているようなものだ。
「手を繋ぐのとか、……キス、とかも。火積くん、いつもものすごく申し訳なさそうな顔でしてるの、自分で分かってる? 私、ちゃんと嬉しいのに。すごい幸せなのに、何か全然伝わってない気がして。一旦告白しちゃったから、私と付き合うのが想像してたのと何か違うって思ってても、火積くんが優しいから言い出せずに、気を使ってくれてるだけなんじゃないかって……」
言い重ねるうちに、かなでの目からほろほろと涙が溢れてくる。
ずっと不安だった。でも見ない振りをしていた。もしも火積が自分が無理をしていることに気付いたら、二人の関係が終わってしまうから。かなでは火積のことが好きだから、ずっと一緒にいたい。恋人同士が経験していく全てのことを、火積と一緒に分かち合いたい。だが、火積が同じ気持ちだとは限らない。
「私の事、もう見るのも、嫌なのかな? だったら、我慢せずにそう言って欲しいの。そりゃ、別れるって言われたら、私は哀しいし、苦しいけど、火積くんが我慢して、私に付き合ってくれてるってことなら、そっちの方がずっと辛い……」
「ちょ、ちょっと待て、小日向」
とうとうしゃくりあげ始めるかなでの両肩を掴んで、火積はかなでの言葉を止める。
何がどうして別れ話という展開まで進んでいるのか。自分はいったいどこで間違えた?
「俺は……あんたと別れる気なんて、ねえ。むしろ、俺が我慢してるって言うより、あんたの方がよほど我慢してたんじゃねえのか?」
ここにきてようやく、新の言葉が深く突き刺さる。
悩んでいないように見せていたって、悩んでいないとは限らない。
そもそも火積だって分かっていたのだ。かなでが自分の悩みを簡単に見せるようなタイプではないのだと。
内に秘めて秘めて、そして最後にどうしようもなくなってから爆発させるタイプなのだと。
なんで、ここまで思い詰める前に言わねえんだ。そうは思うが、結局は火積がそれを言えなくしたのだ。
自分こそが、かなでには相応しくないのではないかという、染みついて離れない、劣等感のせいで。
「あんたを見るのが嫌ってわけでもなくて……照れくさいっていうかなんつーか……あんたが化粧してきてるのに気付いちまったから」
「化粧?」
涙に濡れた目を丸くして、かなでが聞き返す。
化粧……という化粧はしていない。化粧水、乳液の基礎的なケアと、それから初夏の強い日差しから身を守るための日焼け止めと。
「……あ」
考えていて、かなではふと思い当たる。朝の準備の際に鏡を覗いていて、唇が荒れかけているのに気付いた。彼氏と逢うのに唇が荒れたままっていうのは有りえないよね、と思って薬用のリップを取り出して。
それから、ふと数日前にメル友である水嶋新から届いたメールのことを思い出したのだ。
『偶然か意図的か! 今度のかなでちゃんと火積ぶちょーのデートの日って、『キスの日』だってかなでちゃん知ってた? 火積ぶちょー、ちゃーんとスマートにちゅーしてくれるとイイネ♪』
いつも、キスをする時にはぎこちなく、緊張の面持ちでしてくれる火積の姿を、どこかから覗き見ているかのようだった。文面を思い出し、小さく笑いながら、かなではふと、普段はあまり利用することのない薄いピンクのリップグロスを手に取った。火積が『キスの日』という記念日を知っていて、かなでと逢う日をこの日に選んだとは思わないけれど、新が知っているのなら。もしかしたら。
「……っ」
絶句したかなでの頬が見る見るうちに赤く染まる。
潤んだ瞳と相まってそれはもう火積にしてみれば酷い破壊力だった。
「……小日向」
低く呟くと、かなでが消え入りそうな声でごめんねと答える。火積は首を横に振った。
「あんたが何も言わねえのをいいことに、胡坐かいてた俺も悪い。……その、あんたがどうってことじゃなくて、俺はただ、俺自身に自信が持てねえっつうか、別に世間一般で言うところのイケメンってやつでもねえし、さっきも言ったが愛想ねえし、気が利かねえし……むしろ、あんたが俺を捨てる方が自然っつーか……」
「火積くん、カッコいいよ」
「そ、そうか。そういうこと言ってくれるの、あんたぐれえだとは思うが。……ありがとよ」
「……火積くんが好き」
「……あ、ああ」
自分も好きだと答えるべきかと一瞬火積が躊躇したその時、先にかなでの想いの方が零れ落ちた。
「……キス、したい」
「……」
何かこれをこいつに言わせるのは結構情けない感じじゃねえのか。
そう思いつつも、自分は言葉を使わない方がいいのではないかと思い始める。口下手な自分は、言葉を伝えようとすると、すぐに墓穴を掘る。
かなでの頬に残る涙の跡を不器用に掌で拭う。そのまま掌で彼女の柔らかな頬を覆うと、驚いたように瞬いたかなでが、慌てて目を閉じた。
軽く唇を重ねると、濡れたような感触が火積の唇にも移る。それに少し驚いて、だがそれは不快なものではなくて。
火積は何度も繰り返し、啄むようにかなでの唇に触れた。
これまでにも触れるだけのキスをしたことはあるが、こんなに何度も繰り返し触れられたのは初めてだ。合間なく塞がれるから、つい息苦しくてかなでは空気を求めて軽く唇を開く。そこに、同じようにわずかに開いた火積の唇がぴったりと重なった。
……自分が無意識に避けていたのは、実はこれだったのかと火積は悟る。
言葉は理性的だ。口に出せば建前が勝つ。だから、自分は言葉で本心を伝えようとすると、上手くいかない。
自分は本当に彼女の隣にいていいのか。彼女は本当に自分を選んでいいのか。
そう葛藤しながらも、結局のところ火積の心は既に固まっていた。
(俺は、あんたを離したくない)
(あんたに近付けば近付くだけ、俺は結局もっとあんたが欲しくなるだけだ)
舌が絡みつき、互いの唾液が混じり合い、そして止めようもなく甘い吐息と声が漏れる。
それがたまらなく幸せで、心地良い。
そして、この快楽にはまだ先があることを、人の本能としてきちんと火積は知っているのだ。
「……っ、……すまねえ」
かなでの両膝から力が抜け、がくんとその場に崩れ落ちそうになるのを、火積が咄嗟に抱き止めた。「わ、私こそごめんなさい」と謝るかなでの火積のシャツを掴む指先が小さく震えている。
その指先に、初めて火積は何の了承もかなでに取らず、自分の無骨な指を絡めてみた。
小さくて柔らかくて。だが、きちんと弦に鍛えられたヴァイオリニストの細い指。それがとても愛おしいのだと、心の底から実感した。
「……小日向。その……急に何言ってんだかって感じかもしれねえけど。……俺は、あんたが好きで。多分あんたが考えてるよりもずっとあんたのことが好きで。あんたに近付いたら、もっとあんたが欲しくなるって分かってたから、今まで不必要に近寄んねえようにって頑張ってたってとこがあってよ……」
「……うん」
火積の胸に顔を埋めたまま、かなでが小さく頷く。
「でも触っちまったらもう抑えが利かねえっていうか。その……あんた、本当の意味で、俺のものになる気、あんのか……?」
恐る恐る火積が尋ねる。胸の中から視線だけを火積に向けたかなでが、唇を尖らせた。
「……火積くん、それ直接聞く?ってことを結構平気で聞いてくるよね」
「そ、そうか? ……すまねえ」
でも、嫌なら別に無理すんな。そう言いかけた火積の唇に、懸命に背伸びをしたかなでがちゅ、と可愛らしく音を立ててキスをする。
「嫌とか、思うわけないよ。……何であんなキスしといて、嫌だって思うとか考えるのかな?」
拗ねたように言うかなでに、先程のキスを思い出した火積が真っ赤に染まる。それを見つめて笑いながら、かなでが火積が絡めた指先を、ぎゅっと握り返す。
「……火積くんのものになりたい。火積くんがそう言ってくれるの、ずっと待ってた」
また「すまねえ」と恐縮する火積に苦笑しながら、かなでは「謝らないで」と返す。
初めて何の気負いも迷いもなく自分を求めてくれたことが、これ以上にない幸せなのだとちゃんと火積が理解してくれるといいなと思っていると。
『キスの日』という記念日の名にふさわしく。
夕焼けに染まる山下公園の片隅で、まるで映画のワンシーンのように。
長身の火積の影が、小柄なかなでの影に融け合うように。
一つの形に重なった。
あとがきという名の言い訳
火積が若干ヘタレているような…いや、充分ヘタレだとは思うんだけど(笑)しかし至誠館高校吹奏楽部は楽しいな!(笑)
ちなみに、わざと回収しなかった伏線があるのですが、それは続きの部分で回収します。突っ込まれる前に(笑)
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2018.01.28