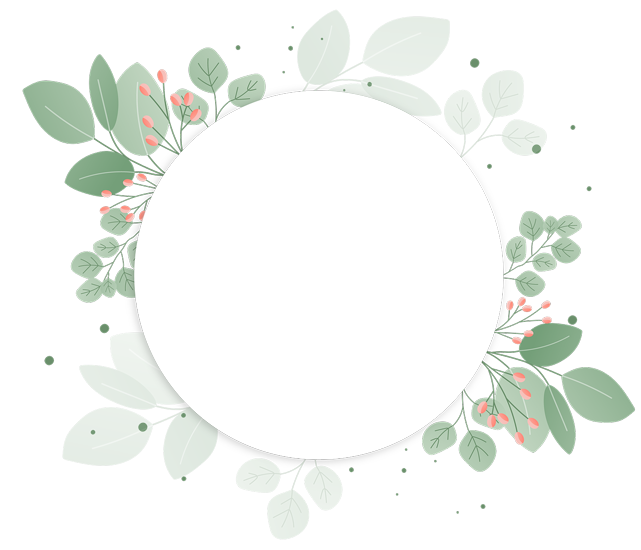休日に立ち寄った本屋で、何気なく手に取った雑誌をパラパラと無造作に捲りつつ紙面を眺めていた小日向かなでは、ふと目に止まった特集記事に、つい声を漏らした。
ぽろりとこぼれ落ちた自分の声が、予想以上に大きく響いたので、慌てて周囲を見渡すと、幸いなことに少し離れたところで同じように本棚に並んだ冊子の背表紙の文字を目で追っていた如月律しかいなかった。
だがさすがに律の耳にはかなでのその大きすぎる独り言がきちんと届いたようで、棚の上部へ向けられていた律の視線が、ふとかなでの方へと向けられた。
「かなで、どうかしたのか?」
「ううん、別に大したことじゃないよ」
些細なことなので、改めて律に報告するまでもない。苦笑しつつかなでは小さく首を横に振ったが、逆に流そうとする方が対応に迷うらしい。その表情は変わらないが、黙り込んだ律が困惑していることに気付いたのは、やはり付き合いの長い幼馴染みのかなでだからこそだろう。
探し物を中断させてしまったことも含め、何だか申し訳ない気持ちになりながら、かなでは眺めていた雑誌の頁を律に示した。歩み寄って来た律がそのページの大きな見出しに目を止めて、ぽつりと呟く。
「……記念日特集?」
「知らない記念日が結構いっぱいあるんだなあって、ちょっと感心してただけなの。驚かせちゃってごめんね」
言いながら、かなでは律がずっと同じ場所で立ち尽くしたまま、背表紙の文字を追っていたことを思い出す。傍目から見れば何だか難しいことを考えているように見える律だが、実際は意外に単純なことに頭を悩ませていることが多い。そもそも本屋に立ち寄ることになったのも、本を見たいと言った律の申し出からだった。目的のものが見つけられないのだろうか。
「それより律くんの探してる本、見つかったの? もし場所がよく分からないなら、店員さんに聞いてみようか?」
「いや、それは別に構わない。置いてあれば幸いだとは思って寄ってはみたが、探しているのはかなり専門的なものになるから、おそらく取り寄せなければ購入は無理だろう」
どうやら律も、駄目で元々の気持ちで本屋に入ってはみたものの、やはり目的のものは置いてはなくて、他に何か目新しい本に出会わないかと、棚を眺めていただけのようだ。
そして、意外にも律はかなでが見ていた記事の内容に興味を引かれたらしく、そのまま紙面の続きに視線を向ける。それならばじっくり読んでしまおうと、かなでは律と肩を並べて、可愛らしくレイアウトされた雑誌の紙面を覗き込んだ。
「……7月7日を記念日とするのは、七夕だけではないんだな」
特集は『恋人同士で過ごす色々な記念日』がテーマになっていて、『記念日』として馴染んでいる日付にも、知っているものとは違う様々な記念日が、箇条書きで幾つも連なっている。
律の声に改めてその日付の箇所を見てみれば、代表的な『七夕』の他に、記念日の名称が三つも書かれていた。
『ラブ・スターズ・デー』・『サマーラバーズデー』・『サマーバレンタインデー』……どれも、七夕を元にして近年設定された記念日であるようだ。
「内容自体は、どうやら企業戦略的なものが多いようだな」
「でも確かに、七夕って数字もゾロ目で覚えやすいし、恋人同士が一年に一度だけ再会するっていう恋にまつわるイベント事だから、恋人の記念日っていうのにしやすいのかもしれないよね」
よくよく思い返せば、七夕というものは離れ離れの恋人同士の一年に一度の逢瀬というとても切なくロマンティックな記念日であるはずだ。それなのに自分の経験を振り返ってみても、実際に七夕にすることと言えば、笹の葉を飾り付けて願い事を書いた短冊を吊るすという、恋愛には全く縁のないことをしていた記憶しかない。
そんなふうに改めて考えてみると、七夕というのは意外に大衆的な記念日だなあとかなでは思った。
(そう言えば、私も『律くんのおよめさんになれますように』とか書いたことあったなあ……)
それは、幼かったかなでの小さな初恋の想い出だ。昔から、かなでにとって律は憧れの男の子だったから。
「由来が由来なんだから、本当は七夕もクリスマスみたいに、もっと恋人たちの特別な記念日!って感じになってもいいのかもしれないね。でも、私はやっぱり七夕って言ったら、子どもたちがわいわい短冊にお願い事書いてるってイメージなんだけど。ねえ、律くんはどう?」
意見を求めて律を見上げると、何かを考え込むようにして律は雑誌の一点をじいっと見つめている。彼が話し出すまで成り行きを見守るしかないかなでの視線の先で、ふと律の長い指先が空を泳ぎ、羅列している記念日の一つを指し示した。
「七夕といえばもうすぐだな。……お前さえよければ、これを一緒にやってみないか?」
「えっ?」
思いがけない申し出に、慌てて律の指し示した部分を見直す。
そこには『サマーラバーズデー』の文字。「七夕に因んで、意中の人にプレゼントをする日」と説明書きがある。
「つまり、私と律くんでお互いにプレゼント交換するってこと?」
昨年の夏の再会以降、幼馴染みから恋人同士へと関係が変化した自分たちは、まさに目の前にいるお互いが『意中の人』であるはずだ。そう思いながらかなでが尋ねると、律は軽く首を横に振った。
「いや、お前の方は何も準備しなくていい。ちょうど、俺からお前に渡したいものがあったんだ。いつ渡そうかと悩んでいたんだが……」
かなでにプレゼントをするには、彼女の誕生日も恋人同士の定番イベントであるクリスマスも、まだ少し遠すぎた。
もちろん無理にイベント事に関連付ける必要はないのだろうが、この記念日であれば数日以内にその日を迎えることが出来る。律にとってはかなでに送りたいものを渡す、いい機会だ。
「ちょうどこの日は休日だったろう。……お前さえよければ、二人で一緒に過ごさないか」
「うん、もちろん! 喜んで!」
律が星奏学院高等部を卒業して数か月経つ。そのまま大学部への進学ではあったが、菩提樹寮は高等部卒業を期に退寮することが規定になっていた。大学部のキャンパスは高等部の校舎からそう遠くにあるわけではないので、現在律が暮らしている星奏学院の学生御用達の防音設備が整ったマンションも、幸いなことに菩提樹寮から徒歩圏内にある。だが、同じ場所から登校し、同じ場所へ帰宅していたあの頃に比べれば、かなでが律と共に過ごせる時間は確実に減っている。
だからこそ、律のこの申し出は、実はかなでにとっても願ったり叶ったりのものだった。
偶然目にした雑誌のささやかな特集記事に、かなでは素直に感謝した。
そして数日後の7月7日、かなでは律と約束した時間に、律が暮らしているマンションを訪れた。
律は一度ヴァイオリンの制作や練習を始めると寝食を忘れて没頭しがちため、かなでは律の食事の世話をするために、オーケストラ部の活動が終わった後に、よくここを訪れている。
そういう意味では慣れた訪問だが、今日は少しだけ心持ちが違う。今日は律からの招待で、特別な記念日を二人で一緒に過ごすのだ。
実は、かなでは律が自分に贈ろうとしてくれているものにはある程度予測がついていた。だが、それはそれで以前からずっと心待ちにしていたものであるので、楽しみであることに変わりはない。
いつものように、敢えて呼び鈴は鳴らさず、律から預けられている合鍵で、かなでは玄関のドアを開ける。
ヴァイオリンを修理しているか、作っているか、弾いているか。
律の行動パターンは、この三種にほとんど占められているが、この三種に取り組んでいる間、律は尋常でない集中力を発揮し、呼び鈴を鳴らしても聞こえていないことが多い。
これまで律の食事の用意のためにここを訪れ、呼び鈴や携帯を鳴らしてみても律が応じてくれず、玄関先で締め出しを食らったことが何度かあり、そのうちに「お前なら、別に自由に入ってきても構わない」と、律が合鍵を渡してくれたのだった。
「おはよう、律くん。お邪魔します」
声をかけながら部屋の奥へと進んでいくと、相変わらずヴァイオリン調整に必要なものが雑多に積み上げられた、いわゆる律の『作業場』で、律が一挺のヴァイオリンを手に取って見つめているところだった。
修理の最中なのだろうかと、それ以上部屋へ踏み込むのが躊躇われて、かなではつい部屋の入り口で足を止めて立ち尽くす。
だが、すぐに律が人の気配に気が付き、かなでへと視線を向けた。
「おはよう、かなで。……時間通りだな」
穏やかな律の笑みに、別に作業の邪魔をしてしまったわけではないことを悟り、かなではほっと胸を撫で下ろす。
部屋の至るところに積み上げられたものを、うっかり崩したり踏んづけたりしてしまわないよう、そうっと足音を忍ばせるようにして、律の側に歩み寄った。
「これって、今律くんが修理しているヴァイオリン?」
律が大切そうに見つめていた、彼の手の中のヴァイオリンを覗き込み、かなでが尋ねると、小さく首を横に振る律が、すっとそのヴァイオリンをかなでへ差し出した。
「いや、これは俺が初めて作ったヴァイオリンなんだ。……お前さえ良ければ、少し弾いてみないか?」
「え、いいの?」
ぱあっと顔を輝かせ、かなでが律の手からヴァイオリンを受け取る。今練習中の曲の仕上がりを見てもらおうと、荷物の中には当然のように愛用のヴァイオリンがあったので、ケースから弓を取り出し、早速律のお手製ヴァイオリンを弾いてみることにした。
まずは、低音から高音へ順番に。調弦をするように音を響かせて、ゆっくりと一音一音の余韻を確かめてみる。
防音された狭い室内に、かなでが丁寧に紡ぎ上げる澄んだ音色が響き渡った。
「……どうだ?」
先程までとは違う、どこか不安げな表情で律が尋ねる。耳はかなでより遥かにいいはずだから、音の善し悪しが分からないわけがないのに、自分の手で作り上げた初めてのヴァイオリンを客観的に評価することは、まだ出来ないのだろう。
ヴァイオリンを肩から下ろしてくるりと律を振り返ったかなでが、嬉しそうに律に駆け寄った。
「すっごく綺麗ないい音だよ! こんないい子作っちゃうなんて、律くんってやっぱりすごい!」
「そうか、……気に入ってくれただろうか?」
「もちろん!」
含みなく、満面の笑みで頷くかなでに、律は安堵したように息を付き、頬を緩める。ならば、と、かなでが腕の中に抱いたヴァイオリンの表面を、そっと愛おしそうに指先で撫でた。
「……お前がこれを貰ってくれるだろうか?」
「え……?」
「これは、俺が初めて自分でも及第点が付けられると思えたものなんだ。……俺自身が認められるヴァイオリンを作ることが出来たなら、その最初のヴァイオリンは、お前に貰って欲しいとずっと思っていた」
大学を卒業後、律はヴァイオリン職人であるかなでの祖父に弟子入りし、本格的に職人となる修行を始めるつもりだと言っていた。それまでは大学で音楽を学びつつ、自分のヴァイオリンのメンテナンスを頼んでいたヴァイオリン工房でアドバイスをもらいながら、自己流でヴァイオリンを作るための勉強をしている。
当然のことながら、プロが作るヴァイオリンの完成度に比べれば、出来上がりの差は歴然だが、このヴァイオリンは、ヴァイオリンとしての役目を果たす基準は充分にクリア出来ているはずだった。
これでようやく、職人としてのスタート地点に立つことができたと律は思っている。
「つまり、この子が律くんの処女作ってことだよね。……そんな大事なもの、私が貰っちゃってもいいの?」
「ああ。お前だからこそ、貰って欲しいんだ」
舞台での演奏に使うには、まだ音が小さく、その響きも良くはない。
だが練習に使用するのには、特に差し支えはないはずだった。
「……ありがとう」
かなでが噛み締めるようにそう告げて、ぎゅっとヴァイオリンを抱き締める。
目を閉じて、先程の律と同じように、愛おしむようにヴァイオリンを撫で……微笑むかなでが、律を見上げた。
「あのね、律くん。……実は私、律くんが渡したいものがあるから『サマーラバーズデー』をやりたいって言ってくれた時、もしかしたらそれって、律くんのヴァイオリンなのかなって、ちょっとだけ思ってたんだ」
「……そうか」
サプライズ的なものを演出するつもりは毛頭なかったが、予測されていたということは、おそらく律の世界にはヴァイオリンしかないということを、かなでがきちんと理解しているという、その証左なのだろう。
「意外性も何もなかったな。……すまない」
「そんなことないよ! そうじゃないかなって、確かに思ってはいたんだけど、実際に貰ったらすごく、すごく嬉しいから! ……私、大事にするからね。律くんのヴァイオリン」
「……ああ、よろしく頼む」
ふと、昔かなでの祖父が、職人にとって寝食を削って魂を込めて作り上げた作品は、まるで自分の子どものようなものだと言っていたことを律は思い出す。ヴァイオリン職人としてはまだまだ駆け出しの拙い作品ではあるが、きっとかなでなら発した言葉の通りに、とても大切に、律の初めての『作品』を守ってくれるだろう。
その後二人は、ヴァイオリンの練習をしたり、ここ最近の高等部オケ部での律の実弟・響也の部長っぷりや、かなでの様子について報告を聞きながら、静かな律の部屋で、ゆっくりと時間を過ごしていく。
かなでと律の休日の過ごし方は、こんなふうにのんびりとしていることが多い。別にかなでが望めば、律はどんな賑やかな場所にも付き合ってくれるのだが、そもそも律は外に出歩くより屋内で自分の速度で時間を過ごす方が好きなのだと、かなでが充分に理解しているからだ。
もちろんかなでも、律とゆっくり話したり、厳しいながらもヴァイオリンの練習を見てもらったりすることが一番好きなのだから、これはもうお互い様というやつだ。
それが、かなでの親友である支倉仁亜に、「君たちは恋人の段階を通り越して、既に老夫婦の域に達しているな」と呆れられる所以でもあるのだろうが。
(そろそろ律くんの夕飯の準備しないと。……そういえば、今日は寮母さんがお休みの日だったから、私も自分の夕飯の準備しないといけないんだよね)
時計を見て現在の時刻を確かめつつ、かなではこれからの予定について思いを巡らせる。
菩提樹寮の家事を一手に引き受けている通いの寮母さんは、月に数回、決まった休暇があり、その日は寮生たちが食事の用意を自分で行わなければならない。集団での寮生活の中で、協調性や自主性を身に着けさせるためという立派な名目があるが、そもそも寮生が少ない菩提樹寮では、かなでが編入してくるまで自炊出来る寮生が一人もいなかったため、昔からこの日は皆が皆、外食で済ませるのが定番であり、学校側の思惑通りには事は上手く運ばないようだ。
かなでが入寮して以降、響也とニアについてはかなでが自分の夕食を作るのに便乗して、かなでの手料理を一緒に食べているが、今日は二人ともそれぞれに予定があって、外で済ませてくると言っていた。ならば菩提樹寮に帰っても、結局かなでが作る夕食は、かなでの一食分だけだ。料理は好きだが、律の夕食を作った後、寮に戻って自分の分だけ作るというのは億劫なので、かなでは律の冷蔵庫を開けて食材を確認しつつ、尋ねてみた。
「ね、律くん。私、夕飯一緒に食べてってもいい? 今日は寮母さんお休みの日だから、寮に戻って改めて自分の分作るの、面倒だし」
「それは構わないが……響也や支倉は大丈夫か?」
律の中でも二人の夕飯をかなでが作ることは、決定事項であるらしい。考えてみれば、去年まではあの二人にプラスして、律もまたかなでの手料理を一緒に食べていたのだ。
かなでは苦笑しながら冷蔵庫を閉める。
「響也はオケ部の子たちと遊びに行ってて、皆で夕飯まで食べてくるって言ってたし、ニアは学内新聞の取材で都内まで行ってくるから、遅くなるんだって。今日は私、戻っても寮で一人なんだ」
「……そう、か」
かなでの返事に、律はふと掌で口元を覆い、何かを考え込んでいる。
それを不思議に思いながらも、かなでの思考はいつしか、冷蔵庫の中にある食材で作れそうな本日の夕飯メニューに埋め尽くされていた。
茄子が残っていたので、律の好物である茄子のしぎ焼きをメインに数種類のかなでの手料理をテーブルに並べ、少し早目の夕食を二人で終える。
かなではリビングに置いてある律の時計で現時刻を確認した後、食器を流しへと運ぶ。寮母のいない菩提樹寮は門限があってないようなものだが、後片付けをして帰れば、ちょうどいい頃合いになるだろう。
そう考えながらかなでは手際よく使った食器を洗い、布巾で拭いて食器棚に戻しておく。後片付けはきちんとしておかないと、こういうことに意外に無頓着な律は、流しに食器を浸けておくくらいの最低限のことはするだろうが、下手をすれば次にかなでがこの部屋を訪れる時まで、食器の山が成長していくだけの事態になりかねない。そうなると、結局片付けるのはかなで自身ということになるのだ。最後に、少しだけ多めに作っておいたしぎ焼きにラップをかけて、冷蔵庫の手前の目につく場所に置いておく。そうすれば、タンスの肥やしならぬ冷蔵庫の肥やしにならず、明日の朝食か昼食かで律が食べるだろう。
「よし、これでいいかな」
基本的に『作業場』以外の場所は物が少ないので、片付けは楽だった。キッチンも使ったものはその都度片付けてくれるのなら問題ないのだろうが、律にその辺りの期待をするだけ無駄だということは、付き合いの長いかなではよく分かっている。
「じゃあ、律くん。私はそろそろ帰るけど……」
手を洗って持参したハンドタオルで拭きながら、かなでが振り返ると、てっきり『作業場』に戻ってヴァイオリンの調整の続きを始めるものだと思っていた律が、そこには立っていた。
「もしかしてお茶でも入れに来た? ついでだし、準備して帰ろうか?」
「あ、いや。……そうではなくて……」
料理をしない律がキッチンに来る理由といえば、それくらいしか思い当たらないので、そう尋ねてみると、珍しく律は歯切れ悪く、辺りに落ち着きなく視線を彷徨わせている。
どこか緊張したような律の様子に、一体何事かと不思議そうにかなでが首を傾げると、やがて思い切ったように律が切り出した。
「実はヴァイオリン以外にも、お前に渡そうと思っていたものがあったんだが……」
「えっ!」
これは、正真正銘のサプライズだった。
律がかなでに渡したいと思うようなものは、ヴァイオリン以外にはないとかなでは考えていたため、他に何を渡されるのか、全くもって予想がつかない。
「受け取ってもらえるだろうか?」
それが何かを言わないまま、律が尋ねる。
だが律が『くれる』というものを、わざわざ断る理由はないので、分からないなりにも、かなでは素直に頷いた。
「うん。私がもらっていいものなら、喜んでもらうけど……」
そう答えたかなでの目の前に、律がすっと小さな箱を差し出す。
それを見て、かなでは思わず息を呑んだ。
箱の大きさは手の平に乗る程度。見た目にもそんなに奇抜なものではなく……どちらかと言えば、中身を簡単に予測できるほどに分かりやすい装飾だった。
それでもこれまでの律の言動を思い返せば、かなでの単純な期待は見事に覆される可能性が高い。あまり過度な期待はしないようにと自分に言い聞かせながら、想像以上に軽い箱を手に取り、おそるおそるかなではそれを開けてみた。
そして開いた箱の中には、かなでの期待通り、シルバーの土台にハートを四つ連ねたクローバーの透かし彫りが施された指輪が収まっていた。
「……かなで。今、あの指輪を持ってるか?」
静かな声で律が尋ねた。
呆然としつつも小さく頷き、かなではいつも自分の首から下げている鎖を引っ張り出した。
その先端には、かなでが幼い頃に律から貰った、王冠型の指輪がある。律が『妖精の王冠だ』と言って、お守り代わりにくれたもの……さすがに今ではサイズが小さすぎて、小指にしかはめられなくなってしまったが、それでも律からもらった大切なお守りなので、未だにこうして肌身離さず持ち歩いている。
「お前がこの指輪を大事にしてくれているのを嬉しく思う半面、ずっと気がかりでもあった。……幼い頃に渡した指輪をこれほど大事にさせるほど、俺は今、お前に何も与えてやれてはいないのではないかと」
目に見えるもの、触れられるものが全てではないと分かっている。律たち音楽に携わる者は、特にそうだ。
だが幼い頃に贈った小さな指輪を後生大事に守り続けるかなでに、あの頃とは違う律の今の気持ちを、上手く彼女に伝えられていないのではないかと、ずっと律は不安だったのだ。
「今日は『意中の相手に贈り物をする日』……ヴァイオリン以外に、俺が何をお前に贈ってやれるだろうかとずっと考えていた。俺の、お前への想いを伝えるために、何を渡せばいいのかと……」
幼い頃を思い返してみても、律にはかなでに何か形のあるものを贈った記憶がない。
誕生日でもクリスマスでも、かなでが律に対して望むものは、いつも律のヴァイオリンの音色だったからだ。
そんな中、唯一律が、かなでに与えた形あるもののことを思い出した。それこそが、あの指輪だった。
「お前にこの指輪を渡した時、お前がとても嬉しそうに笑っていたことを思い出した。単純かもしれないが、贈るのが指輪なら、お前はあの時と同じ笑顔を俺に見せてくれるかもしれないと思って……」
「……律くん」
「ヴァイオリンを弾くには邪魔になるかもしれない。だから、この指輪と同じようにペンダントにして、ずっと肌身離さず、持ち歩いてくれると嬉しい。そうすれば、俺の想いがお前の事をいつも守ってくれる。……俺は、そう信じている」
「……うん」
かなでが、小さく頷いた。
その大きな瞳にはうっすらと涙が浮かび、頬はほんのりと桜色に上気している。その表情から、かなでがこの指輪を心の底から喜んで受け取ってくれたことが、律にも読み取れた。
「あっ……あの。でも、律くん」
ぎゅっと箱ごと指輪を握り締めて何かを思いついたかなでが、慌てた様子で律を仰ぎ見る。
「どうした? かなで」
「あの……も、もちろん、そのまま学校に指輪付けて行けないし、ヴァイオリン弾く時には違和感感じちゃうかもだから、律くんの言うとおり、いつもは鎖に通して持ち歩こうとは思うんだけど!」
――今、付けてみても構わない?
消え入りそうな小さな声で、かなでは律にそう尋ねた。
「……付けて、くれるのか?」
律にとって、そのかなでの申し出は意外なものだった。自分がヴァイオリンの演奏の妨げになるものを好まないため、指輪という装飾品は逆にかなでにとって重く感じてしまうのではないかと考えていたためだ。
「うん、もちろん。……あの、ひ、……左、の。薬指でも……いい?」
……さすがの律にも、かなでの言いたいことは伝わった。
「お前がそれで構わないのなら。……俺は、初めからそのつもりだ」
ヴァイオリンを教える際に、指のポジショニングを調整したりすることがあるため、かなでの指に律は何度も触れていて、その細さは自分の指先がきちんと記憶している。
だからこそ、指輪を選ぶ時にも、その10本の指の中から、一番嵌めていて欲しい指のサイズを選んだつもりだった。
かなでの手の中の箱から指輪だけを抜き取り、律はそっとかなでの小さな左手を取る。
……まるで、神様の前で永遠を誓う時のように。
律はゆっくりと、かなでの左手の薬指に、シルバーの指輪を押し込んだ。
それは、この世に誕生したその時から、かなでの薬指に嵌められることを運命づけられていたかのように、寸分の隙間もなく、ぴったりとかなでの薬指を彩った。
「……すごい、可愛い」
まるで可憐な花が開くような笑顔で、幸せそうにかなでが薬指の指輪を見つめる。
それは律が願った通り、あの時と同じ……いや、律が記憶する限り、一番幸せそうに笑う、かなでの笑顔だった。
「ありがとう、律くん。貰ったヴァイオリンと一緒にずっと、ずっと大事にするね」
その艶やかな笑顔に、律の胸が締め付けられるように痛む。
それは決して嫌な痛みではなく……ずっと、囚われていたいような、心地よい痛み。
まるで、その痛みに導かれるように。
輪郭を確かめるように、律の指先がかなでの柔らかな頬を撫で。
……そして身を屈めた律の唇が、かなでの唇へと降りてくる。
驚いたように一瞬かなでの身体が強張る。その緊張を解すためか、律の腕はそのままかなでの細い姿態を捕らえ、途切れない口付けは、どんどんその深さを増していく。
キスの甘さに酔ったように、かなでの身体が力を失くし、律の胸へ預けられた。弱い力ながらも、かなでの両腕が懸命に律の身体を抱き返した。
……いつだったか、律に恋人としての甲斐性はないだろうと言っていたのは、ニアだっただろうか。
だが、かなでは他の誰も知らないであろう、恋人としての……男性としての律の姿を知っている。
恋人としての律は、普段の姿からは想像がつかない、淡白という言葉からは縁遠い、情熱的な男性だとかなでは思う。
……そう本当は、あの律の情感に満ちたヴァイオリンの音色を聞けば、その本質は自ずと分かるはずなのだ。
「……かなで」
いつもより少し低く、どこか余裕がない律の声。
その声が、かなでの身体をぞくりと震わせる。
「響也や支倉は、帰寮が遅くなると言っていたな。……泊まって行けとまでは言わない。遅くなっても、必ず菩提樹寮まで送り届ける。だから……」
もう少し、ここに一緒にいないか。
そう、律がかなでの耳元で囁いた。
「え……でも」
さすがにかなでも、律の言わんとすることが分からないほどに初心ではない。それに、今律に灯された熱が身体の奥で燻っていて、かなでだって律と離れたくないと思う。それでも、どこか冷静であろうとする理性が、警鐘を鳴らす。遅くなるとはいえ、響也やニアは、菩提樹寮に帰ってくる。二人から夕飯はいらないと言われた時に、「じゃあ、律くんとこで済ませてこようかな」と言ってしまったので、二人にはかなでが今日律の家を訪問したことは知られていた。
男子棟に戻る響也は、特に用事がなければ朝まで顔を合わせることがないので問題ないだろうが、あまり遅くなってしまえば、隣室であるニアには不在を気付かれる。その時に何も勘繰られない自信が、かなでにはない。
もちろん付き合っている男女なのだから、そういうことがあってもおかしくないのだろうし、例えニアが報道部員であっても、自分たちのことを簡単に吹聴することはないというのは分かっている。
……ただ単純に、自分たちが『そういうこと』をしているというのを、親友である彼女に知られることが、たまらなく恥ずかしいのだ。
そんなことを考えていると、律に素直に「うん」と返事が出来ない。どうしよう、何て言おう、と半ば混乱の絶頂にいると、部屋の隅に置いていたかなでのバッグの中から、マナーモードの携帯が振動する気配がした。
「あっ、あの、携帯……!」
天の救いとばかりに、かなでは律から離れ、慌てて自分のバッグに飛び付いた。背後で律が困惑するのが分かったが、ごめんねと心の中で詫びつつ、中に入っていた携帯電話を取り出すと、メールの着信を知らせる文字が表示されていた。
「ニアからだ」
届いたメールを見ると、送り主は先程脳内に浮かんでいたニアからのものだった。件名は呆れ顔の顔文字のみで、内容が予測できない。眉間に皺を寄せつつ、かなではメールを開いてみた。
差出人:ニア
件 名:┐('д')┌
やあ小日向。如月兄との在宅デートは順調かい?
しかし都会というものは思いがけないハプニングに満ちているな。
君はゲリラ豪雨というものを知っているか?
そう、最近よく聞く、さっきまで晴れていたのに突然降り出す大雨のことだよ。
そして都会はそんな突発的な自然災害に、すこぶる弱い。
つまり何が言いたいかと言うと、そのゲリラ豪雨のせいで見事に電車が止まって
しまったんだ。
そして現時点で運転が再開する兆しは皆無。
だが、幸いにも明日は引き続き休日だ。こちらには親戚関連で一晩くらい泊めて
くれる当てもあるし、せっかくだから都会の夜景でも眺めて、お土産に有名人気
洋菓子店のロールケーキでも持って帰るとしよう。
今夜は寮母もいないことだし、君は君で如月兄との甘い夜を満喫するといい。
明日、私が菩提樹寮に戻るまでに、ロールケーキのお供に欠かせない美味しい
フレーバーティの準備をして待っていてくれれば、余計な詮索はしないでおく
としよう。
では小日向、また明日。
ニアにしては珍しい、長文の文面を読み終え、かなでは大きく溜息を付く。文章を追うのに精いっぱいで、内容が上手く頭の中に入ってこない。真っ先に理解したのは、以前雑誌で見て、二人で食べてみたいと話していた、東京の有名な洋菓子店のロールケーキを、ニアがお土産に買ってきてくれるということだった。
そして、次に理解したことは。
(……ニアが今日は、菩提樹寮に帰って来ない)
「……律くん」
携帯を元のようにバッグの中に戻し、かなでが律を振り返った。
「どうした、かなで。支倉が何か言ってきたのか?」
かなでがメールのチェックを終えるまで、ただ黙って待っていた律が尋ねる。かなでが律の誘いを躊躇うのには、かなでの隣室で生活する支倉の存在があることは分かっていた。彼女の帰宅が早まるようなら、律は先程彼女に告げた自分の望みを呑み込んで、かなでを菩提樹寮に帰さなければならない。
だが律の不安とは逆に、かなでは律の腕の中に飛び込んでくる。咄嗟に抱き留めた律が、腕の中のかなでを見下ろした。
「かなで? いったい……」
「ニア、今日は帰らないって」
ぎゅうっと律の身体に縋り付くかなでが、ぽつりと呟く。律は、軽く目を見張った。
かなでの言葉に。腕の中の柔らかな温もりに。
先程かなでに告げた自分の邪な希望が、叶うことを律は知った。
「明日の朝は、響也の朝ごはんの準備するから戻るけど……。今夜は律くんの傍にいていい? 私も、律くんと一緒にいたい」
かなでが、律の期待以上の言葉をくれる。
律はただ、細い彼女の体を、返事の代わりに強く抱き返した。
かなでからは何もいらないと言ったのに、今日は自分の方が貰ってばかりだったと律は思う。
ヴァイオリンを贈った時の、澄んだ音色。温かく美味しい、愛情たっぷりの食事。指輪を渡した時の最高の笑顔。そして何より、一緒に過ごした今日という一日の穏やかで幸せな時間。
そしてこれから。お互いがお互いだけのものであることを実感するための時間。
今日は7月7日。サマーラバーズデー。
意中の相手に贈り物をするという内容にばかり目を向けていたけれど、改めてその言葉の意味を捉えるならば。
『夏の恋人たちの一日』。
……恋人と過ごす甘い夏の一時は。
二人にとって、むしろこれからが本番なのかもしれない。
あとがきという名の言い訳
最近如月兄弟がとにかく可愛いので(笑)、こちらも書いていてとても楽しかったです。
律は割にぐいぐい来るな(笑)
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2016.11.05