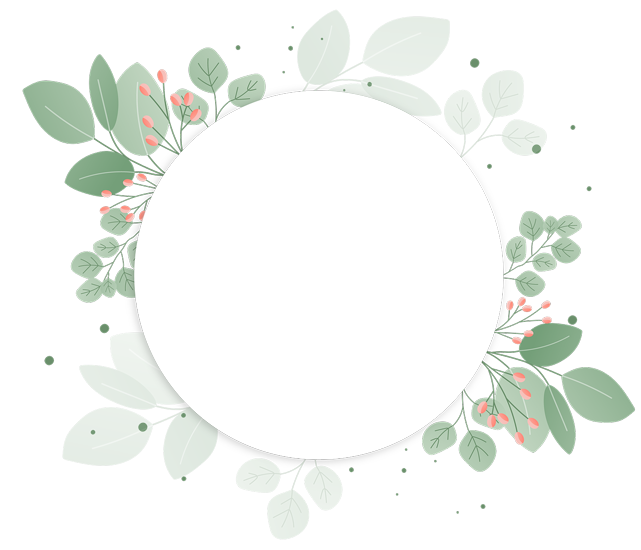もう深夜と言っても差し支えない時刻だった。星奏学院高等部の生徒が複数名暮らす菩提樹寮はよく言えば趣のある、はっきり言ってしまえば老朽化甚だしいボロ屋敷で、十名にも満たない数少ない入寮者の中で女子は仁亜を含めて二人。そのもう一人の入寮者がラウンジにあるソファの上に座り込んで雑誌らしきものを眺めている。以前から女子の入寮者が少なかったためか女子用バスルームは手狭で、二人で相談して交代で入浴するようにしている。だが共になかなかの長風呂なので、後から入る方の就寝が深夜になるのは珍しくない。宵っ張りの仁亜はその後も何だかんだと起きてはいるので問題ないが、もう一人の方は夜更かしも早起きも苦手で、先に入浴を済ませた時にはさっさと自室にこもってしまうことが多い。そのためこの時間まで起きてラウンジにいることは珍しかった。
「こんな時間まで起きているなんて珍しいな、小日向。もう初夏の気配とはいえ、いつまでもこんなところで油を売っていたら湯冷めするだろうに」
静かに声をかけると、小日向かなでは弾かれたように肩を揺らし、仁亜を振り返る。小動物を思わせる丸くあどけない瞳が大きく見開かれた。
「え、嘘。もうこんな時間!?」
壁時計の針の位置を確認し、うう、と小さく唸りながらかなでは読んでいた雑誌を閉じる。「もう寝ないと朝練の時間に起きれない……」と嘆くかなでに、「分かっていると思うが、私は起こさないぞ」と仁亜は忠告した。
「しかし君が読書に夢中になるのは、夜更かしを越えて更に珍しいな。何か興味深い記事でもあったのか?」
尋ねながら、改めてかなでの手の中の雑誌の表紙をよく見れば、それは雑誌ではなく料理のレシピ本だった。
基本的にラウンジのマガジンラックに入っているのは週刊誌やカタログの類だったが、かなでの料理の腕を知った通いの寮母が喜んで初級から上級まで、さまざまなレベルのレシピ本を置くようになった。
かなでも寮母の思惑に上手く乗り、二人の時間の折り合いが付いた時などは新しいメニューに挑戦し、仁亜たちもその御相伴に預かっていたりする。
「おや、また何か新しいメニューに挑戦するつもりか? リクエストを受け付けているなら、この間は中華だったから今度はフレンチが食べてみたいものだが」
「あ、ううん。そうじゃなくてね」
ふるふると首を横に振りながら、かなでは周囲に散らばっていた他のレシピ本もかき集め、仁亜に向かって掲げてみせる。
「ちょっと疲労回復とか、元気になれる料理のレシピがないかなって思ってて……」
大地先輩にね、とほんのりと頬を赤く染め、かなでが俯く。そんなかなでの様子に知らず仁亜は口角を上げ、自室へ向けていた爪先をキッチンへと方向転換し、踏み込んで行く。
「ニア?」と怪訝そうに尋ねるかなでにひらりと片手を振った。
「何やら面白そうな話の匂いがするじゃないか。ゆっくり眠るためのホットミルク一杯を飲む時間、君の話を聞かせてもらうとしよう」
そうして二人で少し甘めのホットミルクを淹れ(余談だが、結局淹れたのはかなでだった)、リビングのソファにお互いに背中を埋めて向かい合う。ふうふうと息を吹きかけて熱めのミルクを冷ましつつ、かなでが話したのはここ最近の『大地先輩』の様子である。
榊大地はかなでや仁亜の一学年上の先輩で、かなでの恋人だ。
数か月前星奏学院を卒業し、今は国立大学の医学部に通っている。生活基盤が変化した特有の忙しさで、なかなか会うこともままならないとかなでが愚痴っていたのは数日前のことだ。仁亜はその時「君が会いたいなら、そう我儘を言ってみればいい。向こうだって会いたくないわけがないだろうから、どうにか都合をつけてくれるだろうさ」とアドバイスらしきものをしたのだが、かなでは律儀に実行したようだ。ここ最近は電話やメールでお互いの近況をやりとりするだけだったが、思い切って「近々逢えませんか?」と尋ねてみると大地からの返事は当然YESで、数週間後の7月7日土曜日に久しぶりにデートをすると、かなでは仁亜に報告した。
「でもね、大地先輩、電話の声もどことなく疲れてる感じで……。私が無理言って会ってもらうんだから、ちょっとでも元気になってもらえたらって思ったの」
お弁当を作ろうとかなでは考えた。それでラウンジにあるレシピ本をひっくり返し、滋養のある料理を吟味していたというわけだ。
「なるほど。君の弁当が絶品なのは間違いないし、榊も別に不満はないだろうが……それは、弁当でなければいけないのか?」
考え込むように唇に人差し指を当て、仁亜は壁に貼られているカレンダーの数字を眺めている。意外なことを言われ、かなではぱちりと大きく瞬きをした。
「お弁当じゃなきゃってことはないけど、何か違うアイデアがあるの?」
「君たちが会うのは7月7日だと言っただろう。お誂え向きの記念日があるのさ」
「記念日?……七夕じゃなくて?」
「そう。……サマーバレンタイン、というね」
「さまーばれんたいん……」
仁亜の言葉を字面通りに呟き、やがて合点がいったように「バレンタイン!」とかなでが言葉を脳内で変換した。満足そうに微笑んで、仁亜が頷く。
「まあ、業界の販促活動の一環ではあるがね。本家本元のようにチョコレートをやり取りするのがメインではないようだが、幸いチョコには疲労回復やエネルギー補給の効果もあり、かつては薬として扱われていた代物だ。君の目的にも十分適ったイベントじゃないか?」
「う……でも、大地先輩、あんまり甘いの得意じゃない……」
「だが、本来のバレンタインデーにはちゃんと榊用に奴の味覚に合わせたチョコを作っていただろう? 同じように君のお手製なら、ヤツは喜んで受け取るだろうさ」
そっか、とかなでは表情を輝かせる。数か月前の元祖バレンタインデーの時も、甘いものが苦手な大地のためにかなではコーヒー風味のものやジンジャー入りなど、甘さ控えめでいて味は特上のチョコレートをせっせと作っていた。どこぞの神戸のセレブ共の言ではないが、彼女が将来の進路をヴァイオリニストではなくバティシエやシェフに方向転換したとしても、充分に成功するだろうと仁亜は常々思っている。
「……うん、チョコの方が勉強の合間に摘まみやすいし、日持ちもいいし、いいかも! ありがとう、ニア」
「アイデア提供の報酬としてお裾分けでもいただければ、私としては提案のし甲斐があったというところだよ」
「勿論、ニアの分も作るからね」
にこにこと笑いながら何種類作ろうかな~と鼻歌交じりに呟くかなでに、仁亜はもう少し突っ込んだことを提案してみる。
「……まあ、榊としては、チョコよりも君を頂く方が疲労回復にはより効果的かもしれないがな」
「…………………………ハイ?」
ぼそりと呟いた仁亜の言葉に、笑顔を凍りつかせたままかなでが振り返る。ある意味予想通りの反応に、にやりと笑いながら、仁亜はホットミルクのカップを両手で抱え込む。
「おや、健全な青少年がもらって元気になるものと言ったら、定番じゃないのか? まあ、逆に体力を消耗する嫌いもあるが。しばらく会っていないのなら、随分ご無沙汰だろうしな」
「いやいやいやいやいや、ちょっと待って……」
あけすけな仁亜の物言いに、みるみるうちにかなでが真っ赤に染まっていく。かなでは奥手で天然だが、仁亜の言葉にピンとこないほど幼くもない。固有名詞を出さない仁亜の言葉の意味を正確に読み取り、仁亜ににじり寄ると、えいや!と両手でかなでは彼女の口元を塞いだ。
「違うから! 私たち、そんなんじゃないから!!」
「……小日向? ……まさか」
まだ、なのか? かなでの掌を剥ぎ取り、半ば愕然と呟く仁亜に、かなでは何度も首を縦に振る。仁亜は露骨に眉根を寄せ、顔を顰めた。
「そんなはずがないだろう、相手はあの榊大地だぞ? 君たちが付き合い始めていったい何か月経ってると思ってるんだ」
「で、でも、本当に、まだそんな感じじゃなくて。そもそも、大地先輩受験で忙しくてそれどころじゃなかったから!」
受験のことを持ち出されれば、納得できなくもない。医者を目指す大地の志望校は星奏学院の長い歴史を遡ってみても合格例の少ない、超が付く難関校だった。恋愛ごとにうつつを抜かすような余裕はなかっただろう。
余談だが、その難関校に一発合格決めた大地の報告に、普通科の職員室では万歳三唱が木霊したとかしないとか。
「それにしても、意外だな。榊の事だからそういう面は万事抜かりなく進めているものだと思っていたが」
だが、そう考えれば合点がいくこともある。かなでが大地と付き合い始めてからも、かなでの様子が目に見えて変化したことが一度もないからだ。正直、二人に何か進展があれば、かなでの態度からそのことを見ぬく自信が仁亜にはある。
「……あの、ニア?」
先ほどの慌てふためきようと打って変わり、どこか不安げに眉を八の字に下げるかなでが上目遣いに仁亜を見つめた。
「あの……やっぱり、大地先輩って、そういう経験……っていうの? 豊富なのかな。私がこっちに来る前のこと、私は知らないから……」
「さあ?」
素気無く仁亜は答える。かなでが見るからに落胆した表情になるが、大地の恋愛遍歴については仁亜は全く知らないに等しいので意地悪をしているわけではない。そもそもかなでを通じてオーケストラ部の活動に深く関わるまでは、寮生だった如月律の親友で、更に女生徒からの写真の注文数が段違いの収入源との認識しかなかった相手だ。それでも同じ普通科だと言うこともあり、目立つ人物であることには違いないので、噂程度は耳に入ってきてはいたが。
「残念ながら榊が誰かと付き合い始めたとか別れたとかの噂は良く流れてきていたが、それが本当かどうかを突っ込んで調べようと思うほど、私には奴に対しての興味がなかったな。……まあ、気になるなら本人に聞いてみれば早いだろう」
「気になるって言うか……先輩が私の前に誰かと付き合ってたとか、そういうことはどうでもいいの。私は今の大地先輩が好きで、今の大地先輩とお付き合いしてて、そういう経験を踏まえて大地先輩が今の先輩になったのなら、それでいいって思ってるから」
こういうことを本心で言えるから、この小日向かなでという少女は面白いのだと、仁亜はつくづく思う。
「で、でもね。私があまり子どもだから、先輩が気を使ったり、我慢してる……ならまだいいけど、全く私に対してそんな気持ち持てないんだったらどうしようって……、ちょっと、ニア?」
失礼なことに、仁亜は肩を小刻みに震わせてくすくすと笑っている。膨れてかなでが仁亜の脇腹を肘で突くと、楽しそうな仁亜がかなでの頭を一撫でした。
「まあ、そういうことも含めて。何か思うところがあるなら、サマーバレンタインに全部ぶつけてみればいい。心配しなくても、君は充分に可愛いよ。榊にくれてやるには勿体ないくらいだ」
少し思案した後にそうする、とかなでは小さく頷き、そしてじとりと仁亜を睨み付ける。
「……可愛いって、小動物的な意味込めてない?」
「ちょうどいいじゃないか。榊は豆柴愛好家だろう?」
しれっと言った仁亜の腕を、全く強くない拳でかなでがぽかぽかと叩く。
さしずめ、今度は猫パンチといったところか? と笑う仁亜に、がっくりとかなでは項垂れた。
そして、7月7日。数日前から大地に渡すための甘味の少ないチョコレートを何作も試作し、仁亜や幼馴染みの響也を含むオケ部部員たちに試食してもらってお墨付きをもらい、可愛らしくラッピングしたそれを抱えて大地と待ち合わせした駅に向かったのだが、改札を抜けて空を仰いだかなでは落胆を隠せなかった。
年に一度、銀河を渡って織姫と彦星が再会する日……だが、そもそも日本のこの時期は梅雨真っ盛りだ。そんなふうに晴天が少ない時期だからこそ、あの伝説が出来たのではないかとかなでは常々思っているが、例外でなく今日も朝から空は曇り模様だった。天気予報も徐々に雨足は強くなると言っていたので、危惧しながらも傘を片手に電車に乗り込んだが、降りる頃には予報に違わず、尋常でないどしゃ降りに変わっていた。別に屋外に遊びに行く予定ではないから、雨だからと言って大地と逢えなくなるわけではないのだが、鈍色の空とアスファルトを叩く大粒の水滴を思うと気が滅入る。軒先で早い速度で流れていく黒雲を睨み付けるように見据えていると、数分後に水を蹴る音が近づいてきた。
「ひなちゃん!」
現金なもので、毎日のように耳元で聞いている声が現実に自分の名を呼んでくれると、それまでの憂鬱が全て吹っ飛ぶような心地がした。そちらに顔を向けると、軒先に駆け込んで傘を畳んだ大地が、片手を挙げてかなでに向かって笑いかけた。
「久しぶり、早かったね。随分待ったかい?」
問われてかなでは大きく首を横に振る。実際、待ち合わせの時刻にはまだ十数分余裕がある。電車のダイヤの関係でかなでの方が早く着いてしまっただけだ。
「まだ電車の遅延が出ていないだけマシだけれど……思いがけず、酷いね」
大地が先程のかなでと同じように曇天を仰ぎ、溜息を付く。釣られるようにかなでも小さく溜息を零しながら、軽く頷いた。
「映画でも見ようかって言ってたけど、映画館は屋内だからいいとして、移動がちょっと辛いかな。スニーカーが既にこの有様だよ」
肩をすくめた大地の足元に視線をやれば、確かにスニーカーが底辺からじわりと濃い色に変わっている。靴が湿る不快感はかなでも馴染みのものだったので、無意識に眉間に皺を寄せる。
「まあ、屋根のあるところを移動していけばそのうち乾くかな。……さて、今は何を上映」
「あの、大地先輩」
言いかけた大地の言葉を遮り、かなでが背の高い大地の顔を見上げた。
「映画はまた別の日にして、場所を変えませんか? 雨を気にしなくていい、ゆっくり話せるところ」
かなでの提案に、面食らったように大地が小さく瞬く。
「そりゃ、これと言って観たいものがあったわけじゃないからね。別に構わないけれど……いったい、どこへ?」
「ご迷惑じゃなければ、大地先輩のおうちへ。モモちゃんにも会いたいし、それ、そのままじゃ気持ち悪いでしょう?」
濡れたスニーカーを指差し、かなでが気遣うように大地を見上げる。その視線を受けて自分のスニーカーを見つめ、「それはそうだけど……」と呟いた大地は、かなでに聞こえるか聞こえないかの小さな低い声で「まいったな」と一人ごちる。
「生憎今日は両親共に出かけてるから、家に来ても碌にもてなしもできないよ?」
「それは、全然大丈夫です。何だったら、私がお昼ごはんも作っちゃいます」
にっこりと笑ってそう答え、あ、でもお台所使うの、失礼かな?と悩むかなでに、大地は小さく溜息を付き「まあいいか」と腰に手を当てた。
「キッチンも食材も好きに使って構わないよ。せっかくの申し出だし、お言葉に甘えようかな。……君と久しぶりにゆっくり顔を見ながら話したいのは、俺も同じだしね」
ほぼ毎日と言っていいほど電話で会話はしているのに、顔を合わせるのは久しぶりだ。かなでももちろん同じ気持ちなので、満面の笑みで頷く。
「モモちゃんに会うのも久しぶりで、嬉しいです! 元気にしてますか?」
「相変わらずだよ。雨続きでなかなか思うように散歩できないから、欲求不満みたいだけれど。君が遊びに来てくれるなら、少しはストレス解消になるかな」
「ふふ、だったら嬉しいんですけど」
「ついでに俺のストレスも解消してくれるかな。せっかく受験が終わったと思ったら、今度は講義の応酬で、さすがに容量オーバーになりそうだ」
「私と一緒にいて解消できるなら、もちろん!」
笑った大地に自然な仕草で手を差し出され、かなでは深く考えることなく、その大きな掌に自分の手を預けた。ぎゅっと一度握り締めた手を「……いや、やっぱりこっちかな」と呟き、指と指の間を絡め、大地が握り直す。
掌全体が密着するその繋ぎ方にかなでが赤くなってちらりと伺うように大地を見上げると、涼しい顔で大地が「じゃあ、移動しようか」とかなでの手を引いて歩き出した。
電車に乗っている間は繋がれたままだった手は、大地宅の最寄駅に到着し、どしゃぶりの雨の中を傘を差して大地宅へ向かうまでに、否応なく離すことになる。大地の温もりから切り離された手は、雨の効果も相まって冷え切ってしまい、同時に雨に備えて履いてきたサンダルも、濡れることが致命的にはならないが、剥き出しの爪先から体温を奪っていった。大地は門をくぐり、玄関にかなでを押し込むと、奥の浴室からタオルを取ってきてかなでに渡してくれた。もう夏が近いため、濡れて冷えたからと言ってどうなるわけでもないのだが、乾いた布地で皮膚を拭うと少しほっとする。そうこうしているうちに奥の部屋からフローリングの床を蹴る軽い足音が近づいてきた。振り返ると、豆柴のモモが大地の顔を見て、それからかなでの顔を見る。怪訝そうに首を傾げた後、かなでのことを思い出したのか、尻尾を振りつつ駆け寄ってきて、わん、と甘えた声で吠えた。
「モモちゃん、久しぶり~! 私の事、ちゃんと覚えててくれてる~」
「そりゃ、こんなに可愛い子のこと、忘れないよな、モモ」
「可愛いとか、そんなのワンコには分かりませんから!」
かなでにハグされたモモの頭を撫でながら大地が軽口をたたくと、頬を膨らませてかなでが抗議する。
そんなことより、と大地が玄関を上がってかなでを促した。
「拭き終ったら上がって、俺の部屋に行っててもらえるかい? 俺はコーヒーでも淹れて来るから」
「あ、はい。お構いなく」
差し出された手にタオルを返却し、かなではモモとじゃれ合いつつ、キッチンの方へ消える大地の背中を見送る。カチャカチャとカップを出し入れする乾いた音を遠くに聞きながら、モモの邪気のない目の中を覗き込んだ。
「何とか自然に、先輩の家に来れた……」
そう、かなではここを訪れることを意識的に狙っていた。雨が降っていなければ、まずどう切り出して大地の部屋に来るかが課題だったので、気持ちを憂鬱にした悪天候は、実は幸運なことでもあったのだ。
「何か、進展とか……あるかな?」
モモの頭を撫でながら、頬を染めたかなでがそう話しかける。
数日前、仁亜に言われた一言が、ずっと気にかかっていた。その時は大げさに騒いで流したものの、実際のところそのもやもやはかなでの中にずっと燻っていた『不安』だったのだ。
「……『あの榊大地なのに』、か」
大地の女性遍歴などかなでには知る由もないし、あの時仁亜に言った言葉にも嘘はなかった。他の女の子と大地がどうだったのかは気にならない。もちろん自分ではない誰かを大切にする大地を想像すると、胸が多少痛くはあるけれど。
だが大地が女性の扱いに慣れていることは、彼の立ち振る舞いを見ていれば嫌でも分かるのだ。もうすぐ付き合い始めて一年が経つと言うのに、キスより先に進まないのはやはりかなでに問題があるのではないだろうか。大事にされていると考えれば喜ぶべきことなのだろうが、そのことに対しては、喜びよりむしろ不安の方が勝る。
「上手く聞けるか分からないけど、頑張ってみるから。応援してね。モモちゃん」
モモの前脚を両手で握って決意を報告すると、器用に後脚でバランスを取るモモは、また元気に「わん!」と鳴いて尻尾を振る。まるで「大丈夫!」と言ってくれたみたいで、かなでは嬉しくてまたぎゅっとモモの身体を抱き締める。
「ひなちゃん?」と両手にマグカップを持った大地に声をかけられるまで、結局かなでは玄関先でいつまでもモモとじゃれ合っていた。
「ご、ごめんなさい……」
「いや、モモも喜んでたからね。久しぶりのお客様だし、あんなにはしゃいでたんだから、モモも楽しかったんだよ。……でもいい加減、飼い主の方も構ってもらえれば、とは思うけどね」
大地の部屋に入ってラグマットの上に座り、かなでが恐縮して身を縮める。苦笑した大地が、湯気の上がるマグカップをそんなかなでに手渡した。
コーヒーの深い芳香。湯気に溶け込んでいるそれに気が付き、かなでは慌てて自分の荷物を引き寄せた。ごそごそとバッグを漁り出すかなでに、大地が不思議そうに首を傾げた。
「ひなちゃん。どうかしたかい?」
「あ、あの。大地先輩。……実は今日、記念日なんです」
「記念日?」
おうむ返しに尋ねる大地に頷き、かなではバッグの中のラッピングしたものを引っ張り出しながら、先日仁亜に聞いた話を大地にも聞かせる。7月7日には販促目的の記念日がいろいろとあること。その中に恋人同士の記念日として、「サマーバレンタイン」というものがあること。疲れている様子の大地の体にいいものをと考えていたら仁亜がこの記念日を教えてくれ、チョコはどうかと提案してくれたこと……。
「先輩、甘いものは苦手だから、甘さは控えめで。でもコーヒーのお供になって、ついでに栄養補給になるようにって思って、いろいろフレーバー試してみたんです。味は、バレンタインの時は美味しいって言ってくれてたから、大丈夫かなって思いますけど、あのもしどうしてもチョコがダメなら、私が持って帰りますから遠慮なく言ってください!」
一息で言い切って、かなではラッピングしたチョコレートを大地の鼻先に突き付ける。面食らったようにそんなかなでとチョコレートの箱を見比べた大地は、微笑みながらその箱を受け取った。
「……電話をする時は疲れていることは気付かせていないつもりだったけれど、やっぱり君にはお見通しだったんだね。君が俺のことを思って作ってくれたチョコレートだろう? ありがとう。もちろん、遠慮なくいただくよ」
想像以上に嬉しそうな表情の大地に、かなではほっと安堵の息を付く。掌の上で軽く箱を弾ませながら、大地はもう片方の指先で自分の顎のラインに触れ、何かを思案する。ぽつりと独り言のように呟いた。
「サマーバレンタインか……。本来のホワイトデーのように、俺がひなちゃんに何かを返すことが出来る日が、別にあるのかな?」
「ニアは商品の販売促進が狙いだって言ってましたし、お返しの話は聞かなかったですけど……。あの、先輩? 先輩がちょっとでも元気になればって思って、それでサマーバレンタインのことを聞いたからチョコにしたってだけなので、いらないですよ? お返しとか」
大地の意図に気が付いて先回りでかなでが釘を刺すと、大地が肩を竦めた。
「ひなちゃんはちっとも俺に君を甘やかせてくれないな。……まあ、無理に押し付けるより、チャンスを伺って君にサプライズで何かプレゼントをする方が、君のびっくりした顔も嬉しそうな顔も見れて、俺にとっても一石二鳥なのかもしれないね」
意外にあっさりと大地は引き下がり、その後コーヒーカップを口元に運びながら、かなでにとっては破壊力抜群の爆弾を平然と投下する。
「……それで君は、俺に一体何を聞きたいのかな?」
「へ!?」
間の抜けた大声がかなでの唇から漏れる。「ききききき、聞きたいことって?」と明らかに動揺したかなでが尋ねると、大地は苦笑しながら玄関の方を指差した。
「さっき、モモ相手に言ってたじゃないか。『上手く聞けるか分からないけど、頑張ってみる』って。俺としては君がそんなに身構えて聞かなきゃならないような隠し事はしていないつもりなんだけどな」
まさか聞かれているとは思わなかった。
元々かなでは大地から何とか自分で納得できる答えを聞き出すつもりはあったが、どう誘導尋問すればそれを引き出せるのかが分からなかった。駆け引きというものがまるで出来ないことはかなで自身がよく分かっているので、思いがけず大地から水を向けてくれたのはありがたいことではある。これが仁亜ならば、報道部の取材で培った話術で、たとえ大地相手でもこちらの胸の内を晒すことなく、上手く聞きたいことを聞き出せるのだろうが。
(……そうだ、ニアだ)
そもそもかなでが悩み始めたのは、仁亜の『あの榊大地が相手なのに』という発言が発端だ。だったら、仁亜に多少の責任を背負ってもらっても罰は当たらないだろう。
「あの……ニ、ニアに、言われたんですけど」
そう切り出したかなでに、大地はわずかに目を細める。
支倉仁亜はかなでの親友であるし、昨年の夏、オケ部がアンサンブルコンクールに奮闘している時にはいろいろと助力してもらった。そういう恩もあるし、別に嫌いだとまでは思わないのだが、大地にとって実は彼女は若干苦手な部類に入る。どれだけ甘く見積もってみても、彼女は間違いなく対岸の火事に火をくべて、燃え上がるさまを楽しむ人種だ。そして素直で人を疑わないかなでは、自分が火種を持たされていることに気付かない。
「付き合ってるのが大地先輩なのに、まだ……キス、だけなのはおかしいって……。そ、それってやっぱり、私が子どもだからなんでしょうか」
「……支倉……」
頭を抱え、押し殺した低い声で大地が呟く。聞いたことのない大地の声に、かなでがびくっと怯えたように身体を震わせた。
「ああ、ごめん。違うんだ」と、大地はかなでに向かって片手を挙げ、それから一度、ゆっくりと深呼吸をする。一気に沸点に達しそうになった脳に酸素を送り、一旦落ち着かせた。
「……ひなちゃん」
どう話を展開させるか、脳をフル回転させながら大地が呼びかけると、かなではまるで叱られた子どもみたいに、上目遣いに大地を見上げ、小さな声で「……はい」と答える。その仕草に、これまでと全く違う衝動が湧き上がりそうになるのを、大地はまた一つ深い溜息を付いて抑えた。
「……君は、どう思ったの?」
「え?」
「支倉が言った通り、俺が君に手を出さないのは俺らしくないって?」
……軽口が過ぎるのはいつもかなでに指摘されることだ。大地なりに紛れもない本心から放った言葉でも、あまりに躊躇なく放つために重く受け止められることがない。かなでに出逢うまでは、むしろそれは大地の周囲の人間関係を円滑に進めるのに有効で、自分の長所だと思っていた。
それなのに、その長所だと思っていたものが、今は大地をとても薄っぺらいに人間に見せている。
『自業自得』という言葉がこれほどまでに符合することもないだろう。今更変えようのない自分らしさが、我ながら情けなかった。
いつになく突き放すような冷たい大地の言葉に、目を丸くしたかなでは、慌てたように首を横に振った。
「そ、そんなことないです。私にとっての大地先輩は、自分の事より私の事を先に考えてくれて、私のためなら自分の気持ちを抑えて、私にそれを絶対に見せない……そんな優しい人で」
でも、とかなでがぎゅっと両手を強く握り締める。
「ニアに言われるまで、私考えたことなかったんです。私は、先輩に不満とか全然なくて、あるとすれば今は学校も違っちゃってなかなか逢えないからそれが寂しいってことくらいで。それでも疲れてるのに先輩、毎日必ず電話してくれるし、私の悩みとか困った事とかちゃんと相談に乗ってくれたりするのに、私いつも自分の事ばっかりで、もし……もし先輩がニアが言ってるみたいな気持ちを私のためにずっと我慢してくれてるなら、それに気付きもしないで先輩の優しさに甘えてる私ってホントに酷い」
「ひなちゃん。……ひなちゃん」
言葉を重ねるうちに、感情が高ぶって涙声になるかなでの手を大地は掴み、その細い身体を抱き寄せる。宥めるように名前を呼びながら、ゆっくりと背中を叩いていると、やがて強張っていたかなでの身体が力を抜いて、大地の胸に預けられた。
「……ごめん。俺の言い方が意地悪だった。……支倉はともかくとして、君にそんな軽い男だって思われてると考えたら、少しだけ、自分が腹立たしかったんだ」
大地の腕の中でかなでが顔を上げ、涙目でじっと大地の顔を見つめる。指先で浮かんだ涙を拭いながら、もう一度首を横に振った。
「大地先輩が、私を大切にしてくれてるのは分かってるんです。……ただ、それが先輩に無理させてるんだったら申し訳ないし、何より……その……先輩が、私のこと、女の子としての魅力に欠けてるって思ってて、これ以上進展の仕様がないって思ってたりしたらどうしようって」
かなでの言葉は最後まで続かなかった。
軽く触れた熱い大地の唇が、かなでの言葉を奪う。突然のキスで目をぱちくりとさせることしか出来ないかなでの顔を、目尻を染めた大地の顔が、至近距離から覗き込む。
「……誰が、女の子としての魅力に欠けるって?」
「あ、あの……でも」
反射的に身体が大地の腕の中から逃げ出そうとするのだが、強い力がそれを許さない。大地の胸に手を付いて離れようと頑張るのに、いつのまにかするりとかなでの腰に回ってきた大地の両腕が、増々力を込めて、かなでを逃がさないようにする。
「……この際だから言っておくけど、俺の鋼の自制心に君は感謝してくれてもいいと思うよ。バードキスで満足しているような君に、それ以上無理はさせられないからね」
「や、やっぱり我慢してたんですね。……あの、でも、何で?」
「それは愚問じゃないかな。……もちろん、君に嫌われたくないからさ」
そう、ただ唇が触れ合うだけのキスで、かなでが満足しているのは彼女の反応を見れば容易く分かる。当然それで大地が満足できるはずもないのだが、かなでに万が一抵抗されたらと考えると、それ以上先に進む勇気が大地にはなかった。
大地が受験生ではなくて、もう少し二人でゆっくりと過ごす時間が多ければ、また変わっていたのかもしれない。星奏学院に在籍している間はできるだけ一緒にいたつもりではあるが、オケ部の後輩たちや、アンサンブルの構成メンバー……要するに、自分たちの周囲には、自分たち以外の存在があることが多かったのだ。その中でかなでとの距離感を上手に測って近づけていくのには、やはり時間が足りなかった。
「そういう意味では、俺は純粋に君を大切にしていただけじゃなくて、俺自身の打算や思惑を充分に混ぜていたわけだけれどね。……臆病すぎて、軽蔑するかい?」
自嘲的に笑って尋ねる大地に、一瞬息を呑んだかなでがまたふるふると首を横に振る。小さく安堵の混じった息を付き、今度は少し意地悪な表情で大地がかなでを見つめる。口元は笑っているが、目が笑っていない。
「さて、ここまでの話を総合してみると、だ。……俺は少し君に踏み込んでみても構わないってことなのかな?」
かなでは困ったように眉を八の字にして大地を見つめ返す。
……それでも、悪天候とはいえ久しぶりの大地とのお出かけデートを蹴ってこの部屋に来たのは、かなで自身がそれを望んだからだ。
悲壮とも言える決死の表情で頷くかなでに、大地は眩しいものを見るかのように目を細め、それから双眸を伏せ、少し斜めに顔を傾け、強くかなでの唇に自分の唇を重ねていく。ぎゅうっと両目を閉じて真っ暗になった視界の中、大地の唇が強引にかなでの唇を割り開いた。
「……ん、……ぅんっ」
より深く重なる場所を確かめるように何度も何度も触れる唇は、深く浅く重なることを繰り返し、やがて大地の舌がかなでの口内を丁寧に味わうように舐めた。少し離れるたびに自分が漏らす濡れた声が恥ずかしい上に、息つく間もなく塞がれるので呼吸が苦しい。
「……ひなちゃん、ちゃんと鼻で息して」
苦しげに眉根を寄せると、それに気付いた大地の低い声がそう教えてくれたのだが、今度は鼻を抜ける吐息がひたすらに甘く、恥ずかしさは一向に解消されない。どれくらいの時間、そうして深いキスをしていたのだろう。名残惜しげに濡れた唇から引いた糸を舐め取った大地がゆっくりと離れると、かなでは息も絶え絶えに大地の胸の中に再度顔を埋めた。
「……まいったな」
こんなに応じてくれると思わなかった。と掠れた声でかなでを抱き締める大地が呟くので、かなでは耳まで真っ赤になる。確かに軽く触れるキスで満足しきっていたはずなのに、いざ深いキスを教えたら、ぎこちないながらも最後は大地の舌の動きに合わせて懸命にかなでの方から舌を絡めていた。
「幸か不幸か、こんな時に限って両親は一日帰らないし」
「え」
「……このまま一緒にいると、一気に距離を詰めてしまいそうになる。早く菩提樹寮まで送った方がいいんだろうけど、外がこれだしね」
困っているのかそうでないのか分からない淡々とした口調で、大地が窓の外に視線をやる。身を起こしたかなでが同じように窓を見れば、大粒の雨が窓を叩いている。
「……先輩」
「ん?」
「今日履いてきたサンダル、先輩に逢う時にって準備した新しいのなんで、濡らしたくないんですけど……」
かなでの声は尻すぼみに徐々に小さくなっていく。何とも唐突で拙い我儘ではあったが、それがかなでに出来る精一杯の二人の距離感を縮めるための合図であることが分からないほど、大地は鈍い男ではない。
もう一度、まいったな、と声にならない声で大地は呟く。かなでを自分の部屋へ招き入れることも含めて、こんな展開はまるで予想していなかった。
いつも通り、映画でも観て、街を歩いて、疲れたらお洒落なカフェでスイーツや食事を楽しむ。そして日が暮れる頃、かなでを菩提樹寮に送り届け、名残惜しげにさよならを告げて、触れるだけのキスを交わして。
そして、いつしか大地の中で不快に燻るようになった邪な願望に目を背け、物わかりのいい頼れる先輩のイメージを維持したまま、彼女と過ごす一日が終わる。この内なる獣を、一体いつまで飼い慣らせるのだろうと一抹の不安を覚えながら。
……そのつもりだったのに。
「……悪いけれど、多分俺は君が思うほど無欲で紳士な男じゃないよ。そんなに無防備に隙を見せるなら、容赦なくそこにつけ込む程度には、ね」
「あ、はい! 望むところ、で、す……?」
言っているうちに、承諾のサインの出し方はこれでいいのだろうかとかなでは首を傾げ、語尾に不自然にハテナマークが付く。かなでらしいといえばかなでらしいその返答に、大地は思わず吹き出してしまう。
「大地先輩、笑うなんてひどいです!」
「ごめんごめん。……こんな時でも、君は変わらずに可愛いなって思っただけだよ」
むーっと膨れるかなでの頭を撫でてやると、「また、ワンコ扱い……」とかなでが明らかに拗ねた。ああ、また悪いところが出ているな、と自嘲的に考えながらも、撫でる手を止めずにいると、不満げに唇を尖らせていたかなでが思い切ったように、えいやっと大地に飛び付いてくる。
何事かと目を見張ると、かなでの唇が大地のそれに重なる。
へたくそでぎこちなくて、とても幼いキスだったけれど、それはまぎれもなく、初めてのかなでからのキスだった。
「……私、モモちゃんじゃないので! これくらいのことはちゃんとできますので!」
何故モモと張り合っているのか分からないが、かなでは憤然としてそう言う。
そんなかなでが可愛くてたまらない。だから、大地はあえてかなでをからかうことにする。
「それがひなちゃん、残念なことにモモもしてくれるんだよ。機嫌がいいと、舐めてくれるからね」
「ええ……」
愕然とした顔をするかなでの頬を、大地は指先で撫でた。
「……だから、せめてこれくらい」
そう言いながら、その柔らかな曲線を描く頬を押さえ、甘く口付ける。
一瞬、強張ったかなでの唇は、懸命に大地の動きに応えようとしてくれる。……それが、とても嬉しかった。
「……心配しなくても、モモにはこんな気持ちは抱かないよ」
……こんな、どこまでも汚らわしくて。どこまでも純粋で。
何よりも大切にしたいのに、何よりもめちゃくちゃにしてやりたくなるような。
そんな、相反する強い衝動。
『こんな』気持ちの詳細を大地が語ることはなかったが、その表情から何かを読み取ったのか、かなではどことなく安堵したような表情で、「なら、いいんです」と、ただ笑った。
その後、コーヒーを新しく淹れなおして、かなでがくれた甘さ控えめのチョコレートをかなでに促されて大地は口にする。
「甘さ、大丈夫でした?」
と不安げにかなでが尋ねるので、「味見してみるかい?」とチョコレートの箱を掲げてみせる。
彼女の事だから自分でもちゃんと味見をしているだろうし、周囲の……それこそ仁亜たちに太鼓判を貰っているのだろうに、やはり大地本人のが食べるものに対しての心配は別のものなのだろう。大地の問いに素直に頷いた。
なので、大地は手頃なサイズのそれを自分の口に含み、そのままかなでの頭を引き寄せて、自分の熱でわずかに表面を溶かした甘くないチョコレートをかなでの唇に押し込んでやる。
成す術もなく口移しでお手製のチョコレートを食べる羽目になったかなでが、何とも言えない表情で、「……こんなに甘いとは思っていませんでした」と呟くので。
また彼女を怒らせる羽目になると分かっているのに、つい大地は笑ってしまうのだった。
あとがきという名の言い訳
自分で書く大地の台詞がとにかく「結婚詐欺師みたくね?」とか思ってたので、公式や中の人や大かなメインで創作書かれる方って偉大だなって思いました(笑)
他の方の大地で思うことないんです。自分が書く大地だけなんです……
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2019.12.30