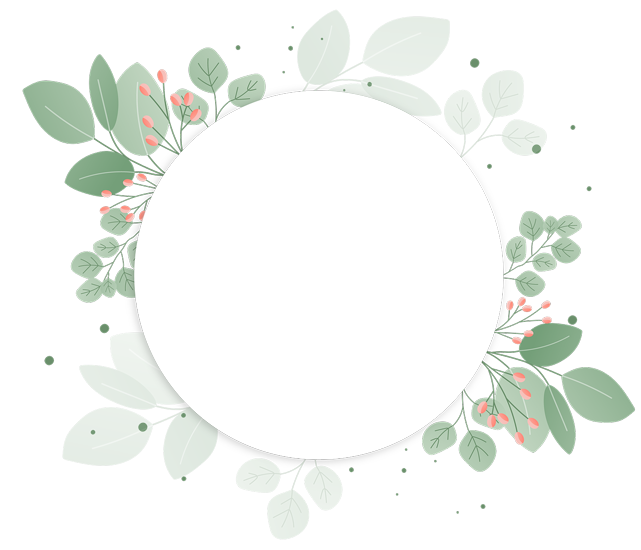ゴールデンウィークに集中していた吹奏楽部の練習が終わり、ハードスケジュールを何とか乗り越え、燃え尽き症候群に陥っている部員たちの中で、一人だけ無駄に元気な水嶋新が、部活動日誌を付けていた小日向かなでの傍に寄ってきて、そう声をかけた。
至誠館高校吹奏楽部の中で、担当楽器がヴァイオリンであるかなでの存在は異質だ。唯一の女子部員であることも相まって、練習日は他の皆と同じだが、練習内容は別メニューが組まれていたため、死屍累々の他メンバーと違ってかなでには体力気力の余裕があった。よって、後片付けや日誌付けなどの雑務を引き受けたのだが、新がじゃれついてくるとどうしてもその手が止まる。幾ら彼氏彼女の間柄とはいえケジメは大事だと、部長である火積には常々言われているので、かなでは心を鬼にして新を振り返った。
「新くん。遊ぶ計画はちゃんと部活が終わって、解散してからで……」
「部活はもう終わりですってー。これ以上何かやれって言われても、指一本動かせませんもん。そしたら今度はかなで先輩の予定が埋まっちゃう前に、さっさと予約入れないとって思うでしょー?」
新の理屈は相変わらず独特でよく分からないが、彼の背後から鋭く向けられている火積の視線がひたすらに痛い。退けていてものらりくらりと躱して、新の望みどおりの答えをかなでから引き出すまで、この問答が終わらないことを分かっているから、かなでは方向性を変えた。
「……空いてる、空いてるから。その日は部活もお休みだし、新くんと約束しても大丈夫だよ。だから、最後のストレッチ、ちゃんとやってね」
かなでの返事にやったーと無邪気に万歳をし、新は大人しく練習後のストレッチをする部員たちの中へと戻って行く。
肺活量や筋力を鍛えることも大事なことなので、至誠館高校吹奏楽部の活動は楽器の練習の他に、ジョギングや筋力トレーニングなどもきっちり行っている。前部長の際には個人の力量で無理なくできる程度だったが、新部長の火積はその辺りが非常にストイックで、かなで以外の部員は文化部に入部したはずなのに予想外の体育会系のノリに悲鳴を上げている。もっとも、それで付いていけないと思う俄かな生徒は仮入部期間が終了する頃には姿を消してしまったので、現在残っている部員たちはきちんとやる気と根性が備わった精鋭たちだ。不満は人一倍多い新も、何だかんだ言いつつもきちんと火積の練習メニューをこなしている。
案外、新がこうして大っぴらに不平不満を口にするから、他の部員たちもあまり心に澱みを溜めることなく火積のスパルタに追従できているのかもしれない。
「……すまねえな、小日向。俺が不甲斐ないばかりに水嶋の操縦まで任せちまってよ」
「操縦……」
小声で労ってくれた火積に、かなでは乾いた笑いを浮かべる。火積は至極真面目な顔で言った。
「八木沢部長ならもっと上手いことアイツを扱えたんだが、俺相手だとちっとも言うことを聞きゃしねえ。水嶋の好き勝手にさせるわけにはいかねえが、アイツの存在が至誠館にとってでけえのは俺にも分かる。……面倒だとは思うが、何とか水嶋がサボらねえように見張っててくれ」
「心得ました。……でも、ああ見えて新くん、火積くんのことは信頼してるし、練習が大事なこともホントはちゃんと分かってるから、大丈夫だよ」
びし、とおどけて敬礼しながら、かなでは笑う。
つられたように苦笑する火積が「だといいんだがな」と、溜息を付いた。
トロンボーン奏者として新の実力は確かに抜きんでているが、如何せん斑が多すぎる。調子がいい時はプロ顔負けの演奏をするのだが、集中力が切れたときの演奏はとても聴けたものではない。そこをどれだけ安定させ、いい音を出させるかが、当面の新の課題だった。
「あー、ぶちょーズルーい! オレのかなで先輩と勝手に目の届かないところで親交深めるの止めてくださいよー!」
「うるせえ! つべこべ言わず、さっさと終わりのストレッチ完遂しろ!」
前部長の八木沢なら笑顔で説き伏せていたが、現部長の火積は言葉の代わりに容赦のない鉄拳制裁がお見舞いされる。拗ねて唇を尖らす新に笑いながら、かなでは新しい至誠館高校吹奏楽部の姿を微笑ましく見守る。
……火積はかなでを必要としてくれているが、『吹奏楽部』として考えた時、自分のヴァイオリンという弦楽器がいつか不穏分子になることをかなでは分かっている。部活動は雑用的なことも多いので、マネジメントに集中するのも一つの手だとは思えるが、それで妥協できるほどかなでの奏者としての矜持も低くはない。
来る夏の全国アンサンブルコンクールまでには、火積と相談して何らかの結論を出さなければと思っている。火積たちの言葉を素直に信じるのであれば、二連覇を目指すためにはかなでのヴァイオリンは必要としてもらえるのかもしれない。だが、今後を思えば『吹奏楽』として至誠館高校の演奏のスタイルを確立することは絶対に必要になる。
……かなでに続く至誠館高校吹奏楽部のヴァイオリニストは、おそらくはもう二度と現れないだろうから。
「そういえば、かなで先輩。何でオレが今度の土曜日に予定を入れようとしたか、聞きたくないですかー?」
全ての練習をこなして新に家まで送ってもらっている途中で、新がそんなことを聞き、細い長身を折り畳むようにしてかなでの顔を覗き込む。部活が休みだから、という以外に理由があるのだろうかとかなでが首を傾げた。
「部活が休みだから、でしょ? ゴールデンウィークに集中したから、メリハリ付けるために今度の土日はお休みって火積部長言ってたし。高校総体の応援演奏もあるから、また来週からは休日返上だしね」
「うっわ、思い出したくない現実を容赦なく突き付けてくるなー!」
両手で顔を覆い、新は天を仰ぐ。くすくす笑いながら、かなでは背の高い新の顔を見上げた。
「……それで、予定を入れようとした理由って?」
「あー、そうでした」
気を取り直したように、新は顔を上げた。
「かなで先輩、今度の土曜日って何日ですっけ?」
唐突な新の問いに戸惑いながら、かなでは真面目に日付を思い出して答える。
「5月9日?」
「ですね。でもって、それが何の日かって、知ってます?」
いよいよかなでは首を傾げる。何の日と即答出来るほど知られた記念日はなかったはずだし、お互いの誕生日でもない。付き合い始めた日は夏だし……と考えていて、ふと思いついたことを言ってみる。
「付き合い始めて何日……みたいな?」
「ざーんねーん、違いますー。……実はその日って、『告白の日』なんですよー」
勿体ぶっていた割に、あっさりと新は答えを白状する。もしかして、早く言いたかったのかな、とかなでは思った。
「あ、5と9で告白の日ってこと?」
脳内で字面を並べて、かなではすぐにその語呂合わせに気がつく。「そうそう」と新が頷いた。
「でも、告白の日だからって、なんで?」
一見答えを与えられたように思えるが、よくよく考えればその日に約束を取り付ける理由にはならない。ふふふーん、と新が意味ありげに笑う。
「それは当然、オレが先輩に告白したいことがあるからですよー」
「えっ」
かなでは驚いた声を上げる。
告白とは普通、想いを告白することではないのだろうか。こう言っては身も蓋もないが、かなでは新が自分を好きでいてくれることを知っているし、逆も新は承知だと思う。自分の気持ちが疑われるような態度を取っていたとは、かなでは思わない。
「それはそれ、これはこれってやつですよ」
唇に指先を当て、新は悪戯っぽく片目を閉じる。どこか楽しげな様子に、その告白というものがそんなに悪い内容ではないのだろうと予測は出来た。だからといって、新の告白の内容が分からないのは変わらないのだが。
「かなで先輩も、何か告白したいネタとかないか、考えといてくださいネ。オレばっかり告白するのもバランス悪いですしー」
勝手にデートをその日に決めたくせに、何故かかなでも告白をしなければならないことになっている。自分は特にない……と言いかけて、かなではふと先程まで自分が考えていたことを思い出した。
(いい機会だから、新くんに相談してみようかな)
かなでが至誠館高校吹奏楽部に入部することになったきっかけは、新だった。街角で新がとても楽しそうにトロンボーンを演奏しているのを見て、自分の演奏に行き詰っていたかなでは、彼と同じ場所に行くことを決めた。……彼と一緒に演奏をすれば、自分も楽しくヴァイオリンが弾けるのではないかと考えたからだ。
その予測は間違っていなかった。吹奏楽部の皆と紆余曲折を乗り越え、時に苦しみ、時に楽しみながら、かなでは自分のヴァイオリンの音色を取り戻し、飛躍した。……そして今、その自分のヴァイオリンこそが、吹奏楽部の本来の音楽を壊してしまうのではないかと危惧している。
……もし、吹奏楽部を辞めるとなれば、やはり新には真っ先に伝えなければならない。新がどこか楽しそうに準備をしている告白と違い、少し重いものになるのかもしれないが、それでもその日をきっかけにして自分の考えを告げておくのはいいアイデアかもしれない。
「うん、……じゃあ、私も。新くんに告白できること、考えておく」
微笑んで頷くと、新の表情がぱあっと明るくなる。かなでの片手を取るとぶんぶんと振り回し、「今度の土曜、楽しみにしてますね!」と笑った。
そして土曜日、5月9日『告白の日』。
かなでと新は予定通りに早朝から落ち合い、仙台の街を手に手を取って歩く。
映画やイベント事等、目的が明確な時は別だが、2人のデートはこうして無為にただ街を歩くだけということが多い。それでもかなではそんな目的のないデートを退屈だと思ったことはなかった。目的はなくても新の話題の引き出しは無駄に宝庫で、かなでも決して口数が少ない方ではないはずなのに、新と一緒にいる時は自然と聞き役に回ってしまう。ファミレスで新の独壇場が繰り広げられているうちに3、4時間経過している、なんてこともざらだった。
しかも、今日は目的がないように見えて、「話をする」ことが最大の目的なのだった。お互いがお互いに対して、何かを告白するのが今日のデートのメインイベントなのだ。……それは元々新が一方的に言い出したことでもあるはずなのに、ちょうど新に相談したい事項があったかなでは、いつしかそれを義務のように感じていた。
「さてと、早速飲み物頼んじゃいますー? 何かつまめる系もあった方がいいですよねー」
部屋に入るなり、ドアの側にある室内電話の受話器を取り上げ、新がかなでを振り返る。
話せればどこでも良かった気がするが、新が選んだのはカラオケボックスの一室だった。かなではいつも通りファミレスで充分だったような気もするのだが、よくよく考えてみれば長居をする気満々でファミレスの一席を占領するのも迷惑行為だと思える。本来の使い方とは違っているが、きちんと決まった時間、料金を払って個室が確保できるのだから、これはこれで正しい選択なのかもしれなかった。
とりあえず飲み物とお菓子の盛り合わせを注文し、新とかなでは並んで曲を入れるためのリモコンの画面を操作する。歌うつもりはなかったが、店員が注文したものを運んでくるまで、カラオケを楽しもうとしているカップルを演じてみた。
やがて、10分もしないうちに店員がドアをノックし、注文した品をテーブルの上に並べて出ていく。まずはお互いに喉を潤して、新が早速山盛りのスナック菓子に手を伸ばしながら尋ねた。
「どっちから行きます?」
カラオケボックスでこの問いなら、本来は歌い出しがどちらかという話になるのだろうが、『告白』の順番であることをかなでは理解していた。新と同じようにブロックチョコを一つ摘み、包装を剥がしながらかなでが新を見つめる。
「私はどっちでもいいけど。新くん、先に話したい?」
こういう時、一応新はかなでの意見を確認してくれるが、基本自分が「こう」だと思った行動しかしない。本人はきちんと人の意見を受け入れて行動しようと努力しているつもりらしいのだが、特に気心が知れた人物が相手だと、無意識に言動が自分のやりたい方へと誘導するものになる。なので、かなでも余程自分に譲れない事情がない限りは、自然と新の意向を確認する癖がついていた。
「あ、いえ! オレは後からで全然いいんで! かなで先輩、お先にどーぞ!」
上向けた掌を差し出され、促されて、かなでは思わず苦笑する。やはり、聞いてはくれるものの、新の中ではきちんと順番が決まっているようだ。
オレンジジュースに挿したストローを軽く噛み、かなでは新を見た。
「私の場合、告白って言うか……ちょっと、新くんに相談したいことになるんだけど……」
「あー、はいはい。全然オッケーです! ……あ、モチロン浮気とか別れる相談とかは即却下ですけどねー」
新の返事に苦笑しながら、かなでは新学年に進級して以降、ずっと自分の脳裏に引っかかっていたことについて、新に告白をする。
「あのね……私、吹奏楽部を辞めた方がいいんじゃないかって思ってて……」
一言を口にして、手に持ったオレンジジュースに向けていた視線を恐る恐る上げてみると、同じようにコーラのカップを抱え、きょとんとした表情でかなでを見つめる新と目が合った。
「……それって、理由聞いてみてもいいですか?」
怒った様子でも困った様子でもなく、それでもいつもの会話より幾分落ち着いた調子で、新が先を促した。
それで、かなでは順を追って説明する。
そもそも、吹奏楽というくくりで考えれば、弦楽器であるヴァイオリンを弾くかなでが吹奏楽部に所属するのは異質であること。
去年のアンサンブルコンクールでは、かなでのヴァイオリンは必要とされていたが、今回新しくアンサンブルを組むに当たっては、今後のことを考えてもヴァイオリン抜きで編成をする方がいいのではないかということ。
ヴァイオリンが必要ないのであれば、かなでが至誠館高校吹奏楽部に所属する理由がないということ……。
新はいつになく真面目な表情でかなでの話を聞いていた。やはり、イベント事に便乗するのには重すぎた話題だっただろうかとかなでが心配していると、テーブルに頬杖を付いてしばらく考え込んでいた新が、ふと中空を見上げた。
「でも、かなで先輩。今までの話って、一番肝心なことが抜けてないですかー?」
「一番肝心な……事?」
かなでが首を傾げる。にっこりと笑う新が、下方からかなでの顔を覗き込んだ。
「ひとまず、吹奏楽部にヴァイオリニストが必要かどうかって話は脇に置いといてー。……かなで先輩自身は、吹奏楽部のこと嫌いになっちゃったんですか?」
「そ、そんなことあるわけない!」
思わずその場に立ち上がってしまいながら、かなでは叫ぶ。
もし、この先一緒に演奏をすることが叶わなくなったとしても、至誠館高校吹奏楽部はかなでが見失っていた大切な音を、取り戻してくれた大切な場所だ。
あの時新と出会わず、吹奏楽部に入部していなければ、今のかなではない。部員も新を初めとして、とても大切で大好きな仲間達だ。彼らから要らないと切り捨てられたって、かなでの思いは変わらない。
「だったら、今まで通りに吹奏楽部員でいればいいんですよ。そりゃ、かなで先輩の言う通り、ヴァイオリン込みのアンサンブル組むのは大変ですけど、それでコンクール勝ち抜けないと思えば、かなで先輩をメンバーから外せばいいわけでしょ? 別にかなで先輩だけじゃなくて、吹奏楽部員全員がメンバーに選ばれるかどうかってのは未知数じゃないですか。かなで先輩が辞めたいわけじゃなきゃ、いる分には全然問題ないですよ」
そもそも、かなで先輩いなかったらオレの扱いに困って、火積ぶちょーがハゲちゃいますよー、と、新は笑った。
新が何でもないことのようにそう言うから、かなでは自分の奥底にある本当の自分の気持ちに気付く。糸が切れたようにソファに座り込んだ。
異分子であるかなでは、誰よりも早く至誠館吹奏楽部の中に、本来は自分の居場所なんてないことを知ってしまった。アンサンブルコンクールの優勝を経て、校内全体に存在価値を知らしめた吹奏楽部は、もう自分がいなくても大丈夫だ。
そして、部員がその真実に気が付いてしまったら。
かなではもう必要がないのだと、そう皆が思ってしまったら。
自分は、「いらない」と皆に言われてしまう。それが、かなでは怖かった。
だったら、自分から離れようとかなでは思った。皆から切り捨てられてしまうより、自分から身を引く方が、幾分か傷が浅い気がしたから。
……新から、はっきりと必要がないと言われれば、思い切れる気がした。
だけど、それは新の指摘通りかなでの本意じゃない。
アンサンブルメンバーになれなくてもいい。コンクールにはソロ部門もあるし、ヴァイオリンを極めていくためには、そこで一人頑張ったっていい。
それでも許されるのならば、かなでは至誠館高校吹奏楽部の一員でいたかった。
「……それにね、かなで先輩。ああ見えて火積ぶちょーも、先輩に吹奏楽部に残ってもらえるように、頑張ってたりするんですよー」
知らないでしょうけど、と新は苦笑した。
かなでのヴァイオリンをどうするかということは、実は八木沢たちが引退する頃から時折話題には上がっていた。勿論、かなで自身がいないところで。吹奏楽部をまとめ、目標だった全国アンサンブルコンクール優勝まで導いてくれた立役者に、今後どう報いていくべきなのかを、かなで以外の部員たちは真剣に考えていたのである。
かなでのヴァイオリンを伸ばすために何かできることがあればいいのだが、吹奏楽の名門と言われる至誠館では、弦楽器を学ぶ環境は整えられていない。近郊で交流があり、オーケストラ部や管弦学部がある学校で合同で練習が出来ないかどうか、新年度が始まって以来、火積や副部長の伊織などがかなでに内緒で掛け合っている最中だ。
「お互いにいろいろ考えてるのに、かなで先輩も火積ぶちょーたちも、変なところで水臭いですよねー?」
呆れたように言って首を傾げる新に、鼻声のかなでが尋ねる。
「私が吹奏楽部にいたいって言えば、いさせてもらえるのかな……。迷惑に、ならないのかな」
その問いに、躊躇うことなく「あったりまえでしょー?」と新が答える。
「むしろ、かなで先輩がいなくなったらオレ、練習全く出来なくて、火積ぶちょー激おこですよ。そしたら吹奏楽部へのダメージ、超デカいと思います!」
「……それは、困るね」
「でしょー?」
……例えば、それが新なりに気を使った、その場しのぎの嘘であったとしても、かなでは嬉しかった。
「やっぱり一度、火積部長とじっくり話してみる」
「……かなで先輩?」
途端に不安そうな表情になる新に微笑んで、かなではそんな彼の目の中を真っ直ぐに見つめる。
「私の事なのに、火積部長や伊織くんに任せっぱなしなのは悪いから。私が自分で何が出来るのか、……吹奏楽部にいるために何をすればいいのか、ちゃんと話し合ってみようって思う」
かなでの答えに、新が安堵したように大きく息を付く。「それ、いいですね!」と手放しで賛同してくれた。
「……ありがとう、新くん。多分、新くんが思ってた『告白』ってこういうことじゃなかったと思うけど、でも話せてよかった」
「まあ、言いづらいことを言うきっかけってこともあるんで、言ってかなで先輩がすっきりできたなら、全然オッケーですけどね」
……かなではふと、新は案外最初から何もかもを分かっていたのかもしれないと思う。自分勝手に振舞っているように見えて、新は意識的か無意識か、意外に周りの空気を読んでいる。普段のかなでの様子から、かなでが思い悩んでいることを感じ取って、今日のような機会を与えてくれたのかもしれない。
「……本当に、ありがとう」
心から感謝を込めてかなでが繰り返すと、少し驚いたような表情で新はかなでを見つめ、それから困ったように空に視線を泳がせる。「そんなに素直に感謝されると、何だかこっちの告白、切り出しにくいですネ」と小さく呟いた声は、他に誰もいないカラオケボックスの一室ではっきりとかなでの耳に届いた。
「……そうだ、新くんの告白を聞かないと。元々そのための記念日だもんね」
そもそも新がかなでに告白したいことがあると言っていたからこそのこの日だということを思い出した。かなで側の告白がとりあえず収束したので、今度は新の告白を聞かなければ、とかなでは頷く。
もしかしたら、そもそもこの日を選んでくれたのはかなでが本心を吐き出しやすいよう、気を使ってくれたのかもしれない。それなら新からの告白は口実で、内容はそれほど重要事ではなくて、新は逆に言い出しにくいのかもしれない。
もしそうであっても、どんなにささやかな告白であろうとも真面目に聞こうと、かなでは改めて背筋を伸ばした。
「新くん、どうぞ」
先ほどの新のように、掌を向けて促す。ここまで来て何故か言いづらそうに顔をしかめる新が、同じように身を起こして背筋を伸ばし、かなでに向き直った。
「……それじゃあかなで先輩。ちょっとこっちに来てもらえます? オレの前まで」
「え? ……う、うん。いいけど……」
戸惑いつつも、新の指示通りかなでは立ち上がり、新側のソファに移動する。それまで対面で向き合っていたが、新の希望通り彼の隣に腰を下ろし、少し高い新の視線を斜め上に捕らえる。
新が一つ咳払いし、そっと手を伸ばしてかなでの片手を取った。
「……一応、予想はしてましたけど、かなで先輩の告白がヒジョーに真面目過ぎて、オレの告白がドン引かれる予感満載なんですよ。……でもオレなりにものすごく深刻な悩みになりつつあるので、もうこの際思い切って言っちゃいますね」
「あ、新くんの深刻な悩み……?」
普段これっぽっちも悩みなどなさそうに見えるだけに、新が持つ『深刻な悩み』の内容が全く想像できず、かなでは慄く。それでも最初の決心通り、受け止められるだけ受け止めようと、気合を入れ直した。
「私で解決できるかは分からないけど、ちゃんと聞くよ。言ってみて」
そう言ってかなでが真っ直ぐに新を見上げると、新は苦笑気味に視線を反らし「まあ、かなで先輩が解決できなきゃ、お手上げですけどねー」と言いながら、もう片方の手も取り、かなでの両手を強く握り締めた。
「……あのね、かなで先輩」
珍しく新の表情から笑みが消え、真剣な眼差しがかなでの目の中を覗き込む。
「オレ……もっと、かなで先輩のこと、触りたいんです」
……あまりに想像外のことを言われてしまい、かなでは一瞬新の言いたいことが分からなかった。
そして脳内で新の言葉をゆっくりと咀嚼し、少々の時間をかけて呑み込んだかなでは、つい困ったように笑う。
「ええ……? 新くんって、充分私のこと触ってると思うけどなあ……」
ブラジルからの帰国子女である新は、出逢った頃からスキンシップが過剰だった。ハグは挨拶代わり、手を繋いだり髪を撫でたりすることも新は全く躊躇うことがなく、幼馴染みの如月兄弟以外とはそこまで異性と触れ合う機会がなかったかなでにとって、新と付き合うことは戸惑いの連続だった。
だが、新があまりに躊躇なくかなでに触れるため、かなでもいつしかそれに慣れてしまった。人前で突然ハグをしたり、頬や額にキスをしてくるのはそれなりにTPOをわきまえて欲しいと思っているが、余程でない限りそれを露骨に拒絶したことはない。愚痴は言いつつも、概ね新の行動は受け入れている。自分の周りのカップルたちと比べても、特に自分たちのスキンシップが不足しているということはないはずだ。
だが、かなでの返答に新は深い溜息を付き、困ったように頭を抱える。
「あー、やっぱり上手いこと伝わってないですねー。……そんなかなで先輩のことが、オレは好きなんですけどー」
「あ、ありが……と?」
新の言葉を、かなではお互いのスキンシップ不足だと捉えた。そして、普段の新が自分に対して行うアレコレから、それは新の気のせいだと結論付けた。だけど新は自分の真意がかなでに伝わっていないと言う。それならば、かなでは新の告白を、他にどう捉えたらいいのだろう……。
「まあ、オレもかなで先輩がそういう方向に解釈するだろうって分かってて、わざと言葉を選んだってとこもあるんですけどね。……あんまりはっきり言いすぎると、かなで先輩が怖がっちゃうかなって思って。こう……本質的なところをマイルドに受け止めてくれないかな~って期待したんですけど、濁したオレがヒキョーでした!」
一息で言い切って、新はぺこんと頭を下げる。それからまた、かなでの両手を改めて握り直し、もう一度仕切り直す。
「もうちょい分かりやすい言葉で言いますね。……かなで先輩、オレはかなで先輩と、もっとエッチなことがしたいです!」
今度こそ、完璧にかなでの思考がフリーズした。
がちっと動きを止めてしまったかなでを、爆弾を投下したはずの新の方は慌てる様子もなく、軽く瞬きをしてかなでの顔を見つめ、かなでが解凍されるのを待っている。
じわじわと頬から耳から熱が広がっていって、一気に真っ赤になったかなでが悲鳴を上げて後ずさった。
「あ、あら、あら、新く……! え、えっち、な、エッチなことって……!」
「あーそれそれ、その反応待ってました! 今度こそ、正確にオレの告白認識してくれたみたいですネ」
反射的に距離を取ろうとしたのに、へらりと笑う新ががっちりかなでの両手を掴んでいて、お互いの腕のリーチ分しか距離が広がらない。
「ほらほらー、かなで先輩。オレが告白した深刻な悩み、解決してくれるんでしょー? 逃げない逃げない」
「だって、だって! そんなこと急に言われても……!」
パニック状態で涙目になるかなでを、まるで憐れむような眼差で見つめ、新が首を傾げる。
「……かなで先輩にとっては突然かもですけど、オレは結構前から頑張って理性保っちゃってましたよー?」
育った環境で身についた己の過剰なスキンシップを、新はこれほどまでに呪ったことはない。
出逢った頃や、付き合い始めのころはまだ良かった。躊躇なくかなでに触れられることは、新にとってプラスでしかなかった。初めは及び腰だったかなでが次第に新の行動に慣れてくれて、ハグや軽いキスを受け入れてくれたことも、ただ幸せだった。
だが、ある程度のスキンシップを受け入れるようになってしまったかなでは、新の方が心配になるくらい無防備だった。
新が抱きしめても、キスを強請ってみても、かなではそれを拒まないし、警戒もしない。……だがそれは、新が望むことを全て受け入れてくれるということと、同意でもないのだ。
「オレが、あれくらいで満足するとでも思ってました? そんなわけないでしょ。目の前に好きな女の子がいたら、そりゃ当然いろんなことしたくなっちゃいますよ」
これまでの新なら、自分の欲求に素直に行動し、かなでの気持ちを無視していたかもしれない。
だが、新はかなでを失いたくなかった。かなでを怖がらせて、嫌われたくないという強い思いが、新にこれまでに経験したことがない究極の我慢を強いていた。
「でもオレ、分かっちゃうんですよね。このままずーっと我慢するのムリだろうなーって。だってオレ、先輩のことむちゃくちゃ愛しちゃってますもん。そしたらどうしても、先輩の事欲しくなりますよね」
別に新は、かなでに自分の欲求を押し付けたいわけじゃない。無理をさせたいわけでもなく、ただかなでには、自分がこんな邪な想いを持っていることを、きちんと理解して欲しかった。
「そうしないとかなで先輩、今日みたいに簡単にオオカミの檻に入って来ちゃうでしょ? ……こういうこと考えてるオレと個室で二人きりとか結構ヤバい状況ってこと、ちゃんと分かってます?」
尋ねれば、かなでは涙目のままふるふると首を横に振る。デスヨネーと新が溜息を付きつつ、天を仰いだ。
「……まあ、エッチなことしたいって一応言ってみましたけど、今日これからそうしたいって話じゃなくて、オレは常々そういうこと考えちゃうので、これからはちゃんと気を付けてくださいって話なんで」
あんまり重く受け止めないでくださいね、とつい冗談の中に混ぜてしまうのは新の悪い癖だ。かなでの性格や、これから先の二人のことを考えても、切り出した以上きちんと結論付けなければならないことは分かっているのに、二人の関係が重苦しいものになることが怖くて、楽な方に逃げてしまう。
……そして新は忘れかけていたが、そんな新の逃げ道を塞いでしまうのがかなでという存在なのだった。
「……待って。待って、新くん。……新くんの真剣な告白なんだから、ちゃんと私に答えさせて」
逃げようとしていたはずのかなでが、いつの間にか逆に引き気味の新の両手を握り返して、ソファの上にきちんと正座する。振り払うことは容易かったろうが、何故かそれが出来ず、新もつられるようにかなでに向かい合って正座してみる。確かに背筋は伸びるが、すぐに足がしびれるだろう。そうは思うが、真面目なかなでの様子に自分だけ崩した姿勢でいることが躊躇われた。
「……ごめんね、予想外の告白で、頭の中パニクっちゃって。何か今の数分で脳がフル稼働してる感じなの……」
「そ、ですね」
神妙に新が答える。
え、何コレ。そんなフラチなこと考える新くんなんて嫌いって言われるフラグ? ……と、新はそんなマイナスなことを考えてしまう。
かなでが現状に満足していることは当然分かっていた。それでも言わずにいられなかったのは新側の事情だが、かなでにはそういう男の本能的な部分の事なんて関係がない。ミスったかなと早くも後悔の念を抱き始める新に、かなでが告げたのは意外な言葉だった。
「……私、新くんにそんな我慢させてるとか、全然考えたことなかった。それは率直に謝る。ごめんね」
「あ、イエ。こちらこそ突然スミマセン」
至極真面目に謝られて、ついつられて新も謝ってしまう。謝らないでと、かなでは首を横に振った。
「……あの、確かに私、新くんとそういうことするって、あんまり考えたことなかった。……でもそれは絶対したくないとかそういうことじゃなくて、私がそういうことに疎くて、それを想像するところまで考えが至らなかっただけで……」
「……?」
新が別の意味で首を傾げる。
予想していた会話の流れに、きちんとかなでの言葉が沿っていかない。
いったいこの会話は、どういう立ち位置に着地するんだろう?
そう訝しむ新に「でも」とかなでが勢いよく顔を上げた。
「でも、私は新くんのことが好きなので! そういうふうに触りたいとか思ってもらえるのは、全然嫌だって思わないし、むしろ嬉しいから! そのことは、ちゃんと分かってて!」
真っ赤になって、半ばやけくそ気味に叫ぶかなでに、新は呆気にとられる。
反射的に身を起こしかけて、早速痺れかけている両足を、ふわふわなソファに取られて前のめりに両手を付き、ぽかんと口を開けたまま、どこか怒ったような表情のかなでの顔を見つめる。
……理解は、少し遅れてやって来た。
「Que alegria!」
流暢なポルトガル語で叫び、新は両腕を伸ばしてぎゅうっとかなでの小さな体を抱き締める。びくりと身体を強張らせるかなでの反応に臆せず、新はその耳元で小さく囁く。
「それって、触るのOKって解釈していいんだよね?」
ぴたりと動きを止めたかなでが、腕の中で深く深く俯く。新の位置からはかなでの頭のてっぺんと髪を丁寧にピン止めで固定しているため、剥き出しになった形のいい耳だけ。その耳を真っ赤に染めたかなでが、小さく頷いてくれた。
「……Obrigado ……eu te amo」
いつも明るく活発な新の声が、不意に低く艶めいた色を帯びる。聞き慣れた新のポルトガル語のはずなのに、咄嗟に意味が浮かばなくて、かなでは思わず顔を上げてその意味を問おうとした。だがかなでの問いは、言葉にすることが出来なかった。
斜めに傾いだ新の唇が、かなでの唇を塞ぐ。そうして触れるだけのキスはこれまでに何度も交わしてきたけれど、このキスは、そこで止まらなかった。
「……ん、……んんっ」
キスってこんなに深くなるものなんだ、とかなでは頭の片隅でぼんやりと思う。歯列を割り、かなでの口内の奥深くに侵入してきた新の熱い舌が、丁寧にかなでの舌をなぞって、舐めて、絡め取る。少しずつ角度は変わるけれど、重なる唇と唇が隙間を作ることがなくて、やがてかなでは息苦しくなってくる。酸素を求めて大きく口を開くと、それをまた新の唇が塞ぐ、堂々巡りだ。
「……ん、……ぅんっ」
かなでが握った拳で新の胸を何度か叩くと、ようやく新が唇を少しだけ浮かしてくれる。引いた糸が音もなく切れて、酸欠も相まったかなでの顔は、これ以上にないくらいに真っ赤になっていた。
「かなで先輩、こういうディープなキスの時は、ちゃーんと鼻で息してネ」
新の方は、ひどく嬉しそうな顔でありながらも、かなでよりは全然余裕が残っていた。こういう時に自分だけが翻弄されている現状が、かなではとても腹立たしい。
「……あれ? 怒っちゃいました? もしかしてオレのキス、あんまり満足してもらえませんでしたー?」
唇を尖らせて、少しだけ拗ねたように俯く新に、そこじゃないし!とかなでは心の中で突っ込んだ。
「キスは! 気持ちよかったけど! でもこっち初心者だから、ちょっと手加減してくれても」
思わず口をついて出た言葉に、新が真顔で目を見開き、「おお……」と感嘆の声を漏らす。あまり深く考えずに発した言葉だったので、自分が何を言ったのかかなではよく分かっていなかった。
新の反応から改めて自分の言動を振り返り、かなでは増々真っ赤になって両手で自分の口元を覆う。そんなかなでの額に自分の額を押し当てて、嬉しそうに微笑む新が、かなでの目の中を覗き込んだ。
「……結構、気持ちよかったですか?」
「……」
かなでがじとりと新を上目遣いに睨んでくるが、頬は紅潮、目は涙目、しかも視線は上目遣いという三点セットはむしろ増々男心をそそるのだと、かなでは学んでおいた方がいいのではないかと新は思う。
(ま、オレにとって不都合はこれっぽっちもないけどネ)
今まで以上に触ることについて、かなでに許可はもらったし。
本能の赴くままに深めたキスは、ちゃんとかなでを気持ちよくできたみたいだし。
後は、自分以外の男の前でこの破壊力満点の表情を簡単に曝け出さないように、気を付けてもらわないと。
(ちょっと痛い目見たら、ちゃんと覚えてくれるかな?)
そんなことを考えながら新は、かなでの腰辺りに置いていた片手をあげ、もう一度かなでと手を繋ぐ。指と指の間をしっかりと絡めて、ぎゅっと強く握り締めて。簡単には離れられないように。
かなでは新の顔と、恋人繋ぎの片手をと見比べて、それから何とも言えない困り顔で新を見上げる。そんなかなでに苦笑しながら、新はもう一度かなでの唇に唇を寄せる。そう言えば、先程の自分の告白はちゃんと伝わっていなかったようだったというのを思い出し、かなでがはっきり認識できる言葉で、きちんと告白をする。
「……愛してるよ、かなでちゃん」
そしてまた、深い口付けをかなでに与えながら。
今度はかなでが、きちんと鼻呼吸をしてくれたら、気持ちいい時間がもっともっと長く続くのにな、と。
呑気に新は思うのだった。
あとがきという名の言い訳
新に真面目なことを言わせるのが難しいのは中の人のせいだと思う!(責任転嫁)
設定資料によれば周囲の空気が読める子のはずですが、え?そうだっけ??とか思っちゃうのも中の人(以下略)
そんな新なだけに最初は欲望全開な告白話になりそうだったのが、かなでの真面目な悩みに救われた感じです。
何かもうここで終わっても収まりよさそうですが、続きも頑張ります。一応。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2019.01.06