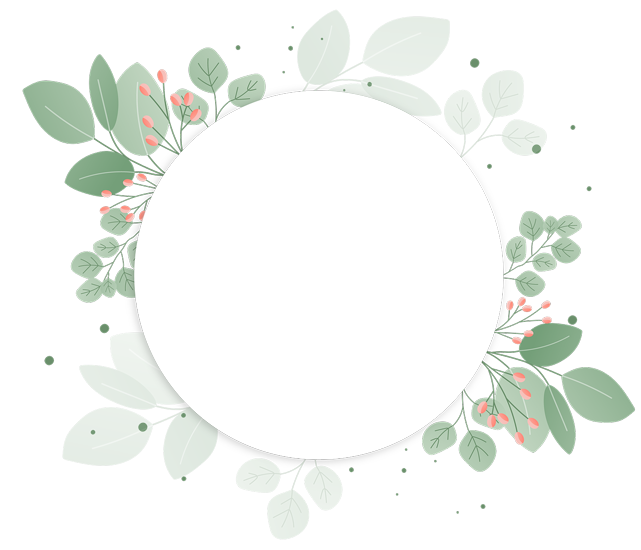同じ新幹線から降りた営業マン風のお兄さんたちが、ビジネスバッグを抱え、足早に背後から追い抜いていく。その流れを遮らないよう、小日向かなでは慌てて建物の軒下へと逃げ込んだ。
しばらくそんな人の流れを眺め、やがて途切れるのを見計らい、かなではゆっくりと歩き出す。待ち合わせ場所と時間は決めてあったが、まだ少し早い時間だ。
観光がてら、周囲をぶらついてみるか、それとも早めに待ち合わせ場所へと移動するか……かなでは少しの間悩む。
駅ビルの中にあるカフェが待ち合わせの場所だ。何か不測の事態が起きても対応できるよう、時間を潰せるような場所を選んだ。待ち合わせの時間までお茶でも飲んでゆっくりしていようと決めて、そちらへつま先を向けた途端、背後から艶のある声がかなでの名前を呼んだ。
「かなで」
一瞬身体を強張らせ、かなでは慌てて振り返る。そんなに大きな声量というわけではない。だが、不思議と耳通りのいい……かなでの大好きな声だ。その声の主を、間違える要素がない。
「東金さん!」
意識せずとも自然に笑顔になりながら、かなではその声の元へ走り出す。歩道上にある、ゲートタイプの車止めに寄り掛かるように立っていた、かなでの恋人である東金千秋が、皮肉げな笑みを浮かべて身を起こした。
「この俺に気付かずに逃げ出そうとは、いい根性じゃねえか。何処に行くつもりだったんだ?」
「に、逃げだそうとしたわけじゃ……っていうか、久し振りなのに、開口一番に言うこと、それなんですか?」
付き合い始めて約10ヶ月。横浜の星奏学院に通うかなでと、地元・神戸の大学に進学した東金は、相変わらず遠距離恋愛が続いている。
フットワークが軽い東金は、当初想像していたよりも、頻繁に横浜まで逢いに来てくれるし、かなでの予定が空けられるときには神戸に宿を取って、かなでが遊びに来れるよう手配してくれる。おかげであまり遠距離恋愛の寂しさを感じることはなかったが、今回は再会までに少し期間が空いていた。
特別な理由があったわけではなく、単に大学に進学したばかりの東金と、高校の最高学年になって、オーケストラ部の副部長に就任したかなでが、それぞれに多忙だったためだ。年度初めの忙しさが落ち着いた頃を見計らって、いつも通りに神戸へと東金が誘いを掛けてくれたのが、たまたまこの時期になったのだ。
「待ち合わせの場所で待ってようと思っただけです! 約束の時間までまだ余裕あるし、まさかもう来てるなんて思わないから……」
必死に言い募るかなでに、東金が心得たように笑う。宥めるようにかなでの頭に大きな掌が乗せられた。
「馬鹿、そんなに必死にならなくても分かってる。冗談だよ。……お前の新幹線のチケットを準備したのは誰だと思ってるんだ? お前を驚かそうと思って、早めに迎えに来てやっただけだ」
「あ……」
そういえばそうだった。
東金がかなでを神戸へ誘う時、東金が何かかなでに負担を強いることはない。必ず連休の前半に、新幹線のチケットと宿泊先を準備して。……自分が横浜までかなでに逢いに来るときには、かなでの都合に合わせてかなりの強行日程になることだってあるのに、不平不満を言うことはないし、疲れた顔を見せることもない。付き合い始めた頃に危惧していたような、東金の大きすぎる器にかなでが付いて行けなくなる日が来る……ということもなく、想像以上に東金は『尽くす』恋人だった。勿論、尽くされることが当たり前にならないかなでが相手だからこそ、現在もきちんと関係を続けることができている。もしかなでが与えられるものを何の疑問も持たずに受け入れて、更に増長するような女であれば、すぐに東金の興味は失われてしまっただろうから。
「さて、せっかく今日のスケジュールを前倒ししてるんだ。久し振りのデートを満喫するとしようぜ」
笑う東金に片手を差し出され、かなではふとその大きな掌と、笑顔とを見比べる。嬉しそうに微笑み返し、「はい!」ととてもいい返事をしたかなでは、躊躇いなく東金の温かな掌の上に自分の小さな掌を重ねた。
「……珍しくお前から『行きたいところがある』って言うから、どこに行くかと思えば……」
落ち合ったときの上機嫌はどこへやら、呆れたように東金が溜息をつく。
今日のデートの目的地は元々かなでが選ぶことになっていた。いつもは東金が勧める劇場や美術館、観光地など……かなでが喜ぶ、またはかなでの今後の演奏の為になる場所を東金が厳選してくれるのだが、いつもデートのプロデュースを東金に任せっきりなのは悪いからと、かなでの方から「今回は、私の希望を聞いて下さい!」と提案したのだ。
そんなかなでが不慣れな神戸の街でスマートフォンの地図アプリを駆使しつつ、東金を連れてきたのは、駅近くにある、所謂「猫カフェ」だった。……よりによって『あの』東金千秋を、猫カフェに連れてくる豪胆さは、さすがにこの小日向かなでしか持ち得ないものだろう。
……ここに相方の土岐蓬生や後輩の芹沢睦がいなくてよかったと東金は心の底から思う。あの二人がいたら、どうにも表現の仕様がない、ひどく生温い眼差しで見つめられたであろうから。
「猫カフェなんざ、横浜にだってあるだろうし、そもそもお前んとこの星奏学院には山のように猫が常駐してるだろうが。わざわざ金払って猫と戯れる必要があるのか?」
「えっと……そりゃ、森の広場に住み着いてる野良ちゃん達と、猫カフェの人間に慣れた子達じゃ違いますよ。私もたまには、もふもふしてる暖かいものに癒やされたいです!」
真っ直ぐに東金を見つめて必死に言い募るかなでに、東金はもう一度深い息をつく。
「……まあ、かなでがそれで良いなら、付き合ってはやるがな」
何だかんだと、東金はかなでに甘い。そして意外に、与えられた状況に乗っかって楽しんでしまえる適応能力も持ち合わせている。
最初こそ、猫カフェに連れて来られたことを不本意に感じていたようだが、一旦今日はここで過ごすのだと納得してしまえば東金の行動は早い。さっさと受付に歩を進め、ポカンと東金を見上げて、その端正な風貌と堂々とした態度に頬を赤らめている店員のお姉さんに、料金システムの説明を促していた。
(……よし、第一関門突破‼︎)
そんな東金の背中を見ながら、かなではぐっと両手を握りしめる。
東金が一旦足を踏み入れてしまえば、そこがどんなに自分にそぐわない環境であろうと、それなりに楽しんでくれる性格だというのを知っているので、とにかく東金に猫カフェに入ってもらうことが、かなでが己に課した最初の試練だった。
そういうことを考えている時点で、もちろんかなでの真の目的は猫カフェの猫たちに心身を癒されることなどではない。
(目指せ、東金さんとかわいい猫とのツーショット! 叶うならば、できるだけ自然な笑顔の写真を‼︎)
バッグの中に収めている高性能のデジタルカメラに布地越しに触れるかなでは、えいえいおー、と東金の視線が届かない場所で、こっそり小さく拳を突き上げるのだった。
かなでが通常ならば撮られることがないであろう、東金のレアなシャッターチャンスを狙うのにはもちろん理由がある。
それは、そもそも東金から二人で逢う日を6月12日と指定されたことに端を発する。
遠距離恋愛中である二人は、東金の努力により他の同じ立場の恋人達よりは逢う頻度が多い方だとは思うのだが、それでも物理的な距離はどうしようもない。逢えるチャンスがある時にはもちろん逃さないようにしていたが、当然のことながら、そう都合よく逢える日ばっかりではなかった。
そうなると、自然に逢う日は記念日的なものを押さえるようになる。曜日の都合や東金のライブ活動の関連で、ピンポイントでその日に逢えるかというとそうではないのだが、元々東金がそういう記念日を満喫したがる方なので、何だかんだ言いながらも、お互いの誕生日やクリスマス、バレンタインやホワイトデーなどはしっかり二人で過ごしていた。
そんな風に、東金と逢えるのは何かの記念日ということが多かったため、今回、何の変哲もない6月12日という日付に、かなでは大いに戸惑った。
(これ……下手すると日付を忘れちゃうやつだ……)
かなではかなでなりに、自分がそこそこ抜けた性質の持ち主であることを自覚している。もちろん、今回は横浜でなく神戸に行く予定で、新幹線のチケットが送られてくることが決定しているため、約束そのものを忘れることはあり得ない。だが、かなでは星奏学院オーケストラ部の副部長として夏の全国アンサンブルコンクールに向けての準備に追われていて、心身ともに余裕がなかった。やるべきことに忙殺されているうちに、何の準備もしないまま、約束の日が来るという可能性は高かった。
(何か、もう一つ気に留めておく要素がないかな)
12日は土曜日なので、週末なのだと記憶しておけば何とかなりそうな気もするが、ここ最近は忙しすぎて曜日の感覚がなくなっていることもある。東金との久しぶりの逢瀬を心の底から楽しむためにも、万全の策を打っておきたいかなでだった。
……そこまで色々考えている時点で、むしろ忘れることはなさそうなのだが、かなではとにかく自分の記憶力を信用していなかった。
何か、もう一つ6月12日という日付を覚える要素を……と、インターネットで検索をかけてみると、すぐにヒットしたのが「恋人の日」という記念日だった。
翌日の6月13日が縁結びの神といわれている聖アントニオの命日で、ブラジルではその前日である12日に恋人同士でフォトフレームを贈りあうといった習慣があり、それが発祥となっている記念日なのだという。説明書きで、『お互いにフレームと、中に飾る写真を送りあってはいかがでしょう』と勧めてあり、思いがけない記念日の発見にかなでは感心してしまった。日本では額縁のPR活動の一環で実施しているとのことなので、あまりロマンティックなものではなく、むしろ販促的な面が大きいのだろうが、フォトフレームを贈りあうというのは、とても素敵な習慣だと思う。そこにお互いの写真を入れて交換するというのは、尚更。
「東金さんの写真、あるにはあるんだけど、何というか……無駄にカッコいいんだよね……」
ライブ活動にファンサービスは付きものなので、東金は土岐や芹沢とともに写真を撮られる機会が多い。そのためか、かなでの携帯電話の中に残る東金の姿は、ある意味『完璧』なものだ。雑誌やブロマイドに使われるような、隙のない格好良さ。
「いいんだよ? うん。これはこれでいいんだけど……」
一人で頷きつつ、かなでは携帯の画面の小さな東金の姿を見つめる。
自分の独占欲や優越感や……そんな良くない感情で出来上がったものだと分かっているけれど、どうしてもかなではこの東金の姿が、『本物ではない』と感じてしまう。東金がかなでに向けてくれる笑顔は、もっと自然で、無邪気で……上手くは言えないけれど、とにかくもっと特別だと思う。
それは多分、東金がかなでに対して心をある程度許してくれているからの笑顔で、かなでにしか見せることのない表情だからだ。
(どうせなら)
『恋人の日』に、もしお互いの写真を入れたフォトフレームを贈り合うのなら。
かなでしか知らない、特別で、そして何よりも、飾らない東金らしい笑顔の写真をもらいたい。
……この時点でかなでは、贈り『合う』のであれば、自分の写真を東金に渡す必要があることには思い至っていない。偶然知った、恋人に逢うのに相応しい記念日に沿ったことを実行するという使命で、頭がいっぱいになってしまった。
そう、『かなでにしか見せない、自然な東金の笑顔の写真を撮る』という使命で。
「ねえ、ニア。携帯から写真を綺麗にプリントアウトってできる?」
目標を立てたものの、達成に至るまではいくつか難関がある。一番は、フォトフレームに収められるようなレベルの写真が、かなでに撮れるのかどうかだ。かなでも携帯を使って写真を撮ることはあるが、それをプリントアウトするまではやったことがない。身近で一番こういうことに詳しそうな、隣人で報道部の支倉仁亜に、助言を仰ぐことにした。夜中に突然やってきて、突拍子もないことを尋ねるかなでに、仁亜は幾分面倒くさそうに、顔をしかめた。
「相変わらず君の疑問は脈絡がないな。……できるかできないかで答えれば、『可』だろう。だが、それには携帯やプリンターのスペックや画像の解像度や……『綺麗』に出力するために、色々と条件があるが」
「私の携帯からだとどうかな?」
「君の携帯は、カメラ機能に特化していない機種だろう。そんなに写真を撮る機会がないから、ほどほどでいいと言っていなかったか?」
機械関係にあまり詳しくないかなでに付き合って、仁亜はかなでの携帯の機種変更に立ち会っている。そのため、かなでが現在所持している携帯の状況については、おそらく本人よりも詳しく把握していた。かなでの上げる条件に合わせて、機種を選んでやったのは仁亜だからだ。
「あ、そっか。……じゃあ、フォトフレームに収められるくらいの綺麗な写真って、私の携帯からじゃ難しいかな」
「まあ今時の携帯は性能がいいからな。フォトコンテストに出すとかいうレベルでなければ構わないと思うが。……私としては、何故突然君が写真撮影に目覚めたのか、その理由のほうが気になるな」
にやりと何かを含んだ笑みを見せる仁亜に、元々かなでは隠し事をしようという気がない。あっさりと、先ほどの東金の写真を撮りたいと思うに至った経緯を話して聞かせた。
「……ほーう。あの西の覇者のレア写真の撮影、ねえ……」
心底楽しくて仕方ない、と言わんばかりの仁亜の物言いに、あまり仁亜に対して警戒心を持っていないかなででも、何となく失敗したかな?という気分になってしまう。何か無茶な要求でもされるのかと、つい身構えてしまうかなでに、不意に立ち上がった仁亜は自分の引き出しの中から何かを引っ張り出し、それをかなでの鼻先に差し出した。
「私のデジカメの予備だ。型は古いが性能はいい。撮り終わったらカメラを扱っている専門店に持ち込めば、現像もしてもらえる。これでよければ無期限で貸し出そう」
「え、いいの?」
思いがけない仁亜からの申し出に、数十秒前までは確かに満ち満ちていた警戒心がかき消えた。そっと両手で受け取ると、満面の笑みを浮かべる仁亜が小首を傾げる。
「どうせだから、上手な写真の撮り方もレクチャーしてやろう。写真を撮りたい理由がそれならば、より良い写真を撮らなければ意味がないだろうからな?」
「本当に? 助かるよ! ありがとう、ニア!」
素直に感謝を述べるかなでに仁亜は軽く頷き、それからかなでが神戸に出かける日の前日まで、良い写真を撮るコツやデジタルカメラの扱い方を事細かに説明し、「健闘を祈るよ」と穏やかに菩提樹寮から出かけていくかなでを見送ってくれたのだった。
……勿論、そこにはしっかりと仁亜の勝手な思惑が存在することを、かなでは知る由もなかった。
この『猫カフェ』のシステムはそんなに複雑なものではなく、ワンオーダー45分制で、写真撮影可というものだ。
保護猫の譲渡目的も兼ねられているので、SNSへのアップも推奨しているという。……店員のお姉さんが、何故かそれを、利用するかなでと東金の二人にではなく、東金に向かってのみ一生懸命説明していたのは納得できかねる部分ではあるが。
「とりあえず45分で入店するが、それで構わねえよな?」
東金に尋ねられ、かなでは頷く。
じっくり猫と過ごすことが目的ならば、45分なんてあっという間だろうが、かなでの最大の目的は、東金と可愛い猫とのツーショット写真を撮ることだ。そのためには45分もあれば十分だと思える。逆に、あまりもたついてしまえば東金にかなでの本当の目的を悟られかねない。
勿論、素直に写真を撮りたいと言えば、東金が快く撮らせてくれることは分かっている。だがかなでが撮りたいのは、あまりレンズを意識していない自然な東金の表情なのだ。
「あ、あの、東金さん。さっき店員さんもああ言ってましたし、練習の合間とかに眺めて和みたいんで、私、ネコちゃんの写真、いろいろ撮ってきますね。東金さんは飲み物とか頼んで、ゆっくりしててください」
「……ああ?」
承諾とも問いかけとも取れる声を東金が漏らすが、かなでは勝手に承諾と受け取って、バッグの中からデジタルカメラを取り出した。予め目をつけておいた、部屋の隅の方にいた茶トラの猫に「こんにちは、お写真撮らせてね~」と話しかけつつ、レンズを向ける。「……デジカメ持参とか、ずいぶん用意周到だな」と苦笑交じりに呟く東金にひやりとしながらも、茶トラと同じように寝転んで、近づいてくるかなでにけだるげに視線を向ける猫たちの写真を、何枚も撮影していった。
そうこうしているうちに、東金が座っているソファの上に黒猫が近寄っていく。東金はわざわざ自分から思い思いの場所でくつろぐ猫たちに近づこうとはしなかったが、勝手に近づいてくる猫を邪険にはしないということも、昨年の夏、森の広場の野良猫たちと東金とのやりとりを見ていたかなでは知っていた。案の定、見知らぬ人間に興味津々の黒猫がおそるおそる東金に近づき、それから安心したように身体を擦り付けてくるのを、東金はどこか優しい眼差しで見下ろして、そっと片手を伸ばして、その艶やかな毛並みを撫でてやっていた。
(黒猫ちゃん、グッジョブ!!)
心の中でガッツポーズを決めながら、かなではデジカメの望遠機能と連写機能とを駆使して、その東金が滅多に見せることのない、穏やかで柔らかな表情を懸命にデータに収めていく。
仁亜からのアドバイスは、「自然な表情を写真に撮るには、被写体に気付かれないように離れた場所から撮影をすること、そして一瞬のシャッターチャンスを逃さないようにするために、連写で撮影をすること」だ。
……かなでは、これが立派な『隠し撮り』のコツであることには思い至っていない。
やがて、あっという間に45分の時間が過ぎ、退出のために東金に店員が声をかけてくる。元々好き好んでこの場に来たわけではない東金は、猫に夢中になることもないが、寄ってくる人なつこい猫にはそれなりにおやつを与えたり、おもちゃで遊んでやったりと猫カフェならではの時間を過ごしていた。ただし、ワンオーダーで頼んだ紅茶はあまり口に合わなかったらしく、カップを口に運んだときに少しだけ表情を歪めていたのにかなでは気付いていた。
そんなかなでは初めの15分くらいはとにかく東金の写真を撮るために頑張っていたのだが、ある程度撮り終えたところで、「遊んで?」と言いたげに足下に寄ってきてつぶらな目で自分を見上げてきた子猫の誘惑に負けて、いつしか撮影そっちのけで全力で子猫と戯れていたのだった。……これが正しい『猫カフェ』のあり方なので、後悔はしていない。
(まあ、狙っていた東金さんの写真はちゃんと撮れてるはずだし……)
できあがりは後でホテルに戻って一人になったところで確認してみないと分からないが、仁亜が教えてくれた連写機能のおかげで、シャッターチャンスは逃さなかったはずだ。そう思いつつデジタルカメラを握り締めていると、ソファから立ち上がった東金がふとこちらに視線を向けた。
「時間だ、かなで。そろそろ行くぞ」
はい、と返事をして、かなでは慌てて飲み終えていなかった冷えたミルクティーを喉に流し込み、東金を追いかける。支払いをしようとした東金は、かなでが辿り着く前にレジ前で店員のお姉さん方に捕まっていた。
「あの、良かったらここに飾る写真を撮らせていただけませんかぁ? 保護猫の譲渡活動のために、お客様と猫とが仲良く過ごしている写真を撮らせてもらってるんですー」
語尾にハートマークが付きそうな甘ったるい声で、お姉さんが東金に写真撮影を依頼していた。確かにレジ前に掲げられた大きなコルクボードには、いろんな客と猫との写真がたくさん貼り付けてある。別に嘘ではないのだろうけど、ここに入店してからのお姉さん方の態度を見ていると、あまり良い気分はしないかなでだった。……勿論、自分がそんな不満を言えた義理ではないことは分かっているのだが。
東金は一瞬だけ不快そうに眉をひそめ、それからちらりと肩越しにかなでを振り返る。思わず身を固くするかなでをじっと見つめ、それから何かを思いついたように指先を顎付近に当て、にやりと笑った。
「……そうですね、構いませんよ。よろしければ、こちらからもこのチラシを置かせていただければ嬉しいのですが」
東金が自分のバッグの中からチラシの束を取り出す。かなでも何度か見たことのある、東金たちのライブ告知のチラシだ。内容に目を通し、お姉さん方が黄色い声を上げる。「楽器の演奏とかされるんですか? 私、絶対ライブ観に行きます!」と頬を染めるお姉さん方に、かなではふと首を傾げた。
自分たちの力量を正しく把握する東金は、選んだ会場を埋められるくらいの集客は最初から見越しているし、こんな行き当たりばったりの形で告知活動をすることは珍しい。だが、きちんとチラシを持っていたところをみると、かなでが知らないだけで案外草の根活動的なこともちゃんとしているのかもしれない。
そんなことをつらつらと考えていると、東金がかなでを手招いた。
「かなで、来いよ」
深く考えることなくかなでが東金の傍に歩み寄ると、一つ頷く東金が、お姉さんが撮影用に連れてきていた先程の黒猫を抱き取り、そしてそのままかなでの腕の中に柔らかな生き物を押しつけてくる。反射的に黒猫を受け取ったかなでの背後に東金が立ち、そして……
「どうぞ、撮影して下さい」
東金がにこやかに告げる。
お姉さん方からは悲鳴のような声が上がり、かなでは逆に言葉を失った。
背中全体で東金のぬくもりを感じる。……これはいわゆるバックハグというやつなのではなかろうか。
「……猫にかまけて、俺を構わなかったお仕置きだ」
低く耳元で響く声に斜めに東金を見上げると、言葉の割に柔らかな表情で東金はかなでを見つめていた。
そして、お姉さん方の狙いは東金単体の写真だったのだろうが、『お客様と猫が仲良く過ごしている写真』を注文した手前、「いちゃつくカップルと猫が仲良く過ごしている写真ならいりません!」と言い出せるはずもなく、かなでと東金、そして空気を全く読まず、なつっこくかなでの胸にすり寄ってくる黒猫のスリーショットを撮る羽目になったのである。
「やれやれ、価格に見合わねえ不味い茶だったが、思いがけずチラシも置かせてもらえたし、広報活動の一環だと思えば安いもんか……」
猫カフェなどの動物とのふれあいを目的とする施設は、スタッフである動物たちの世話にかかる費用も見越して、価格帯は高めに設定してあるところが多い。出された紅茶の質について文句は言うものの、東金もその辺りは心得ているのだろう。店を出るときにはレジ前の募金箱の中に数枚の紙幣を無造作に突っ込んでいて、別の意味で店員のお姉さんが目を見張っていたことに、かなでは気付いていた。
その東金らしい、ストレートではない優しさに一人にこにこしながら、かなでは東金の数歩後ろを付いて歩く。東金は先に立って歩くことが多いが、かなでの歩調は把握しているらしく、置いて行かれることはほとんどないため、あまり気にならない。
店から離れ、広い公園に足を踏み入れた東金の足が止まり、ふと東金がかなでを振り返る。釣られて足を止めたかなでが首を傾げつつ東金を見上げると、唇の端をゆがめるようにして笑う東金が、かなでに片手を差し出した。
「……さて。それじゃ見せてもらおうか。お前があのカフェで何を必死に撮っていたのか」
「は?」
反射的に大声を上げてしまい、かなでは慌てて周辺を伺う。東金も予め織り込み済みで切り出したのだろう。かなでの大声を咎めるような人物は周囲に誰もいなかった。
「えっ……と、さっきも言いましたけど、ネコちゃんの写真です、よ? 練習の合間とか、時々見て、和めたらいいかな、なんて」
俯きつつも、必死で誤魔化す言葉を口にしてみるが、それで騙されてくれるような東金ではない。
「だったら、お前なら使い慣れていないデジカメじゃなくて、携帯を使うだろう。練習の合間に見るなら、普段持ち歩いている携帯の方が使い勝手がいいからな。……しかも、そのデジカメはあの星奏学院の支倉が去年のアンサンブルコンクールの時に持ち歩いていたものだ。まさかお前、あの猫女と共謀して俺の写真で荒稼ぎでもするつもりじゃないだろうな」
先程までは冗談を含んでいた東金の口調が、わずかに真剣味を帯びる。顔を上げると、口元は弧を描いているものの、決して笑ってはいない東金の眼差に行き当たって、ふと背筋がひやりとした。
怒らせている……というよりは、むしろ……
(き、傷つけてる……!)
「……お前が主導でやっているとはさすがに思わねえが、猫女の口車に簡単に乗せられそうではあるからな」
「猫女って……ニア……ですか? ……確かに、ニア相手だと私なんか上手く言いくるめられそうな感じはしますけど、だからといってニアが私を利用したりすることはないと思いますし……あの、いろいろと誤解です……」
どうにか上手く誤魔化せないかと思考を巡らすものの、かなでの性格上、それができるとは到底自分でも思えなかった。任務失敗だなあと肩を落としつつ、かなでは正直に全てを東金に打ち明ける。
今日が『恋人の日』という記念日であること。
この日は恋人同士でフォトフレームを贈り合うという習慣があること。
フォトフレームに入れるため、東金の写真が欲しかったこと。
……できればそれは、かなでしか知らないような、柔らかな表情の東金の写真であって欲しかったこと……。
「それで、ちょっとでも良い写真に撮れないかってニアに相談したら、このデジカメを貸してくれたんです。撮り方もいろいろと教えてくれて。そうしたら、私が欲しいなって思う、私しか知らない東金さんの写真が上手く撮れるんじゃないかなって……」
「……」
かなでの拙い説明を、東金は黙ったまま聞いていた。かなでが口をつぐんだところで、深く溜息をつき、少し呆れの混じった声でかなでの名を呼ぶ。
「かなで。……そのデジカメ、貸してみろ」
「は、はい。……あ、でも、連写機能で撮ってたから、私もどんな風に撮れているのか分からないんですけど……」
かなでがおそるおそるバッグの中からデジカメを取り出し、東金に差し出す。受け取った東金は、特に手間取ることもなくカメラを操作して、かなでが撮った写真を眺めていく。「……途中で本題を忘れやがったな?」と苦笑されて、かなでは思わず視線を反らす。途中からは、ひたすらに可愛らしい猫ばかりが写っているはずだ。
「お前、このデジカメをこの後どうするつもりだった?」
「えっと、最終的にはフォトフレームに入れる写真にしたかったので……どこかに現像に出して、プリントアウトしてもらうつもりでした」
その後、データは破棄してしまうつもりだった。かなでは仁亜のことは親友として大好きだが、報道部員として、そして撮り溜めた写真で小金を稼ぐ商売人として、彼女には迂闊にデータを渡してはいけないことは分かっていたのだ。
「このデジカメ、データをメモリーカードに保存する設定になっているのには気付いていたか?」
「……?」
「つまり、お前がメモリーカードの存在に気付かずに、丸投げで店にプリントアウトに出して、データそのものを見つけきれずにデータの削除の仕方を猫女に聞こうとデジカメを返そうものなら、まんまとメモリーカードのみを抜き取られた可能性があるわけだ。……まあ、デジカメの扱いに慣れてない奴が相手でないと、使えない手だがな」
「……私、慣れてない、ですもんね……」
がっくりとかなでが肩を落とす。
道理で仁亜が細々と世話を焼いてくれたわけだ。かなでにとってレアな写真は、きっと東金のファンの方々にも垂涎もののレア写真になるだろう。
そういう写真が出来上がると分かっていて、仁亜が手に入れる機会をみすみす逃すわけがなかったのだ。
「東金さん……私も、データ見てみてもいいですか?」
しゅん、と落ち込みつつ、ちらりと東金を見やってかなでが尋ねる。何故か小さく息を呑んだ東金が、無言でデジカメを返してくれた。
受け取ったデジカメを慣れない手つきで操作し、かなでは自分が撮ったデータを確認してみる。
最初の方は、上手く撮れていない。ピントが合っておらず、東金という被写体が端っこの方にいたり、見切れていたりする。その中に、数枚だけかなでが意図していたような写真がある。作られた表情ではなく、自然に、穏やかに、あの黒猫と戯れる東金の微笑み。良い写真が撮れたな、と思うのと同時に、直接見たかったなとも思う。何とか奇跡の一瞬を捉えようとして、かなでの意識はずっとデジカメの方にあったから。
「……勿体ないけど、データ、消しますね」
「いいのか?」
静かに尋ねた東金に、こくんとかなでは頷いた。
「さすがに、ニアに狙われるの分かってて、こんな写真残すわけにはいかないです。……この東金さんの表情を私以外の人に知られるのも嫌だし……」
少し唇を尖らせて呟くかなでに、再度小さく息を呑んだ東金は、はあ、と詰めていた息を大きく吐き出した。扱いが分からずもたつくかなでから「消してやる」と言ってデジカメを奪うと、自分が写っているデータを躊躇せずにさくさく消していく。その淡々とした作業を、かなり残念な気持ちで見つめるかなでにデジカメを差し出しながら、もう片方の手を突きつける。
「携帯を寄越せ」
「はい?」
首を傾げつつも、有無を言わせないその態度に、かなではバッグの中から携帯を取り出し、デジカメと引き換えにするようにして東金に渡した。迷いのない扱い方で、しばらくディスプレイをスクロールさせたり、カメラ機能を立ち上げて視点を切り替えてみたり、レンズの収める範囲を確認したりしていた東金は、かなでの片手に携帯を握らせると、その手を持ち上げて、ある程度の高さで固定する。
「この位置で構えてろ。俺がいいと言ったらシャッターを押せ」
いいな?と念を押されて、よく分からないまま、かなでは頷く。ついでに、携帯のディスプレイを覗かないこともそこで約束させられた。
よく分からないまま、中途半端な高さで固定された腕がぶれてしまわないように、もう片方の手を添えてかなでは携帯を構える。数メートル離れたところまで移動した東金が、「1、2、3で、シャッターを押せ」と指示してきたので、とりあえず頷いた。
目を伏せた東金がふ、と息をつく。そのタイミングを逃さないように、かなではディスプレイを見ないようにしながらも、シャッターボタンの上に指先を置いた。
「行くぞ。……1、2……3!」
ピッ……カシャッ、と、聞き慣れたシャッター音が手の中で鳴る。視界の片隅で、ディスプレイが一瞬固まって、また撮影モードに戻る。果たしてかなでは東金の指示通りに上手くタイミングを合わせられたのだろうか。
おそらく東金の写真を撮らされたのだということは分かる。だが、なぜ彼が急に写真を撮らせたのか、その理由が分からない。同時に、タイミングを合わせることのみに集中していたかなでは、自分が彼のどんな表情を収めたのかすら分かっていなかった。
(とにかく、ちゃんと撮れたのかどうか……)
かなでは携帯を操作して、写真のフォルダを表示する。一番下に増えているサムネイルをクリックして、表示して。
そして、軽く息を呑む。
レイアウトは予想通りのものだった。今自分を取り巻く風景の中に、東金が一人写っている。
だが、その表情が。
見慣れたいつもの自信に満ち溢れた笑顔じゃなく、雑誌やポスターに写る時の綺麗に整えられた微笑みでもなく。
眼差しは甘く、唇は嬉しげに弧を描く。
……かなでが知らない表情では決してない。
久しぶりに逢う時に。
その強い瞳がかなでを捉える時。
その一瞬にだけ、見ることができる。
かなでだけに向けてくれる、かなでへの想いに溢れた表情だ。
「……柄でもねえな」
背後からかなでの携帯を覗き込んだ東金が、軽い舌打ちとともにバツが悪そうに呟く。恐る恐る、上目遣いにその表情を伺ってみると、伸びてきた片手がかなでの頭上に乗せられ、長い指がくしゃくしゃに髪を乱す。
「フォトフレームに入れるのはやめておけ。さっきの猫の話じゃねえが、携帯に残したまんま持ち歩いた方が、いつだって見れるだろ」
照れ隠しなのか、告げる言葉は無駄にそっけない。
かなでも何をどう返していいのか分からず、何度か何かを言いかけて、口をつぐんで。そして、もう答えの分かり切った問いを東金にぶつけてみる。……分かっていても、本人の口から聞いてみたい言葉がある。
「……あの。この表情……何を考えてたら、こういう甘い表情になっちゃうんですか?」
「ああ? ……そんなん、いちいち答えてやる義理はねえな」
東金の口調は相変わらず不遜で、態度は大きい。
それでもかなでを見下ろす眼差も、髪を撫でる指先も
かなでに届く、彼が与えてくれるすべてのものが、甘く、優しい。
そのことが、すべてかなでの想いに応えるためなのだという真実を。
言葉にしなくても、明確に教えてくれていた。
「それにしても『恋人の日』、ねえ……」
東金が予約を入れてくれていた、かなで一人では絶対に一人で踏み入れることはないであろう格調高いレストランの個室で食事を終え、かなでが泊まる予定のホテルまでの薄暗くなった道のりを、二人並んで歩いていると、ふと思い出したように東金が呟いた。
「最近は、ホントにいろんな記念日がありますもんね。私もまさか、この日にピンポイントで恋愛に関する記念日があるなんて、最初は思っていませんでした」
約束の日付を忘れないための苦肉の策ではあったが、それっぽい記念日があってよかったとかなでは思う。こじつけと言えばこじつけの記念日ではあったのだが、何だかんだと言っても猫カフェは楽しかったし、無事に東金の写真を撮ることもできた。今になって思えば、猫カフェで撮影した東金の写真も、少しだけ残しておけばよかったと後悔する。
東金に教えてもらえば、仁亜の手に渡らないように写真のデータを入手することもできたかもしれないのに。
「『恋人の日』という名目で、やることがフォトフレームの交換ってのもどうなんだろうな? ……もっと別に、『恋人の日』らしいことがあるんじゃねえのか?」
東金の声が、徐々に笑いを含んだものになっていく。
恐る恐る隣を仰ぎ見るかなでの視線の先で、どこか楽し気に「どう思う?」と尋ねる東金が、何とも言えない笑顔を浮かべていた。
「どう、と言われましても……」
「お前の隠し撮り行為をまだ芯から許したわけでもないんだぜ? 何かやってみせろよ。『恋人の日』らしいことを」
ああ、これはいつものやつだな、とかなでは心の中で溜息をつく。
多分、東金はかなでからのキスをねだっている。
東金はキス魔だ。……こう断定してしまうのもどうかと思うが、事あるごとにキスをされる、もしくはねだられるので、おそらくかなでの勘違いじゃない。実際に本人にそう言えば、絶対に否定されてしまうのだろうということも予測がつく。
(鈍いお前にも分かりやすいように想いを伝えてやってるだけだぜ? 例えば外国のどこかであろうが、唇へのキスは特別なものだからな)
一度、何かとキスをねだられるのが恥ずかしくて抗議した時に、そんなふうに返されたことがある。……確かに、それも分かりやすい一つの手段だと思うけど。
思えば、逆に東金はキス以上をかなでに要求しない。それ以上に進むための機会が少なかったというのは間違いないのだが、おそらくキス一つでも相変わらず狼狽えてしまうかなでには、まだその先のことは時期尚早だと東金に思われている。
そうなのかな? とかなでは思う。
確かにかなでは奥手で、男女交際の何たるかなんて今でも全然理解していなくて。
自分が欲しい彼の表情の一つすら、欲しいとは素直に言い出せなくて。
だけど、ずっとずっと、東金のことが好きだ。
そしてその『好き』という気持ちは変わらないということはなく、否応なく、大きく、深いものに、現在進行で育っている。
それは、これっぽっちも疑いようがなくて。
……多分、いちいちキスをねだって、確認なんてしなくても。
この想いは変わらないと言い切れるのに。
ああ、だけど。
かなでだって、この想いを上手に東金に伝える術を知らない。
正しい強さと量と深さで、伝わっているのかどうかが分からない。
……だから東金も、何か違うものでそれを測りたくなるんだろうか。
それほどまでに、かなでは自分の恋人を不安にさせているのだろうか。
かなではその場に立ち止まり、東金を見つめる。
……戸惑うでも狼狽えるでもないかなでの様子に、何かいつもと違う雰囲気を感じ取っているのだろう。
いつだって、東金の興味が離れてたり薄れたりしないよう、彼の予想を裏切る行動が取れていたらとかなでは思う。だから、これから彼に伝える想いも、正しく彼の予測を裏切って。
そして、彼が自分へとくれる想いに、見合うものであって欲しい。
勢いで踏み出した足が数歩先にある東金との距離を0にする。自分の中にその存在を包み込むつもりで両腕を回してみても、それは彼の胴回りくらいの高さにしか届かなくて。
それでも、ぎゅうっと彼の身体を抱きしめて、かなでは震える声で東金に告げる。
かなでにとって、キスよりも少しだけ気楽に行える愛情表現で。
そして、キスをするよりも決死の覚悟で告げる、その言葉。
「……今日は、ずっと、一緒にいたいです」
「……かなで」
「一人だけで、ホテルに戻りたくないです」
ますますぎゅうっと力を込めて、東金の均整の取れた体に縋りつく。かなでの細い腕の中で、東金は微動だにしない。
呆れられるのか、馬鹿にされるのか。もうどちらか二つの反応しかしてもらえない気がして、かなでは密かに息を呑む。
『恋人の日』らしいことって、こういうことでいいんですか? ……そんなふうに、冗談の中に紛らわせてしまおうか、とかなでが身を起しかけた時、腕の中で固まっていた東金の身体が解凍されて、柔らかくかなでを抱きしめ返してくれた。かなでの髪に頬を埋める気配がして、そして東金はそこで盛大な溜息をついた。
「……分かっちゃいたが、相変わらず予想の斜め上からとんでもねえ攻撃を繰り出してくるヤツだな」
「そう……ですか、ね?」
責める口調だが、かなでの髪を撫でるその手は優しい。拒絶される気配はなかったので、かなでは素直にその広い胸に体を預けてみる。
「まさか、お前の方からそんなことを言われるとは思ってなかった。……かなわねえな」
「……多分、東金さんが想像するよりも、私は東金さんのことが好きだと思うので……」
「どんだけ名前で呼べって言っても、一向に『東金さん』が抜けねえのにか?」
「それとこれとは話が別です」
何度も「千秋」と名前で呼べと言われているが、そこの恥ずかしさはまた別物だ。
やたらきっぱりと言い切ったかなでに、東金が小さく笑ったのが、触れる場所から伝わってくる。
「……いいぜ、今日は無理矢理にでも言わせてやる。……『恋人の日』の夜は、まだ長いからな」
何を告げていいのか分からないまま、何かを反論しようとしたかなでの唇を、東金のそれが塞ぐ。
相変わらず、一度始まるとしつこくて。
深くて、どこまでも、ひたすらに甘い。
かなでが何か懸命に考えようとすることを、すべてどうでもいいことに変えてしまう、熱いキスだ。
「こ、『恋人の日』って、こういうことする日じゃ、ないんですけど……?」
咄嗟に出てきた言葉は、我ながらそこはどうでもいいと思える内容だったけれど。
「だから、俺たちだけの『恋人の日』を作ればいいだけだろ」
と、あっさりと東金が言ってしまうので。
そういうものなのかもしれないな、と。
ぼんやりと熱っぽい思考で、かなではただ思うのだった。
あとがきという名の言い訳
とにかくかなでに東金の写真を撮らせなきゃ……!と考えた末にできたネタです。
何故舞台が猫カフェだったかというと、自分のスマホの写真フォルダを見たときに、見事に猫しか映っていなかったせいですね……(遠い目)
一応、最初は動物園とか考えてたんですけどね。神戸の動物園がどんな様子なのかがよく分からなかったので、想像が追いつく範囲で書いてみました。
東金はキス魔ですよね‼(ん?)
ようやくコルダ3の表が埋まりました。この後同数の裏を書かなきゃいけないことに頭を抱えますが(笑)書いてて楽しいことには違いがないので、のんびり無理のないペースで頑張っていこうと思っています。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2023.02.12