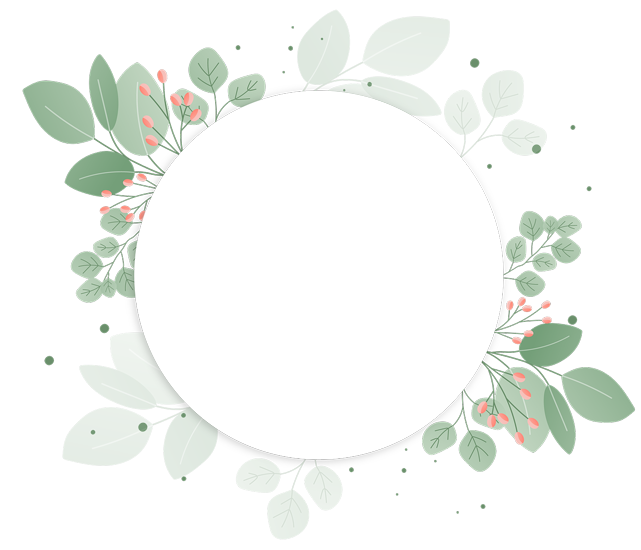正確には、ずっと悩み「続けて」いる。もう、かれこれ1年近くになるだろうか。
自分の思考が袋小路に入りやすいことはそれなりに自覚しているが、大なり小なり様々な悩みを持つ分、これまでは短い間隔で、自分の中でそれなりに折り合いをつけてきた。勿論、根本的に解決するわけではないので、同じ悩み事が再浮上してくるのはしょっちゅうだが、それでも同じ悩みを数ヶ月も引きずっていることは意外に少ない。
だがこの悩みに関しては、どれだけ時間が経っても解消される気配すらない。それはおそらく、七海一人で解決できる話ではないからだ。
あれは、去年のクリスマスの頃だったろうか。冬休みに仙台から横浜まで遊びに来ていた幼馴染みの水嶋新が、顔にはっきりと「興味津々」の四字熟語を記して、七海に尋ねたのだ。
「ねえねえ、宗介。……かなでちゃんと、どこまで行った?」
七海は盛大に飲んでいたカフェオレを吹き出し、もう一人同席していた新の従兄弟で同じく幼馴染みである水嶋悠人は、明らかに剣呑とした空気をその身に纏う。
「……新、お前はほんっっっっっっっとに、デリカシーという人間として大切なものが皆無だな! かけらほども!!」
「え? だってハルちゃんは気にならない? むしろオレらみたいなオトシゴロの高校生って、一番気になる話題じゃない!?」
説教モードに入る悠人と、怒られることが心外だと言わんばかりに目を丸くする新の傍らで、慌てて駆け寄ってきたカフェの店員に平謝りしながら、七海は代わりのカフェオレを再度注文するのだった。
「だいたい、宗介も宗介だ。いちいち新の下衆な質問に反応するなよ。適当に流せばいい」
「そんな器用なことができたら、生きるのにこんなに苦労しないよ……」
溜息混じりの悠人の言葉に、店員から渡された布巾でテーブルの上を拭きながら、七海は項垂れた。「まあ、それもそうか」と悠人があっさり納得してくれたことを、喜べばいいのか嘆けばいいのか、全く分からない。
「で? 結局どこまで?」
空気が読めるのか読めないのか、新は追求の手を休めることはない。悠人がまた何か言いたげに新に視線を向けるのを、七海は片手で制した。良くも悪くも付き合いは長いのだ。新のしつこさは嫌というほど理解している。悠人が何とかやり過ごそうと頑張ってくれても、おそらく新が追求を諦めることはないだろうし、七海自身が上手く誤魔化せるような技量も、当然持ち合わせてはいない。ならば素直に答えてしまうのが、いち早くこの話題から逃げ去るコツだ。
「……多分、新が思うような進展みたいなものはないよ。学校も違うし、お互い部活が忙しいし、たまにデートするのが精一杯で……」
七海が一つ年上で悠人と同じ星奏学院に通う、小日向かなでと付き合い始めたのは夏の終わり。その後、星奏学院では文化祭、七海の通う天音学園では理事会に向けての演奏会などがあり、その練習に追われていた二人は、あまり頻繁には会えなかった。やりとりは電話とメールが基本で、たまに学校帰りや休日に会い、カフェでお茶をしたり、近場のデートスポットに遊びに行く程度だ。
新が言いたいのが、恋人としての関係性がどこまで進んでいるかということだというのは分かるが、そもそも会うことすらままならないのだから、進めようがない。ようやく二人で会うことへの緊張感が解れてきて、何度か手を繋ぐことがあった、くらいの健全な関係だ。
しかも、その手を繋ぐことも、かなでの方から申し出てくることが大半だった。それを改めて思い出して、七海は瞬時に落ち込んだ。
「えええっ! それって大丈夫!? 現代の若者の恋愛としてどうなの?」
「お前の価値観でモノを測るな。宗介と小日向先輩に合った物事の進め方ってものがあるだろう? 健全でいいことじゃないか」
なあ?と慰めるように悠人に問われ、七海は曖昧に微笑む。……正直、世間の一般常識と照らし合わせれば、自分の恋愛速度が遅過ぎるということは、七海にも分かっている。だからといって、その速度を早めることは不可能に近い。それが出来る性格であるならば、こんなに悩み多き青春時代を過ごしてなどいない。
「宗介はそれでいいのかもしんないけどさ。かなでちゃんの方がどうかは分かんないよね?」
こんなに寒い時期なのに、氷入りの炭酸飲料をほぼ飲み終えている新は、名残惜しそうにずずっとストローの音を立てる。悠人がその新の発言なのか行動なのか、どちらが引っかかったのかは分からない(おそらく、両方だろう)が、不愉快そうに顔をしかめた。
「お前と小日向先輩を一緒にするなよ。失礼だろ」
「いやいや、案外女の子の方がそういう欲求は大きいんだってば、ハルちゃん。精神的に成熟するのは女の子の方が先って言うし」
更にかなでは、見た目は幼く見えるが、年齢は間違いなく自分たちよりも一つ上だ。そもそも付き合っている七海は、見た目以上にかなでが大人っぽい一面を持っていることを知っている。だからといって、かなでが何か積極的に七海に恋人らしいことを要求したこともない。それこそ、先程思い出していたように、時々二人で出かけるときに「七海くんが嫌じゃなければ、手を繋いでもいい?」とかわいらしく尋ねられるくらいだ。
そういうときは、大抵七海が「男らしく! 恋人らしく!! 俺の方から手を繋がなければ!!」と意気込んでタイミングを見計らっているときなので、おそらくかなでがその七海の決意に気がついて切り出してくれているのだろう。
(うわ……やっぱりダメダメだ、俺……)
新に指摘されるまでもなく、こんな自分はどうなのだろうと七海は内心頭を抱える。かなでにとって頼れる恋人になりたいと常日頃思っているのに、どうにも空回っている感が否めない。それでも夏の終わりからここまで、「恋人同士」という関係を続けてこられているのは、偏にかなでの心が海よりも広いおかげだ。
「はっ! これはもしや、チャンスなのでは? かなでちゃん、宗介との関係にじれじれ~ってしてるとこだと思うし、オレが男らしく押してみれば、かなでちゃん、宗介じゃなくてオレの方を選んでくれるかも……」
「……あのなあ、新……」
呆れた声で諫めようとする悠人の言葉尻に被せるように、ばんっとテーブルに両手をたたきつけ、立ち上がった七海の大声が店中に響く。
「小日向さんがそんなに理由で、簡単にお前になびくわけないだろ!!」
がたん、と大きくテーブルが揺れ、はっと我に返ると、反射的に自分たちのコップを死守した新と悠人が目を丸くしている。そろそろと視線を巡らせると、カフェオレのおかわりを運んでいた店員までがきょとんとした顔でそこに立っていた。
「……ご、ごめん」
恐縮してすとんと椅子に腰を下ろすと、「新……」と責める目つきで悠人が新を睨んだ。新は悪びれない様子で「まあ、一番大事なことは見失ってないみたいだし、いいんじゃない?」とどこから目線か分からない言葉を呟く。
そして、まるで何事もなかったかのように「お待たせいたしました」とカフェオレのカップを七海の目の前に置いて、平然と去っていった店員は、やはり接客業のプロだった。
そんなやりとりから早数ヶ月。七海とかなでの関係は、亀の歩みならぬ、カタツムリの歩行またはハシビロコウの動き並みの速度で、感覚的には数ミリずつ、何とか進んでいた。バレンタインの頃に七海の方から手が繋げるようになって、ホワイトデーの頃にようやく触れるだけのキスが出来るようになって……それから春になって学年が変わり、星奏学院オーケストラ部の副部長として部員をまとめる立場のかなでは、これまで以上に忙しくなった。かくいう七海の天音学園にも新入生が入り、これまでとは違う、先輩としての立場で振る舞うことに四苦八苦している。
せっかく後輩が出来たのだから、頼れる先輩として頑張らなければと意気込んでいた七海だが、どちらかというと感覚的にチェロを弾いている七海は、教えることがあまり上手くない。先輩であり、新しく室内楽部の部長になった氷渡貴史の方が、後輩への指示の出し方が的確で、冥加・天宮という2大巨頭がいなくなった天音学園室内楽部を上手く率いている。その氷渡から七海は「お前は後輩の指導はしなくていい、むしろ自分の練習に集中しろ」と言われていた。
先輩としての自分のふがいなさに落ち込んでいた七海だが、ある時何かの用事で学園に現れた御影諒子に、こう告げられた。
「あれは、氷渡くんなりにあなたの才能を認めてのことじゃないかしら。慣れない他人への指導へ時間を費やすより、自分の才能を磨くために練習に集中しろって言ってるのよ。練習に関係のない、雑多なことは自分が引き受けるから……って」
半信半疑で聞いていた七海がそのことを実感したのは、夏の全国アンサンブルコンクールへの参加申し込みをする時だった。
去年のように絶対的な実力を誇る冥加や天宮はいない。アンサンブルコンクールの経験者は七海と氷渡の2名のみで、天音学園へ入学した以上、ある程度の才能はある生徒たちばかりだが、他の室内楽部部員にも新入生にも、冥加たちに匹敵する実力を持っている生徒はいなかった。
そして、あの二人を擁していても尚、かなでたちの星奏学院には勝てなかったのだ。更に星奏以外にも仙台の至誠館高校、神戸の神南高校、九州のサンセシル女学院……強豪校は他にもある。
果たして、現状のメンバーで勝ち抜けるのか……。
氷渡の判断は、早かった。
「……よし、今年のアンサンブルは捨てる。七海はチェロのソロ部門でエントリーしろ」
1年で現部員の実力を底上げし、来年七海が最高学年になった時、七海が率いるための人材を作り上げると氷渡は言った。
「いや、でも……俺が、ソロで……ですか?」
いくら認めてくれたとはいえ、去年は氷渡にぼろくそに言われていた七海のチェロだ。アンサンブルの一役を担うことは許されていても、ソロで出場することは想定していなかった。
「お前はソロ向きだろう。どう考えても」
むしろ何が不満だとでも言いたげに、氷渡は眉根を寄せる。
「我が強くて、感覚重視で……冥加さんのヴァイオリンにも、天宮さんのピアノにも埋もれない個性……正直腹が立つくらいだぜ」
指折り数えながら、氷渡は苦笑する。
「冥加さんが作り上げた室内楽部のアンサンブルの価値を下げるわけにはいかねえ。コンクールに参加しておいて初戦敗退なんてもっての外だ。……そして現状タイトルを取れる可能性があるのは七海、お前くらいだ。だから、今年の天音学園の実績はお前に託す。その代わり、来年お前のチェロを支える土台は俺がここにいるうちに作ってやる。……いいな、お前は天音の代表だ。見苦しい真似、するんじゃねえぞ」
「は、はい!!」
七海は勢いよく返事をする。
御影の言うとおり氷渡は七海の実力を認めてくれていた。冥加や天宮に並べ立てる、タイトルを取れるほどの実力があると……最初は嬉しくて、足取りも軽く、鼻歌でも歌いかねないほどに浮かれていて……最後の「見苦しい真似、するんじゃねえぞ」という言葉に隠された重圧に、その場にしゃがみ込みたいような、重い気持ちになった。
(それはつまり、今回ソロ部門で勝てなければ、俺は氷渡先輩の信頼を裏切ってしまうって事になるんじゃ……)
実力を認めてもらうことは嬉しい。だが、本当に自分がその期待に応えられるほどの実力があるのかと問われれば、はっきり「ある」とは言い切れない。だが、過去に思いあまってチェロを投げ捨てようとしたあの時よりは、少しは自分のチェロと自分の音に自信が持てるようになったとは思う。
「……そっか、チェロのソロ部門……」
数日後、カフェで待ち合わせた七海とかなでは、今年のアンサンブルコンクールについて、お互いの学校の状況を報告し合った。星奏学院はかなでと部長である如月響也、そして悠人の3人でアンサンブルに参加し、3人はそれぞれ、ソロ部門にもエントリーするという。つまりは悠人もチェロのソロ部門にエントリーするというと言うことで、七海にとっては手強いライバルが増えたということだ。
「でも、学院選抜もちゃんとやって私たち以外のメンバーを選出して、出来れば去年みたいに弦楽五重奏にしてみたいとは思ってるの。そうしないと、七海くんのところみたいに、来年ハルくんがアンサンブルをどうするかって問題が出てくるから」
全国を目指すに当たり、去年からかなでたちとアンサンブルを組んでいた悠人は、良くも悪くも星奏オケ部の中で頭一つ分実力が飛び抜けている。来年悠人が中心となってオケ部をまとめていくことを考えると、悠人に明確な実力があることは余計な軋轢を生まず、利点も多い。
だが、アンサンブルコンクールで全国優勝を目指すという点で考えれば、今年の天音学園と同様、悠人に引けを取らない演奏者を育てていく必要がある。
そして最終的にソリストになることを目指しているかなでたちは、同時にそれぞれの音を磨き上げることにも力を入れ始めた。
「響也と争うことになるのはちょっと嫌なんだけど……ソリストを目指す以上、そういうのも慣れなきゃいけないのかなって」
少し困ったような笑顔で、かなではそう言った。ヴァイオリンを弾くことは好きだけれど、音楽で人と争い合うことがあまり好きではないのだ、と以前聞いたことがある。争うくらいなら、ヴァイオリンを弾きたくないというくらいに思い詰めて、一時期伸び悩んでいたのだということも。
「そういえば、七海くんとハルくんも競い合うことになるんだね」
「ああ……そうですね」
以前からソロ部門に挑戦したいという気持ちは悠人から聞いていたので、特に驚きはなかった。氷渡の期待に応えるのが一層難しくなるというのは分かってはいるのだが……。
「でも、俺、ちょっと楽しみなんです」
「楽しみ?」
こてんと首を傾げてかなでが問いかける。七海は大きく頷いた。
「ハルと1対1で勝負するの、中学の時以来で……お互い、実力も手の内も知り尽くしてるから、勝つのがどれほど大変かってのも分かるんですけど、お互いに手加減もないの分かってるから、競い合ってどれだけいい音が作り出せるか……想像すると楽しみで」
昔から、二人はお互いに対して妥協がない。頑固者同士というのも分かっていて、持論を引っ込める気がないので、二人で同じ曲を作ろうとすると、大抵は洒落にならないくらいの大喧嘩になる。
だが、そういう互いの意地をぶつけ合ってできあがった音楽は絶対にいいものになると、経験上分かっている。
その意地の張り合いを全国規模のステージの上で行うのだ。いい勝負になるのは目に見えているし、互いのチェロが、どんなに素晴らしい音を作り上げるのか、是非聴いてみたい。
七海の言葉をぽかんとして聞いていたかなでが、ふと解けるように笑った。
「ふふ、……何だかもう、七海くんとハルくんのどちらかが優勝するの、決まっちゃってるみたい」
「え? ……あ、そうですね……」
かなでの指摘に、七海は我に返る。すっかり悠人と二人でコンクールの決勝の舞台で競い合う気でいたが、ソロ部門にエントリーする生徒は全国から集まるのだ。決勝に残れるのかすら、まだ分からない。
自意識過剰な発言をしてしまったことに赤くなる七海から視線をそらし、かなでは頬杖をついて窓の外を見つめる。「そっか、楽しみか……」と自分に言い聞かせるように呟いた。
「……きっと、小日向さんと響也さんも、いい勝負になると思いますよ」
思わずそう声をかけると、少し驚いたように目を見開いたかなでが、七海を見つめる。余計なことを言ったと分かったが、一度口にしてしまったものは、時、既に遅し。
「あの……小日向さんがヴァイオリンで争うの好きじゃないって知ってますけど、それとこれとは別って言うか! いい演奏をし合うってことにコンクールの勝ち負けは関係ないですし……でも、コンクールだからこそ、実力以上のものが出せるって事もありますし!」
自分は一体、何が言いたいのだ。心の中で、自分に突っ込みを入れつつ、七海は更に言い募る。
「あ、あの、俺、その時の小日向さんと響也さんのヴァイオリン、絶対聴きたいって思います! お二人が競い合って作り上げる音楽は、絶対素晴らしいものになると思います! それで……あの」
かなでがじっと七海を見つめる。本気で自分が何を言いたいのかが分からなくなってきた。思わず口ごもる七海に、とうとうかなでが吹き出した。
「七海くんの中では、私と響也も二人で決勝に行くことが決まってるみたいだね」
「え? そ、それは、もう」
緊張しやすい自分はどうか分からない。だが、かなでと響也、そして悠人は決勝に行くものだと七海は信じていた。出来るなら、自分もちゃんと緊張せずに実力を発揮して、決勝の舞台で悠人と競いたいと願っている。
「……そこを疑わないのが、七海くんの強いところだよね」
自信がなさそうに見えて、案外七海は臆面がない。実力を出し切れば、ファイナルの舞台に立てるという謎の自信が根底にはある。ある意味、その強さと呼べる部分を理解していないのは、七海だけだ。
かなでは、視線を伏せて穏やかに笑った。
「大丈夫だよ。ちゃんと全力で響也と競い合うから。もし手を抜いたりしたら、響也に一生嫌味言われちゃうしね」
……響也との付き合いは一生続くのだということを暗に言われて、若干引っかからないでもない七海だったが、自分がいつか悠人や新との関係を断ち切ってしまうのかと考えると、それはないという気がするので、幼馴染みとはそういうものなのだと自分を無理矢理に納得させた。
そして二人の話は本題へと移る。そもそもお互いの夏のアンサンブルコンクールの予定を報告し合ったのには別の理由があったのだ。
「うーん、やっぱり夏休みに出かけるの、ちょっと難しいかなあ……?」
スケジュール帳を睨みながら、かなでが眉間に皺を寄せる。せっかくのまとまった休みなので、久し振りにどこかでデートでもと思っていたのだが、お互いのソロの練習に加え、更にかなではアンサンブルの練習もある。東日本大会から決勝まで、勝ち残れば3回も会場で演奏することになることを考えると、一ヶ月半の夏休みをそう気楽に過ごすわけにはいかない。
「でも、ホワイトデーに七海くんにお返しもらった後、まともに二人で会えてないもんね。一日でいいから、一緒に過ごせないかな……」
困ったように眉を八の字に下げて、かなではスケジュール帳を睨み続ける。七海が「……あの!」と思い切ったように声を上げた。
「特に予定がないなら、8月9日はどうですか?」
提案された日付を、改めてかなでが確認する。ちょうど東日本大会が終わって、セミファイナルが始まるまでの合間の期間だ。セミファイナルまでに充分な時間があるし、うまく勝ち上がっていたとしても、中休みが取りやすい時期だ。かなでは顔を輝かせて頷いた。
「うん、コンクールの日程的にも問題なさそう! 七海くん、狙ってこの日なの?」
いくつか候補を出してからならともかく、この日のみを七海が指定したことに、かなでは少しだけ引っ掛かりを感じて尋ねてみる。もちろん、天音の練習スケジュールから、七海の都合が一番いいのがこの日だったというだけなのかもしれないのだが。
「え? ええーっと、そ、そうですね? コンクールに被らないから、いいんじゃないかと思っただけなんですが……」
歯切れは悪い気もするけれど、余程自信のある事柄でなければ断定的な物言いを七海がしないことは知っていたから、かなでもそれ以上食い下がらなかった。特にこの日が駄目な理由が見つからなかったせいでもある。
「じゃあ決まり! 一緒に出かけるの、楽しみにしてるね」
スケジュール帳に、嬉しそうに予定を書き込むかなでに頷きつつ、七海はこっそり胸を撫で下ろす。
もちろん、この日を指定したのには、七海にとってちゃんとした理由がある。
8月9日は、とある記念日なのだ。
超スローペースながらも、少しずつ歩みを進めていた、七海とかなでとの関係。
何気ない日にスマートに距離を縮める……などという芸当は当然のことながら出来なくて、誕生日、バレンタイン、ホワイトデーと、イベントの力を借りながら、何とか一歩ずつ進めてきた。
だが、何度となくそれを繰り返したせいで、逆に七海はイベント事がなければ何も進めない気になっていた。
(何か新しいイベントを探さないと……)
かなでが何かを望んだわけではない。二人が納得できるのなら二人のペースで進んでいけばいいのだが、いつしか七海の中には「早く先に進まなければ」という強迫観念が植え付けられていた。当然のことながら、以前新から言われた一言が脳裏のどこかに残っていたからだ。
意外にも3月のホワイトデーが終わってしまうと、恋人同士が過ごすイベント事は冬のクリスマスまで大きなものがない。……もしかしたら、七海が知らない記念日がもっと存在するのかもしれなかったが、少なくともその時の七海には思いつくものがなかった。
何か他にイベント事がなければ自分たちの関係性は、クリスマスまで進展することがない……ならばその前に何かないのか……できれば、夏のコンクールに影響がない日程で……そういう条件下で、七海が探し当てたのが、8月9日……『ハグの日』だった。
単なる日付の語呂合わせで、決して真剣に『記念日』として祝う類いのものではない。ただ、いろんな意味でこの記念日は七海にとってちょうどいい記念日だった。
(手を繋いで、キスが出来たとなれば……次はハグで問題ないよな!)
要するに『彼氏彼女』の距離の詰め方からしても、抱擁くらいが「ちょうどいい」進行速度だと思ったからだ。……キスとハグと、どちらを先と考えるべきか、という部分にちょっと引っかかったが、触れる面積から考えれば、キスの方を前段階と考えていいだろう。
(しかも、そのものズバリ、『ハグをする日』なんだし、切り出しやすいはずだ!)
『ハグの日』だから、ハグをするのだ。そういう決まりなのだと説得すれば、かなでもきっと嫌がらないはずだ。記念日とはそういうもののはずだから。
そう自分に言い聞かせ、まずは自分の心を納得させることに専念する七海は、この方法がよからぬ弊害を生んでしまうかもしれない可能性には気がついていなかった。
『ハグの日』だからハグをする、という法則を作ってしまうと、来年の『ハグの日』までは、ハグする理由がなくなってしまうということを。
記念日に囚われることの弊害に気がつかないまま、七海は問題の8月9日を迎える。
暑くなる前に動きたいというかなでの意見に沿って、午前中の早い時間に待ち合わせ、地元から少し離れた観光名所の庭園までバスを乗り継ぐ。嫌いなわけではないが、賑やかな場所を避けがちな七海と、星奏学院に編入してから1年、観光地でありながら忙しくてほとんど名所らしい名所に行ったことがないというかなでに合わせて選んだ場所だった。
広い庭園内を二人でのんびりと歩き、展示物を眺め、茶寮で和風のデザートを堪能し終えると、思った以上に時間が過ぎていた。
だからといって、帰宅するにはまだ早すぎる時間だ。しかも七海からすれば、一番肝心な今日の本題を達成していない。
「……七海くん、大丈夫? 暑いのなら、もう早めに帰っちゃう?」
本題を切り出すタイミングを測っているため、つい黙りがちになる七海の顔を、心配そうに表情を曇らせたかなでが覗き込む。その近さに反射的に後ずさった七海が、慌てて何度も首を横に振る。
「ぜ、全然! 大丈夫です!! それに、せっかく久しぶりのデートなんですから、こんなに早く帰っちゃうのはもったいないです!」
ハグしませんか? と切り出すことに頭が一杯の七海は、同じくらい恥ずかしい言葉を発していることに気がついていなかった。一瞬目を丸くしたかなでが、嬉しそうに頬を染めて微笑んだ理由も、よく分かってはいない。
「……じゃあ、今からだと夕方になっちゃうとは思うんだけど、高台の公園の方に行ってみようか。観光名所だけど、時間的に人の流れと逆行する形になるし、のんびりするのにいいかも」
七海の脳内では、会話の流れから実にスマートに七海が「小日向さん、実は、今日は『ハグの日』なんですよ。記念日に合わせて、俺たちもハグをしてみませんか?」と切り出し、「そうなの? なら私も七海くんとハグしたい」と嬉しそうに笑うかなでが七海に抱きついてくる……という一連の流れができあがっている。だが、それを『どこで』実行するのかが曖昧で、明確にイメージできていない。
かなでが次の目的地に提案した公園は、海を見下ろす展望所があり、季節が季節なら、綺麗なバラが咲き誇るイングリッシュガーデンがある。夏のこの時期にバラは咲いていないが、それでも雰囲気はとてもいい場所だ。デートスポットとしても有名であるし、そんな背景の中で抱擁し合う自分たちの姿を想像すると、とてもロマンティックだと思える。
異論を挟む余地はない。七海は何度も大きく頷いて肯定の意を示す。何故かかなでは少し困ったように微笑んで、軽く首を傾げるのみだった。
駅まで戻れば観光用の周遊バスがあるので、迷いなく二人はそれに乗り込み目的地へ向かう。最寄り駅で降りて歩く方法もあったが、夏の日差しは強く、アスファルトからの照り返しは一種の凶器だ。エアコンの効いたバスに揺られていれば、汗も引くし、午前中の疲労も多少は解消される。
そう考えていて、七海はふと思い至る。……ハグすることを最終目的として今日を選んだのに、汗をかくと分かり切っている屋外でデートをすることにしたのは、失敗ではなかったのだろうかと。
もちろん、七海は気にならない。散々歩き回っていて、しかも夏の真っ只中なのだ。汗をかかない方がおかしいし、かなでの汗を嫌なものだなんて思うはずがない。だが、逆の立場から考えるとどうなのだろう。
汗をかいた状態で、かなでは果たして七海とハグをしてもいいと思ってくれるだろうか。いくら七海の方が構わないと言ってみても、かなでの方が七海に遠慮してしまう可能性は高い。
何よりも、この暑さで当然汗をかかないはずがない自分がかなでに触れてしまうことを、彼女は嫌がったりしないのだろうか。
(露骨に嫌がったりはしない……しないとは、思うけど!)
表面に見える反応と、心の奥の嫌悪感は別だ。かなでのことだから、どう思ったにしても負の感情を七海に見せることはないだろうけど、笑顔の裏側で「汗だくでハグするとかどうなの?」とか不満を抱かれていたりしたら。そして、ちょっとしたかなでの反応でそのことに気がついたら……。
七海は間違いなく死ねる。
(何でそこに気付かないんだ俺は……!)
着ていく服は新しいものがいいだろうと、今年の夏に買ったばかりのTシャツを下ろしたりもしていたのに、微妙に自分は詰めが甘い。どうして無難に屋内の映画館とか……せめて、動き回らないでも済む場所を選ばなかったのだろう。
「七海くん、降りるの次だよ?」
他の乗客を気にしてか、ずっと黙って窓の外を眺めていたかなでが、目的地の名前がアナウンスされても動く気配がない七海を覗き込むようにしながら、降車ボタンを押す。「ありがとうございます」と力なく呟いた七海は、この時点で既に『ハグの日』のメインイベントを達成することを、半ば諦めていた。
「さすが、高い場所なだけある。風、気持ちいいね」
無邪気に笑うかなでが、両手を空に広げ、うんと伸びをして、それから七海を振り返る。「そうですね」と応じる七海も笑顔だが、心の中は落胆しきっている。
そもそも、せっかくかなでがあまり暑くない朝早い時間から動こうと言ってくれていたのだ。落ち合ってすぐにハグの話をしていれば、この記念日を無駄にすることはなかった。
もちろん、落ち合ってから以降、ずっとタイミングを伺っていただけで、別にデートの終わりにハグをしようと決めていたわけでない。どこに行こうが、何をして過ごそうが、ハグするチャンスはあったはずなのだ。
それを実行に移せないのはただ、七海に勇気がないだけだ。
……そもそも、記念日に頼らなければハグをしたいとも言い出せない、そんな七海のふがいなさが全てに起因する。
かなではきっと、それこそ何もない普通の日に、七海がハグをしたいと言い出したとしても、それを頭ごなしに拒否したりする人じゃないのに。
(それでも、まだ、怖いんだ)
かなでが七海の想いを無下にしたりはしないことは分かっている。だが、『分かっている』ことと『怖い』というのは七海の中では別の話だ。拒絶されないことは『分かっている』。でも、ハグをしたいと言って、かなでがどう思うのかが『怖い』。
何故なら、かなでが七海を好きでいてくれる。その事実そのものこそが、七海にとっては奇跡なのだから。
「……七海くん?」
相づちは打つが、きちんと会話らしい会話をしてくれない七海を訝しんで、かなでがそうっと七海の顔を覗き込んでくる。はっと我に返る七海に苦笑しつつ、かなでは片手を伸ばして、七海の手を取った。
「ちょっと、座ろう?」
かなでに手を引かれ、七海は側にあったベンチにかなでと共に腰を下ろす。どう反応していいか分からず戸惑う七海に、かなでは安心させるように小さく頷いた。
「……七海くんが、何か言いたいことがあるなら、ちゃんと言って? もしこれが私の思い過ごしで、特に何もないのなら、それはそれでいいから。でも、多分思い悩むより、ちゃんと吐き出しちゃった方がいいんじゃないかって思うよ」
付き合い始めてから約1年。ゆっくりとではあるが、お互いの距離感や価値観……最初のうちは暗闇の中で手探りして伺っていたようなそれも、ある程度は分かるようになってきたとかなでは思っている。
それでも七海は、かなでほど相手に向かって気持ちをぶつけるのが上手くない。悠人や新の話を聞いていると、むしろ彼は昔はもっと明け透けだったのだろうと予測しているが、冥加玲士という七海の憧れの人物がそんな七海を変えた。……それは、もういい。その封印された彼らしさを解き放つ過程をかなでは見ることが出来ている。
そのことは貴重で得がたい、幸せな経験だ。むしろ、そんな機会を与えてくれた冥加に,感謝に近い気持ちも抱いている。
(そういう意味では、私たちはとても似ているから)
かなでも、冥加をきっかけに自分の中の何かを囚われた人間だ。そして今、七海と共にそれを少しずつ解放しようとしている。誰にも理解されないそんな状態を共有できる七海という人間は、かなでにとってとても大切な存在だ。
だからこそ、七海はもっとかなでに対して自由に振る舞っていいと思う。拒絶されないよう、否定されないよう、七海は無駄なくらいに予防線を張るけれど、かなではそんな七海をもっともっと許容する覚悟がある。
(それが、『好き』ってことでしょう?)
何もかも、無条件で許すわけじゃない。だが、七海が想像するよりもずっと、かなでは多くのことを受け入れることができるはずなのだ。
「……あの」
かなでの覚悟が伝わるように、かなでが真っ直ぐに七海を見つめていると、やがて一旦ぎゅっと目を閉じた七海が、思い切ったように目を開けて、顔を上げた。
「あの! 小日向さん! 今日が何の日か、小日向さんはご存じですか!?」
思いもよらぬ問いに、かなでは目を丸くする。
何度か細かく瞬きをして口をつぐんだ……が、かなでは七海の予想に反して、一つ頷くと、あっさりと答える。
「『ハグの日』だよね?」
今度は七海が目を丸くする番だった。
「え、あの……知って……? 何で……?」
呆然と問いにならない問いを繰り返す七海に、かなでは首を傾げる。
「何でって……昨日、ニアとそういう話をしたから」
明日は『ハグの日』だな。と、隣室の支倉仁亜が声をかけてきたのは、夕飯の後だった。
朝からちゃんと動けるようにと、忘れ物がないか荷物をチェックしていたかなでが、眉根を寄せてそんな仁亜を振り返る。
「ニアってば。ちゃんとノックして入ってきてよ」
「ノックするまでもなく、元々ドアは開いていたぞ。この寮は古くてドアの立て付けが悪いからな。隙間が見えたのなら、覗き込みたくなるのは人の心情というものだろう?」
よく分からない理屈を並べ、仁亜は遠慮なくかなでの部屋に足を踏み入れる。本当にドアが開いていたのかどうかは分からないが、仁亜がかなでの部屋に断りもなく入ってくるのは初めてのことではないので、半ば諦めの境地でかなでは溜息をつく。
「……で、何の日だって?」
「だから、『ハグの日』。読んで字のごとしだ。8月9日の語呂合わせで、深い由来も何もない記念日だが、ここ最近ネットなどではよく見る記念日だな」
「へえー」
そういうことに疎いかなでは、素直に感心する。報道部の性質か、仁亜は意外に雑学に精通している。記念日だの流行り物の由来だの、何気ない会話の中によく混ぜ込んでくるので、突然の話題にも特に引っかかることはなかった。
「……明日のデートは七海の方が指定してきたと言っていたな? もしかして、それが狙いじゃないのか?」
「それって?」
「だから、『ハグ』だよ。あいつの性格から予測は出来ていたが、付き合い出して1年も経つのに、幼稚園児並の進展具合なんだろう? いかにもそういうことを理由にして進展を測りそうなタイプじゃないか、七海は」
「……そんなこと、何で分かるのかな?」
頬を桜色に染め、かなでが膨れっ面をする。
何故分からないと思うのだろうな?と仁亜は肩をすくめた。
「まあいい。君らの恋愛の進行状況がどうであろうが、私には何の関係もないからな。だが、一応心の準備はしておいた方がいいかもしれない。君もどちらかといえば、突発的なことには対応できないタイプだし。いきなり抱擁されたら、パニックで七海を突き飛ばしかねない。そうすると、七海は拒絶されたと誤解するかもしれないからな」
そうしたらこじれるだろう?とむしろとても面白そうにニアは笑う。
「余計なお世話!!」
睨み付けると、仁亜は軽く手を振って入ってきたのと同様に、音もなく部屋を出て行く。かなでの部屋のドアが静かに閉まった数秒後、はっきりと分かるように仁亜の部屋のドアが開いて、閉まって。
そして、かなでは大きく何度目かの溜息をついた。
「『ハグの日』……か」
確かに日付は七海が指定してきた。もしかしたら、そういう思惑があるのかもしれない。だが、遊びに行く予定の場所は屋外の広い庭園で、夏の日差しの下で歩き回る予定だ。人の目もあるし、ハグをすると考えると、不向きな場所ではないだろうか。
そんなことを考えて……かなでは、別にいいかと思い至る。
七海の思惑がどうであれ、久し振りのデートはとても楽しみで、もし七海がハグをすることを狙って明日を選んだのだとしても、別にかなでには拒否をする気持ちがない。
……抱き締めてもらえるなら、それはそれで楽しみだ。
「もしニアの予想が違ってたら……私から『ハグの日』の話をしてみてもいいかも」
二人のペースで進んでいって構わないとかなでは思っているけれど、進展するならそれもまたいいことだと思う。大事なのは、お互いに無理をしないことだ。
そう結論づけ、かなでは準備したものが間違いなく収まっているバッグを、ゆっくりと閉じた。
「小日向さんが、知っていたなんて……」
「あの……ごめんね? そんなに落ち込むなんて思わなくて」
がっくり項垂れている七海に、かなでは申し訳なさそうに声をかける。
別に七海が作り出した記念日ではないのだし、かなでが知っていてもおかしくはなかった。だが、かなでが知らないことが前提の今日の計画だ。その前提が崩れてしまうと、何とも締まらない、間抜けな記念日になってしまう。
「……ニアから聞いてても、それは別に関係ないかなって思ってたの。今日が楽しければ、記念日であろうとなかろうと、関係ないって。でもね。……七海くんが、落ち合ってからずっと、何かタイミング伺ってるなあっていうのが分かって……ああ、じゃあやっぱりそうなのかなって思ったんだよね」
「ああああああ……」
両手で顔を覆ってますます落ち込む七海の肩を、苦笑するかなでが慰めるように軽く叩いてくれる。何度か気遣うように声をかけてくれたのは、その『ハグの日』の事を言い出すきっかけを作ろうと頑張ってくれていたそうだ。……さすがに『ハグの日』だから、ハグしよう!とは、かなでの方からも言い出せなかったらしい。
「ほんっとに、俺って……ダメダメですね……」
「そんなことないよ。私の方からちゃんと『今日ってハグの日だよね』って言ってたら、また違ったかもしれないし。私も言い出せなかったんだから、お互い様だよ」
そう言ってくれるのは、かなでの優しさだ。七海が理想とするように、七海がもっと自然に、何のわだかまりも持たず、かなでとの距離を測れたらいいのだ。だが、いつもかなでの方から水を向けてもらって、何とか壁を一つずつ乗り越えるのが精一杯。
情けないとは思うが、それが自分なのだと、七海も分かっている。
空回りして、失敗して。でも、それをかなでに許容してもらいながら自分はまた一つ成長していく……結局は、七海はそういう意味でも臆面がないのだ。
「……えっと……」
「あ、そうだね。サプライズ感はないけど、せっかく二人とも分かった上での記念日なんだから。……してみる?」
改めて、どう切り出そうかと迷っていると、かなでがあっさりと七海の意図に気付き、はい、と両手を広げてくれる。あまりにあっさりと許されるので、逆に七海が躊躇していると、はっと気がついたようにかなでが身を引いた。
「でも、汗かいちゃってるし、七海くん嫌かな。『ハグの日』だから絶対しなきゃいけないってことでもないし、それ言ったら『ハグの日』以外はしちゃ駄目なのかって話になるし、日を改めた方がいいのかな?」
「い、いえ! 俺は、全然構いませんので!」
七海が危惧していたことにかなでが気付いたので、逆に七海にとってのハードルは下がる。そんなことより、『ハグの日』を理由にしていたら、その日以外ハグが出来なくなっていたかもしれない可能性に思い至り、七海の背中を冷たいものが流れる。
……もちろん、してはいけないという決まりはないのだが、自分の性格から考えて、気にして言い出せなくなる可能性は充分高いと思われた。
「あの、俺も汗かいてますけど、それは……」
「私は全然大丈夫だよ」
にっこり笑って、かなでは再度七海に向かって両手を広げてくれる。では失礼して……と、七海は恐る恐るかなでとの距離をつめ、そっとその体を抱き締めてみる。
(……うわ)
想像以上だ。
……想像以上に、かなでは小さかった。
七海は自分が小柄な方だと知っているけれど、そんな七海が抱き締めても分かるほどに、かなでは華奢で小さく、そして何とも柔らかい。薄手のワンピースは汗で少し湿っていたけれど、それを嫌だとは感じない。ふわりと香るのは、甘いかなでの匂いだ。それを実感して、反射的にかなでの背中に回した腕に力がこもってしまう。少しびっくりしたように体をこわばらせたかなでは、次の瞬間にはふっと力を抜いてその体を七海に預け、腕の中で小さく笑った。
「七海くん、やっぱり男の子だね。思ってたより、ずっと大きい」
きゅっと背中に回った細い指先がシャツをつかむのが分かって、七海は何とも言えない気持ちになる。
こんなつもりじゃなかった。
自分たちの歩む速度は、ゆっくりゆっくり、まるで亀の歩みのようで、一歩ずつ段階を踏んで昇っていくつもりだった。自分の性格上そうしていくのが精一杯で、一足飛びに距離を縮めることなんてどだい無理な話で。
かなでもそうだと思っていた。何故なら、七海の方から距離を詰めることが出来なくても、かなでは七海を責めなかったから。七海の様子を伺いながら、お互いの歩幅を確かめながら、かなでも自分と肩を並べて、手を繋いで進んでいくものだと思い込んでいた。
でも、二人が『恋人』になってからもう一年が過ぎた。
何も変わらないように見えていても、本当は変わらないものなんてない。七海はあの頃よりもずっとかなでのことが好きで、そして一年という月日は少しだけ七海を成長させた。心ではなく、もっと単純なことで。
背が伸びて、チェロを持ち運ぶ手も力強くなった。劇的に、ではないけれど、かなでと視線を合わせようとすると、自然と少し下向きになる。
気付かなかったのか、それとも気付かないふりをしていたのか、七海にも分からない。
でも、今かなでを抱き締めてみて、七海は初めて実感した。
多分、七海が望めば、七海はかなでを思い通りに出来てしまう。それほどに、自分が成長しているのだということを。
「……七海くん?」
黙ったままの七海を伺うように、かなでが腕の中からちらりと上目遣いに七海を見上げてくる。それがもう、たまらなかった。
考える間もなく、体が動く。唇に何かもっと柔らかいものが触れた、と思ったら、至近距離でかなでがその大きな目を更に大きく見開いていた。ぱちぱち、と瞬きをしてから、気を取り直したようにかなでの目が閉じる。許された、と思ったら、更に行動は大胆になった。
「んんっ」
唇の隙間から、かなでの聴いたことがないくらい甘い声が漏れる。背中に回っていた手が慌てたように七海の腕を掴み、だからといって引き剥がせるわけでもなく、それ以上どうしようもなくてそこで行き詰まる。
自分の舌がひどく甘くて熱いものに触れている気がして、何だかひどく気持ちが良くて。そして、七海はふと、我に返る。自分がかなでに対して何をしているのかに気がついて……弾かれたように身を起こした。
「すっ、すみません……っ! 俺、そんなつもりじゃなくて……!!」
どんなつもりだったのかと問われれば答えようがないが、いつの間にかかなでに深いキスを強要していた自分に気がつき、七海は足の先から頭のてっぺんまで一気に赤く染まる。
これまたこれ以上にないくらいに赤くなった涙目のかなでが、ようやく自分の両手の行き先を見つけて、自分の唇を覆う。七海は土下座しかねない勢いで、頭を下げた。
「ほんとにすみません! 小日向さんの気持ちも聞かないで、俺、何てことを……!」
「あ、あの、七海くん。謝らないで。……急で、ちょっとびっくりしただけで……イヤ、とかじゃないから」
震える声で、かなでが呟く。恐る恐る七海が顔を上げると、気を取り直したように何度か軽く咳払いをしたかなでが、視線を伏せた。
かなでの言うとおり、それが嫌がっている仕草ではないことは七海にも分かる。
そしてその仕草は、……たまらなく可愛かった。
一歩ずつ、ゆっくりと。自分たちにふさわしい進み方は、そういうスローペースなもの。
……その前提を、覆したいと七海が思うほどに。
「こ、小日向さん。あの、俺……、ゆっくりでいいって思ってたんです。周りからもいろいろ言われてはいたけど、俺たちは俺たちのペースで進んでいけたらいいって。今日も『ハグの日』なんだからハグまでできたらいい、それで上出来なんだって思って……でも、本当は違ってたんです」
意気地がないから、勇気がないから、言い出せなかっただけだ。
本当はとっくに、段階なんて悠長に踏んでいられないほど想いは育っていて、ただそれを解き放つきっかけを、ずっと見つけることが出来なかっただけで。
「イヤならイヤって言って下さい。小日向さんがイヤだと思うのなら、それは仕方がないことだってちゃんと分かってます。でも、俺は……俺の方は、それじゃもう耐えられないって気付いちゃったんです。だから……」
決定的なことを言葉にする勇気はない。それでも、かなでは七海がどんな気持ちを抱いているのかは分かってくれる。それを盲目的に信じられるのは、真っ直ぐで実は臆面がない、七海の持つ強さだ。
……そして、その強さが、かなでが七海を好きな理由の一つなのだ。
「……だから、イヤじゃないんだってば……」
消え入りそうな声で、かなでが言う。
え、つまり、それは結局、どういうことなんですか? と、見るからに顔を輝かせる七海が尋ねる。
分かってて聞かないで!と、半分キレたように叫ぶかなでが、割と容赦のない力で、七海の太もも辺りをつねりあげた。
夕暮れを待って、今度は徒歩で駅までの下り坂をのんびりと歩きながら。
ハグの前に、こういう距離の詰め方もあったよね、とかなでが笑いながら、七海の片手を取る。
あ、なるほど、と頷く七海が、それでも一度かなでの手を離して、ポケットから取り出したハンカチで丁寧に手を拭った。
改めて、指と指を絡め合い、手のひらを合わせて手を繋ぐ。
ハグのその先へ、二人で歩調を揃えて、肩を並べて同じ速度で進んでいけるように。
離れないように、繋いだ指先に互いに力を込めた。
あとがきという名の言い訳
七海くん、相変わらず書くのが難しい。ていうか、こういう感情を持たせることが申し訳なく思えますね(笑)純粋な子のはずなのに……。でも、中に出てくるように臆面のない子だとも思ってますよ。でなきゃ妄想をあそこまで発展させることはないと思う(笑)
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2021.07.04