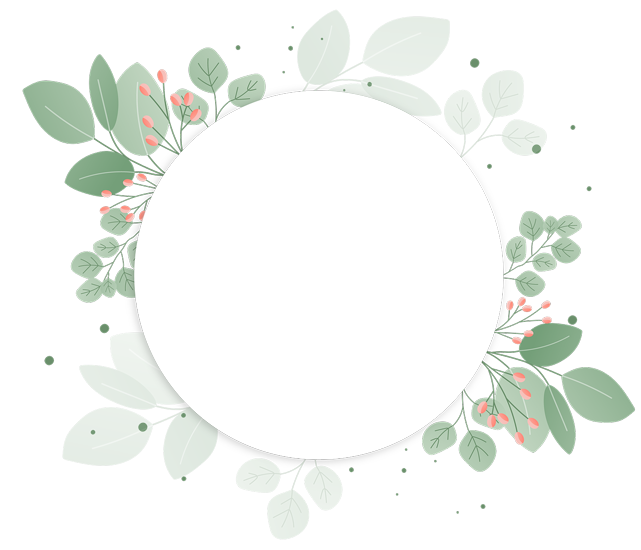二泊分の荷物を詰め込んだキャリーケースを従え、いつも通りビジネススーツをきっちりと着込んだ母が、心配そうな顔でそう言った。
母の出張は珍しいことはない。昔から留守番よろしくと言われて、いってらっしゃいと笑って送り出す立場だったかなでの家事能力は、今では母を越えていて、数晩一人で過ごしても何ら問題はないのだが、それでもやはり出張で家を不在にするたびに残されるかなでを心配するのは、母親としての常なのだろう。
「うん、大丈夫。お母さんも気を付けて、お仕事頑張ってね」
笑顔でひらひらと手を振って送り出すと、後ろ髪を引かれる様子で何度もかなでを振り返りつつキャリーを転がす母は、これまたいつものようにある程度の距離を進んだところで振り返るのを止め、凛と背筋を伸ばし、颯爽と歩くキャリアウーマンの後ろ姿になる。そんな母の姿に憧れを抱くものの、きびきびとした母と違い、自他ともに認めるのんびり屋の自分はああいう格好いい大人の女性になることはないんだろうなと諦観の溜息を付いた。……そもそも、憧れはあってもあまりそうなりたいとは思っていない時点で、かなでが母のようになる可能性は薄い。
「……さてと。私も朝ごはんの用意しなきゃ」
両手を腰に当て、かなでは一人ごちる。かなでも今日は出掛ける予定があった。
そのままドアに鍵をかけて、かなでは母屋へと向かう。そこそこに立派な規模であろう寺には、心機一転を図るために転校を決めたかなでを快く受け入れてくれた遠縁の親戚が暮らしている。あまりお互いが無用な気遣いをしなくていいようにと、下宿という形ではなく、母と共に離れを間借りさせてもらっているが、洗濯や風呂そして炊事などの水回りだけは母屋を利用させてもらわねばならなかった。
寺の朝はお勤めがあるため早い。この時間ならば、母屋の住人達は既に朝食を終えているはずだった。台所を使わせてもらっても問題ないだろう。
「おはようございます」
案の定、裏口から直接つながる台所には人の気配がない。それでも律儀に挨拶をしながらかなでは台所に踏み込み、大きな冷蔵庫を開けて中身を確かめた。
法事などの時、相当の人数分の精進料理を準備することも珍しくないらしく、ここに置かれている冷蔵庫はかなり大きい。その片隅に母娘が使うための食材を置かせてもらっていたのだ。
(ツナとコーンでオムレツ作ろうかな……でも私一人だけだし、鰹節と葱としらすで玉子かけごはんも捨てがたい……)
母はおらず自分一人だけの朝食なので、出来得る限り簡単に、かつ美味しく済ませたい。冷蔵庫の中にある食材で、自分の欲求を満たせるメニューを考えていると、不意に背後から声が上がった。
「……メニューを考えるのなら、冷蔵庫を閉めてから考えたらどうだい。みみっちく我が家の電気料金を上げて、嫌がらせがしたいのではないのなら」
無意識に冷蔵庫の前に座り込んで長考の体勢に入っていたかなでは、文字通り飛び上がって背後を振り返った。
そこには朝のお勤めを終えて、シャワーでも浴びてきたのだろうか。少し髪を湿らせたままの母屋の住人、長嶺雅紀が立っていた。
「あ、ご、ごめんなさい、長嶺先輩。それと……おはようございます」
慌てて冷蔵庫を閉めて立ち上がり、かなではぺこりと丁寧に頭を下げる。おはよう、と応じた長嶺が、台所の様子を伺うように視線を巡らせた。
「君は今から朝食かい?……ならば、ちょうど良かった。我が家の電気料金を若干上げてくれたお詫びに、俺の分も作ってくれないか」
「あれくらいでそんなに料金上がったりしません!……って、長嶺先輩、朝ごはんまだだったんですか?」
普段なら、母屋は朝食をとっくに終えている時間だ。驚いて問うかなでに、長嶺は何でもないことのように言った。
「ああ、今日は両親ともに檀家さんの法事に出かけていてね。……俺は君との約束があったから、手伝いには行けなかったんだよ」
「えっ!」
更に驚いて、ついかなでは声を上げる。
そう、今日かなでは長嶺と出掛ける約束をしていた。この夏以降、いわゆる彼氏彼女の関係になった二人だが、お互いに家族にはそのことを打ち明けていない。そういう関係性で同じ敷地内に暮らすことは、母屋と離れという距離はあれど、いろいろと問題があるだろうと長嶺が言ったからだ。
学校でも、一部の二人に近しい生徒たちには知られているものの、一度騒ぎになったのを否定して以来、二人の関係を改めて問い質すものはいない。確かに二人でいる機会は増えてはいるのだが、それも親戚づきあいの範囲内ということで、周囲が勝手に納得してくれているようだ。
殊更に隠したいというわけではないのだが、あまり大っぴらに主張するのもどうか。そして長嶺が受験生ということもあり、二人で出かけたりすることは極力避けていたのだが、かなではどうしても今日、長嶺と一緒にいたい理由があった。まだ母の出張が決まっていなかったので、家族がいる中、寺の敷地内で一緒にいるのはまずいだろうと、どこかに出かけませんかと長嶺を誘ってみたのだ。
長嶺は特に嫌がる素振りも見せず、二つ返事でかなでの誘いをOKしてくれたので、てっきり何も予定がないのだと思っていた。もしかして、自分のために無理矢理予定を空けさせてしまったのだろうか。
「ごめんなさい、長嶺先輩。法事の予定が入っているなんて全然知らなくて……」
「つまり君は、俺が家の手伝いよりも君との約束を優先したとでも思っているのかい? それはまた、随分と自信過剰なことだな」
「ふえ?」
予想外に意地悪な返答が来て、思わずかなでは間の抜けた声を出す。長嶺が面白そうに喉の奥で笑った。
「……冗談だよ。いくら多少一般家庭より厳しかろうと、息子の将来を左右するこの時期に、無理に家の手伝いをしろとはうちの両親も言わないさ。余程の規模でなければ、法事で俺がいないとどうにもならないということはないのだから」
「えっと、でもそれはそれで、今度は受験勉強の邪魔をするってことになるんじゃ……」
恐る恐るかなでが言うと、長嶺が呆れたように大きな溜息を付いた。
「この時期になって、まだ準備不足で慌てているようじゃ、それこそ合格は無理だろう。そして受験までの残された時間を息抜きに使うのか、復習に使うのかは俺の自由だろう?」
……かなでが所属する吹奏楽部のOBである狩野などは、昨日も問題集とにらめっこをしながら「マズイ、ぜんっっぜんわっかんねー……」と頭を抱えていたような気がする。だが確かに、前部長である八木沢は長嶺と同じように既に準備万端の様子で、嘆く狩野を苦笑交じりに宥めていた。
「じゃあ、今日は一緒に出掛けてもらっても大丈夫なんですか? 長嶺先輩に無理をさせてるわけじゃなく……?」
「納得したなら、そろそろ朝食の準備をお願いできるかい? いい加減空腹も限界だ」
「はい」
嬉しそうに笑って頷き、かなでは和食と洋食どちらにしますか?と長嶺に呑気に尋ねる。
十数分後、かなでが手際よく用意した、予定よりも少々手間暇をかけた二人分の和風の朝食が、母屋の食卓に並べられた。
「本当に、行き先は俺の希望でいいのかい?」
バイクに跨り、かなで用のヘルメットを差し出しながら、長嶺が尋ねる。それを受け取るかなでは大きく頷いた。
「私は、今日長嶺先輩と一緒にいられたら、それでいいんです。それが第一目的だから、場所はどこでも構いません。例えば図書館で受験勉強とかでも」
「やれやれ、君はどうしても俺に息抜きをさせたくないらしいね」
苦笑して息を付くと長嶺はメットを装着し、かなでを促す。同じようにメットを被ってバイクの後ろに乗りながら、かなでは「そういうことじゃありません!」と抗議した。
「まあ、冗談はほどほどにしておこうか。俺も行きたい場所があったからちょうどいい。せっかくだから君に付き合ってもらうとしよう」
言うなり長嶺はバイクのエンジンをかけ、車体は滑るように動き出す。かなでは振り落とされないように、慌てて彼の背中にしがみ付いた。
普段から登下校で通っている慣れた道を辿り、長嶺のバイクは繁華街の方へ向かっていく。あまり時間をかけることなく、バイクは迷わずに地下の駐車場へと降りていった。
「……お買い物、ですか?」
バイクを降り、外したヘルメットを長嶺に返しながら尋ねると、それをハンドルに引っかけながら長嶺が小さく笑った。
「まだ購入まではしないがね。時間に余裕があるうちにある程度目途をつけておきたいと思っていたんだ」
そう言う長嶺がかなでを連れて入ったのは、とある雑貨屋だった。普段かなでが立ち寄るような可愛らしい店ではなく、どちらかと言えばシンプルなデザインの小物が並んでいる。その中で長嶺は、キッチン用品が陳列してある棚の前で足を止めた。
「さて、一体最低限どれを揃えればいいものなのか、教えてもらえるかな。小日向さん」
「えっ」
思わず声を上げ、かなでは棚の品物と長嶺とを見比べてしまう。寺では全く料理をしない長嶺がキッチン用品を物色しに来るなんて、どういう風の吹き回しなのだろう。
「長嶺先輩、お料理始める気なんですか?」
「出来ることなら始めたくはないけれど、始めざるを得ないだろうね。希望の大学に受かれば、来年の春から関東で一人暮らしなのだから」
溜息交じりの長嶺の答えに、かなでは彼の志望校が関東の大学だったことを思い出した。受かればと但し書きを付けているが、長嶺の成績は優秀であったし、推薦までもう一か月を切っているこの時期にこれほどの余裕を見せているのなら、おそらく問題なく合格を決めてしまうのだろう。ならば、長嶺が既に合格のその先を見据えていても、彼の性格上何ら不思議なことではない。
(そっか……春には長嶺先輩、お寺からいなくなっちゃうんだ……)
もちろん、かなでも分かってはいたのだが、今は敢えて考えないようにしていた。改めてそのことを本人から告げられると、希望する進路を選び取れるのは喜ばしいと思いながらも、彼がいなくなることはとても寂しい。つい気持ちが下降気味になるかなでを、訝しげに長嶺が見つめた。
「どうかしたのかい、小日向さん」
落ち着いた声で名を呼ばれ、かなでははっと我に返る。……今からこんなことでは先が思いやられる。それに今日はかなでからの誘いで、長嶺の受験前の貴重な時間を割いてもらったのだから、楽しい気持ちで過ごさなければ罰が当たる。
そう思い至って、かなでは暗い気持ちを振り払うべく、ふるふると小さく首を横に振った。
「いえ、大丈夫です。最低限必要なもの、ですよね?」
気を取り直して陳列されている商品を見上げ、あれやこれやと指差し、かなでは長嶺にその品物の使用法を説明していく。真面目にかなでの話を聞く長嶺は、時折細かい質問を挟みながら、自分が使用可能な道具を吟味しているようだった。
最近のキッチン用品は便利なものが多く、種類豊富だ。上手く揃えれば、料理初心者の長嶺でもそこそこ調理が出来るようになるだろう。そう考えて、一風変わっているが便利な調理具なども教えてみたが、長嶺はあまり興味を示さなかった。
「君が考えるところの必要最低限で構わないよ。どうせ1年ほどの辛抱なのだから」
「1年?」
長嶺が受験する大学は4年制だったはずだ。例えば滑り止めに短大や専門学校を受けているにしたって、最低でも2年は関東にいることになるはずだ。かなでが不思議そうに首を傾げると、長嶺は呆れたように溜息を付いた。
「やれやれ、俺より1年も長く準備期間があるくせに、君は既に浪人覚悟なのかい?」
「……えっ……と」
長嶺の言葉で、彼の言いたいことはかなでにも分かった。……分かった、のだが……。
「私が、来年関東の大学を受験するのは、長嶺先輩の中で決定事項になってるんですか……?」
まだ母親にも言っていないが、かなでは来年横浜にある星奏学院の大学部を受験するつもりでいた。星奏には気心の知れた幼馴染みたちがいるし、夏にアンサンブルコンクールに参加するために付属の寮に数日滞在し、こっそり大学部の見学をさせてもらった時に、どことなく穏やかなキャンパスの雰囲気が自分に合っているような気がしたのだ。もう一度どこかでカリキュラムの内容を確認したり、オープンキャンパスに参加してみたりで吟味してみようとは考えているが、現時点では確かにかなでの進路の第一希望だった。
「俺の勝手な思い込みで言っているつもりはないんだけれどね。違っていたかな?」
「……違わない、ですけど」
でも何だろう、この見透かされている感じは。
「君が夏に横浜の星奏で楽しそうに過ごしていたことは知っているし、自惚れさせてもらうなら、俺が関東に行くということが、君があちらに行くことの理由の一つになると思っているんだけれどね。……何にしても、君が来年俺を追って関東に来るのなら、俺は自炊生活を何とか1年間乗り切ればいいわけだ」
「ええと……それって1年後、私が長嶺先輩のお食事の用意をすることが決定事項ってことに……」
言いながら、かなではかあっと頬を赤く染める。
それはつまり、同居生活のお誘いということになるのでは……?
「脳内で盛り上がっているところ悪いけれど、俺と君とでは受験する大学も違うし、生活のパターンも異なる。すれ違うのが目に見えているから、同居はあまりお勧めしないよ。……冗談はさておき、いくら家事が苦手な俺でも1年も経てば基本的なことは出来るようになっているだろう。凝ったものを作る気はないから、最小限のもので構わないのだよ。そもそも君の腕に追いつくのは難しいだろうから、君が関東に来た暁には時々御相伴に預かれればそれでいいさ」
「もー!すぐにそうやってからかうの、止めてもらえません?」
恨みがましく上目遣いにかなでが長嶺を見上げると、彼は小さく肩を竦めて踵を返す。
「……まあ、俺にも同居とまでは行かないまでも、味噌汁が冷めない距離で、くらいの望みはあるがね」
と、小声で呟いた彼の声は、置いてけぼりを食らいそうになって、慌てて彼の背を追ったかなでの耳までは届かなかった。
ある程度の買い物を目星がつけられたと長嶺が言うので、その後はかなで好みの雑貨屋や本屋などに立ち寄りつつ、二人は繁華街デートを満喫する。
食事も済ませておいた方がいいと長嶺が言うので、夕方少し早い時間、混み出す前のイタリアンレストランで夕食を取った。母が不在のかなでにとっては、一人分の夕飯の支度をする手間が省けてありがたかったのだが、長嶺の方から外食を持ちかけて来たということは、もしかしたら法事に出かけたという長嶺の両親も今日は帰りが遅いのかもしれない。ならば少しだけ遅くまで二人でいられるかなあと呑気にかなでは思った。そして、そのかなでの期待は裏切られることはなかった。
「小日向さんは、時間は大丈夫なのかい?」
バイクを停めた地下駐車場に戻り、いつものようにかなで用のヘルメットを差し出しながら長嶺が問う。かなではそれを受け取って、こくんと頷いた。
「今日からお母さん出張なので離れに戻っても私一人だったんです。だから遅くなっても大丈夫です」
「ああ、そうか。それで夕飯を外で済ませようと言っても断らなかったのか」
「おかげで、食事の支度せずに済みました」
笑ってかなでが言うと、釣られたように微笑んだ長嶺が背後を示す。
「ならば、あと少し俺に付き合ってもらおうかな……乗りなさい」
かなでが後部座席に腰かけ長嶺の背に掴まると、長嶺のバイクは滑るように走り出す。地下駐車場から這い出し、瞬く間に大通りの中に混ざり込み、車の間を縫うようにすり抜けて行く。陽が落ちるのが早くなったので、辺りは既に薄暗い。初めてバイクに乗せてもらった頃は、長嶺に縋り付いているので精一杯だったかなでだが、さすがに乗り慣れて来ると恐る恐るながらメット越しに周りの風景を伺えるようになる。迷いなく長嶺が操るバイクの道筋に覚えがあった。
渋滞を抜けて、車の往来が減った坂道をバイクは難なく登って行く。そうして辿り着いたのは、かなでの想像通り、いつか長嶺が連れてきてくれたテレビ塔の見えるあの場所だった。
「少し寒いかな。大丈夫かい?」
「はい、全然平気です!」
長嶺の秘密の場所に、もう躊躇うことなく自分を同行させてくれることが嬉しい。満面の笑みでかなでが振り返ると、停めたバイクに寄り掛かるようにして長嶺が眼下の夜景に視線を向ける。並んで同じようにかなでが夜景を堪能していると、ふと思い出したように長嶺が言った。
「そういえば、小日向さん。差支えなければ教えて欲しいことがあるんだが」
「はい、私で答えられることなら。何ですか?」
「どうして今日、俺は君に誘われたのかな。特に目的もないのであれば、別に受験が終わって落ち着いてからでも問題なかった気がするんだけれどね」
かなでから今日を一緒に出掛けられませんか?と尋ねられた時からずっと不思議だったのだ。
こうと決めたら頑として動かない意固地さは多少あるものの、かなでは基本的に一般的に女子というものが言いそうな我儘を言う方ではない。法事の予定と受験勉強のことを長嶺本人以上に気にしていたことからも、長嶺の都合を全く考慮しないまま自分の意志を押し付けようとしていたわけではないことが分かる。
だからこそ是非この日にと、かなでが『今日』にこだわった理由が気になる。何かの記念日だったろうかとも考えたのだが、自分やかなでの誕生日でもなければ、それらしいイベント事のある日でもない。
近年巷で有名になってきたのは明日のハロウィンくらいのものだが、その前夜祭のつもりならもう少しハロウィンらしい過ごし方をするだろう。そもそも、イベント当日ならともかく、その前日にこだわるというのもおかしな話だ。
長嶺の問いに、かなでは微かに目を見開く。まさか、理由を追及されるとは思っていなかったのだろう。困ったように視線を泳がせ、それから自分の爪先へと落とす。他には誰もいない高台に、小さなかなでの声が響いた。
「あの……ホントにくだらないことだったりするんですけど、笑ったりとかしません?」
「さあ? 何事も聞いてみないことにはね」
笑わない、という保証を長嶺はしない。例えばどんなささやかな理由であろうと、そこに彼女なりの信念があるのならば、怒ったり馬鹿にしたりするつもりはなかったが、何と言っても彼女はいつも、長嶺の意表を突いてくる。その彼女なりの理由が微笑ましいものであれば、長嶺の対応もそれなりのものになる。これはこれで自分なりに嘘のない誠実な回答だと思うのだが、かなではうう、と小さく唸った。
「何かすっごく馬鹿にされそうだから言いたくないなあ……」
「それなら俺は、その理由が気になって延々と考えてしまって、うっかり受験に失敗してしまうかもしれないね。その時は責任は取ってもらえるのかい?」
軽口で脅しをかけてみると、増々悔しげにかなでは長嶺を睨む。
「先輩の将来を盾にするとか、卑怯じゃないですか!?」
と抗議するので、長嶺は不敵に笑い返した。
「君に卑怯と言われるほどに有効な脅迫になっているのならば結構だ。俺を浪人させたくないのならば、観念してさっさと白状したらどうかな」
二の句が告げられず、ぱくぱくと無意味に口を動かしていたかなでは、やがて諦めたのか、一つ大きく息を付き、それから徐に顔を上げた。
「今日が何の日か、長嶺先輩御存知ですか?」
「……それが分かっていたら、脅迫めいたことを言ってまで君を追求する必要がないと思うけれどね」
長嶺が言うと、ですよねーとかなでが肩を竦める。
「じゃあ、先輩。島崎藤村って知ってます?」
これまた随分と見当違いの方向へ話が飛んだ。しばしの沈黙の後、長嶺は深く追求することを諦め、「まあ、一般常識程度には」と答えるに留める。
「今日は、その藤村さんが初恋の詩を発表した日ってことで、『初恋の日』なんですよ」
「……へえ」
……としか、長嶺には答えようがない。話し始めて堰が切れたのか、かなではつらつらと語り続ける。
「藤村さんに所縁のある宿が制定した記念日なんですけど、そのお宿が長野にあるんです。そのせいか分からないけど、中学の頃の国語の先生が藤村さんが好きで、初恋をテーマにしたはがきコンテストみたいなのに応募させられたりしましたよ。懐かしいなあ」
小さく笑って、懐かしむように遠くを見つめて目を細め。それからかなではもたれ掛っていたバイクから身を起こし、数歩進んだところでくるりと長嶺を振り返る。
「詩とかそういうのは興味がなかったんだけど……この日が『初恋の日』だってことがずっと頭の中に残ってて。いつか自分が初めて恋をしたら、この日はその相手とずっと一緒に過ごしてみたいなあなんて。ずっと憧れだったんです」
至誠館高校に編入して、長嶺と出逢って。
紆余曲折ありながらも、初めて想いが通じた相手と一緒に過ごすことの出来る憧れの記念日だった。
……そんなことを想像すると、とても胸が痛いのだけれど、万が一この恋がいつか終わりを告げる日が来て、その後何度も何度も、誰かと恋に落ちるのだとしても。
初恋の相手と過ごす『初恋の日』はかなでにとって今日のこの日だけだったから。
「君の、初恋?」
「はい」
「俺が?」
「はい。……何かおかしいですか? いや、可笑しいと言えばそうかもですけど。17歳で初恋とか、遅いですよね」
「そうではなくて。……君には確か、幼馴染みがいただろう?」
淡い初恋というものは、幼い頃に傍にいる異性に抱きがちなものだと長嶺は考える。自分を顧みた時にそういう存在がいたかどうかを考えると、全く心当たりがなくて、一概にそうだとは言えないものだと分かってはいるのだが、以前にかなでから、同い年と一つ上の異性の幼馴染みがいると聞いた時に、確かめたわけでもないのにそこに淡い恋物語を創り上げてしまっていた。
実際に横浜でその幼馴染みたちと親しげにしているかなでを遠目に目にする機会もあったため、その影響もあるのかもしれない。
「え、響也と律くんですか?……まあ、確かに幼馴染みですけど、初恋相手というよりはちっちゃい頃から一緒にいすぎて、むしろ兄妹の感覚に近い気がします」
長嶺の問いに、かなでは生真面目に答え、それからはにかんだように頬を染めて笑う。
「そう言えば、遠縁だけど長嶺先輩と私の方がきちんとした親戚関係なのに、響也たちの方がよっぽど親戚っぽいですね」
恋に落ちるには近過ぎた距離。
だからこそ、やはりかなでにとって恋と言える甘い気持ちを持ちえたのは、長嶺が初めての人なのだ。
「……初恋の長嶺先輩と、『初恋の日』に一緒にいたかったんです。特別なことも何もしなくていいから、ただ、ずっと一緒に」
忙しい人で、こんな風にのんびりしていていい時期ではないことも、ちゃんと分かっていた。それでもただ、一緒にいたかった。
そんなささやかで、それでいて大層なかなでの願いを叶えてくれた長嶺に、かなではこれ以上にないくらいに感謝していたのだ。
「……そうか」
しみじみと嚙み締めるように呟き、ふと長嶺が解けるように笑みをこぼす。彼のそういう表情も珍しく、かなでが思わず見とれていると、伸ばされた長嶺の手がかなでの手をそっと握る。
「ならば、必然的に俺も『初恋の日』とやらに、初恋の相手と一緒に過ごせたというわけだ」
「……え?」
「俺の初恋の相手が君だと、何か不都合があるかい?」
ぽかんと口を開くかなでに、何でもないことのように長嶺が言う。
「だ、だって、初恋の相手って……」
「俺の日常を思い返せば、想像がつくだろう? 早朝から寺のお勤めに始まって、ホルンの練習に勉強やら何やら……そうこうしているうちに進学した高校は、至誠館という元・男子校で、しかも進学校だ。誰かと恋に落ちる暇なんてない」
「それでも、恋をするチャンスっていくらでもあるものなんじゃ……」
「心を動かされる出逢いがなければ、余程それを望んでいない限り簡単に落ちるものじゃないよ。……君も自分の経験として知っているものだと思うがね」
淡々とかなでの疑問を塗りつぶしていく長嶺に、かなでは二の句が告げなくなる。
確かに、本当に恋と言えるほどの強烈な出逢いにはそうそうお目にかかれるものじゃない。
恋をしたいという望みがなければ、無造作にその辺りに転がっているはずのきっかけをうっかり拾い上げることもない。
だからこそ、長嶺に出逢うまでの約17年もの間、かなでは誰かに恋するという気持ちを知らずにいたのだから。
そうして、長嶺もかなでに出逢うまでの約18年間、かなで以外に心を揺らす存在に巡り逢わなかったと言ってくれるのなら、それはかなでにとって、とても幸せなことだ。
「……そんな理由があるとは知らなかったが、君の誘いを断らなくてつくづくよかった。思いがけず俺にとっても大事な記念日になったようだ」
「だったら、よかった」
幸せそうに笑うかなでの頬を、長嶺の大きな掌がゆっくりと撫でる。
言葉のない長嶺の仕草に含まれる意図を正確に感じ取り、かなでは目を閉じた。
少し待つと、唇に柔らかな熱さが触れる。ただ触れて、離れて。震える瞼を押し開くと、とても近い場所に端正な長嶺の顔があった。
秋から冬へと移行する季節、肌に触れる空気は既に冷たい。どちらからともなく、温もりを分け与えるようにお互いの存在をその両腕の中に捉える。……そうは言っても、当然のことながら、小柄なかなでの両腕の中に、長嶺の長身は収まってはくれなかったのだけれど。
「……かなで」
耳元で、低い長嶺の声が響く。空気が冷たいのと、くすぐったいのと……それに、何かよく理解できない不思議な感覚で、かなでの身体が小さく震えた。
「……俺のものになりなさい。俺だけのものに。君は、頷くだけでいい」
「……え?」
目を見開いたかなでが、身を起こして長嶺を見る。意地悪そうな笑みを浮かべてはいるものの、長嶺の目は笑っていない。真剣そのものだった。
「長嶺先輩、それって……」
「ちゃんと記憶できているようだね。……以前にも君に言ったことのある言葉だ」
そう、アンサンブルコンクール全国大会決勝の日。全国大会優勝を決めたかなでに、想いを告白してくれた長嶺が告げた言葉と同じものだ。
「……だが、今の言葉はあの時とは少し意味合いが違う。その意味を、君は理解してくれるかな?」
「あ……の……」
いくら周囲から天然とからかわれるかなででも、自分が今置かれているこの状況で、しかも他でもない長嶺からその言葉を告げられて、その奥にある意味が読み取れないほどに致命的に鈍くはない。
真っ赤になってかなでは視線を下に向ける。どう答えていいのか分からなくて、しばらく顔が上げられなかった。
「あの……もし、私がそれを断ったら。いったいどうなるんですか……?」
即答は出来ない。だからと言って、そう簡単に突き放せもしない。ならばもういいと、長嶺がこの関係を断ち切ってしまわないとは言い切れないからだ。
「おやおや、俺は随分と君からの信用がないね」
苦笑交じりに呟き、長嶺はかなでの背に回した掌で、宥めるようにかなでの背中をゆっくりと撫でる。
「断られれば、また別の機会を探るだけだよ。今更俺の方から君を手放す気はないのだからね。だが、君があまりにも可愛いことを言い出すし、状況的にも今日は好条件が揃っている。ならば、君の言うところの特別な記念日を、もっと特別なものにしないかと提案しているんだよ」
「好条件って……?」
「君のお母さんは、今夜は出張で戻らないんだろう? うちの両親もそうなんだよ。遠方の知人宅に泊りがけで法事に出かけている。少なくとも、明日の夕方までは戻らない」
「え。……ええっ!?」
長嶺が夕飯まで済ませて、なかなか帰ろうと言い出さなかったことに、ようやく合点がいく。まるで、初めから仕組まれていたようで、妙に腹立たしい。
「教えてくれればよかったのに! ていうか、初めからそれを見越してたんじゃ……」
「変に邪推するのは良くないな。そもそも、今日誘ってきたのは君の方からだろう?」
両親の不在は随分前から決まっていたが、それはかなでに誘われるよりも前だった。そして、かなでの母親の出張がなければ、夕暮れまでには寺へと戻っていただろう。
今日がその日だと、何かに導かれているような気がした。だから、その波に乗ろうと試みているだけだ。
「今日君が断ったとしても、いつかは俺のものにするつもりなのだから、そこは君の希望に任せて構わないよ。……どうする? かなで」
自信に満ちた笑みを浮かべ、長嶺がかなでの顎を持ち上げ、自分の方へと向けさせる。頬を赤く染めたまま、かなでが恨めしそうに長嶺を睨み付けた。
「……断らないと思ってるんでしょう?」
「さあ、どうだろう? 別に断られたからといって何かが変わることはないけれど、素直に頷いてもらえるように、俺なりの努力はしてみようと思っているよ」
言うなり、長嶺はかなでの唇に深く自分の唇を重ねる。無理矢理に開かされた唇から、熱い舌が入り込んで来て、丹念にかなでの口内を味わう。
こんなに深い口付けは初めてだった。かなでは突き放すことも抗うことも出来ず、ただ長嶺から与えられるものに翻弄される。
身体の中から聞こえてくる濡れた音も、つい漏れ出てしまう甘い吐息混じりの声も、恥ずかしくて耳を塞いでしまいたいと思うのに、かなでを抱き締めたままの長嶺の腕がそれを許さない。解放されたいのに、初めての深いキスがひどく気持ちが良くて、いつしかかなではぎこちなく長嶺の舌の動きに応え始めていた。
やがて長嶺の唇がわずかに浮き、かなでが目を反らせないように両手で頬を覆った長嶺が、熱に浮かされたように潤んだかなでの目の中を覗き込んだ。
「では、もう一度聞くことにしようか。……かなで、俺だけのものになりなさい。心も身体も、俺だけのものに。君は頷くだけでいい」
震える力ないかなでの指先がゆるゆると持ち上がり、長嶺のシャツの袖を掴む。
小さく頷いたかなでに、長嶺は満足げに微笑んだ。
「……いい子だ」
そして、かなでの震えと熱が治まるまでその身体を抱きしめていた長嶺は。
ひどいとかずるいとかヘンタイとかぶつぶつと愚痴を零すかなでの気が済むまで。
秋の夜の小さな街灯の下で、ずっとかなでの髪を優しく撫で続けていた。
あとがきという名の言い訳
ASの設定資料集を読みながら書き続けてはいたのですが、秘密の場所デートまで進んだところで見事に筆が止まりました。
ちょうどダウンロード版のセールやってたので、思い切って至誠館と天音を購入してしまいました。うん、予想通り面倒な男だった、長嶺!(笑)
若干年齢制限を入れた方がいい気もしましたが、まあ渡瀬の創作読んでる人はこれくらいはなんてことないだろうし、ということで(笑)
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2017.03.20