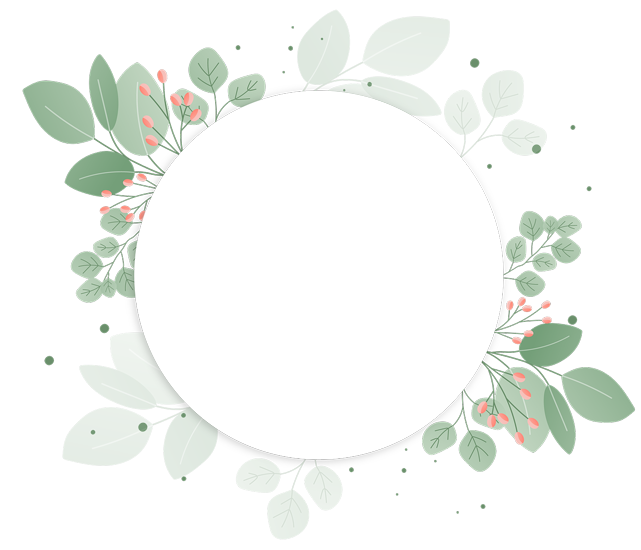「11月5日空いてませんか?」……それは、饒舌な彼女にしては珍しい、とても短い誘いの言葉だった。
確か5日は休日だったので、誘われるのは別に不思議なことではない。でも、わざわざメールで聞くことはないのに、と須永は思う。
須永が顧問を務める星奏学院高等部のオーケストラ部に、付属の大学部に進学した彼女は週に数回、後輩の指導に訪れる。メールを受け取ったその日も、日中オケ部で顔を合わせていたのだから、そこで直接誘ってもらっても、全然構わなかったのに。
そう考えて須永は逆の状況を考えてみる。自分が彼女を誘いたいと思って、面と向かって逢う機会があって。果たして自分は彼女を直接誘うことが出来るのだろうか。
導き出した答えは否だった。自分に不可能なことを相手に強要する訳にはいかない。
更に言えば、ここで折り返し電話をかけて「どうせなら直接誘ってくれればいいのにさ。可愛い女の子の誘いを無碍なく断れないでしょ?」と軽く言ってしまえるのが、須永自身の考える正しい『星奏学院高等部音楽科教師・須永巧』の姿なのだが、取り繕っても仕方のない相手に見栄を張るほど無駄なことはない。
少し迷った末に須永は「大丈夫、空いてるよ」と同じように端的なメールを返す。
11月初旬はちょうど中間考査の採点が終了する辺りで、雑務の多い教師業がようやく小休止を迎える時期だった。
派手な外見と、それに見合った気障な言動に、生徒たちは純粋に騙されてくれているが、実はそんな須永の外面は仮の姿だ。
星奏学院の臨時採用試験を受ける時、一緒に受験するメンバーの中に一際インパクトの強い同期の小倉宗一郎がいたため、第一印象が薄れてしまわないようにと一念発起し、須永は高校デビューならぬ就職デビューを果たしたのである。
それが功を奏したのか、無事に臨採に合格した須永たちは、オケ部の顧問と副顧問を引き受け、生徒からの信頼を得た。肝心な指導の方も、見た目の人気に加え、意外に真面目で丁寧な須永の指導は生徒たちからの評判も良く、その甲斐あって無事にこの春、小倉と共に本採用を勝ち取ることができたのだ。
外側の皮を一枚厚めに着込むことは、地味で目立たず、小倉から親しみを込めて(と信じている)『空気』と呼ばれていた須永には、思いのほか都合が良かった。本当の自分を曝け出すことなく、当たり障りなく過ごしていれば、無駄に失敗することも、傷付くこともない。だが物事からつかず離れずの一定の距離を置くことは、心から夢中になることもない。それもある意味、自分らしいと半ば諦めの境地に達していた須永の前に現れたのが、小日向かなでという一人の女生徒だった。
小日向は偶然須永の本性を知った生徒だった。
須永と違い自分と他人との距離が近く、素直で物怖じしない性格の小日向は、須永が己を守るために懸命に外側に張り巡らせていた境界線を物ともせず、実はこの年になってもまともな恋愛経験がなく、全く女慣れしていない真実の須永に辿り着き、そして何故かその本質こそをとても慕ってくれたのだ。
懐いてくる小日向のことを、教師の中では須永たちが一番彼女に年齢が近く、また須永の情けない本性を知ってしまったことで気安く思う気持ちを恋だと錯覚する、思春期にありがちな熱病だろうと高をくくっていたのだが、まさか自分の方が彼女に恋をすることになろうとは思ってもみなかった。
だが臨採とは言え、当時の須永と小日向は、あくまで教師と生徒の関係だった。
彼女を好ましく想う反面、この職に引っかかるまでとにかく苦労の連続だった須永は、自分たちの立ち位置を思うと、真っ直ぐに自分へと向けられる小日向の想いを、受け入れることが出来なかった。真面目だと言えば聞こえがいいが、要はようやく手に入れたものを全てを放り出してまで、小日向との恋にのめり込む勇気が持てなかっただけだ。だが、そんな優柔不断で臆病な須永さえ、小日向はあっさりと許したのだ。
気の合う仲間たちを集め、『週末合奏団』というアンサンブルで活動していた小日向は、星奏学院の伝説となっていたジルベスタコンサートの再演を果たし、新たな伝説を作り出す。
そして、そのジルベスタ―コンサートの夜、小日向のヴァイオリンは須永に向けて『愛の挨拶』を奏でてくれた。小日向の想いを乗せて耳に届いてくるその音色を、どうしても須永は振り払うことができなかった。
須永の在学中に校内で話題になった、叶わぬはずの恋が成就するという『ヴァイオリン・ロマンス』の奇跡。高等部卒業から約8年、まさか須永自身にその奇跡が起こる日が来るとは思ってもみなかった。
ヴァイオリンの音色に導かれ、須永が小日向の元へ辿り着く。その現実こそが須永と小日向の想いの証だったが、それでも尚、自分の立場を考えれば、彼女に好きだとは伝えられない。そんな煮え切らない須永に、満面の笑みで小日向は言ったのだ。
「私、先生の迷惑になりたいんじゃないんです。想いを返して欲しいんでもなくて……ただ、私が先生が好きってことが嘘じゃないって、ちゃんと分かってて欲しいんです」
健気にそう言ってくれる小日向を突き放すことは、須永には出来なかった。何よりも須永自身が、生まれて初めてようやく手が届きかけた恋を捨てられなかったのだ。
それでも須永の想いは、はっきりとは彼女に伝えられず、彼女も特に何も望まずの曖昧な関係のまま月日は過ぎ、小日向が高等部を巣立った今年の春。
卒業式の日に、今度は須永が小日向のために、ヴィオラで『愛の挨拶』を弾いた。
彼女から告白されて一年と少し。相変わらず自分たちは教師と生徒のままで、それでもほんの少しだけ、他の生徒たちよりも近しい距離で……須永が望んだ関係性を維持したまま、その瞬間を迎えたのだ。
どこからか須永のヴィオラの音色を聴き付けた小日向が、いつかと真逆の図式で息を切らせて、須永のいる屋上に現れた。輝くような、幸せそうな笑顔を向けた彼女が須永に向かって、「これからもよろしくお願いします」と、深々と頭を下げてくれた。
「こちらこそよろしく」と自分の中にある『余裕』を総動員して大人の男を装った須永が答え、自分たちの新しい関係は始まった。
……そのはずだったのだが。
(何で俺、ちゃんと彼女に『好きだ』って言ってないのかな……?)
須永は当然、彼女の卒業を期に小日向と真面目に交際を始めるつもりで、彼女への想いを込めてあの時『愛の挨拶』を弾いた。その音を受け止めて「これからも……」と言ってくれた彼女も、そのつもりでいてくれたと思いたい。
だが自分からも、そして小日向からも改めて「好きです」とも「付き合ってください」とも言わなかったことが、今になって須永に引っ掛かりを残している。
一度、一緒に飲んだ小倉に酔った勢いで愚痴ったことがある。決定的な言葉を言わないままで、はたして本当に自分たちは付き合っていると言っていいのだろうか、と。
それを聞かされた小倉は、失笑した挙句、小馬鹿にしたように鼻で笑った。
「今時、青春真っ盛りな思春期のガキどもですら、いちいち「好きです、付き合ってください」から交際始める方が珍しいだろ。なーんとなくくっついて、なーんとなく終わるってのが社会の常識なんだよ」
それは社会の常識じゃなくて、単にお前の経験ではってことだろ。
そうきちんと反論できたかどうか、あまり強くはないのにその時点で結構な量のアルコールを摂取していた須永は、よく覚えていない。
兎にも角にも、そんなふうに始まった自分と小日向の交際(?)も、もうすぐ8ヶ月が経過する。恋愛経験皆無の二人らしく、小倉には既に匙を投げられているほどの、亀の歩みの清い交際だ。
お互いに大学・教師生活が忙しく、これまでは雑務が減る学校の長期休暇の時期に二人で映画を観たり、食事をしたりの可愛らしいデートが数回あった程度だ。だが、小日向がライフワークよろしく続けている『週末合奏団』のコンサートを須永が聴きに行ったり、彼女が高等部のオケ部の指導に来たりするので、幸いにも逢えない寂しさを感じたりすることはない。
彼女も特に須永に対して不平不満を訴えることはないし、おそらくこれが自分たちにふさわしい恋の進め方なのだろうと、納得してはいる。
それでも、自分たちは本当にこのままでいいのかと焦りにも似た気持ちを抱いてしまうのは、やはり須永の方が年上で、それでいて男だからなのだろうか。
「おはようございます、須永先生」
約束の11月5日、待ち合わせたみなとみらい駅で、たくさんの人々が乱雑に行き交う間を縫うように小日向かなでが現れた。ちなみに卒業してからも、変わらず彼女は須永を先生呼びのままだった。須永と顔を合わせるのはオケ部の練習であることが多いため、生徒の目を気にしてくれているのだろう。
「おはよう、小日向さん」
「いいお天気でよかったですね。雨が降っちゃったらちょっとやだなあって思ってたんですけど……」
小日向の言葉に、そういえばと須永は首を傾げる。
「俺、詳しいこと分かんないままここに来ちゃったけど、今日は結局どこに行くの?」
5日は空いていると返信した後、小日向からは待ち合わせの時間と場所の連絡があっただけだった。今日何のために誘われたのか、須永は目的が分からないままだった。
駅で待ち合わせたということは電車に乗るのだろうが、この路線はいわゆるデートスポットが多すぎて、どこが最終目的地なのか皆目見当がつかない。
「あ、えっと。中華街まで行こうと思ってるんですけど。ちょっと、須永先生と二人で行ってみたいところがあって」
どこか不安そうに、上目遣いに須永を見上げた小日向がそう言った。……相変わらず、無意識に須永を煽ってくる子だ。その角度で女性が男を見上げてくるのはどのくらい心臓に悪いのか知ってんのかな……と考え、それから須永は何かを振り払うように何度も首を横に振った。
「あの……駄目なら別に、他のところでも」
須永の動作を否定と取ったのか、俯く小日向はどこか沈んだ声でぽつりと告げる。慌てて須永は再度首を横に振った。
「いや、違う。駄目なんじゃなくてさ……ちょっと邪念を振り払っておかないと、俺の心臓が持たないっていうか」
「え?」
「いやいやいや……とにかく、中華街が目的地なんでしょ? OK、大丈夫。行こう行こう」
誤魔化すように言って、須永は小日向を促し、その細い両肩を掴んで改札方向へ向き直らせる。
そのまま両肩を押して二人で前後して歩き出しながら、その掌の中で感じる彼女の身体の細さを柔らかさとを実感して、また須永は彼女の背後で一人、邪念を振り払うのに一苦労するのだった。
観光地としても名高い休日の横浜中華街は、何処を見ても人ばかりだ。もしかしたら学院の生徒と鉢合わせするかもと不安だった須永だが、この人込みの中で見知った顔に出逢うのはむしろ奇跡に近いだろう。
そもそも須永が指導を担当しているかオケ部所属かでもない限り、制服を着ていない私服の生徒を見分ける自信もない。特に女子は、私服で印象ががらりと変わるから。
逆に外見を無駄なくらい派手に繕っている自分が生徒側から発見される可能性はあるが、それでも小日向となら、オケ部の指導方針についての打合せという、もっともらしい言い訳が出来る。
(まあ、別に隠しておきたいってわけじゃないんだけどさ……)
もう教師と生徒ではない。オケ部の指導をしている彼女は須永と顔を合わせる機会も多いので、そのうちに恋愛関係に発展したということも、普通にあり得る話だろう。だから生徒たちに見つかっても、堂々と「デート中だよ。教師と言えども私生活は自由でしょ」と言い切ってしまえばいい。無意識に周りに愛嬌を振り撒く彼女が、自分のものだとそれで周知できるのなら、むしろ好都合だと思う。それでも出来ることなら、やっぱり学院の生徒たちとは遭遇しないようにと願ってしまうのは、高校生の彼女こそに恋をしてしまった、須永自身の罪悪感の成せる技なのかもしれない。
「えっと、ここがこれだから、こっちに行って……」
須永が脳内で葛藤している間、小日向は小日向で目的地に向かうため、スマートフォンの地図アプリを立ち上げ、周囲の風景と画面とを懸命に照らし合わせている。そう言えば彼女は地方の出身で、星奏学院に編入後は部活を含めた学校生活と合奏団の活動が忙しく、それらに関連する場所以外にはほとんど行ったことがないと話していた。しかもかなりの方向音痴らしく、道案内を彼女に任せると通常の三倍は時間がかかると、在学時に彼女の幼馴染みが嘆いていたことを須永は思い出した。
「あのさ、小日向さん? 最近出来た新しい店とかじゃなきゃ、俺、普通に道分かると思うよ」
地図を見るのは心底苦手らしく、眉間に深い皺を刻んで画面を睨んでいた小日向が、「ホントですか?」と顔を輝かせて須永を振り仰いだ。
「まあ現役の頃からは少し間が空いてるけど、一応学生時代にはしょっちゅう遊びに来てて、『俺の庭』宣言してたくらいだし?」
冗談めかして言うと、小さく小日向が笑った。じゃあ、とそれまで格闘していた地図アプリを閉じ、スマートフォンをバッグの中に押し込んだ。
「横浜媽祖廟ってところに行きたいんですけど、場所分かりますか?」
「媽祖廟? 関帝廟じゃなく?」
一般的に観光地として知られているのは、関帝廟のはずだ。間違いではないかと念押しすると、小日向は大きく頷いた。
「はい、媽祖廟です。……出来れば今日、須永先生と一緒に行ってみたくて」
何故か頬を染めた小日向が、小さな声で言った。
「そう? ま、いいや。そうだな、媽祖廟ならこっちから行く方が近いかな」
よく分からないなりにも、彼女が行きたいと言うのだから従おうと、須永はご要望の媽祖廟の方角へ爪先を向けた。先に立って歩きかけて……それから須永は、ふとその足を止めた。
「……須永先生?」
突然立ち止まった須永の背中に、不思議そうに小日向が声をかける。あのさ、と視線を反らしたまま、須永がたどたどしく言葉を紡ぐ。
「あの、良かったら。……手とか、繋ぐ? 人多いし、はぐれたら大変だし……」
過去にも何か似たような誘い文句を口走った記憶がある。何だそれ俺全く成長してないじゃん、つかそれ以前に、もうちょっと年上の男としてスマートな誘い文句が別にあるでしょ、と、自分で自分を突っ込む一方、不器用すぎる誘い方に小日向がどんな反応をするのかと内心ひやひやで彼女の様子を伺っていると、同じように過去の風景に思い当たったのか、小日向は小さく吹き出して、それからあの時と同じように嬉しそうに笑って、はい、と頷く。
おずおずと差し出された小さくて白い彼女の手を、これまた恐る恐る、まるで壊れ物を扱うかのように須永が握る。
相変わらず柔らかくてすべすべしてて、自分とは全然違う手触り。そんなふうに、触り慣れない女の子の手にまた感動して。
これじゃまるで思春期真っ只中のガキもいいとこだと、自己嫌悪に陥る須永だった。
媽祖廟の場所は知っていたが、須永が学生だった頃に中華街を訪れるのは食べ歩きが目的の第一であることが多かった。幾つか点在する廟がパワースポットになっていることは耳にしたことがあるが、わざわざ立ち寄るような場所ではなかったため、須永もここを訪れるのは初めてだった。
一歩中に入って須永は更に驚く。そこにいたのは八割が女性で、たまに見かける男性も全て彼女連れ……つまりカップルしかいない。その光景だけで、須永はここが何のための廟なのかを一瞬で理解した。
「……ねえ、小日向さん。ここに祀ってあるのって、もしかして恋愛かなんかの神様?」
声を潜めて尋ねると、あっさりと小日向が頷いた。
「そうですよ。この媽祖廟って、恋愛成就のパワースポットとして有名なんだそうです。前にニアが教えてくれました」
屈託なく笑う彼女に、「ふうん、そうなんだ」と何気なさを装いつつ相槌を打つ須永の脳内は、実は軽く混乱していた。
何故なら彼女の恋の相手は須永のはずで、それなら彼女の恋は既に叶っているはずだからだ。わざわざこんなところで恋愛成就を祈願する必要性がない。
(これって一体どういう状況なんだ? でも、実はもう俺に愛想尽かしてて、別の誰かに心変わりってことなら、俺と一緒に参拝するなんてことしないよな。いやでも、そもそもまだ俺が覚悟決めてないって彼女が思ってたら、俺との恋が成就するようにって祈ってくれてる可能性もあるし……)
こんな時、やはりあの日ちゃんとした言葉を告げていなかったことが悔やまれる。言葉にしなくてもヴィオラに込めた想いは届くなんて自惚れずに、少なくとも一言「好きだ」と告げておけばこんなにモヤモヤとした気持ちにはならずに済んだのに。
小倉が言うように漠然とした雰囲気だけで互いの想いを悟れるのは、恋愛経験上級者かせいぜい中級程度の人間だけだ。経験値皆無、正真正銘恋愛初心者の須永がその域に達するには、あまりにも経験値が少なすぎる。
須永の隣で廟に向かって手を合わせ、何事かを真摯に祈っている小日向には、浮付いた様子も切羽詰まった様子も感じない。穏やかな横顔はどことなく嬉しそうにも見えた。
外側は冷静さを保ちつつ、その内側は焦燥感に満ち溢れている須永も、彼女と同じように手を合わせ、切実な祈りを捧げる。
(せっかくだから、この機会にお互いの立ち位置がはっきり確認できますように)
たったそれだけのことを面と向かって口に出せず、つい神様に頼ってしまうのは、20代半ばのいい大人としては、いささか情けない姿だった。
お参りの後、小日向は御利益の種類が分かりやすいピンクの巾着型のお守りを購入し、須永も同じものを買うべきかと一瞬本気で悩んだが、そこはさすがに大人の男としてのプライドが邪魔をしたので、無難に交通安全のお守りを買っておく。廟を出て腕時計の文字盤を見ると、帰るには随分と早過ぎる時間帯だった。
「さて、小日向さん。これからどうしようか」
せっかく中華街まで来たのだからどこかで昼食でも取ろうと思いつつ須永が尋ねると、驚いたように小日向が須永を見上げた。
「え、まだ一緒にいていいんですか?」
「もちろん。だってお昼にもなってないのに、ここまで来て帰るのは勿体ないでしょ。ランチにはちょっと早いけど、中華でも食べてかない?」
満面の笑みで「ハイ!」と頷くので、やっぱり自分は慕われているのだと須永は実感する。
彼女が生徒だった頃は、この素直で可愛らしい反応にどう返してやると正解なのかが分からなくて、逆に怖かった。でも今は、その分かりやすい好意に、ただ安堵する。
そもそも、彼女がここに来たがった理由を、須永が深読みしすぎているだけなのかもしれない。女の子は占いの類が好きだと相場が決まっている。好奇心旺盛な彼女の事だから、恋愛のパワースポットだと知って「ちょっと行ってみたい」くらいの軽い気持ちで来た可能性の方が、よっぽど高い。
それなのにいちいち須永が不安になってしまうのは、おそらくは須永自身が今の自分たちの関係に納得をしていないからだ。眉唾物のヴァイオリン・ロマンスという伝説にあやかって、想いを込めた音色が相手に届いて……自分たちは恋人同士という新しい関係性に変わったはずだけれど、年齢を重ねて若い頃以上に臆病に、そして狡猾になった須永は、無意識に自分が傷付かないための逃げ道を用意するようになった。
想いをはっきりとは形にせず、互いの位置関係が曖昧なことに不安を覚える反面、それを改めて確認しようとしないのは、いつか彼女が須永から離れていく日が来たら、醜い感情をぶつけ合うんじゃなくて、自然に距離を置いて綺麗に終わらせたいと願うから。
そして、この恋が失われる時が来るのなら、手放すのは自分からではないことも、須永は分かっている。
本人が何処まで自覚しているのか分からないが、小日向かなでという女性は、普段はどちらかと言えば地味目で大人しく、存在感の薄い子なのに、一度ヴァイオリンを手にすれば、眩しくて目が離せなくて……男女問わず、その音色と存在とで周囲を魅了する。
そして、その為人は、可愛くて真っ直ぐで……こんなに魅力的な彼女が、自分の本性を知って尚、自分を好きでいてくれたことがいまだに不思議でならない。
更に彼女の周辺にいる異性は、とにかく目立つ人種が多い。
ちょうど自分が学生の頃、須永が到達できないと思っていた『向こう側』の一握りの存在と、同じ属性の人間たち。……そして何よりも、小日向自身が『向こう側』にいるべきはずの人間だ。
そんな輝かしい存在に囲まれながら、どうして小日向は『こちら側』にいる自分を選んだのか、その理由は分からないけれど。
須永と彼女の立ち位置の違いに気付いた時、彼女は本来自分が居るべき『向こう側』の存在に目を向けるのかもしれない。須永が過去に失った幾つかの恋と、同じように。
その時に、出来るだけ傷付かないで済む境界線を、この期に及んで須永は必死に守ろうとしている……。
「……須永先生?」
彼女の声に呼ばれ、ふと須永は我に返る。
テーブルを挟んだ向こう側、彼女のリクエストで、よくガイドブックに載っているという有名店のランチを食べることになった。最初のうちは会話も弾み、話題の尽きない彼女の言葉に笑顔で相槌を打っていたのに、マイナスに陥り出した思考の中に、いつの間にか深く沈んでいた須永だった。
「……ごめん、ちょっとぼうっとしてた」
苦笑しつつ詫びると、心配そうな表情で、小日向が須永を見つめる。食事をする手を止めて、そっと箸置きに持っていた長い箸を戻した。
「あの……私の我儘で、無理に付き合わせちゃってすみませんでした。先生普段から忙しいし、中間考査も終わったばかりだし……疲れてましたよね」
「ああ、いや。それは別に、全然。これくらいでヘタってたら、教師業なんて務まらないしね」
いざ教師になってみて分かったことは、教師業にはとにかく雑事が多いということだ。今になって、自分が学生の時に、「いちいち俺のとこに面倒事を持ち込んでくるな」とやる気ゼロだった白衣の音楽教師の気持ちが分かる気がする。
現在は小休止だが、今月のうちには学祭もあるし、それが終われば期末考査、学期末の成績表などの雑事、学期初めの準備など、やることが目白押しだ。むしろ今後の多忙を思えば、これまでの忙しさなどまだ楽だったとすら思える。
そう考えながら目の前の一品に箸を伸ばし、ふと須永は思い付く。この話の流れは『今日の目的』という須永の疑問を解消する絶好の機会ではないだろうか。
「……あのさ、小日向さん」
「はい?」
小日向と同じように、箸置きにそっと箸を戻し、姿勢を正して須永が名を呼ぶと、まだどこか気落ちした様子の小日向が、生真面目に返事をした。
「最初に言っておくけど、これは別に迷惑とか、疲れてるとか、そういうことじゃないから、そこは勘違いしないようにね。ただ、俺の都合で知りたいってだけだから。……何で今日、媽祖廟だったの?」
(これって、別に変な質問じゃないよな? 中華街の廟で有名なのは、むしろ関帝廟の方なんだし……)
発した言葉が普通に響いているのを確認しつつ、須永は自分の質問の内容を反芻する。すると、何故か一気に頬を桜色に染めた小日向が、あわあわと焦ったように視線を泳がせた。
「で、ですよね。中華街まで来て、食べ歩きとかが目的とかじゃなくて、真っ先に恋愛成就の廟に行くとか、変ですよね……」
「いや、別に変だとは思わないけど……。女の子はそういうの好きだって聞くし」
何を目的に中華街に来るかなんて、人それぞれだ。第一候補になることは少ないのかもしれないが、媽祖廟も充分に有名なパワースポットなのだから、別にそれが目的で中華街に来ても可笑しくはない。とは言えパワースポットだということは知っていても、恋愛に特化しているということは、須永も知らなかったが。
「単に何でかなって不思議に思っただけでさ。言いたくないなら、別に無理に聞き出したいわけじゃないし」
知りたいのは山々だが、小日向を困らせたいわけじゃない。理由が分からなければ、結局後で自分が無駄に思い悩むだけなのに、そこで押し切れないのが結局須永の駄目なところなのかもしれない。
「言いたくないってことはないんですけど……」
テーブルの上でぎゅうっと両手を握り締め、小日向は思い悩んでいる。思いつめたようなその様子に、「もういいから」と須永が言いかけたその時、思い切ったように小日向が顔を上げた。
「……須永先生、今日が何の日かご存知ですか?」
「――え?」
また随分と予想外のところに話が飛んだ。戸惑いながらも、須永は真面目に今日が何の日か思い出そうとする。11月5日、土曜日。日付にも曜日にも、特に引っかかることはない。だがそうして考えているうちに、須永はふと思い出す。
今日のために彼女が須永にメールをしてきた時、彼女は真っ先に日付を指定した。つまり、わざわざこの日を選んで彼女は須永を誘ったのだ。
「『縁結びの日』なんです。今日」
おそらく最初から答えが出て来ることは期待していなかったのだろう。須永が何かを言う前に、あっさりと小日向は答えを提示した。
「縁結び、の日?」
全く聞いたことのないその名称を、面食らったように須永が繰り返す。小日向が小さく頷いた。
「11月5日、『いいご縁の日』で、『縁結びの日』。媽祖廟のことを聞いた時に、この記念日のこともニアから聞いて……報道部でネタがない時、こういう話題は女子の反応がいいから、重宝してたんだそうです。他にもいろいろと、雑学に詳しいんですよ」
「ああ、なるほど……何か分かる気がするな」
須永たちが赴任した際、特集記事を組むために随分と細かいことまで根掘り葉掘り聞き出そうとしていた支倉仁亜のことを思い出し、須永は苦笑する。そう言えば、須永が在籍していた頃も、報道部は小さなものから大きなものまで、一度食いついたら離さないしつこい取材姿勢が売りだった。あの執念は報道部伝来のものなのかもしれない。
……そして、小日向が今日自分を誘ってきた理由は分かったが、何故今更「縁結び」なのか、結局その疑問がまだ解消されていない。
『縁結びの日』に恋愛成就の神様に一緒にお参りするなんて、良縁を願う相手とでしか考えられない。それは分かっているのに、もっとはっきりとした答えをいまだに欲しがっている自分に須永は気付く。
「小日向さん、この際だからついでに確認しておきたいんだけど――俺たちって、付き合ってるんだよね?」
努めて冷静さを装いつつ、震えそうな声を懸命に押さえて、須永は口を開く。勢いに乗って、何よりも一番聞きたかった、その核心を突いた。
小日向はこれまでの比じゃなく、大きく目を見開いた。その反応に自分が何かミスを犯したことは分かったものの、ここまでずっともやもやと胸の中を巣食っていた疑問を吐きだせたことに、須永はどこかすっきりとしていた。
「……わ、私は、ずっと、そのつもりでいて……須永先生もそう思ってくれてるって。でも、それが勘違いなら、私、恥ずかしい……」
「ちょっ……! 違う、誤解! そっち方向に行かないで小日向さん!」
見る見るうちに、その大きな目に涙が浮かぶ。慌ててテーブルから身を乗り出して、否定の意味で須永は何度も首を横に振った。
「じゃなくて! ほら、今日が『縁結びの日』だからって、君が今更『縁結び』祈願に来たなんて言うから!もしかして、俺がちゃんと言葉にして伝えてないから、俺たちが両想いだってことに君が気付いていないんじゃないかって思って……!」
慌ててジャケットのポケットを探り、差し出した須永のハンカチを、素直に小日向は受け取る。静かに浮かんだ涙をハンカチで拭いながら、ぐず、と小さく鼻を鳴らした。
「……あのヴィオラの音色を聴かせてもらって、それで先生の気持ちが分からないほど、鈍くないです」
優しくて暖かくて……ひたすらに甘い。不器用な愛情に満ちたあの時のヴィオラの音色。
今もなお、小日向の心を捕らえ続ける、愛おしい須永の音だ。
「だったら、どうして……」
「先生は、恋は叶ったらそこで終わりって思ってるんですか?」
涙が残る目で須永を見つめ「林檎は赤い」くらいの当たり前のことを言う口調で、小日向が尋ねる。……今度は須永が虚を突かれる番だった。
「ずっと、須永先生との縁が続けばいいなって。そう思ったんです」
ニアから教えてもらった『縁結びの日』。
単なる語呂合わせの記念日と分かっているし、本気で御利益を期待しているわけではないけれど、せっかくだから、どうせなら須永と一緒に神様にお願いしたかった。
自分たちの縁がずっとずっと続くこと。
そしてその縁が、いつか本当に『良縁』と呼べるものに育っていくこと。
「気が早いのは分かってます。だって私たち、付き合ってるって言っても、何回かデートして、手を繋いだことくらいしかないんだし」
「こ、小日向さん……」
「もしかしたら、先生には迷惑なのかもしれないけど、私、恋愛にゴールがあるとして、そこに向かうために、その途中で達成しなきゃいけない過程とかがあるなら、どれだけ時間をかけても、それは全部先生と一緒にクリアしていきたいんです!」
「ちょ、ちょっと。待って、小日向さん」
声量落として! と真っ赤になった須永が、口元に立てた人差し指を当て、ひそめた声で訴える。席は個室だったが、訴えに力が入る余りつい大声で熱弁を振るっていた小日向が、我に返って身を小さくした。
「ご、ごめんなさい。つい……」
「うん。いや……相変わらず男前だな、小日向さん」
つい、感嘆の言葉を須永は呟く。素直な気性ゆえか、昔から小日向は一旦こうだと決めてしまえば、全く迷わない女の子だった。
その真っ直ぐさは、須永に小日向の想いから逃げることも、自分の想いを誤魔化すことも許さなかった。そしてその結果、今こうして二人で一緒にいるのだ。
「……とりあえずさ、メシ、食べちゃわない? そろそろ人も増えて来るし、こういう話するのに、目の前に食べ物が残ったままじゃ、落ち着かないでしょ」
正午を過ぎて店内全体が賑わい始めている。苦し紛れの提案に、小日向もまた素直に頷き、その後は無言のまま、二人は目の前の料理を片付ける事に専念した。
食事を終えて店を後にし、二人はしばらく中華街の人込みの中を歩いていた。きちんと話をしないといけないことは分かっているが、あまりにも込み入った話なのでさすがに人目が気になる。食事を終えたばかりで次の店に入るのも躊躇われるし、かと言ってこのまま帰るわけにもいかない。どうしようかと思案する須永のジャケットの袖を、小日向がそっと引いた。
「須永先生、もしこの後どこに行くか決めてないなら港の見える丘公園まで歩きませんか? 今日は天気もいいし、今は薔薇が綺麗に咲いてる頃だと思うから」
「……ああ、なるほど。いいかも」
丘公園なら徒歩で充分行ける場所であるし、この時期は公園内のバラ園が見頃を迎える時期だ。何よりもあの場所でじっくり話すとなると、その図式はベンチに座って隣合せ、という形にしかならない。
さっきの今で小日向と対面で話すのは、須永の心臓に悪かった。
「じゃあ、行こうか」
さすがに落ち合った時のように、簡単には手を繋げない。歩調には気を付けつつ、須永がゆっくり歩き出すと、困惑する小日向が須永の背中を見つめている気配がする。
須永が振り返れずにいると、小日向が小走りに須永を追ってきて、数歩後ろを歩き出すのが分かった。
そうして何とも言えない沈黙の中、二人は急勾配の坂道を上って港の見える丘公園まで辿り着く。横浜のベイブリッジを一望できる展望台を通り過ぎ、薔薇の咲き誇るイングリッシュガーデンの出来るだけ目立たない場所に設置されたベンチに、並んで腰を下ろした。
静かに隣に座っている小日向は、電池が切れてしまったかのように大人しかった。付き合い始めてから8か月、彼女が何か不満を言うことはなかったけれど、彼女は彼女なりに須永と同じように互いの距離感にずっと悩んでいてくれたのかもしれない。
そして彼女は先程、その本心を曝け出してくれた。今度は須永の方が、彼女に本音を伝える番だ。
「小日向さん」
「……はい」
思い切って彼女を名を呼び、須永が沈黙を破ると、小日向が緊張した様子で返事をする。
先ほどの彼女自身の言動について後悔しているのだろう、その表情は暗いままだ。そんな顔をする必要はないのに、結局はまた須永が上手くないせいで彼女は傷付いていく。
唐突に聞こえるかもしれない。だけどせめて、いつも真っ直ぐに気持ちをぶつけてくれる彼女に、同じように須永の気持ちがちゃんと伝わるようにと、須永は思い切って口を開いた。
「……こんなこと言うのも今更なんだけどさ。俺ってホント、女の子と付き合った経験ないから。君が言ってたその……恋愛の途中にある、こなさなきゃならない過程っての? それをどのタイミングでどうこなせばいいのか、実は全然分かんないんだよね」
情けないけど、と、自嘲気味に須永が笑う。
小日向がどこか痛いような表情で、「そんなことは……」と否定の言葉を言いかける。須永はそんな彼女を片手で制した。
「だけど、これだけはちゃんと言えるよ。俺はこんなだから……君が望む時に、君が望むことを上手にしてあげられる自信が全くないんだけど……多分俺、君じゃなかったら、生徒と教師の境界線、越えてみようなんて勇気、持てなかったよ」
必要以上に須永が恋に臆病なのは、成就すると思い込んでいた恋があっさりと手の中からすり抜けてしまった、苦い経験があるからだ。
でも、だからと言って、淡い恋を奪い取ったはずの級友や、後輩を恨む気持ちは不思議となかった。
須永が何よりも怖くて悔しかったのは、ただ外見だけに価値を置いて、あっさりと鞍替えをするような……そんな女の子を好きだと思って、自惚れていた自分自身だ。
殊更に外見を飾り立て、女の子たちが好みそうな甘い言葉を振り撒く……自分を守る外側の面にそういう人物像を選んだのは、この外面に集まってくる女性たちには心を許してはいけないと、須永自身が判別するためだったのではないかと思う。
今度は絶対に、騙されたりしない。
変に期待を持って、舞い上がったりもしない。
そうして念には念を入れて自分を守っていた須永の内側にとても自然に入り込んできた異質な小日向を、須永は最初のうちは頑なに遠ざけようとしていた。
でも、須永の心の繊細な場所にそっと触れて、決してその情けない部分を軽蔑したりせずに、真摯に想ってくれる小日向を、これまで須永が好きだと思っていた女性たちと同じようには思えなかった。そして須永自身も、相手に掌を返されても、怒ることも詰ることも出来ず、あっさりと諦めることが出来たこれまでの恋と、小日向へ抱く想いがまるで違うことに気付いた。
例えば小日向が、須永のことを諦めて、別の誰かを好きになったとしたら。
そう考えると、堪えきれないほどに胸が痛かった。
これが本当に人を好きになることなんだと、初めて分かった気がした。
学生の頃、恋をしていたはずの自分は、本当はただ話しやすくて気の合う相手に親しみを覚えていただけで、初めから『恋』と呼べるほどの強い想いではなかったのかもしれない。だからこそ彼女たちのことを簡単に諦めることが出来たのだろう。
小日向は唇を引き結び、綺麗で大きな瞳で、真っ直ぐに須永のことを見つめている。
大きく息を吸って。吐いて。
それから、須永はゆっくりと唇を開く。
……この言葉を形にするのも、実は生まれて初めてだったということに、音になって空気を震わせた自分の声を耳にして、改めて気が付いた。
「小日向かなでさん。……俺は、君のことが好きだよ」
「……っ」
小日向が息を呑む気配がする。
……気配しか分からないのは、言い終えた後につい須永が視線を反らしてしまい、まともに彼女の顔を見ることが出来ていないからだ。
「い、今更だなーって分かってるんだけど、ちゃんと言ったことがなかったなって思って……って、ちょっとちょっと、小日向さん!?」
ちらりと横目で彼女の様子を伺い、そして慌てて須永は彼女の方へと向き直った。俯く彼女がはらはらと涙をこぼしているからだ。
「ご、ごめんなさい。……あの時のヴィオラで、ちゃんと分かってたつもりだったのに、言葉にしてもらえたら、何か……やっぱり嬉しいんだなって思って」
頬を流れる涙を指先で拭い、とても幸せそうに小日向が笑った。
「私も……私も、須永先生のことが大好きです」
その言葉に、須永も小日向の気持ちを理解する。
たとえ、それが分かり切った想いだったとしても。
知っていたことだったとしても、きちんと形にしてもらえれば、こんなにも嬉しいものなのだ。
「……ヤバい」
何故か頬を赤く染めた須永が、額を押さえつつ呟く。
驚いた小日向が、そうっと下からそんな須永の表情を覗き込んだ。
「先生? どうかしたんですか?」
「ちょ、だから小日向さん、そんなに無防備に近寄んないで!」
触りたくなってヤバい、と。
首まで赤くなる須永の本音が、ぽろりと零れ出た。
「……触っちゃっても、大丈夫だと思います、けど」
「だって天下の往来でしょ? 人目もあるしさ……」
「先生気付いてないみたいですけど、ここデートスポットですからね? ……周り、カップルだらけです」
声を潜めた小日向の言葉に周囲を見渡せば、確かに寄り添うカップルばかりの光景が目に入る。
「うわ、マジか! ……そういや昔、日暮れにこの辺り通りかかると、小倉がやたらと繁みの中覗きたがってたな……」
ふと何気なく思い出したことを呟き、それから須永ははっと我に返る。
小日向を見ると、先程の須永のように真っ赤に染まり、視線を落として揃えた自分の膝を見つめていた。
ああ、だから。その無防備に可愛くなる辺りが。
……触りたくなるからヤバいと言っているのに。
再度、須永は辺りに視線を巡らせる。ベンチに落ち着いているようなカップルはそもそもお互いしか見えていない世界にいて、それ以外の公園内を散策する人々は、敢えてその別世界は目に入れないように気を使ってくれている。
……自分たちだけが自重しても、特に周りに影響がないのであれば、我慢をする方が余程体に悪い。
そっと、小日向の細い肩に掌を乗せた。弾かれたように顔を上げた彼女の頬を、もう片方の手で撫でてみる。手を繋いだ時みたいに、その頬は滑らかで柔らかくて心地いい。そのまま唇を親指でなぞってみると、これまた柔らかくて、しっとりと潤っていた。リップかなんかでちゃんとケアしてるのかな、女の子だもんな。と関係のない感想が浮かんでくる。
息がかかるほど近い場所で小日向の顔を覗き込むが、彼女は目を見開いたままで、閉じる気配がない。その瞼が伏せられる前に、須永の唇が彼女の唇に触れてしまった。
そんなに強く口付けたわけでもないのに、唇が触れ合って生まれる音がやけに大きく響くような気がした。軽く触れてすぐに離れると、慌てたように時間差で小日向が目を閉じるので、もう一度須永は彼女にキスをする。ただ触れ合うだけの軽いキスなのに、これ以上になく幸せな、満ち足りた気持ちになり、何度も何度も、唇を重ね合った。
ああこんな時、本当に世界には自分たちしかいないような気持ちになるものなのだ。
これまで人目も憚らずイチャついてるカップル共を苦々しく思っていた須永だが、今なら彼らの気持ちが理解できる気がする……。
口付けたまま、須永はぎゅっと彼女の細い身体を抱き締めてみる。腕の力加減がよく分からず、抱擁すら初めてだったのだと改めて気が付いた。
「……あー駄目だ。ホントにどうしよ……」
唇を離して、照れくささを隠すように須永は彼女のふわりとした髪の中に顔を埋める。仄かに甘いシャンプーの香り。……余計に心臓に悪かった。
「どうかしたんですか?」
恐る恐る抱き返してくる、細い両腕。小日向は懸命に力を込めているのかもしれないが、それはやはり物足りないくらいにか弱くて。
そんな些細な事でも、互いの性別の違いを実感させられる。
「……あの、さ。小日向さん。こんなこと言うと、ドン引かれるかもしれないんだけど……」
告げるのには、勇気が要る。
それでも、告げるべき本心を告げられなくてわだかまりが燻ったままだった、この8か月の足踏み状態が須永の背中を押す。
――今日は君を、このまま帰したくないな。
「……なんて」
つい最後の最後で冗談に置き換えてしまうのが、須永の意気地のなさだった。
そして、腕の中でかすかに身体を強張らせた小日向の須永の背中に回された両手が、ほんの少しだけ、力を増す。
「……はい」
――私も、帰りたくないです。
消え入りそうな小さな声だったけれど、確かに小日向はそう答えたのだ。
「切り出した俺が言うのもなんなんだけど……何か一足飛び過ぎやしない? 本当に、いいの?」
まさかそんなにあっさり受け入れられるとは思ってもみなかった須永が、困ったように小日向の顔を覗き込む。恥ずかしそうに頬を染めたまま、小日向が小さく頷く。
「だって、さっき須永先生が言ってたじゃないですか」
恋愛に、乗り越えるべき過程が幾つかあるのだとして、それをクリアする正確なタイミングがいつかだなんて、はっきりとした瞬間は経験に乏しい自分たちには分からない。
「だったら、私たちは私たちのタイミングでそれを決めてもいいんじゃないかって思います」
8か月もの長い間、進展することなく停滞していたままのお互いの関係性。
それでもその想いは、決して成長していなかったわけではないのだから。
「本当に君って子は……」
須永よりも随分と度胸があり、変なところで男前。
そして何よりも、外側を取り繕うことに必死で、肝心なところで意気地のない、情けない須永のことを、真っ直ぐに想ってくれている。
そんな彼女のことを心から愛おしく想う。
距離が近づくことは、もっと奥にある須永すら知らない須永自身を彼女に曝け出すことで、それはやはり勇気がいることだ。
でもきっと、彼女なら受け入れてくれるのだと、今の須永なら信じられるから。
「ご利益なんて、別に信じてなかったんだけど……」
本当に縁結びの神様っているんですね、と感嘆して小日向が呟くので。
須永も、目に見えぬ神様ときっかけを与えてくれた記念日とに。
今日だけは素直に感謝することにした。
あとがきという名の言い訳
初書き須永センセなんですけど、初書きなのに急展開でごめんなさい(笑)
あくまで10周年記念の主旨に合わせたものなので、またどこかで違う形で須永センセを書きたいなと思ってます。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2016.11.05