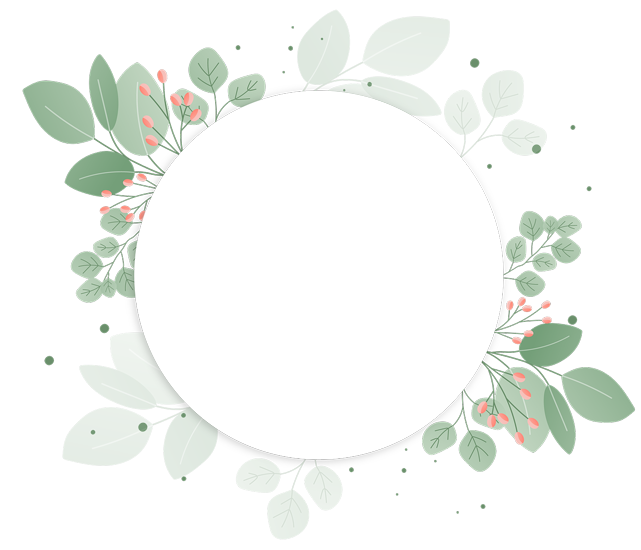神南高校管弦楽部室――前部長・副部長が引退がなかったことのように入り浸るその場所で、珍しく新部長の芹沢睦と副部長の小日向かなでの二人だけがそれぞれにノートパソコンの画面を熱心に眺めていた。
最高学年でありながら、全く受験生であることを感じさせない前任者2名は、今日はクリスマスに予定しているライブの会場視察に出かけている。残されている新任者にもきちんとやるべきことは残されていて、管弦楽部新体制初の大掛かりなイベント事を二人だけで企画するように前部長から命令されていた。
まずはその日程を決めるところから、二人は頭を悩ませていた。11月下旬の文化祭で新体制を初披露するのが順当であるのだが、お祭り好きな前任者たちから「お前らのオリジナリティを見せてみろよ。敷かれたレールを踏襲するだけじゃつまらねえだろ」と無茶振りをされている。余談だが、そういう前部長は3年生の引退時期に自分の誕生日があったため、『管弦楽部新部長生誕祭』などと銘打ってライブを開催したのだと、今年編入してきた小日向は、芹沢から重い溜息交じりに教えられた。相変わらず規格外のことを平気でやってのける前部長である。
「あ、でも芹沢くんの誕生日もいい時期じゃない? 同じように生誕祭とか……」
「やりません。……そもそもあの人と同じことをただ繰り返すだけなんて、絶対に納得してはくれないでしょう?」
即答する芹沢が、実は結構な負けず嫌いであることを小日向は知っている。不本意そうにしながらも、前部長を越える新体制披露イベントを開催しようと、必死で頑張っているのだ。
副部長としてせめてその手助けが出来ればと、何かきっかけがないか、小日向は情報をかき集めている最中だった。
そんな中、一つの項目が目に止まり、小日向は同じようにノートパソコンを眺めている芹沢の背中に声をかけた。振り返った芹沢が、小日向が指し示した画面に視線を向ける。
「ペアーズデー……ですか?」
どうせなら、珍しい記念日か何かに関連付けられないかと、準備期間を考慮し、11月から12月前半にかけての記念日を探していたところ、ふと目に止まった。
耳慣れない記念日だが『ペアの日』ということで、恋人同士なり友人同士なり、2名ずつで関連付けて何かできないかと思ったのだが、続く説明文を読む芹沢がふと困ったように笑った。
「残念ながら、小日向さん。『ペアーズデイ』とは言っても、割と一つのことに特化してしまった記念日のようですよ。これだと、やることが限定されてしまうので管弦楽部の企画としては難しいかと思います」
「え……」
指摘されて、慌てて芹沢が見ていた説明文を読んでみると、
ペアーズデー(靴下の日・恋人たちの日)
日本靴下協会が1993年に制定。靴下を2足並べた時の形が11・11に見えることに由来。
1年に1度同じ数字のペアが重なる日であることから、恋人同士(ペア)で靴下を贈り合おうと呼びかけている。
とある。
文字の並びから単純にペアで何かをする日だと思ったのだが、確かにこの内容では芹沢の言うとおり、音楽に関連する企画に結び付けるのには無理がある。
「むしろ、某お菓子の日の企画に絡めて考えた方がまだ応用が効くのかも。うーん、面白い記念日だって思ったんだけどなあ」
小日向が残念そうに溜息を付くと、芹沢が何気なく壁にかかっているカレンダーに目をやる。偶然にもその11月11日が休日であることに気が付いた。
「管弦楽部のイベントとは別にして、せっかく見つけたんですから、やってみてもいいんじゃないですか?」
「え?」
「要するに、恋人同士で靴下を贈り合うという記念日なんでしょう? 業界の戦略に乗せられている気もしますが、俺と貴方でお互いに靴下をプレゼントし合うというのはいかがですか? ……付き合い始めてから今まで、他にそれらしいイベントも出来ていませんし」
この夏、全国アンサンブルコンクールを共に闘う中で惹かれ合い、コンクール優勝後に付き合い始めた二人だが、その後は引継業務やら何やらで忙しく、常に一緒にはいるものの、恋人同士らしい時間は過ごせないままでいる。近々訪れる芹沢の誕生日にもライブの予定が入っており、先輩2名を交えたいつもの顔触れで祝うことになるのは、ほぼ確定事項だった。
仕方がないことだと納得してはいるものの、デートもままならない現状に、少し寂しく思っていた小日向にとっては、この芹沢の申し出は意外であり、そして何よりもとても嬉しいものだった。
「そうですね……ただプレゼントするだけでは面白くないので、どうせなら事前に渡しておいて、当日に披露し合うというのはどうですか? その日はちょうど何も予定が入っていない、珍しい休日ですしね」
学校は休みでも、ライブ活動の事務的な部分を請け負っている芹沢は、休日であっても忙しくしていることが多い。だが、10月終わりから12月の頭にかけては、諸悪の根源である先輩2名が受験準備の真っ最中でライブ活動を休止するため、空き時間が増えている頃だった。
「それは、確かに楽しそうだけど……芹沢くん、いいの?」
普段の成績からみても、先輩2名が推薦で早々に大学合格を決めるのは確実で、そうすれば12月からは以前の多忙な生活に戻ってしまう。11月はようやく芹沢が休息を取れる貴重な月であるはずなのに、自分に付き合わせていてはその貴重な時間を無駄に過ごさせてしまう気がした。
「いいも何も、あの方々が貴方にちょっかいを出してこない貴重な時期を逃す理由が、一体どこにあるんですか」
にっこりと完璧な笑顔で言い切る芹沢に、小日向は返す言葉がない。
芹沢に半ば押し切られるようにして、前日の10日の放課後に靴下を贈り合うこと。11日当日に、お互いが受け取った靴下を身に着けて、小日向が一人暮らしをしているマンションで逢うことを決め、そしてまた二人はお披露目会をどう開催するかについて頭を悩ませ始めた。
その後、芹沢が学校行事としては盲点となっていた、ハロウィンと関連付けた企画を立ち上げた。
自由参加型の仮装パーティを開催し、その中でハロウィンに関連付けた曲目で新生・神南高校管弦楽部の演奏を披露することにしたのだが、見た目に派手で更にハロウィンに関連付けることで音楽に興味がない生徒たちを取り込み、結果全校生徒を万遍なく巻き込むことに成功したこの企画は無事に前任者たちのお気に召したようで、二人からは「まあ、悪くはない。ギリギリ及第点ってとこか」と、幾分回りくどくはあったものの、無事に合格を告げられた。
こうして芹沢と小日向は、長く厳しい引継ぎ業務から、ようやく解放されたのだった。
その後、ひと月も経たないうちに文化祭での演奏を控える管弦楽部は、相変わらず多忙な毎日ではあったが、混ぜっ返す受験生たちが準備期間に入って部活に顔を出さなくなったため、恐ろしいくらいに順調に練習が進んでいた。
「順調なら順調で、今度は『インパクトがない』と難癖をつけられるんでしょうけどね……」
と、重く溜息を吐く芹沢の様子から、これまでの苦労が見て取れたが、何はともあれ平穏に日々は過ぎ、無事に約束の11月10日を迎えることが出来た。
放課後、一緒に帰宅した芹沢と小日向は、小日向のマンションの入り口の前で薄い箱にラッピングされたものをお互いに交換し合う。
「では小日向さん、明日の正午過ぎにお伺いします」
「うん、ランチ作って待ってるね。……それ、気に入ってもらえるといいんだけどな」
中身は靴下だと決まっているから、サプライズ感は薄い。だが選択肢が狭まる分、感性の見せどころではあるので、小日向はそれなりに気合を入れて選んだつもりだった。
「普段の貴方の選択眼を見る限りでは、特に不安はありませんが。……俺の方こそ、貴方のお気に召すかどうか心配ですね」
「それこそ、芹沢くんが選ぶものなら安心できると思う。私なんかより、全然センスがいいんだもの」
良くも悪くも、注文の多い先輩方に振り回されることで、とにかく芹沢の目は肥えている。そういう意味でも、芹沢が小日向に似合わないものを選ぶこと自体考えにくかった。
「……そこまで信用されると、若干胸が痛みますが」
「え?」
ぽつりと零れた芹沢の声を聞き逃し、小日向が小さく首を傾げる。「いいえ、何でもありません」と微笑んだ芹沢が首を横に振った。
帰途に付くその背中を、小日向は怪訝な表情のまま見送った。
部屋に戻り、冷蔵庫の中にランチ用の食材が揃っていることを確認した後、ベッドの上で小日向は芹沢からもらったプレゼントの封を開けてみることにする。
ちなみに、小日向が芹沢に贈った靴下は、見た目よりも履き心地にこだわった、綿100%の素材だ。普段着でも演奏時でも使えるようにと、黒地のシンプルなデザインで、ふくらはぎの半ばまで隠れる、長めのものを選んでいる。
華やかな先輩方2名とは異なり、芹沢は機能性を重視した方がいいと考えたのだが、果たして小日向の予想は的を射ているのだろうか。明日の芹沢の反応を思うと、期待半分不安半分の複雑な心情だった。
(さて、芹沢くんの方は……)
丁寧に包装紙をはがし、綺麗に折り畳まれた靴下を箱から取り出して広げてみる。色は偶然にも同じ黒。
左右平行にブランケットの上に並べてみて、小日向はその表情を輝かせた。
「か、可愛い……」
語尾にハートマークが付きそうな感嘆の声が思わず零れてしまう。
並べた靴下の長さは、想像以上に長いニーハイソックスで、おそらく小日向が履くと太腿の真ん中くらいまでの高さになる。
そしてそのニーハイソックスは、上の部分が可愛らしい猫の顔の形になっていたのだ。
何となく芹沢はレース地等の上品なデザインの靴下を選ぶような気がしていたので、こんな可愛い系のものを選んできたことに意表を突かれてしまう。
きょとんとした丸い目でじっとこちらを見つめてくる猫の顔に、小日向はほっこりとしながら、飽きることなくそのニーハイソックスを眺める。
……そして、ふと思い至る。
このニーハイの魅力を損なうことなく身に着けるためには、選ぶ洋服が限られてしまうということに。
「えっと……これってもしかして、ミニのスカートかショートパンツじゃないと、猫ちゃんの部分が見えないってこと……?」
しかも猫の顔がある辺りは、小日向の太腿の半ばくらいだ。相当丈が短くないと、肝心な顔の部分が隠れてしまうことになる。
……背中を、冷たいものがすうっと流れていくような気配がした。
翌日約束通り、正午丁度に芹沢は小日向の部屋を訪れた。
芹沢は白のシャツに薄地の黒のジャケットを羽織り、青灰色のパンツを合わせたラフなスタイルで、その足元にはきちんと、昨日小日向が送った黒の靴下を履いてくれている。
ドアを開けて芹沢の私服姿を目にした時、小日向は何故か違和感を拭えなかった。別に似合っていないわけではなく、むしろかなり格好良いと思うのにどうしてだろうとひとしきり悩んで、そもそも彼の私服姿を見ることが初めてなのだと気が付いた。
休日に二人で会う時もライブの事務作業が理由であることが多いため、芹沢も小日向もいつも制服姿だったのだ。
「お邪魔します、小日向さん。……こちらは、よかったらお茶の時間にでも一緒に食べましょう」
そう言って芹沢が差し出したのは、名の知れた洋菓子店の紙箱だった。喜んで受け取り、テーブルの上に置いて覗いてみると、美味しそうなショートケーキが二つ入っている。
「こちらに合いそうな茶葉もお持ちしましたので、後でキッチンを使わせてください。差支えなければ、お茶をお入れします」
「うん、是非! 芹沢くんの入れてくれる紅茶、美味しいから楽しみだよ」
そう言う小日向は二人の昼食用に、芹沢が好きなシーフードグラタンとサラダ、コンソメスープを作っていた。芹沢が時間に正確なことは分かっていたので、熱々の状態でテーブルの上に準備してある。
「早速だけど、冷めないうちに食べちゃおっか。あ、飲み物はレモン水と烏龍茶があるんだけど、どっちがいい?」
テーブルに促しながら尋ねると、芹沢からは「では烏龍茶で」と返答があった。
芹沢が椅子を引いて座る気配を背後に感じながら、小日向は冷蔵庫からウォーターボトルを取り出し、作り置きの烏龍茶とグラスとを準備する。それらを両手に持ち振り返ると、芹沢がじっとこっちを見ていることに気が付いた。
……正確には、小日向の膝上にある、猫の顔辺りを。
「え……っと、何か、変、かな?」
恐る恐る小日向が尋ねる。
実際、今日の自分の格好にはかなり不安があった。昨夜散々悩んだ末に、見せる相手は芹沢なのだからと思い切り、小日向はきちんとニーハイソックスの猫の顔が見える長さのミニスカートを履いている。鮮やかな赤色を気に入って購入したプリーツスカートだったが、小日向が持っているものの中で一番丈が短く、なかなか履く勇気が持てずにタンスの中に仕舞いっ放しにしていたものだ。
「……いえ」
首を横に振り、芹沢が穏やかな口調で言った。
「とても良く似合ってますね。華やかなものよりは、可愛らしいデザインの方が貴方には合うと思っていましたが、俺の思い込みではなくてよかった」
何よりも反応を見るのが怖かった芹沢に褒められ、小日向は一気に気持ちが軽くなる。ぱあっと表情を輝かせ、自分の膝上の猫の顔を指先で撫でた。
「芹沢くんがこういうの選ぶなんて、私も思わなかった。すっごく可愛くて、びっくりしちゃったよ」
「気に入っていただけましたか?」
「うん!」
即答して大きく頷くと、芹沢も嬉しそうに微笑む。
「それなら尚更よかった。……俺の方も、貴方にいただいたものが履き心地がとても良くて気に入りました。普段使いでもいいですし、ステージに上がる時にも履けそうですね」
「あ、うん。実際そういうところも意識して選んだんだよ。靴下って、見てると色々種類もあって面白いけど、いざプレゼントとして買おうと思うと、選ぶの難しいよね……」
烏龍茶を注いだグラスを二人分置き、食事を始めながら、二人はそれぞれに靴下を選んで購入した時の苦労話を聞かせ合う。
やがて、会話は様々な方角へ行き交い、巡り巡って最後には、やはり次の管弦学部の演奏会をどのように行うかという、いつもどおりの内容に落ち着いてしまうのだった。
会話をしながらじっくりと時間をかけて昼食を終えると、思った以上に時間が経過していた。「美味しいランチを頂いたので、後片付けは俺がやりますよ」と芹沢が申し出てくれたので、その言葉に甘えて小日向は洗い物を芹沢に頼むことにする。それでも全てを彼に任せるのは申し訳なく、またどうせなら近くで話していたいという思いから、芹沢の隣で彼が洗ってくれた食器を布巾で拭き上げて、食器棚に片付けていくことにした。
「……そういえば貴方の私服姿を見るのは、今日が初めてですね」
芹沢が手際良く洗い終わった食器の水気を切り、小日向の方に差し出す。それを受け取りながら、彼がこの部屋を訪れた時に自分も同じように考えたことを思い出し、小日向は笑って頷いた。
「私たちが会う時の格好って、考えてみればいつも制服かステージに上がる時の衣装なんだもんね。私も芹沢くんの私服姿、新鮮だなあって思っちゃったよ」
「そうですね。休日に貴方にお会いする時でも、ほとんどライブかその打合せか、ということが多かったですからね。……いつもそういう雰囲気の格好をされているんですか?」
「えっ!?」
何気なく尋ねてきた芹沢に、あまりに服が浮き過ぎていて、せっかく芹沢が選んでくれたニーハイソックスを着こなすため、目一杯無理をして背伸びをしているのが彼に見透かされているのではないかと、小日向は一気に不安になった。
……だが、その問いかけで芹沢がほんのわずか声のトーンを落としたことには、小日向は気付かない。
「そ、そうだね。あんまり大人っぽいのとか、フリル系とかは似合わないから、やっぱりこんなふうに動きやすい感じが多いかな?」
いわゆる『女の子らしい』格好をすることはほとんどないので、この言葉は嘘ではない。……ただし、ショートパンツは何とか試せても、こんなに丈の短いミニスカートを履くことはほとんどないのだけれど。
「……そうですか」
溜息交じりに静かに呟いた芹沢の声は、今度こそ小日向が分かるほどに、はっきりと低かった。
「芹沢くん……?」
その芹沢の声音には覚えがある。基本的に誰に対しても冷静で、常に変わらない丁寧な対応をする芹沢なのだが、ごく偶に小日向だけに聞かせる声がある。
――それは、小日向を叱る時の声だ。
「な、何か、怒ってるの?」
確かに自覚はないが、自分は普段からどこか抜けているらしく、芹沢に心配をかけ、いろいろと苦言を呈される。だが今日は、芹沢が小日向の部屋を訪れてから今まで、特に目についた失敗はしていないはずだ。急に怒り出す理由が分からない。
「怒ってはいません……ただ、貴方のことがつくづく心配になるというだけです」
洗い終えた最後の食器を、芹沢が小日向に差し出す。分からないままにそれを受け取り、拭き終えて、棚に戻す。その小日向の一連の動作が終わるのを見計らい、芹沢がぽつりと呟いた。
「……貴方の、その警戒心のなさが」
食器棚の扉を閉めた時に、芹沢のその呟きがふと小日向の耳に届く。意味を捉え損ね、ぱちりと一つ大きな瞬きをした小日向が、芹沢の方に目を向ける。
……芹沢の位置が、体温が伝わりそうなほど、近い。
「芹沢くん……?」
「そもそも、俺の申し出をあっさり貴方が受け入れた時からどうかとは思っていたんです。いくら恋人同士だからって、そんなに簡単に一人暮らしの貴方の部屋へ、俺を入れてしまっていいんですか?」
「で、でも」
11月11日、恋人同士で靴下を贈り合う記念日。
でも、ただ贈って終わるのでは面白くないから、どうせならちゃんとお互いに貰ったものを身に着けた姿を見せ合おうと決めて。
外で待ち合わせたなら、贈り合った靴下のことなど二の次になってしまうから、室内でゆっくりできた方がいいですねと言ったのは芹沢。
それならランチを作るから私の部屋で一緒に食べようかと提案したのが小日向。
自分たちの周りは、賑やかな第三者たちのおかげでいつだって騒がしい。だからせっかくの記念日は、二人だけで、何にも邪魔されずに静かにゆっくりと過ごしたい。
小日向が頭に浮かべたその条件を満たす選択肢の中では、自分の部屋が最適だったというだけだ。
「……そんなに俺を信じ切ってる貴方だから。俺が『これ』を選んだ理由も、あまり深く考えたりなんてしないんでしょうね」
身を屈めた芹沢の長い指先が、ふと小日向の脚にある、あどけない猫の顔に触れる。
――ただ、触れただけ。
それなのに、自分以外の人間が滅多に触れることのない場所を、芹沢に触れられただけで、背筋にぞくりとした感覚が走る。
「……もちろん、可愛らしいものの方が貴方に似合うだろうと思ったのは本当です。でも、ただ可愛いからという理由では、男はこんなものは選ばないんですよ」
華やかな先輩2名に群がる数多くの蝶たちを観察していれば、彼女たちがどんな手を使って彼らの視線を自分たちの方に向けようとしているのか、その方法は見て取れる。
そして小日向なら、男の目を引こうという気持ちすら、持たないであろうことも分かっていた。
普段から母親の買い物に付き合わされることが多いため、婦人服のフロアに長居することはそこまで抵抗がなかった。そうしてじっくりと吟味して選んだものは、小日向に似合いそうだと思ったが、反面、彼女はあまり身に付けそうにないものだとも思えた。
だからこそ、逆にこれを贈った時に、彼女がどうするのかを見てみたいという好奇心に駆られたのだ。
ニーハイソックスを履きこなすには服を選ぶ。その魅力を最大限に引き出すか、それとも羞恥心が勝って、せっかくのニーハイを、無難なありきたりなものにしてしまうのか。
……どうせ贈るなら、芹沢の期待するように彼女が可愛らしく、上手に着こなしてくれればとは思っていた。だが実際彼女が狙い通りに、難なく贈ったものを身に着けているのを見ると、それはそれで複雑な気分だった。
……それが普段通りの格好だと言われれば、尚更。
一般男性の目から見れば賛否両論だと聞くが、小柄な彼女が長めのニーハイソックスと赤いミニスカートを合わせた姿はよく似合っているし、惚れた欲目は抜きにしても、充分に可愛らしいと思える。
だが彼女はきっと、こんな可愛らしい姿を、自分以外の男の目にも簡単に曝け出せるのだ。彼女の美徳でもある、その素直さゆえに。
周囲の男が、……一番傍にいる芹沢という存在が、どんな想いを抱えて彼女という眩しい存在を見ているのか、考えもしない。
だからこそ、男心を煽る格好を無邪気にしていられるし、自分の部屋に男を招き入れても、警戒すらしないのだ。……そのことが、芹沢には苛立たしい。
「ちょ、ちょっと待って! 芹沢くん」
あの、色々と、誤解です……と真っ赤になって片手を挙げ、小日向が自己申告をする。誤解、とは?と芹沢が怪訝な顔で眉根を寄せた。
「あの、つい見栄を張っちゃったせいで、芹沢くんにいろいろ勘違いされちゃってる気がするから、とにかく、全部言うね」
まずは、と小日向は俯き加減で指先で短いプリーツスカートの裾を摘まみ、ぽつりと呟く。
「……こんなに短いスカート、普段は絶対履かないし」
「……は?」
「オンナノコっぽい格好しないってのは本当だけど、ミニスカートって言えるのはこれくらいしか持ってないし。そもそもこれ、色味とデザインが気に入っちゃって衝動買いしたけど、短すぎて履けなくて、ずーっとタンスの肥やしにしてたんだから」
何故かやけくそ気味に申告する小日向に、芹沢は呆気にとられたまま「……はあ」としか答えようがない。一つ言ったことで弾みがついたのか、がばっと顔を上げた小日向が、芹沢を睨むように見据える。
「それにね! 警戒心ないって芹沢くん怒ったけど!私、誰も彼も抵抗なく部屋の中に入れてるわけじゃないんだから! 何人かで遊びに来てくれたクラスの子とか、管弦学部の子とかは入ってもらったことあるけど、ここで二人っきりになったのは芹沢くんだけ!」
「……」
「それは、芹沢くんを警戒してないとか、そういうことでもないの! 例えば……例えば、ここで二人きりで、何か芹沢くんが心配してくれてるみたいな状況になったとしたって、私は、それが芹沢くんなら別にいいって思ってるからだよ! 何も考えてないって……そういうふうに思われるのは……っ」
あ、駄目だ。泣く。
泣くつもりなんてなかったのに、自分で言った言葉で自分の脳内が整頓されて、考えていることが明確になっていく。
……確かに小日向は、芹沢を怖い存在だとは意識していなかった。二人きりになることを特に警戒してはいなかったし、そういう意味では芹沢の言う通り、小日向の女の子としての考えが到らない部分だったのかもしれない。
だが小日向は、決して芹沢のことを男性として意識していないわけではないのだ。
芹沢が小日向の意志を無視して行動を起こすような人ではないと信じている。その点では確かに小日向は芹沢のことを無条件に受け入れ過ぎていると言える。だがもし、彼が小日向の想いを汲みながらも、それでも尚、こんな自分を求めてくれると言うのなら、小日向は初めから彼を受け入れる覚悟があったのだ。
その覚悟を、何も考えてないと非難されることは辛い。つい声が震えてしまう。
「……だって、それが今日でも今日じゃなくても。そういうことする相手として考えるのって、私には芹沢くん以外にいないもん……」
勢いに任せて、随分と恥ずかしいことを言っている自覚はあった。芹沢が聞きたいのはこういうことじゃないのかもしれないけれど、それでも自分が彼に言っておきたい気持ちだったのだと分かる。
いつの間にか、真っ直ぐに芹沢を見つめていた視線が、下へ落ちていた。膝上の黒い猫と目が合って、何とも居た堪れない気分でいると、ふと辺りが暗くなり、優しい温もりに包まれた。
芹沢に抱きしめられたのだと分かったのは、慣れた彼の爽やかな香りを思い切り吸い込んだからだ。
「……すみません」
それは普段とも、叱る時とも違う。
低く、そして優しく深い、労わるような声だった。
「正直、貴方がそこまで考えてくれているとは思っていませんでした。……良くも悪くも、普段から貴方があまり物事を深く考えているようには、俺には見えていなかったもので」
真っ直ぐで、無鉄砲。限度というものをまるで知らなくて、物事を深読みすることが苦手。そして、意外に負けず嫌い。その負けん気の強さが、彼女の無茶に拍車をかける。だからこそ、より一層目が離せない。
それが芹沢が知る、誰よりも、何よりも愛おしく想う、小日向の姿だ。
「確かに、あんまり深くは考えてないけど……それは、そうなんだけど……」
いつも芹沢に叱られている自分を省みると、真っ向から反論することが難しい。だからって、ここで落とさなくてもと、もごもごと口の中で異論を唱えていると、小日向の頬にふと芹沢の長い指先が触れる。
正確で賢くて、ほんのちょっと意地悪な。
大好きな芹沢そのままの音を弾くピアニストの指。
触れて伝わる体温が、意外に熱いと思っていると、その指が少し強引に小日向の顔を上向かせた。
何かを言いかけて、開きかけた小日向の唇に、指以上に熱い芹沢の唇が重ねられる。
……何度か。
誰もいない部室で。ライブ会場の控室で。
いつもそこにある二人分の監視の目がない隙を突くようにして、触れるだけのキスを交わしたことはある。
その時は、嬉しくて、幸せで。
心の中がぽかぽかと暖まるような、少しこそばゆいような穏やかな幸福感の中にいて。
いつかこの幸せな気持ちがゆっくりと育っていって、世間一般の恋人同士たちが経験することを、芹沢と一緒に知っていくんだと、漠然と思っていた。
だから、さっき彼に告げた言葉は決して嘘じゃなかった。いつか小日向が『それ』を知る日が来るのなら、その相手は芹沢以外に考えられない。
……ただ、その瞬間にはこんなふうに胸が痛んで。
何とも言えないような切ない気持ちになるのだということも、知らなかったというだけで。
「……貴方が一度言ってしまった以上、今更取り消しは効きませんよ。俺はそこまで聞き分けのいい男でもありませんから」
「それは、知ってる、けど」
唇を離し、息がかかる至近距離で、何故かひどく嬉しそうに笑った芹沢が言う。
知らず潤んでしまった目を見られたくなくて、小日向は俯いて、悔しげに小さく呟いた。
「……俺のため、ですか?」
ぽつりと芹沢が落とした言葉の意味が分からず、小日向は恐る恐る、上目遣いに彼の表情を伺う。
切なげに目を細めた芹沢の手が、ゆっくりと小日向の脚に張り付いた猫の顔を撫で上げた。
問いかけの意図に気が付いて、小日向は小さく頷く。
「……芹沢くんのため、です」
誰にも見せないミニスカートを履くことも。
無防備に、その存在を自分の内側に入れることも。
身を起こし、小日向から離れた芹沢が、満足げに頷いた。
「それが、俺だけであるならば結構です。……特に、あの方々にサービスするのは止めておいてくださいね。俺の心臓が幾つあっても持ちませんから」
そもそもミニスカートでも履いているのはニーハイソックスなので、決して露出度が高いというわけではないのだが、自分がそうであるように、今日の小日向の姿は男心を刺激するには充分だ。そんな小日向を見て、彼女を猫っ可愛がりにしている彼らが、良くも悪くも大喜びするのは目に見えている。
深い溜息交じりに、あの二人を名指して指定してくる辺りに芹沢の普段の気苦労が垣間見えて、小日向は思わず笑い出した。
「……さて、と。じゃあ、せっかくだから、芹沢くんが持ってきてくれたケーキ、食べちゃう?」
いろいろと一段落したところで、小日向はふと冷蔵庫に入れておいた芹沢の手土産のことを思い出す。後片付けは終わったばかりだが、食後のデザートとして丁度いいのかもと思い尋ねてみると、何故か芹沢は心底意外そうな顔をした。
「ケーキですか? ……小日向さん、もうお腹がすいてらっしゃるんですか?」
「ううん、そういうわけじゃないけど」
空腹というわけではないが、甘いものは別腹というし、何よりも芹沢が入れてくれる紅茶の方が気になっていたのだが。
だったら、と芹沢が微笑む。
「……先程の続きをしてからにしませんか。少し時間をおいてからの方が、より美味しく食べられると思いますが」
「うん、それもそうだね……」
答えかけて、はた、と小日向は動きを止める。
先程の続き。
……って、いったいどの続きのことですか?
考えかけた小日向の身体が、突然宙に浮いた。視線は否応なく天井を向き、爪先がふわふわと覚束ない。細身の芹沢からは想像がつかない力強さで、足元から掬い上げられた。所謂、お姫様抱っこというあれだ。
「ちょっ……芹沢くん!?」
「言ったでしょう? 今更取り消しは効きません、と。『据え膳食わぬは』なんとやらという諺もありますし、貴方がそこまでの覚悟を持ってくれているということも分かりましたので、俺もこれ以上の遠慮をするつもりはありません」
難なく小日向を彼女のシングルベッドまで運び、芹沢はそっとその端に小日向を下ろして座らせてくれる。そういえば芹沢は柔道も強かったのだと、滅多に考えることのない彼の特技を思い出した。
小日向が力なく座り込むその傍らに、芹沢がそっと膝を付く。伺うように小日向の顔を見上げ、切なげに微笑んだ。
「……それでも、貴方が信じてくれたように、貴方が嫌がることを無理強いしようとは思っていません。まだ間に合いますから、どうしても嫌ならば、ちゃんとそう言ってください」
そのどこか苦しげな表情が。
そして、最後の最後で小日向を気遣うその言葉が。
何よりも一番卑怯だと、小日向は思う。
……芹沢を誰よりも好きだと想っている自分が、そんな彼を抗えるわけがない。
「い……いや、じゃ、ない。……です」
消え入りそうな小さな声で、真っ赤になった小日向が呟く。
一瞬、驚いたように目を丸くした芹沢が、ふとその目を嬉しそうに細めた。
「……ありがとうございます。小日向さん」
告げて、芹沢は小日向の片足を手に取り、黒のニーハイソックスの上からその甲に口付ける。
軽い口付けは足の甲から、膝へ、そしてあどけない猫の顔に、ゆっくりと降りた。
「……正直、単なる企業戦略がちょっとしたきっかけにでもなればという、軽い気持ちでしかありませんでしたが」
くつしたの日も捨てたものではありませんでしたねと、しみじみと芹沢が呟いたので、小日向も素直に頷く。
……それが、今日になるとは思っていなかった。
それでもいつかこの日が来ることを、ずっと待ち焦がれていた。
その想いはきっと、芹沢も小日向も同じなのだ。
ゆるゆると上ってくるキスが、やがて唇までたどり着いて。
更に上の耳元で、低く艶のある声で芹沢が「……好きや」と、あまり耳慣れない方言で告げる。
狭い小日向のシングルベッドが、そのまま倒れ込んだ二人分の重量を受けて、ぎしりと鈍く軋んだ。
ペアーズデイという記念日を知るまでは、ただの同じ数字が4つ並ぶだけの日でしかなかった。
そんな11月11日が、来年からは二人の間でだけ、その意味合いを変える。
もちろん、靴下協会の企業戦略の一環などではなく。
ただ、純粋に。
二人の恋の軌跡の一つとして。
あとがきという名の言い訳
とりあえず、どこで芹沢をなまらせるかが個人的な課題でした。あと、ちょっと心狭い感じね!(笑)
途中でいろいろ出て来るエピソードの中に、そのうち普通に創作で書こうと思ってたものがあるので、今後出てきたら「ああこれか」と見守ってやってください。
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2016.11.07