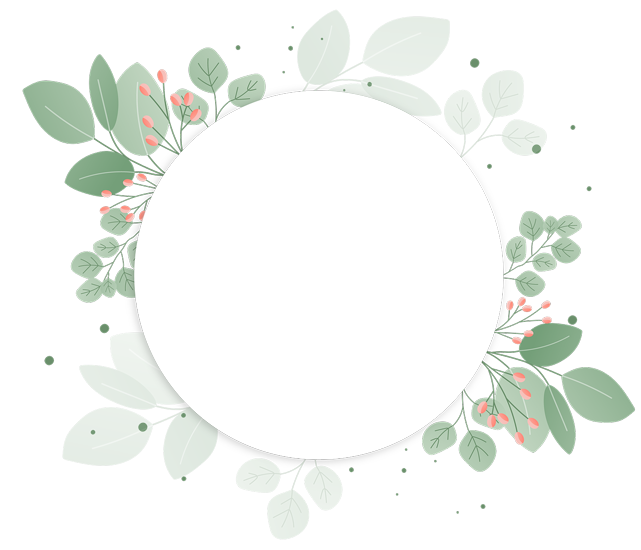だが、幸か不幸か小日向かなでの彼氏である氷渡貴史は、二人が所属する横浜天音学園高等学校室内楽部の前部長・冥加玲士に、かなで以上に心酔しているため、冥加が決めた12月24日から25日にかけて2日間に渡って行われる、天音学園主催のコンサートイベントを蹴ってまで自分たちの幸せを満喫しようという選択肢は、欠片ほども頭に浮かばないようだった。
「冥加部長のご指示だ。当然、参加するに決まってるだろ」
今、室内楽部の部長は氷渡くんじゃなかったっけ?と内心かなでは苦笑する。
初めはかなでにと打診されていた部長職に氷渡を推したのは、かなでの判断だった。
確かにプライドが高く、物言いには色々と難ありの氷渡だが、のんびりでマイペースなかなでより周囲の隅々に目が行き届く人物であるのには間違いない。指示も的確で分かりやすく、冥加のように演奏の中心になって全体を引き上げるような影響力には乏しいが、それでも彼の持つ特性は、新しい室内楽部を率いるのに向いているだろうとかなでは思っていた。
初めは難色を示していた冥加も、かなでと後輩の七海の二人がかりで滾々と説得され、最終的には「天音学園の実績を目減りさせるようなことがあれば、ただでは済まんぞ」という捨て台詞と共に、氷渡を次期部長に据えることを承諾した。かなでと七海から散々おだてられその気になっていた氷渡も、さすがにその時ばかりは戦々恐々としていたが、怖々ながらも走り出した新生天音学園・室内楽部は、現在のところはかなでの目論見通り、順調に機能している。勿論、部長職を離れても天音学園理事としての立場で室内楽部を監視している冥加の影響力はいまだ甚大ではあるが。
そんな中、冥加から室内楽部にクリスマスのコンサートイベントでのアンサンブル演奏の依頼が舞い込んだ。依頼というより、むしろ命令に近いものであったことは余談だが。
天音学園主催と銘打ってはあるものの、実際のところは天音学園の理事職連中の様々な思惑が入り混じったイベント事で、都内の高級ホテルを借り切ってのパーティでの演奏ということになるらしい。かなでにはその辺りの機微はよく分からない。分かったところで何か特別なことがかなでに出来るわけではないのだし、冥加も演奏以外の何かをかなで達に望んでいるわけではない。ただ、自分はその二日間のパーティで、指定された時間、冥加の要求するレベルに足り得る演奏を提供できればそれでいい。そういう単純な図式である方が、かなでにとってもやりやすい。
それはともかく、クリスマスだ。当日に二人きりで過ごすのは無理だとしても、せっかくの初クリスマスをちゃんと恋人同士として過ごしたいと思うのはかなでだけではなく氷渡も同じだと思う。そこで、かなでは放課後に氷渡と二人で立ち寄ったカフェの奥の席で、向かい合う彼に提案してみることにした。
「ねえ、氷渡くん。クリスマスの事なんだけど……」
「ああ、パーティでの演奏の事か。どこかでアンサンブルでの練習時間を取らなきゃなんねえな。お前と七海はともかく、冥加部長や天宮さんは、それぞれに個人で依頼される演奏も多くて、なかなか時間が取れないからな……」
夏のコンクール以後「我儘は充分叶えてもらった」と、氷渡は冥加のアンサンブルの正チェリストの座を七海に譲り、冥加のマネジメントをしている御影の補佐として、天音のアンサンブルの活動を支えている。冥加から声がかかれば、身一つで指示通りにコンクールや演奏会に参加すればいいかなで達とは違い、既にプロのヴァイオリニストとして活動している冥加と、セミプロのピアニストとして仕事を受けている天宮では、そのスケジュールの濃密さは比べようがない。コンクールの実績などからも彼らや彼らが率いるアンサンブルに舞い込む演奏依頼は多く、スケジュールの調整に何より一番頭を悩まされるという氷渡の愚痴を、かなでは何度も聞かされていた。
「それも大変なんだけど、そうじゃなくって……あの、せっかく付き合って初めてのクリスマスなのに、このままじゃ二日ともそのパーティで、二人きりでは過ごせないでしょう。だから、よければ別の日に二人でクリスマスやらないかなって思ったんだけど……氷渡くんにとってはあんまり重要な事じゃないのかな」
クリスマスと言えば途端にパーティでの演奏に直結する氷渡のマネージャー思考に、かなではついつい拗ねた口調になる。
(分かってる!いろいろ難ありのパーティみたいだから、冥加部長のお仕事がやりやすくなるようにするためにもちゃんと演奏を成功させなきゃいけないって分かってるの!でも!)
意味なく手元のティーカップになみなみと注がれた琥珀色の紅茶をスプーンでかき混ぜる。初めての彼氏と過ごすクリスマスを楽しみにしていたのは自分だけなのかと、若干気落ちして紅茶の表面を見つめていると、テーブルの向こうで氷渡がぴたりと動きを止めた気配がした。
「………………い、いいのか?」
長い長い沈黙の後、氷渡がぽつりとそれだけを呟いた。かなでは視線だけを上げてそんな氷渡を上目遣いに見つめる。
「いいのかって?」
若干落ちたままの気持ちで、かなでが小さな声で尋ねると、目尻をほんのり赤く染めた氷渡がそんなかなでから視線を反らす。
「だから……お前はパーティのためのヴァイオリンの練習があるだろうが。クリスマスとか、やりてえのは山々だけど、俺がお前の練習邪魔する訳にはいかねえし……。もう初クリスマスは来年へ持越しくらいの覚悟でいたんだけどよ……」
その一言で不機嫌な気持ちはどこかへ吹っ飛んでしまったので、かなでも大概現金だ。
もちろん、氷渡がクリスマスをちゃんと一緒に過ごしたいと思ってくれていたこともそうだが、何よりも来年まで二人の初クリスマスを持ち越そうなどと考えてくれていたことが、かなでには嬉しい。
少なくとも、来年のクリスマスまでは氷渡はかなでの彼氏でいてくれるつもりなのだから。
「じゃあ、前倒しでクリスマスしようよ! 氷渡くんも、それでいい?」
かなでが念押しすると、氷渡は視線を反らしたままで「お前がそれでいいなら、俺は別に……」とやはり歯切れは悪かった。それでも染まったままの目尻が、そのそっけなさが照れ隠しだと伝えてくれるので、かなではただにこにこと満面の笑みで氷渡を見つめていた。
「そ、それより、前倒しでってことは、想定してる日付があるのかよ? アンサンブルでの練習も組み込まなきゃなんねえから、どの日でもいいってことじゃねえぞ」
「んーとね。12月12日って、氷渡くんの都合どう?」
躊躇いなく間髪入れずに希望を告げたかなでに、それまでの照れはどこへやら、氷渡が目を見張ってかなでの顔を見た。
「……えらくあっさり希望日言いやがったな。その日、何かあんのか?」
「えっ!」
ひどく分かりやすく、かなでが反応する。探るような氷渡の目から逃れ、かなでは視線を不自然に空に泳がせた。
「別に何もないけど……ほ、ほら、クリスマスの直前の週末だと、氷渡くんの言うとおり、やっぱり練習が追い込みかなって思うから、それ辺りがちょうどいいんじゃないかって。勿論、氷渡くんの都合が悪いなら、他の日でもいいよ」
「……まあ、確かに。別に俺も何か他の予定があるわけじゃねえし、練習を踏まえた上でその日にってことなら問題はねえか。パーティの前に浮かれて遊んでて、演奏に支障が出るようなら、冥加部長にも申し訳が立たねえからな」
じゃあ、それで。とかなでが話をそそくさと畳み、紅茶のカップを口元に運ぶ。
ふと、脳内で会話を反芻していて気が付いたことを、真顔で氷渡に確認してみた。
「……二人で遊ぶと、浮かれる?」
「う、うるせえな。さっさと紅茶飲んじまえよ」
真っ赤になってうるさげに片手をひらひらと振る辺りが、氷渡の可愛い部分だとかなではいつも思うのだ。
もちろん、かなでが12月12日を指定したのには明確な理由があった。クリスマスが氷渡と二人きりでは過ごせないと判明した時点で、別の日に代替できないかと考えていたのだが、クリスマスのお祝いはやっぱりクリスマス当日にやらないとあまり意味がないだろうとかなでは思っていたのだ。そこで、何かクリスマスに代わる別のイベント日がないだろうかと付近の日付を調べていて、見つけたのが『ダズンローズデー』という記念日だった。
ダズンローズというのは1ダース(12本)のバラのことだ。欧米にある「12本のバラの花束を恋人に贈ると幸せになれる」という習慣を元に、12並びの12月12日に恋人に愛情の証として12本のバラを送る記念日が日本で制定されたらしい。
恋人同士で過ごす記念日として紹介もされていたし、これならクリスマスの代わりになるかとかなでは思っていたが、『ダズンローズデー』としてこの記念日を送れるのかどうかは、正直微妙だとも感じていた。
「絶対、嫌がるよねえ。氷渡くん……」
どう考えても、氷渡が嬉々として12本のバラをかなでに贈るという場面が想像つかない。かなでが頼み込めば、もちろん嫌々ながらも付き合ってはくれるだろうが、この記念日の紹介文には、バラを贈り合うという説明はなく、返礼をどうするのかも書かれてはいない。つまりは、ただ片方がバラを贈るという、一方的な行為なのだ。氷渡にとって何も見返りがないのに自分にバラを贈って欲しいと強請るのは我儘だと思うし、だからと言ってかなでから氷渡に12本のバラを贈るのもどうなのだろうとも思う。
演奏会などのお祝いの花ならともかくとして、日常的なプレゼントでバラの花を貰ってうれしい高校生男子が果たして存在するのだろうか。……某神戸の高校生セレブ達は別として。
そう考えると、『ダズンローズデー』は魅力的な記念日だとは思いつつも、その日をその記念日らしく過ごすのではなく、あくまでクリスマスの代わりとして過ごすのが得策だろうとかなでは判断した。
そもそも、原点に戻って考え直してみれば、かなでは別に氷渡からバラの花束を貰いたい訳じゃないのだ。
世界中の恋人たちが大っぴらに二人きりで過ごすクリスマスというイベントを充分に満喫できない。その代わりに氷渡とゆっくりと過ごせる時間がかなでは欲しかった。代わりの日に与えられた意味が何であろうが、氷渡と幸せに過ごせる時間であれば、かなではそれで満足なのだから。
そうして迎えた12月12日。クリスマスの代わりだと言っても、まだ17歳の高校2年生。高校はちょっと特殊な学校であっても、世間一般の高校生と比べて大した違いがあるはずもない。もちろん定番の高級ホテルでクリスマスディナー……などという無茶が出来るはずもなく、いつも行くファミレスやカフェよりはちょっとだけ値段は上がるものの、そこそこリーズナブルなお洒落なイタリアンレストランで食事をして、クリスマス前から既に展示が始まっているイルミネーションを眺める程度の、ささやかな記念日を計画した。
かなでから氷渡へのプレゼントは、ちょっと肌触りのいいニット帽を選んだ。ピアスとどちらにしようか迷ったのだが、ニット帽の方がより趣味にこだわらずに身に着けられるような気がしたからだ。綺麗にラッピングしたそれをバッグの中に入れ、かなでは氷渡と待ち合わせた駅の噴水前に急ぐ。時刻は夕暮れに近いが、ふと暮れかけた空を見上げて、かなでの表情が曇る。天気予報では夜更けには雨になると言っていた。その予報が違わない雰囲気で、重い色の雲が立ち込めている。イルミネーションを観るまでは何とか降り出さないでくれるといいなあと、かなでは願った。
氷渡と落ち合い、曇りがちな空を眺めつつ、二人であれこれ相談の上、とにかく早く食事を済ませて、クリスマスイルミネーションを観に行くことにした。予報を信じるとすればメインを堪能できないままに雨が降り出してしまう可能性があったからだ。
レストランには少し早目に入れたので、注文後あまり待たずに料理が運ばれてきた。普段から自分で料理をするかなでは、つい味付けや調理法についてああでもないこうでもないと語り、家で再現が出来ないかと頭を悩ませ、氷渡はそんなかなでの言うことに感心したように、言葉少なに相槌を打つ。そんな取っ掛かりから会話はそれなりに弾み、クリスマスコンサートに向けての練習の進み具合、七海のチェロと合わせた時の改善点、更に最近聴いた曲の解釈に到るまで、ほとんど毎日顔を合わせているというのに二人の話題は尽きない。そんなふうに、食事が終わる辺りまでは、二人の計画通りだったのだが……。
「……マジかよ」
支払いを済ませて店を出るなり、氷渡が愕然として呟いた。かなでも、声には出さなかったものの、概ね氷渡と同じ言葉を呟きたい気分だった。
食事を終えるまでに小一時間程度しか経っていないはずなのに、天候は持ってはくれなかった。まだ霧雨程度ではあるが、暗がりに落ちる雨が、並ぶ店舗から漏れる灯りに照らされて、細い糸のように浮かび上がって見える。
「観に行く予定のイルミネーションって、屋外だよね……」
そう呟くかなでの息が白い。小雨とは言え、12月の夜に降り落ちる雨は、容赦なく冷たかった。
「一応、折り畳み傘は持ってるけど」
「俺も持っては来てるが、この気温と雨の中でそれなりの時間、外にいるのはな……」
氷渡の言わんとすることは分かる。おそらく彼もそしてかなでも、約二週間後のクリスマス演奏会のことを気にしている。
だからと言って、どちらも「じゃあ帰ろうか」とは言い出せなかった。その演奏会のことを考えれば、二人きりで過ごせる時間は今日を逃すと随分先になってしまう。そんなに長い時間を望むわけではないけれど、せめてもうしばらくは一緒にいたい。
それでも、現在の状況で予定を強行してしまえば、二人が最重要だと思っている演奏会に支障をきたしてしまいかねない。どうすべきか。その葛藤に結論を出したのは、かなでの方が先だった。
「……氷渡くん、うちに来ない?」
「はっ!? お前、急に何言い出して……」
「イルミネーションは諦めた!クリスマスまではまだもうちょっと時間あるし、今は夕方暗くなるの早いし、見に行こうと思えば学校帰りとかに行けるでしょう? だからそっちはいいんだけど、そもそも本題はそれじゃないよね? 氷渡くんは、このまま食事だけで今日が終わっちゃってもいいの?」
クリスマスの代わりに、二人だけの時間を過ごす。それが何よりも今日の最大の目的だったはずだ。幸いかなでが今暮らしている天音学園の寮は学園のすぐ裏側にある高級マンションで、今二人がいる場所からも徒歩15分圏内だ。学園のすぐ裏であることから、氷渡の自宅からもそう遠いわけではない。勿論、かなでが氷渡の自宅に行っても構わないのだが、演奏者であるかなでが寒空の中行き来することを、氷渡は許しはしないだろう。
「そ、そりゃ、俺だってこのまま『はい、さよなら』って終わりたい訳じゃねえけどよ……」
「マンションからなら夜景も見えるし、さっき言ってたヴァイオリンの練習の成果を見てもらうことも出来るよね。そりゃ、雨の中氷渡くんが帰るのは大変かもしれないけど……」
「いや、それは別に構わねえよ。俺はお前ほどヤワじゃねえしな。でも、お前んち行くってのは……」
何故かかなでの提案をあっさりと受け入れてはくれない氷渡に、かなでもつい意地になる。ただもう少しだけ一緒にいたいと思っているだけなのに、氷渡はそうではないのだろうか?
「氷渡くんは、そんなに私と一緒にいるの、迷惑なの……?」
つい恨みがましいことを言いながら、上目遣いに氷渡を見つめると、氷渡がう、と息を呑む。じいっとそんな彼を睨んでいると、視線を反らした氷渡が、絞り出すようにして言った。
「……分かった。行く。だから、頼むからそれ止めろ」
「それ?……って?」
きょとんとしてかなでが首を傾げると、氷渡が目を丸くしてかなでを見下ろした。
「無自覚かよ!」
「え? 何が?」
本気で分かっていないらしいかなでに深い溜息を付き、氷渡は片手を挙げて、ぐしゃぐしゃとかなでのふわふわとした髪をかき混ぜる。
「……分かってねーんなら、もういい」
言い捨てると、氷渡はコートのポケットに手を突っ込んで、かなでのマンションの方角へ歩き出す。かなでも慌てて手櫛で髪を整え、バッグの中から折りたたみ傘を取り出し、開きながら氷渡の後を追った。
誰よりも好きな女の子が、上目遣いで甘えてくるのに、逆らえる男がこの世の中にどれくらいいるものなのか。しかも、それが計算じゃなく無自覚で出て来るとか。
「……くっそ、最強かよ……!」
悔し紛れに吐き捨てた言葉は、歩幅の広い氷渡に追いつくために、懸命に小走りになっているかなでには当然届いてはおらず。
ようやく追いついて、覗き込んだ氷渡の目尻がほんのりと赤くなっていることも「寒いせいかなあ」と自己完結してしまったかなでは、本当の原因を知る由もなかった。
「……何か、すげえな」
かなでの部屋に足を踏み入れ、氷渡は呆然と呟いた。「だよね」とかなでは苦笑する。田舎から出てきて、ここが自分たちの住む場所だと最初に言われた時、かなでも、一緒に寮に入った幼馴染みの響也も、あまりの豪奢さに何かの間違いじゃないかと疑い、そしてなかなかこの環境に馴染めなかった。
だが、音楽の勉強に特化した天音学園の寮であればこそと考えれば合点はいく。
防音、冷暖房完備は当たり前。オーディオ類も過不足なく揃い、ヴァイオリンの練習をするにもCDやDVDを鑑賞して勉強をするにも、確かに完璧な環境だったのである。
「広すぎるし、置いてある家具とかもすごいいいものばかりだから、最初は落ち着かなかったんだよね。さすがに4か月以上経ったから、ようやく慣れてきた感じなんだけど」
「すげえって噂は聞いてたし、パンフも見てたけど、これほどとは思わなかったぜ……さすが天音……」
きょろきょろと室内を見渡しつつ、感心したように氷渡が溜息を付く。その反応に満足しながら、かなではキッチンに向かう。
「氷渡くん、コーヒーでいい? 私はあんまり飲まないから、種類はないんだけど」
「別に何でも構わねえが、飲まないくせにちゃんとストックしてあるんだな」
「あ、うん。私は飲まないんだけど、響也が飲むからね」
紅茶党のかなでは、普段はほとんどコーヒーを飲まない。
それでも以前響也が天音学園に在籍していた頃は、よく愚痴を吐きにかなでの部屋を訪れていたため、コーヒーは最低限のものを常備してあった。
そんな裏話をしながら、氷渡用のコーヒーと、自分用の紅茶を淹れてリビングに戻ると、苦虫を噛み潰したような不機嫌な表情で、氷渡が中央のソファに行儀悪く座っていた。
「……どしたの?」
さっきまで普通だったのに、と首を傾げつつ、かなでがソファの前のテーブルに二人分のカップを並べる。ソファの背もたれに肘を付き、不満げに視線を反らす氷渡が、ぼそりと低い声で呟いた。
「如月、そんなにしょっちゅうここに来てたのか?」
「うん。ここで暮らしてると、食事は自炊ってことになるでしょ? 響也ってあんまり料理のレパートリーなかったし、一人分も二人分も作る手間って変わらないから、材料代少し貰って、私が夕飯作って一緒に食べてたんだ。響也の部屋まで作りに行くのはさすがに面倒だし。響也が星奏の寮に入ってからは、ちゃんと三食出してもらえるから作らなくてよくなったんだけど」
ただ、響也専用にしていたコーヒーはいつまでも残ったままだった。時折響也やその兄の律、夏のコンクールで知り合った支倉仁亜などの来客があるために、保存をしっかりとして、少しずつ減らしてはいるところなのだが。
「そういえば、氷渡くんがここに入るのって初めてじゃない? 誰もいないんだからいつでも遊びに来ていいよって言うのに、外で逢うことの方が多いから」
考えてみれば、学校帰りに二人でカフェに立ち寄ったりする時に氷渡が注文するのはほとんどコーヒーだ。彼氏である氷渡が立ち寄ってくれていれば、順調にコーヒーが消費されていた可能性にかなでは思い至った。
「……そりゃ、あれだよ。お前……」
「ん?」
何かをもごもごと言いかける氷渡に、かなではティーカップを抱え小さく首を傾げる。しばらく口を開いたり閉じたりを繰り返していた氷渡は、「……分からねえならいい」と、溜息を付いた。
「あ、そうだ。忘れないうちに」
氷渡の態度に不思議そうにしながらも、かなでは別のことに思い出し、テーブルの上にカップを置くと、傍らにあった自分の荷物をごそごそと漁り出す。しかめっ面でコーヒーを啜りつつ、かなでの様子を眺めていた氷渡の鼻先に、準備していたプレゼントの包みを差し出した。
「はい、これ。ちょっと早いけど、クリスマスプレゼント」
氷渡は軽く目を見開き、視線を空に彷徨わせ、次に片手に持ったコーヒーカップをどうするかにしばし悩み、かなでと同じようにそれをテーブルの上に置いた後、「……悪いな」と淡々とプレゼントを受け取った。
かなでの予測からすると、期待していなかったわけではないが本当に貰えるとは思ってなくて、実際に差し出されてみるとどういう反応をしていいのか分からずに、そっけなくなってしまった。……そんなところだろうか。
「……開けていいのか?」
「どうぞ。ホントに大したものじゃないけど」
ニット帽の質感にはこだわったが、かなでの小遣い程度で購入できるものだし、手編みというわけではないのでプレミアム感もない。なので、初めての彼女からのプレゼントに氷渡が過剰な期待をして、既製品であることにがっかりしないようにとかなでは前置きをしておく。
だが、包みを開けた氷渡の反応は思いのほか悪くなかった。
「……肌触りいいな。あったかそうだし」
「えへへ。実はそれだけは結構こだわったんだ。でも普段使い出来るように、デザインは今氷渡くんが愛用してるのと比べてあんまり違和感感じないようなものを選んでみたんだけど」
正直なところ、品物を選んでいる時にはモノトーンを好む氷渡のイメージチェンジをはかろうかと、赤やオレンジの色彩のものや、ド派手なワンポイントが目を引くものなども考えていたのだが、意見を求めた響也に「お前、あまり氷渡で遊んでやるなよ……」と氷渡への同情を含んだ眼差で諌められ、無難なところで妥協したのは内緒の話だ。
「ああ、これならいつものとこっそり変えてても気付くやつはいねえだろ。……興味本位にからかわれるのは不本意だしな」
氷渡の言葉に、かなでは安堵の息を付く。
人懐っこいとは言い難く癖のある氷渡のことを興味本位にからかうような級友はいないだろうとは思うのだが、万が一イメチェンをはかった際に、意外に地雷を踏みそうなのが、室内楽部の面々だ。
さすがに冥加は興味を持たなそうだが、天宮は「どういう心境の変化だい?」と躊躇なく正面から打ち込んで来そうだし、七海などは「もしかして小日向先輩からのプレゼントですか?羨ましいです!」などと、悪気なく氷渡の逆鱗を鷲掴みそうな気がする。
そういう意味では、正しく好奇心旺盛なかなでのチャレンジ精神に歯止めをかけてくれた響也に心から感謝だ。
「……」
ニット帽を大事に握っていた氷渡はしばらく何かを考え込み、それから徐に傍に置いていたコートのポケットを探る。室内に入ってハンガーに掛けようかと声を掛けたら、頑なに「触らなくていい」と言われたコートだ。
「………………やる」
ポケットから何かを掴み出し、それを硬く握りしめた拳が、かなでの目の前に突き付けられる。反射的にかなでが両手を差し出すと、乾いた音を立てて何かが掌の中に滑り落ちてきた。
「……これって」
かなでは目を見開き、掌の中のものを凝視する。
それは、シルバーアクセサリーだった。
氷渡はアクセサリーを作るのが得意で、彼が身に着けているものもほとんどが自作だと言うのを聞いたことがある。
だから、こういうアクセサリーをプレゼントされることは意外だとは思わない。
だが、かなでを驚かせたのはそのデザインだった。
小さな小さな、銀色のバラの花。
様々な大きさのものが、かなでの細い手首に合わせてバランスよく連なっている。
その、バラの小さな花の数は。
何度数えてみても、間違いなく12個だったのだ。
「氷渡くん、これ……」
「……んだよ、別に間違ってねえだろ」
軽く舌打ちをして、目尻を染める氷渡が視線を反らしてぶっきらぼうに吐き捨てる。
「お前がこだわってた12月12日。……ダズンローズデーってやつだろ。とどのつまり、こういう日ってことなんだろうが」
普段から、口が悪くて横暴で。
冥加第一の冥加教信者で、かなでのことなんて結局は二の次で。
だけど、ちゃんと見てくれている。
かなでの小さな期待を、裏切らないようにしてくれている。
おそらくかなでが迷わずに申告した12月12日という日付に氷渡は疑問を持ち、何かがあるのではないかと自ら調べてくれたのだろう。
かなでが望むことを理解しようとしてくれた。
不遜で傲慢で、他人の事なんてまるで関係ないよう見えて、実際は繊細に丁寧に、人の気持ちを拾い上げてくれる。
それなのにひどく不器用で、そんな一面をうまく表に出しきれていない。
かなでが好きになった氷渡という青年のありのままの姿が、そのブレスレットに一つに現れている気がした。
「……おい、小日向……っ!」
焦ったような氷渡の声。
かなでが嬉しさのあまり氷渡に飛びついて、勢いでソファの上に二人転がったせいだ。
「何しやがんだ、あぶねえだろうが!」
演奏会前に怪我しそうな真似してんじゃねえ!と叱る氷渡の声に何度も頷きながら、かなでは彼の胸元にしがみ付く。
「分かってるよ。分かってるけど、すごい嬉しくて……」
ありがとう、とかなでは呟く。
シャツにじんわりと暖かさが沁み込んでいくので、彼女が泣いていることが分かる。そのために、氷渡もそれ以上強くは言えない。
「ありがとう。ありがとう、氷渡くん。大好き……」
ぎゅっと目を閉じ身体を預けるかなでの頭を、しばらくの間恐る恐る、という様子で氷渡の片手が撫でていた。……が、やがて業を煮やしたように氷渡が両手でかなでの肩を掴み、自分からかなでの身体を引き剥がした。
「……氷渡くん?」
ソファの上に座り込み、きょとんとして氷渡を見るかなでに、視線を反らしながら氷渡がやけくそ気味に叫んだ。
「お前、ちょっとは危機感持て! 他に誰もいねえところでこういう雰囲気になるのがヤベえって、普通馬鹿でも分かるだろうが!」
「は?」
ぱちりと瞬きをして、かなでが氷渡をじっと見つめる。視線を反らしたまま、氷渡は一気にまくし立てた。
「そもそも、二人きりになるって分かってながら男を連れ込むってどういう了見だよ! 前々からてめえのその無防備極まりない態度は気になっちゃいたんだが、無邪気・純粋って言や聞こえはいいが、ここまで来たら世間知らずもいいとこだろうが! しかも、俺相手ならまだしも、如月のヤツと二人きりになるとか」
「え、ちょ、ちょっと待って。響也が来てたのはかなり前だよ? 田舎にいた頃に二人でご飯食べるのなんか当たり前だったし、そんなに怒ることない……」
「俺の女が他の男と二人きりで、しかも手料理とか食わせてたって聞いたら、こっちはいい気しねえに決まってるだろうが!!」
「……」
……不思議なもので、話す相手が激高していると、逆にこちらは冷静に物事が捉えられるようになる。
立て板に水とばかりにまくし立てる氷渡の言葉にパニックを起こしかけたが、反論を挟む隙もないまま、ただ脳内で浴びせられた言葉を反芻させてみると、意外にこれはかなでにとって喜ぶべき事態なのかもしれないと気が付いた。
「……もしかして氷渡くん、妬いてくれてる?」
上目遣いにかなでが尋ねると、ぐうっと氷渡が言葉を詰まらせる。一気に顔に朱を上らせて、かなでから目を反らした。
「う、うるせえ! そんなの、妬くに決まってんだろうが!」
うわあ、とかなでが顔を輝かせてそんな氷渡ににじり寄り、下方から覗き込む。別に氷渡は感情表現が乏しいわけではないのだが、決して素直でもない。
その何とも氷渡らしい、素直じゃない照れ方が可愛らしいと思えるのは、惚れた欲目というヤツかもしれないが。
「えへへ」
笑いながら、かなではぎゅっと氷渡の腰回りに腕を回して抱きついてみる。
暖かくて、何だかいい香りがする。氷渡の存在をとても近くに感じられて、これ以上にないくらいに幸福な気持ちになった。……きっと、氷渡の深い部分を理解していない他の誰も、彼がこんな風に安らかな存在であることを知らないのだろう。
そう考えると、何だか妙な優越感が湧くから不思議だ。
「……小日向」
かなでの細い腕の中で、何故か氷渡の身体が緊張する。呆れとも困惑とも取れる複雑な声音で氷渡が呟き、それから彼は諦観したような大きな溜息を付いた。
「……一応、忠告はしたからな。理解しないお前が悪い」
「え?」
低い声で落とされた言葉が聞き取れず、かなでは間の抜けた声で返答する。その微かに開いた唇を塞ぐように、氷渡の唇がかなでのそれに重なった。
(熱い)
そんなにたくさん交わしたことがあるわけじゃない。
それでも、彼と唇を重ねるたびに、かなではそう思う。
多分、この熱さが氷渡の内に秘めた温度なのだろうと理解する。遠巻きにしているだけでは分からない彼の温度を実感するたびに、かなでは幸せな気持ちになる。
今日も同じで、暖かな想いに満たされながら、かなでは自分の唇が氷渡の熱と同じ温度に均されるのを待って、いつものように唇を離そうとした。
だが、それは叶わなかった。
「氷渡く……」
離れようとしたかなでの唇を、氷渡が執拗に追ってくる。驚いて名前を呼びかけたかなでの声を容赦なく途切れさせた。
無理矢理唇を割って入ってきたものが、彼の舌だと理解するのにしばしの時間を要した。だけどすぐに、そんな客観的な事実はどうでもよくなってしまう。
唇を重ねて、熱を分け合って。彼の熱さと同じ温度になれば、そこが終着だと思っていた。でもそうじゃなかった。
否応なく熱が上がる。同じ温度になるだけじゃなくて、もっともっと、融かされる。
そうして、かなでは氷渡の言葉をようやく理解した。
(もしかして、ずっとそうしたいって思ってた?)
だけどきっと一定の距離を保って、意識的に回避して。
そうしてかなでを大切にしてくれていたんだろうか。
もっと近づきたいとか、もっと一緒の時間を過ごしたいとか。
かなでが脳天気な願いを後生大事にしている間に。
それを一足飛びにしようとしていた氷渡自身の願いを、彼はずっと抑え込んでいたんだろうか。
「……お前があんまり無防備だと、俺の箍が簡単に外れちまうんだよ」
気が付くと、体勢が逆転していた。
ふわふわとしたソファに背中が埋もれている。かなではそろそろと視線だけを上向けた。
氷渡がかなでを組み敷いたままどこか痛そうに表情を歪め、かなでのことを見下ろしている。
「幾らお前でも、これでようやく分かったろ。分かったなら少しは自重しろ。次は容赦しねえからな」
(……何でかな)
高圧的に、居丈高に。
どうして氷渡はこんなふうなんだろう。
かなで自身のことを大切にしろと諌めてくれる時にですら、どうして自分を悪く見せてしまうんだろう。
きっとそれは、氷渡だけの罪ではないと思うのに。
「氷渡、くん」
呼びかけた声は、どうしようもなく掠れて潤んでいた。氷渡が困ったように目を細めた。やり過ぎだったと後悔しているのかもしれない。
「……バラの意味、知ってる?」
「は?」
唐突過ぎるかなでの質問に、氷渡が怪訝な顔で答える。
氷渡から受け取って、握り締めたままだったブレスレットを掲げ、かなでが笑った。
「えっとね、確か感謝、誠実、幸福、信頼……それと、希望、情熱、真実、尊敬、栄光、努力、……あとは、愛情と永遠」
指折り数えながら、かなでが12個のバラに込められていると言われている意味を列挙する。氷渡が増々怪訝な顔をした。
「ダズンローズデーって記念日を知った時に、すごく憧れたの。氷渡くんにこんな12個の気持ちを込めたバラを貰えたら、どんなに嬉しくて幸せなんだろうって」
ダズンローズというのは、結婚式でよく使われる演出だと言う。
かなでも氷渡もまだ家庭を作るには幼いから、相手に捧げられるものはまだまだ小さいものでしかないのだろうけど。
「……もし氷渡くんが12のバラに込められたものを私にくれるとしたら、私には代わりに何が返せるんだろうってずっと考えてた……」
氷渡はきっとこの記念日に込められた意味を知らないだろうと思っていた。
だから、その答えを氷渡に伝える日も来ないはずだった。
だが、氷渡はかなでにちゃんと12のバラをくれた。
枯れることのない、いつも身に着けていられる。
12種の想いのこめられた大切なバラを。
「でも、代わりにできるものなんてないから。案外氷渡くんがくれるものを、私もそのまま返すしか方法がないのかなって思って……」
感謝には感謝を。
幸福には幸福を。
愛情には愛情を。
永遠には永遠を。
そんなふうに、氷渡が与えてくれるもの、望んでくれるものを。
同じようにかなでも与えて、そして望む。
「ごめんね。氷渡くんの言うとおり、私あまり深く考えてなかった。氷渡くんと二人きりになることがどういうことかとか、氷渡くんが私に何を望んでいたのかとか」
驚いたように見開かれた氷渡の深い色の瞳を、かなではまっすぐに見つめ返す。
「でも、これだけははっきりと言えるよ。氷渡くんが望んでくれるなら、それを与えることを私は迷ったりしないよ。氷渡くんが私の意志を無視して、自分の意志を優先する人じゃないってこと、ちゃんと知ってるから」
氷渡は増々目を見開く。
困ったように空に視線を彷徨わせ、それからどうしようもなく、視線はかなでの目線の先に舞い戻ってきた。
「おい……結局それってつまり……」
い、いいのか、と狼狽えた氷渡の声が呟く。
かなでは思わず笑う。さっきまでの強引さはどこにいってしまったのだろうか。
「いいのかって何が?」
「言わせるかよ、わざわざ」
舌打ち混じりに氷渡が吐き捨てるが、顔は真っ赤に染まったままで、イマイチ迫力に欠ける。
「言いたくないなら、言わなくていいよ。……でも駄目だと思ったら止めるから、ちゃんと止まってね」
「……無茶な事言うな」
情けなく息を付く氷渡に、かなでがくすくすと笑う。
ふてくされたように氷渡が視線を反らす。……だが少しの沈黙の後、何かを切り替えたように。……一つ、スイッチを入れてしまったように真剣な眼差でかなでのことを見下ろした。
「……無責任に、放り出すような真似はしない。無理強いもしない。……だから」
うん、とかなでは微笑んで、小さく頷く。
そして、また。
唇が触れた部分から。
かなでの全ては、氷渡の熱に融かされていく。
あとがきという名の言い訳
氷渡書くの難しい……。一言、それに尽きる(--;)
特に話し方に氷渡っぽさを出すのが意外に難しかったです。ちゃんと氷渡になったんだろうか……。
あと、氷渡が相手だとかなでが若干小悪魔になることを発見(笑)何か掌の上で転がす感が(笑)
記念創作は裏頁に続くように作成していますが、それを読まないと話が完結しないということもありません。続きのみを配布することはありませんので、希望される方は基本の裏頁アドレス申請の規定を遵守してください。
よろしければ拍手とアンケート
にご協力ください。
執筆日:2017.10.15